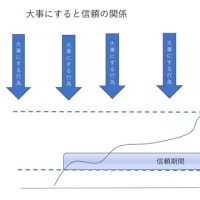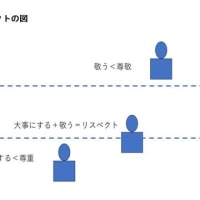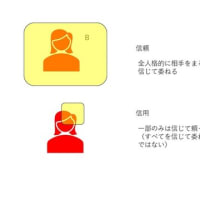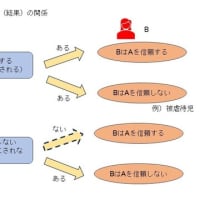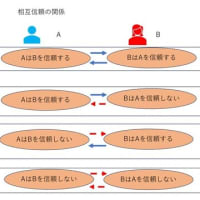教員研修で、以下の項目について、アンケートを最近、行っています。
これは、「学習コンテンツを単に暗記する、再現する」ことにとどまらず、その学習を通して、生徒にどういう学びの力をつけさせるかということを調査した内容です。調査項目については、私が考えたオリジナルなものになっています。
調査対象は公立高校を中心としています。
★アンケート項目
・学ぶ意義や目的を説明し、生徒に理解させている
・学ぶための環境を配慮している(ICTや図書室活用、教具、座席の工夫など)
・情報を精査したり、信頼する情報を知識として身につけさせる演習をしている
・授業で受け取った知識の定着につとめる活動(例:小テスト等)を行っている
・必要な知識をうまく取組み、編集する能力を教育活動に入れている
・知識を使って論理的にアウトプットさせたり、分析的な能力を使うなどの演習をしている
・入ってくる情報を鵜呑みにさせず、批判的な思考力が育つような活動を入れている
・従来の発想から脱した創造的な思考が育つような活動を入れている
・学習課題を大局的につかませ、どんな意味を社会で持つかなどについて説明し意識させている
・生徒による問題発見や問題解決を促すような演習を意図的に提供している
・語彙力や文章力、言語技術が高まるような教材提供や指導をしている
・絵や写真、図解などを使い、生徒の非言語な能力が身につくような教材提供や指導をしている
・振り返りの時間を取ってシートに書かせるなど、メタ認知能力の育成を活動に入れている
・探求する要素を授業に取り入れ、生徒の探求心の育成につとめている
・集中が必要な場面では集中力が高まるような授業運営をしている
・生徒の失敗を肯定的にとらえ、再度チャレンジできるような雰囲気をつくっている
・生徒各自が自分に自信を持ち、自己肯定感を増すような雰囲気をつくっている
・IT機器やツールを利用し、また生徒にもそれを積極的に使わせる授業を行っている
・メディアの持つ特徴を理解し、モラル意識とつながるような活動を取り入れている
・生徒自身に学習計画を立てさせるなど、時間管理能力の育成を意識した活動をしている
・役割分担やチームとして機能させるような演習活動を行っている
・生徒が主張したい意見を相手にきちんと伝える態度育成を意識した活動を取り入れている
・生徒が相手の意見に判断・評価を加えずに傾聴するような態度育成を意識している
・他人へのプレゼンテーションを前提にした資料作成の演習を行っている
・他人への口頭プレゼンテーション演習を取り入れ指導している
・他者とのコミュニケーション能力育成を意図した授業を設計し、実践している
・生徒各自の知を持ち寄って共有したり、その有効性を意識させる活動を行っている
・どうしたらチームの雰囲気がよくなるか、教師として適度に介入したりアドバイスしている
・ファシリテーションという考えやツールを生徒に伝え、生徒にも実践させている
・生徒各自が所属するチームに貢献できたという実感を持たせるような授業を工夫している
・生徒が、他者に対して心を開いて活動できるような雰囲気づくりをしている
・生徒が、他者に対して思いやりを持つ行動ができるような雰囲気づくりをしている
・チーム内で葛藤や衝突があったときに、うまくアドバイスし、解決に導かせている
・チームメンバーの多様性や他者理解を意識できるような活動をさせている
・地域人材を投入したり、グローバルな中での学びを意識させている
・学習だけでなく、キャリア教育(進路指導や生き方の指導)などの要素を入れている
・チーム活動自体の振り返りの機会を設け、自立的活動が成長するよう支援している
★上記のうち、先生方が生徒に身に着けさせることを意識しているもの
・授業で受け取った知識の定着につとめる活動(例:小テスト等)を行っている
・生徒の失敗を肯定的にとらえ、再度チャレンジできるような雰囲気をつくっている
・どうしたらチームの雰囲気がよくなるか、教師として適度に介入したりアドバイスしている
これを見ると、日本の?教師の特徴として、知識の定着が主眼になっていることがうかがえます。
また失敗については肯定的にとらえ、再チャレンジさせたり、グループ学習ではうまくいっていない集団のフォローに入るなどして配慮している様子がうかがえます。
★上記のうち、先生方が生徒に身に着けさせることを意識していないもの
・ファシリテーションという考えやツールを生徒に伝え、生徒にも実践させている
・IT機器やツールを利用し、また生徒にもそれを積極的に使わせる授業を行っている
・地域人材を投入したり、グローバルな中での学びを意識させている
これをみると、そもそも現在の教師にファシリテーション的な動き方という概念自体があまりないことが気になります。
また、ITの活用や地域人材などの外部リソースについてはまだまだ消極的な姿勢の教師が多いということも挙げられるのだと思います。
まだサンプルとしては少ないのですが、何校か試してみて傾向がでてきたので中間報告させていただきました。
これは、「学習コンテンツを単に暗記する、再現する」ことにとどまらず、その学習を通して、生徒にどういう学びの力をつけさせるかということを調査した内容です。調査項目については、私が考えたオリジナルなものになっています。
調査対象は公立高校を中心としています。
★アンケート項目
・学ぶ意義や目的を説明し、生徒に理解させている
・学ぶための環境を配慮している(ICTや図書室活用、教具、座席の工夫など)
・情報を精査したり、信頼する情報を知識として身につけさせる演習をしている
・授業で受け取った知識の定着につとめる活動(例:小テスト等)を行っている
・必要な知識をうまく取組み、編集する能力を教育活動に入れている
・知識を使って論理的にアウトプットさせたり、分析的な能力を使うなどの演習をしている
・入ってくる情報を鵜呑みにさせず、批判的な思考力が育つような活動を入れている
・従来の発想から脱した創造的な思考が育つような活動を入れている
・学習課題を大局的につかませ、どんな意味を社会で持つかなどについて説明し意識させている
・生徒による問題発見や問題解決を促すような演習を意図的に提供している
・語彙力や文章力、言語技術が高まるような教材提供や指導をしている
・絵や写真、図解などを使い、生徒の非言語な能力が身につくような教材提供や指導をしている
・振り返りの時間を取ってシートに書かせるなど、メタ認知能力の育成を活動に入れている
・探求する要素を授業に取り入れ、生徒の探求心の育成につとめている
・集中が必要な場面では集中力が高まるような授業運営をしている
・生徒の失敗を肯定的にとらえ、再度チャレンジできるような雰囲気をつくっている
・生徒各自が自分に自信を持ち、自己肯定感を増すような雰囲気をつくっている
・IT機器やツールを利用し、また生徒にもそれを積極的に使わせる授業を行っている
・メディアの持つ特徴を理解し、モラル意識とつながるような活動を取り入れている
・生徒自身に学習計画を立てさせるなど、時間管理能力の育成を意識した活動をしている
・役割分担やチームとして機能させるような演習活動を行っている
・生徒が主張したい意見を相手にきちんと伝える態度育成を意識した活動を取り入れている
・生徒が相手の意見に判断・評価を加えずに傾聴するような態度育成を意識している
・他人へのプレゼンテーションを前提にした資料作成の演習を行っている
・他人への口頭プレゼンテーション演習を取り入れ指導している
・他者とのコミュニケーション能力育成を意図した授業を設計し、実践している
・生徒各自の知を持ち寄って共有したり、その有効性を意識させる活動を行っている
・どうしたらチームの雰囲気がよくなるか、教師として適度に介入したりアドバイスしている
・ファシリテーションという考えやツールを生徒に伝え、生徒にも実践させている
・生徒各自が所属するチームに貢献できたという実感を持たせるような授業を工夫している
・生徒が、他者に対して心を開いて活動できるような雰囲気づくりをしている
・生徒が、他者に対して思いやりを持つ行動ができるような雰囲気づくりをしている
・チーム内で葛藤や衝突があったときに、うまくアドバイスし、解決に導かせている
・チームメンバーの多様性や他者理解を意識できるような活動をさせている
・地域人材を投入したり、グローバルな中での学びを意識させている
・学習だけでなく、キャリア教育(進路指導や生き方の指導)などの要素を入れている
・チーム活動自体の振り返りの機会を設け、自立的活動が成長するよう支援している
★上記のうち、先生方が生徒に身に着けさせることを意識しているもの
・授業で受け取った知識の定着につとめる活動(例:小テスト等)を行っている
・生徒の失敗を肯定的にとらえ、再度チャレンジできるような雰囲気をつくっている
・どうしたらチームの雰囲気がよくなるか、教師として適度に介入したりアドバイスしている
これを見ると、日本の?教師の特徴として、知識の定着が主眼になっていることがうかがえます。
また失敗については肯定的にとらえ、再チャレンジさせたり、グループ学習ではうまくいっていない集団のフォローに入るなどして配慮している様子がうかがえます。
★上記のうち、先生方が生徒に身に着けさせることを意識していないもの
・ファシリテーションという考えやツールを生徒に伝え、生徒にも実践させている
・IT機器やツールを利用し、また生徒にもそれを積極的に使わせる授業を行っている
・地域人材を投入したり、グローバルな中での学びを意識させている
これをみると、そもそも現在の教師にファシリテーション的な動き方という概念自体があまりないことが気になります。
また、ITの活用や地域人材などの外部リソースについてはまだまだ消極的な姿勢の教師が多いということも挙げられるのだと思います。
まだサンプルとしては少ないのですが、何校か試してみて傾向がでてきたので中間報告させていただきました。