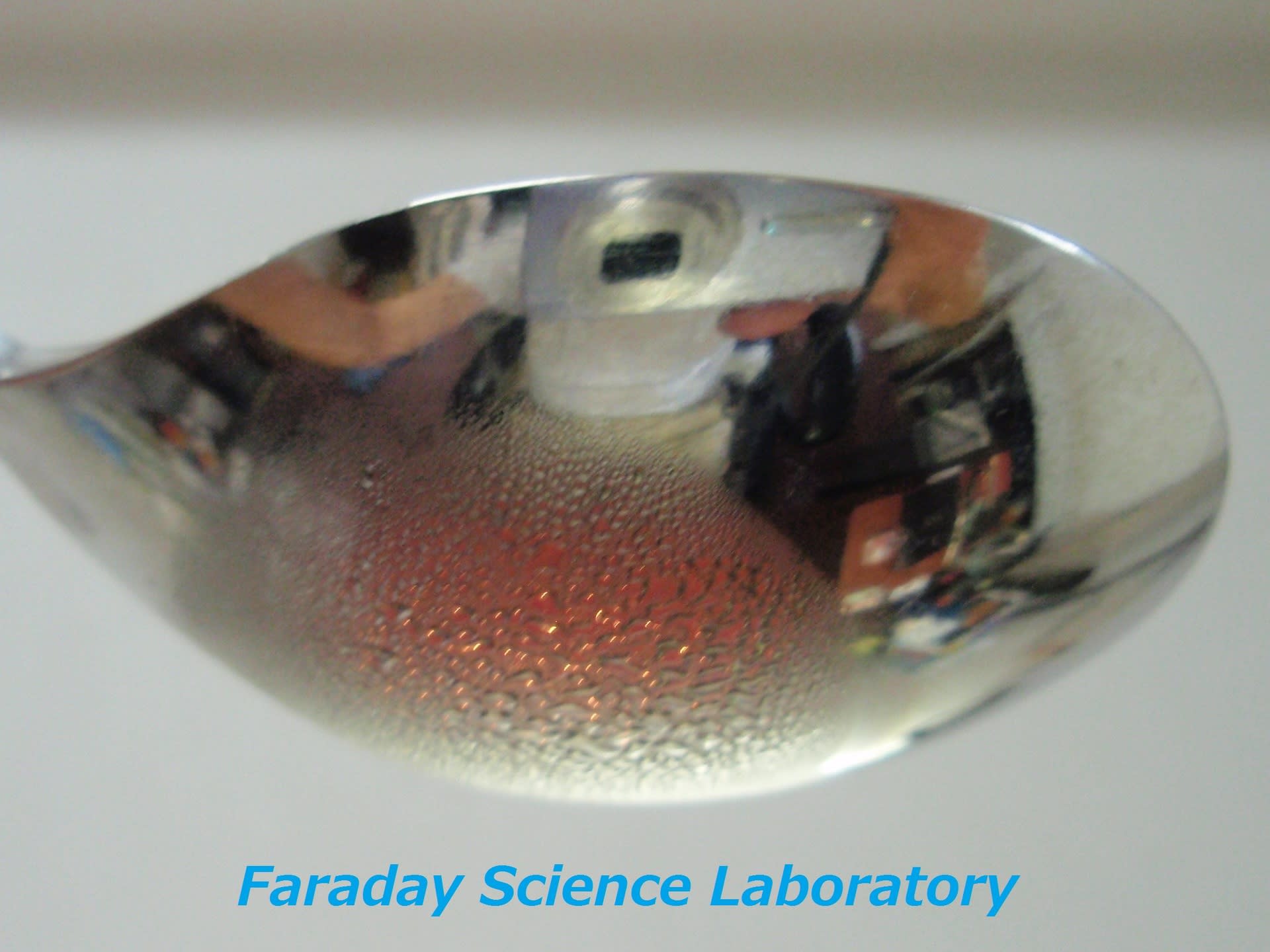いらっしゃいませ! ご訪問ありがとうございます。
前に水にはいろいろなものがふくまれていて、純水(じゅんすい)な水はなかなかないとお話ししました。
では、この地球(ちきゅう)の水に多くふくまれているもの、それは塩です。

というと、ものすごい量の塩が地球の表面(ひょうめん)にあること、おもいうかべますね。塩の海があったり、
人の大きさの大きな結晶(けっしょう)が山からでてきたりします。
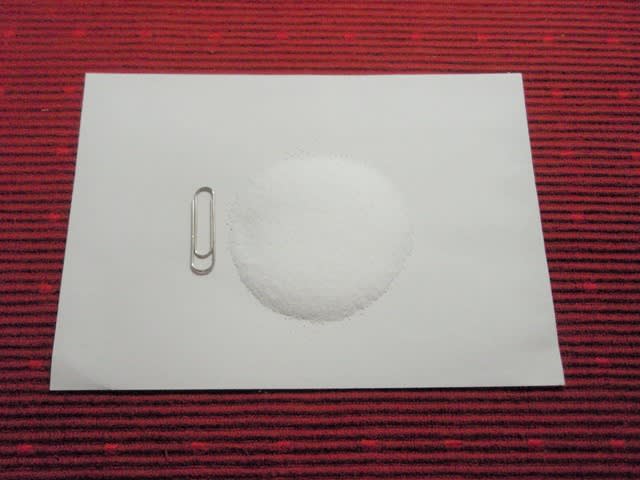
みなさんが身の回りで見るのは、これくらいの塩かな。ほぼ、10グラムです。
さて、この塩は水に溶けやすいのですが、おんどがすこしかわります。高くなる?ひくくなる?
ひくくなります。指さきでかんじるほどではありません。

これは1ミリほどの塩です。ナトリウムと塩素(えんそ)からできています。この塩が水に
溶けて透明(とうめい)になる。何がおきているかは、むつかしい、、、

同じような結晶、さとうがあります。これも1ミリほどですが塩より結晶らしい形をしています。
グラニュー糖(とう)といいます。純度(じゅんど)は、99.95%で、身の回りにある食べ物の中では、
高い純度でしょう。塩とはまったくちがって、炭素(たんそ)、水素(すいそ)、酸素(さんそ)からできています。
水に溶けると、温度は少しだけひくくなります。
最近、耳にするリチウムというものがありますが、これは水とはげしく反応(はんのう)して火がでて、
おんどはたいへん高くなります。あぶないですね! ということで、物が溶けるとき、おんどが高くなったり、
ひくくなったりします。
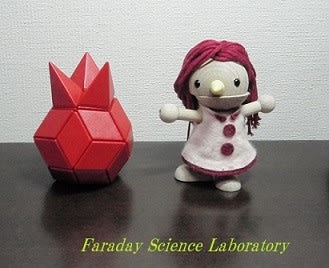
アーレー助手は、これはたいへんむつかしいといっています。たぶん大学生ぐらいでわかるらしい、、、
*** みなさんの中で、9才以下のかたがいましたら、コメントを待って
います。どこかにいるかな??? スマホやタブレット、持っているかな???
では、次回、お目にかかりましょう。
2018年 10月 Faraday Science Laboratory 26
前に水にはいろいろなものがふくまれていて、純水(じゅんすい)な水はなかなかないとお話ししました。
では、この地球(ちきゅう)の水に多くふくまれているもの、それは塩です。

というと、ものすごい量の塩が地球の表面(ひょうめん)にあること、おもいうかべますね。塩の海があったり、
人の大きさの大きな結晶(けっしょう)が山からでてきたりします。
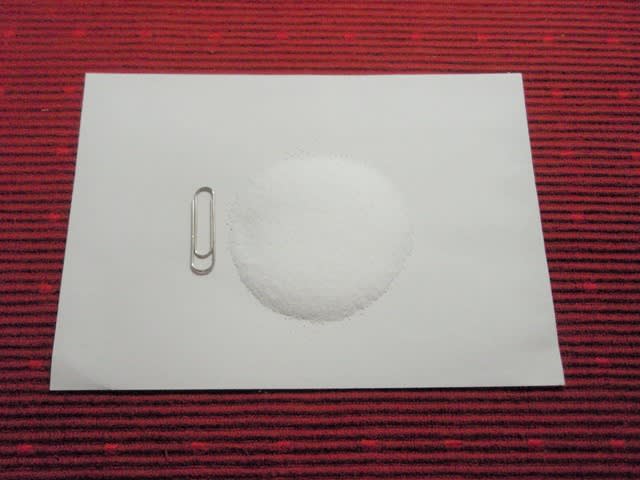
みなさんが身の回りで見るのは、これくらいの塩かな。ほぼ、10グラムです。
さて、この塩は水に溶けやすいのですが、おんどがすこしかわります。高くなる?ひくくなる?
ひくくなります。指さきでかんじるほどではありません。

これは1ミリほどの塩です。ナトリウムと塩素(えんそ)からできています。この塩が水に
溶けて透明(とうめい)になる。何がおきているかは、むつかしい、、、

同じような結晶、さとうがあります。これも1ミリほどですが塩より結晶らしい形をしています。
グラニュー糖(とう)といいます。純度(じゅんど)は、99.95%で、身の回りにある食べ物の中では、
高い純度でしょう。塩とはまったくちがって、炭素(たんそ)、水素(すいそ)、酸素(さんそ)からできています。
水に溶けると、温度は少しだけひくくなります。
最近、耳にするリチウムというものがありますが、これは水とはげしく反応(はんのう)して火がでて、
おんどはたいへん高くなります。あぶないですね! ということで、物が溶けるとき、おんどが高くなったり、
ひくくなったりします。
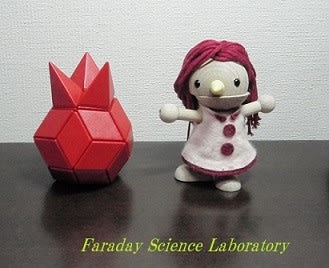
アーレー助手は、これはたいへんむつかしいといっています。たぶん大学生ぐらいでわかるらしい、、、
*** みなさんの中で、9才以下のかたがいましたら、コメントを待って
います。どこかにいるかな??? スマホやタブレット、持っているかな???
では、次回、お目にかかりましょう。
2018年 10月 Faraday Science Laboratory 26