かつてひきこもりの支援をしていた頃、「ひとりじゃない、就活講座」というものをひきこもり状態にある若者たちと一緒につくりました。
その講座に参加された若者たちは、「仕事の経験がない」「面接試験に行く勇気がない」「頭で考えすぎて一歩踏み出せない」「人前で緊張しやすい」「コミュニケーションが苦手」「就職活動に行き詰まっている」「履歴書の空白部分を面接官に説明できない」「自分が誰からも必要とされていない」「社会の役に立っていない」など、「自信のなさ」「不安」「怖さ」を抱え、「就労」へ一歩踏み出せないでいる人たちでした。
就労の願いがあるにもかかわらず、若者たちは勇気を持って踏み出せません。若者たちが「社会と自分をつなぐ」道筋を描くことができないのは、「ありのままの自分」を受け止められつつ(承認欲求を満たされつつ)、「もう1人の自分」(「そんな自分を変えてみなよ」)を生み出すために共に学び、共に闘う他者と出会い直すなかで、若者たちが抱える「躓き」や「弱さ」とを共感し、お互いがつながり合える「居場所」がないからです。
そう思っていた私は、その頃、定期的に面談に来られていた若者たちに声を掛け、「ひとりじゃない、就活講座」を結成します。
「ひとりじゃない、就活講座」は「働きたいけど、働けない若者」が活動を通して出会った仲間(信頼できる他者)との関係性で「欲求する主体」を獲得し、若者たちが「就労へ向かった自治的集団」を組織し、「信頼できる他者」とともに「社会を制作する活動」に取り組んでいく活動でした。
この活動を通して、ひきこもりの若者たちに教えていただいたことは、エンパワーメントの大切さでした。「脊髄損傷患者のための社会参加ガイドブック」の中で、エンパワーメントとは「人々が本来持っている生きる力や主体性を取り戻し、できる限り自立し、自分たちの問題を自分たちで解決していける力を高めていこうという考え方」であると書いています。また、エンパワーメントには、4つの次元があると言っています。
1つめは「自己信頼」です。障がいを負ってしまった自分に再び自信を持ち、自分を信頼できる存在であると感じられるようになること。そのためには、自分の気持ちを受け止め、共感してもらい、わかってもらえたと感じることが大切だと言っています。
2つめは「相互理解」です。同じような問題を抱えた人々との出会いや語らいの大切さです。問題を持っているのは自分だけではないことや、お互いに助け合えることを知ることになります。
3つめは「権利の発見と主張」です。自分の置かれている状況と周囲の環境との関係や、社会、組織との関係を考え、そこで侵害されている自分の権利に気づきも主張すること。
4つめは「社会への働きかけ」です。同じような権利侵害や差別を受けている人々の権利を守るために、仲間や考えを同じくする人々と協力して社会に働きかけることの大切さです。
エンパワーメントは社会的弱者という立場から自分らしさを取り戻し、自分自身を解放し、人間回復をめざしていく考え方です。
ひきこもり状態にあった若者たちは、まさに「ひとりじゃない、就活講座」でエンパワーメントを獲得したのだと思います。
ひきこもり状態にある若者のほとんどが自信を失っています。その自信を取り戻す作業として「自己信頼」の次元がありますが、そのためには、「自分の気持ちを受け止め、共感してもらい、わかってもらえたと感じること」が大切でした。また、同じような問題を抱えた人々との出会いや語らいを通した「相互理解」の大切さです。「問題を持っているのは自分だけではないことや、お互いに助け合えることを知ること」によって、若者たちにパワーが生まれてきたのです。「ひとりじゃない」と思えるようになり、ひきこもり状態にあることによって侵害されている自分の権利について気がつきます。また、同じようにひきこもり状態に人たちと共に社会に働きかける力が生まれてきました。要するに、「ひとりじゃない、就活講座」に参加することを通して、自分らしさを取り戻していったのだと思います。
この「ひとりじゃない、就活講座」では、若者たちが就活をするために必要な企画をつくっていくのですが、その中に「アルバイト体験談」や「現役女子大生における就職体験談」という企画がありました。体験者の「語り」を通して、「より良い生き方」(「こんな生き方があってもいいよね、こういう生き方もできるよね」)を仲間とともに語り直す取り組みでした。
当時、私はここに「語り(ナラティヴ)」の可能性があると感じたことを覚えています。つまり、①自分の物語を語ることで、物語の再構成が可能となる(自己発見の場)、②自分の語った体験談を聴いてくれる相手がいる、③自分以外の視点が加わり、自分ひとりでは気づかなかったことに気がつく、④参加者の質問に応答することで「新たな発見」が生まれる、⑤自分の体験(過去)にも人を作用させられているという実感をもつ、などという教育的な効果ですね。
(もちろん、この取り組みが可能になったのは、「講座」内外で展開した若者たち同士の様々な「おしゃべり」や「対話」が頻繁に行われてきたからだと思います)
若者たち自身が「孤立」と「自己責任イデオロギー」を乗り越えていくためには、若者たちが「当事者性」を意識し、若者たち自身が自分たちの活動を社会や大人に発信し、「働きたいけど、働けない」状況がたんなる「甘え」からくるものではないこと、就労のための準備として様々な活動に取り組んでいることを自分たちの言葉で伝え、訴えかけ、理解してもらわなければなりません。そうでなければ、若者たちが「社会や大人」から本当の意味での「受け入れられている感覚」を得ることができないと私は思っています。
現在、私は福祉の現場で仕事をさせていただいていますが、現場で大切にしていることは、障がい当事者の声であり、語りです。エンパワーメントを獲得するためには、同じ境遇にいる者同士の語らいが非常に重要だと思っているのですが、福祉の現場ではそうした「語らい」の場が希薄であると感じており、私たちのグループホームでは障がい当事者同士の「語らい」ができる環境をつくることを意識しながら運営をしています。
参考文献
・山田育男「居場所を拠点とした世界づくりを地域社会に」『教育』(2010年12月号)
・山田育男「『ひとりじゃない、就活講座』活動記録」『高校生活指導』(2011年夏季号、189号)
当法人のホームページは以下をクリックするとご覧いただけます。
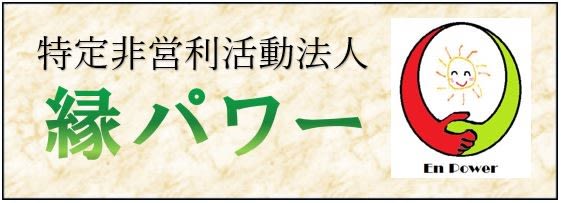
その講座に参加された若者たちは、「仕事の経験がない」「面接試験に行く勇気がない」「頭で考えすぎて一歩踏み出せない」「人前で緊張しやすい」「コミュニケーションが苦手」「就職活動に行き詰まっている」「履歴書の空白部分を面接官に説明できない」「自分が誰からも必要とされていない」「社会の役に立っていない」など、「自信のなさ」「不安」「怖さ」を抱え、「就労」へ一歩踏み出せないでいる人たちでした。
就労の願いがあるにもかかわらず、若者たちは勇気を持って踏み出せません。若者たちが「社会と自分をつなぐ」道筋を描くことができないのは、「ありのままの自分」を受け止められつつ(承認欲求を満たされつつ)、「もう1人の自分」(「そんな自分を変えてみなよ」)を生み出すために共に学び、共に闘う他者と出会い直すなかで、若者たちが抱える「躓き」や「弱さ」とを共感し、お互いがつながり合える「居場所」がないからです。
そう思っていた私は、その頃、定期的に面談に来られていた若者たちに声を掛け、「ひとりじゃない、就活講座」を結成します。
「ひとりじゃない、就活講座」は「働きたいけど、働けない若者」が活動を通して出会った仲間(信頼できる他者)との関係性で「欲求する主体」を獲得し、若者たちが「就労へ向かった自治的集団」を組織し、「信頼できる他者」とともに「社会を制作する活動」に取り組んでいく活動でした。
この活動を通して、ひきこもりの若者たちに教えていただいたことは、エンパワーメントの大切さでした。「脊髄損傷患者のための社会参加ガイドブック」の中で、エンパワーメントとは「人々が本来持っている生きる力や主体性を取り戻し、できる限り自立し、自分たちの問題を自分たちで解決していける力を高めていこうという考え方」であると書いています。また、エンパワーメントには、4つの次元があると言っています。
1つめは「自己信頼」です。障がいを負ってしまった自分に再び自信を持ち、自分を信頼できる存在であると感じられるようになること。そのためには、自分の気持ちを受け止め、共感してもらい、わかってもらえたと感じることが大切だと言っています。
2つめは「相互理解」です。同じような問題を抱えた人々との出会いや語らいの大切さです。問題を持っているのは自分だけではないことや、お互いに助け合えることを知ることになります。
3つめは「権利の発見と主張」です。自分の置かれている状況と周囲の環境との関係や、社会、組織との関係を考え、そこで侵害されている自分の権利に気づきも主張すること。
4つめは「社会への働きかけ」です。同じような権利侵害や差別を受けている人々の権利を守るために、仲間や考えを同じくする人々と協力して社会に働きかけることの大切さです。
エンパワーメントは社会的弱者という立場から自分らしさを取り戻し、自分自身を解放し、人間回復をめざしていく考え方です。
ひきこもり状態にあった若者たちは、まさに「ひとりじゃない、就活講座」でエンパワーメントを獲得したのだと思います。
ひきこもり状態にある若者のほとんどが自信を失っています。その自信を取り戻す作業として「自己信頼」の次元がありますが、そのためには、「自分の気持ちを受け止め、共感してもらい、わかってもらえたと感じること」が大切でした。また、同じような問題を抱えた人々との出会いや語らいを通した「相互理解」の大切さです。「問題を持っているのは自分だけではないことや、お互いに助け合えることを知ること」によって、若者たちにパワーが生まれてきたのです。「ひとりじゃない」と思えるようになり、ひきこもり状態にあることによって侵害されている自分の権利について気がつきます。また、同じようにひきこもり状態に人たちと共に社会に働きかける力が生まれてきました。要するに、「ひとりじゃない、就活講座」に参加することを通して、自分らしさを取り戻していったのだと思います。
この「ひとりじゃない、就活講座」では、若者たちが就活をするために必要な企画をつくっていくのですが、その中に「アルバイト体験談」や「現役女子大生における就職体験談」という企画がありました。体験者の「語り」を通して、「より良い生き方」(「こんな生き方があってもいいよね、こういう生き方もできるよね」)を仲間とともに語り直す取り組みでした。
当時、私はここに「語り(ナラティヴ)」の可能性があると感じたことを覚えています。つまり、①自分の物語を語ることで、物語の再構成が可能となる(自己発見の場)、②自分の語った体験談を聴いてくれる相手がいる、③自分以外の視点が加わり、自分ひとりでは気づかなかったことに気がつく、④参加者の質問に応答することで「新たな発見」が生まれる、⑤自分の体験(過去)にも人を作用させられているという実感をもつ、などという教育的な効果ですね。
(もちろん、この取り組みが可能になったのは、「講座」内外で展開した若者たち同士の様々な「おしゃべり」や「対話」が頻繁に行われてきたからだと思います)
若者たち自身が「孤立」と「自己責任イデオロギー」を乗り越えていくためには、若者たちが「当事者性」を意識し、若者たち自身が自分たちの活動を社会や大人に発信し、「働きたいけど、働けない」状況がたんなる「甘え」からくるものではないこと、就労のための準備として様々な活動に取り組んでいることを自分たちの言葉で伝え、訴えかけ、理解してもらわなければなりません。そうでなければ、若者たちが「社会や大人」から本当の意味での「受け入れられている感覚」を得ることができないと私は思っています。
現在、私は福祉の現場で仕事をさせていただいていますが、現場で大切にしていることは、障がい当事者の声であり、語りです。エンパワーメントを獲得するためには、同じ境遇にいる者同士の語らいが非常に重要だと思っているのですが、福祉の現場ではそうした「語らい」の場が希薄であると感じており、私たちのグループホームでは障がい当事者同士の「語らい」ができる環境をつくることを意識しながら運営をしています。
参考文献
・山田育男「居場所を拠点とした世界づくりを地域社会に」『教育』(2010年12月号)
・山田育男「『ひとりじゃない、就活講座』活動記録」『高校生活指導』(2011年夏季号、189号)
当法人のホームページは以下をクリックするとご覧いただけます。
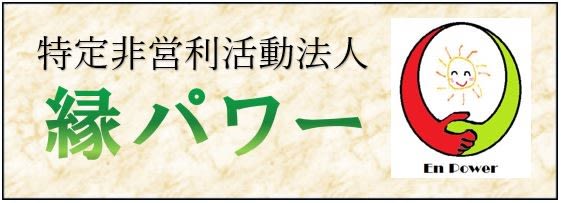




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます