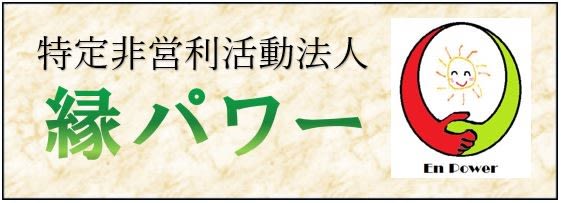信州松本民藝の旅で、再びものづくりがしたくなりました。僕は若い頃、障がい者就労継続支援B型事業所の支援員(職員)をしていたことがあります。

行政が行う障がい者の就労支援は大きく分けて三つあります。就労移行支援(就職支援)、就労継続支援A型(事業所と当事者が雇用契約を結び最低賃金を保証する)、就労継続支援B型(事業所と当事者が雇用契約を結ばない)です。就労支援の実態は厳しく、例えば就労継続支援B型事業所で働く利用者(当事者)の工賃(稼働日数20日として1ヶ月分の給料)は、その殆んどが一万円を満たない額です。収益は、工場の下請け作業や公園清掃や自主製品を製作販売して得ます。
多くの事業所で自主製品の製作販売を試みてます。ジャムやクッキーやパン等の食べ物を作ったり、布製品や機織りや七宝や陶芸や木工製品を作ったりします。支援員(職員)の給料と、当事者の給料(工賃)は別枠です。僕は、当事者の工賃を保障するために自主製品オリジナル木工製品を企画しました。自主製品の主要要件は「当事者と支援員とで作れること」、「売れること」、「量産できること」です。この要件を可能とする商品を企画するのです。

オリジナル木工製品を企画するのは、楽しかったです。販売成績の良い製品は、季節ものと呼ばれる季節の行事に絡めた製品です。バレンタインデー、雛祭り、ホワイトデー、端午の節句、ハロウィーン、クリスマス、お正月に絡めます。大きなものより、小さなものが好評です。その結果、価格500円から1000円程度の季節もの木製玩具を主要商品としました。木目を活かした無垢材に、和紙を貼ったり、粘土を焼いて塗装した部品やボタンをデコレーションしたり、稼働部分に磁石を用いたり、ラッピングにトリコロール柄のリボンを使ったり、掌に乗る程の小さくて可愛いものを作りました。小さくて可愛いものは、作っていても楽しいことが利点でもあります。

楽しく作ることは、とても大切です。生産量を上げるために、辛くなることは良くありません。仲間作りを含めて、楽しく作る環境を利用者(当事者)に保障することが大切です。ものづくりを通して人と繋がる、社会と繋がる、工芸倶楽部は民藝の哲学と通底しており、僕は就労継続支援B型事業所の存在意義はここにあると考えます。
社会福祉士 佐藤 信行
当法人のホームページは以下をクリックするとご覧いただけます。
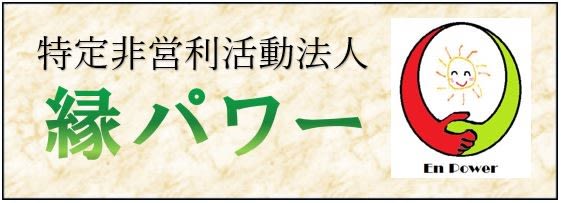

行政が行う障がい者の就労支援は大きく分けて三つあります。就労移行支援(就職支援)、就労継続支援A型(事業所と当事者が雇用契約を結び最低賃金を保証する)、就労継続支援B型(事業所と当事者が雇用契約を結ばない)です。就労支援の実態は厳しく、例えば就労継続支援B型事業所で働く利用者(当事者)の工賃(稼働日数20日として1ヶ月分の給料)は、その殆んどが一万円を満たない額です。収益は、工場の下請け作業や公園清掃や自主製品を製作販売して得ます。
多くの事業所で自主製品の製作販売を試みてます。ジャムやクッキーやパン等の食べ物を作ったり、布製品や機織りや七宝や陶芸や木工製品を作ったりします。支援員(職員)の給料と、当事者の給料(工賃)は別枠です。僕は、当事者の工賃を保障するために自主製品オリジナル木工製品を企画しました。自主製品の主要要件は「当事者と支援員とで作れること」、「売れること」、「量産できること」です。この要件を可能とする商品を企画するのです。

オリジナル木工製品を企画するのは、楽しかったです。販売成績の良い製品は、季節ものと呼ばれる季節の行事に絡めた製品です。バレンタインデー、雛祭り、ホワイトデー、端午の節句、ハロウィーン、クリスマス、お正月に絡めます。大きなものより、小さなものが好評です。その結果、価格500円から1000円程度の季節もの木製玩具を主要商品としました。木目を活かした無垢材に、和紙を貼ったり、粘土を焼いて塗装した部品やボタンをデコレーションしたり、稼働部分に磁石を用いたり、ラッピングにトリコロール柄のリボンを使ったり、掌に乗る程の小さくて可愛いものを作りました。小さくて可愛いものは、作っていても楽しいことが利点でもあります。

楽しく作ることは、とても大切です。生産量を上げるために、辛くなることは良くありません。仲間作りを含めて、楽しく作る環境を利用者(当事者)に保障することが大切です。ものづくりを通して人と繋がる、社会と繋がる、工芸倶楽部は民藝の哲学と通底しており、僕は就労継続支援B型事業所の存在意義はここにあると考えます。
社会福祉士 佐藤 信行
当法人のホームページは以下をクリックするとご覧いただけます。