
既述もした名古屋の研修会に行ってまいりました。
久々の面々とも再会を果たし、とても参考になる講義も聴けて、非常に有意義な時間を過ごす事ができました。
また、講義終わっての懇親会では、某著名人の経営するお店に初めて行く機会に恵まれ、お昼に食べたご当地名産の味噌煮込みうどん同様、お腹の方もだいぶ満たされた
 今回の研修でした。
今回の研修でした。今回の研修会では、その分野の第一人者とも言える先生のお話を拝聴し、改めて勉強になった次第です。
特に印象に残っているのが、「型」(作法)を通してその教えを会得していく宗門旧来のアプローチのあり方……。
ご存知の様に宗門では、「型」(作法)を通して教えを理解していく「行の実践」を重視しております。
その姿勢が、時に「思考の停止」といった批判をも招き、とかく現代社会における価値観からも乖離していると見なされ、最近は宗侶の立場であっても作法の軽視を誘導し兼ねない不用意な発言が目立つ様になってきました。
確かに、作法の意味を確認していく作業は必要でありますが、その「意味を確認していく作業」のみを重視し、結果的に作法の形骸化を招いていたのでは本末転倒でしかありません。決して祖意に倣うあり方とは言えないでしょう。
「教え」を学ぶ過程において、型を共有する事により得られる経験値というのは、宗門にとって生命線でもあると感じます。
その「型を共有する」行為自体は、喩えるなら聴きたいラジオ番組がある場合に、そのチャンネルに周波数を合わせる作業とも似ています。
時代と空間を超えて、祖師方と同じ「教え」を共有したい場合には、我々の方から祖師方と同じチャンネルに周波数を合わせる必要が出てくるでしょう。
それが「型」(作法)の共有であり、「出家」という祖師が選択してきた生き方(型)が尊ばれる所以かとも思われます。
まさに
「ただわが身をも心をもはなちわすれて、仏のいへになげいれて、仏のかたよりおこなはれて、これにしたがひもてゆくとき …(中略)…… 生死をはなれ、仏となる」(『正法眼蔵』別輯・「生死」巻)
という世界の現成であろうかと思われます。
まさしく、同じチャンネルに周波数を合わせる事により、我々は祖師方と同じ教え(チャンネル)を共有する事できるとも言えましょう。
その意味において、ここで言う「型」(作法)を重視する宗門の姿勢とは、決して学人に「思考の停止」を促すものではなく、法に触れる際の必要最低限度の条件として規定されるべきものなのだと思います。
宗門が一貫して「行」を重んじてきた理由はそこにあるものと思います。
當山の単頭和尚さまが取り上げた「型破り」の譬喩の如く、まさにその基本となる「型」の修得がなければ、「型破り」的な大物ぶりをいくら発揮しようとも、それは単なる「型なし」でしかないという事です。
「自由」と「我が儘」を履き違える悪しき誤解も、結局のところ、この「型なし」と同じ理屈が当てはまるものと考えます。「責任」が伴って初めて保障されるべき「自由」の権利は、「責任」なくして行使していたのでは単なる「我が儘」でしかないという事です。
話を元に戻して名古屋での研修会の話......。
その「型」(作法)の重要性を改めて確認した上で、今回はある宗門伝来の古儀について学びました。
その古儀には細かいルールが一つひとつ定められており、そのルールを守りながら行じていく事が、しいては教えの理解にも繋がるとご指導を賜りました。
おぼろげながらも、時に「細かい作法よりも教えの理解が重要である」と考えていた自分の浅はかさを痛感させられた次第です

「作法、是れ宗旨」
宗門の教えには古き良き伝統と美学が残っていると誇りに思えた1日でした

P.S.
良かったらクリックして応援して下さい♪











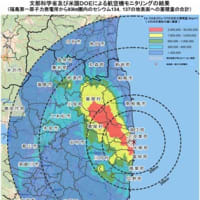

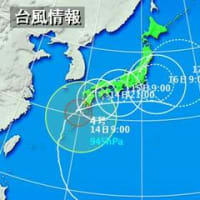


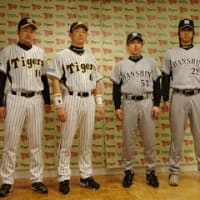
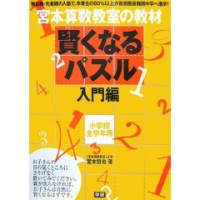

意味と問うて、自己流に取捨改変するよりも、忠実に伝承していくことも大切なことだろうと思っています。
いったん型を崩してしまえば、元には戻りませんから。
「作法是宗旨」を肝に銘じたいと思います。
「型」じけない......ですか
さすがにそこまでは思いつきませんでした
あっぱれです
忠実に「型」を伝承していくこと、それ自体が尊いことなのかもしれません。また、忠実に伝承されてきた歴史そのものが「尊さ」の証なのでしょうか。
「いったん型を崩してしまえば元には戻らない」という言葉は重く受け止めなければならないと思います。
時代に合わせて新しい形(型)を摸索していく場合も、まず「型」の確認が不可欠でありましょう。とくに伝統を重んじる世界ではそうだと思います。
高祖道元禅師750回大遠忌におけるスローガン、「慕古」(~ 振り返れば未来 ~)はまさにその意味で捉えなければならない言葉かと思いました。
未来を見据えた古(いにしえ)の意味を再確認すべきだと思います。