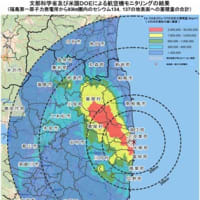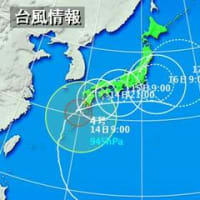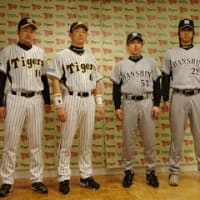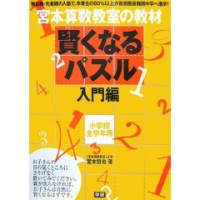拙ログでも度々取り上げてきた「いじめ」問題...。
さすがにもう良いかなと思っていた矢先、大変興味がそそられるブログを発見しましたので紹介をさせて頂きます。
 【恐山あれこれ日記】 : 「自分であるという困難」
【恐山あれこれ日記】 : 「自分であるという困難」
拙ログは、ネット上の仮想バーチャル僧堂「叢林@Net」の堂頭内寮である訳ですが、上に紹介したブログは當山の人権主事さん(非常勤)が管理人を務めるブログであります。
一応、個人的にお世話になった経緯があるので 、洒落
、洒落 として人権主事という配役をお勤め頂いている訳ですが、非常にご多忙な方なので、一応フリーリンクという位置付けで當山の配役單牌(リンク一覧)にも記載させて頂いております
として人権主事という配役をお勤め頂いている訳ですが、非常にご多忙な方なので、一応フリーリンクという位置付けで當山の配役單牌(リンク一覧)にも記載させて頂いております
早速、その内容を拝見していきたいと思います。
>私は、おそらくいじめや、あるいは差別という行為は、大変残念なことながら、完全に根絶することは困難だと思っています。もちろん、個々のいじめや差別は解消したり解決することは可能だと思いますし、しなければなりません。しかし、人間の行為としてのいじめや差別自体を完全に消滅させることは、まず無理だと考えています。なぜなら、それらは「自分」という形式でこの世界に存在せざるをえない人間の根源に喰い込んでいると考えるからです。
人間の行為としてのいじめや差別自体を完全に消滅させることは無理である―。
悲しいかな、我々はまずこの厳しい現実に立って、この問題について考えていかなければならないと思います。
いじめに対する厳罰化を設ける事で解決する部分もあるのでしょうが、それはあくまでも応急処置的な対処法でしかなく、問題の根本解決には到らない部分があるものと確かに感じます。
究極、いじめの発生件数は強制力を以て押さえる事はできても、その原因はただ地下に潜るだけの事でありましょう。
>この問題を考えるとき、私がどうしてもこだわってしまうのは、「自分は自分でありたくて自分であるのではない」という事実です。根源的に、私たちは「自分であること」を他者から負わされ、課せられたのです。物理的に私たちは「生まれた」のではなく、「産み出された」のであり、命名という一方的な行為で、「自分」という刻印を押された存在なのです。
これは実際に師の教えを乞うた学人や、師の著書を拝読した経験がある方々は理解し易い言葉かと思われます。
我々が「自分」という存在であるためには、畢竟、他者の力を借りないと存在し得ない現実…。仏教が「諸行無常」、「諸法無我」を標榜する意味がそこにあるとも感じました。仏教的に非常に理に適った説き方だとも感じました。
特に、
>根源的に、私たちは「自分であること」を他者から負わされ、課せられたのです。
という部分に、師の仏教観が顕れているものと感じます。
仏教はある意味、縁起現成の世界を説く教えですので、「他者から負わされ、課せられた」事で成り立つ自己の現成があるものと感じます。
>私たちが「自分であること」を決意とともに引く受けたのではなく、「自分にさせられた」結果「自分である」存在なら、ここにはすでに原理的な存在の困難、生き難さがあるはずでしょう。
この「生き難さ」という部分は、いわゆる「本当の自分」という言葉に象徴される、「現状の自分」と「そうでない自分」とのギャップにも似た感覚があるのでしょうか。
以前人権主事さんが、上梓された御本の中で「自分探しの旅」というテーマで同じ様な事を論じておられたのを想い出しました。
この「生き難さ」から目を背ける事ができない人間に、仏教という教えは非常に有効、且つ機能的に展開し得るのだと思います。師は常々そう仰っていた様に記憶もしております。
>この存在に耐え、これを引き受けるには、そうするに値する何らかの理由、根拠が必要とされるでしょう。それが「自分であること」を支える力なのです。
ここで言う「何らかの理由、根拠」が「自分であることを支える力」であるならば、いわゆるここで言う「自分」とは、あくまでも「何らかの理由、根拠」により仮設されたものでしかないという事なのでしょう。
それが、仏教で説くところの「無常」・「無我」にも通じてくる部分かと感じております。
それゆえ、「他者との関わり」抜きにして「自己存在」は成り立ち得ないと考えられるのではないでしょうか。
>「自分であること」は最初からこの力をめぐる闘争に投げ込まれているのです。このとき、いつかどこかで、「自分であること」それ自体、ただそれだけのことを、無条件で他者から肯定される経験をしていないと、闘争に踏み込む基礎体力が備給されないと、私は思うのです。
自分という存在は他者との関係性によってのみ生成される―。
その理解が正しいかどうかは解りませんが、その現実から目を逸らさず、真っ正面から向き合って生きていく姿勢、またその生き方を貫く覚悟を決める事が、仏教的生き方の起点でもあると個人的に感じております。
それはまさしく、師の言葉を借りれば「闘争」そのものであり、この混沌とした現実社会に身を曝して生きていく為には、その「闘争に踏み込む基礎体力の備給」が必要になってくるのだと感じました。
>「自分」を開始したのが自分ではない以上、その肯定も他者からされるしかありません。もしその肯定が不十分だと、何らかのもので代償するしかないでしょう。
私なりに師の言葉を解釈すると、ここで言う「代償」が歪んだ形で表れた場合、いじめという排除の論理が具現化してくるのだと理解しています。
それはある意味、世の現実であり、必定の理とも言えましょう。
師が冒頭に述べた
>私は、おそらくいじめや、あるいは差別という行為は、大変残念なことながら、完全に根絶することは困難だと思っています。もちろん、個々のいじめや差別は解消したり解決することは可能だと思いますし、しなければなりません。しかし、人間の行為としてのいじめや差別自体を完全に消滅させることは、まず無理だと考えています。
という言葉の意味は、いじめ撲滅に向けての努力を放棄するものではなく、その社会構造を冷静に分析しているだけのものと感じます。
>私は、いまの「いじめ」問題の経緯をみていると、思春期という、ようやく「自分であること」の闘争に踏み込んできた世代の苦難を思わざるをえません。「自分」という苦役を、他者の排除で代償するしかない孤独を感じざるを得ません。
非常に共感できる部分であります。
やはり問題なのは、思春期の子ども達は「闘争」の真っ直中に身を置くゆえ、時に「他者への排除」を以てでしか自分という存在を自覚できない場合があるのだと思います(また、それを以てでしか表現し得ないとでも言うのでしょうか...)。
それと、情報収集をする際のインフラ(インターネット等)が急激に整備され、目に入ってくる情報があまりにも多くなってきた事も要因の一つかと思われます。
「闘争」真っ最中の彼らにとって、その「闘争」と同時進行で情報を取捨選択していく事が、非常に困難なのだと感じています。
いじめ問題解決に向けての一つのアプローチとして、改めて教育・躾という問題を真剣に考えるのであれば、多少の窮屈さはあっても、秩序の明確化を謳った保守的な教育方針への回帰というのも、一つの選択肢として挙げられるかと思います。
>「いじめ」も「差別」も、それをする側は、必ず自分の行為を正当化する理屈、理屈にならない理屈を準備し、相手に「いじめられる理由」「差別される理由」があると主張します。なぜか。なぜ理屈を主張するのか。それはこれが、根本において自己正当化、すなわち根拠をめぐる闘争だからではないでしょうか。
師の教えを乞うた修行時代がとても懐かしく想い出されます。
道心無きままに安居生活に突入した修行僧は、それこそ気楽な学生生活と一変した叢林という生活環境の中で、新たな「闘争」の機会と向き合う事となります。
そこに、似た様な問題が発生する場合が少なくないと思います。
有無も言わせず身を投じた叢林という新しい環境において、頑ななまでに「根拠をめぐる闘争」と向き合う事となり、それが道心の発露に繋がる場合もあれば、現代社会同様、「いじめられる理由」・「差別される理由」を無作為に相手に押し付ける弊害をも生み出し兼ねません。
それをどう乗り越えていくかが、今後の課題になるものと思われます。
>「いじめ」や「差別」を処罰し禁止するということも、無論必要な対策でしょう。しかし、より深刻なのは、「自分である」という、苦役ともいうべき困難に立ち向かう力をどう養うかを考えることだと思うのです。そのとき必要なのは、他者の「愛情」ではなく、この困難に対する共感であり、この苦役へのいたわりであり、そしてそれに立ち向かうものに対する敬意ではないでしょうか。
今の教育の現場に最も必要とされる価値観なのではないでしょうか。
>ならば、それを供給できる余裕があるのは、ある程度この闘争を経験してきた世代、つまり「大人」でしょう。すなわち、私は、当面、「いじめ」の問題に対処する手段として、学校をなるべく大きく開いて、なるべく多様な大人が学校には入り込み、関与できるようにすることが有効だと思います。
現在の教育現場に対する具体的な一つの提言であろうかと思われます。
それこそ、昔は地域社会ぐるみで犯罪やいじめの防止に努めようとする空気があったものです。
学校教育や家庭の躾一つとってみても、地域社会という共同体で担い合う部分が今よりも多かった様な気もします。
それが許されなくなってしまった原因は一体何なのか―?
課題は多いものと思われますが、その意味も含めて「秩序の明確化を謳った保守的な教育方針への回帰」が必要かと感じています。
>そしてその大人に試行錯誤の自由を認めるべきでしょう。「正しい生き方」「正しい人生」を知っている大人など誰もいません。教育するということは、常に冒険なのです。間違えることを前提に、間違ったときの対策を考えながら、大人は「自分であること」の困難を若い世代と共にし、実例を示したらどうだろうと、私は思うのです。
このアイデアが実際の教育現場で導入される様になったら、荒廃した教育現場の現状も少しは改善されるのではないでしょうか。
拙ログでも度々取り上げてきた、教育現場における官僚的ヒエラルキー体質の弊害(極端とも言えるいじめ問題の隠蔽体質、不祥事数が直接教員の出世に響く能力評価基準...etc.)なども、教育現場に蔓延してきた閉鎖主義的体質の代償かとも思われます。
ここまで来ると、もう国の威厳や行政の面子などと言ってられない現状かとも思われます。それだけこの問題は切迫した状況下にあるのではないでしょうか。
ここは師の仰る様に「学校をなるべく大きく開いて、なるべく多様な大人が学校に入り込み、関与できるようにする」大胆な意識・制度改革が必要なのだと感じます。
教育問題のみならず、国家レベルで抱える全ての諸問題に対しても、師の仰る「試行錯誤の自由」を認める器量が求められているものと感じます。
久々の人権主事さんの熱い語りに、ネット上を介して感銘を受ける事ができました。合掌
 當山人権主事さん(非常勤)の提唱録はこちらから
當山人権主事さん(非常勤)の提唱録はこちらから




P.S.
良かったらクリックして応援して下さい♪

 &
& 
さすがにもう良いかなと思っていた矢先、大変興味がそそられるブログを発見しましたので紹介をさせて頂きます。
 【恐山あれこれ日記】 : 「自分であるという困難」
【恐山あれこれ日記】 : 「自分であるという困難」拙ログは、ネット上の仮想バーチャル僧堂「叢林@Net」の堂頭内寮である訳ですが、上に紹介したブログは當山の人権主事さん(非常勤)が管理人を務めるブログであります。
一応、個人的にお世話になった経緯があるので
 、洒落
、洒落 として人権主事という配役をお勤め頂いている訳ですが、非常にご多忙な方なので、一応フリーリンクという位置付けで當山の配役單牌(リンク一覧)にも記載させて頂いております
として人権主事という配役をお勤め頂いている訳ですが、非常にご多忙な方なので、一応フリーリンクという位置付けで當山の配役單牌(リンク一覧)にも記載させて頂いております
早速、その内容を拝見していきたいと思います。
>私は、おそらくいじめや、あるいは差別という行為は、大変残念なことながら、完全に根絶することは困難だと思っています。もちろん、個々のいじめや差別は解消したり解決することは可能だと思いますし、しなければなりません。しかし、人間の行為としてのいじめや差別自体を完全に消滅させることは、まず無理だと考えています。なぜなら、それらは「自分」という形式でこの世界に存在せざるをえない人間の根源に喰い込んでいると考えるからです。
人間の行為としてのいじめや差別自体を完全に消滅させることは無理である―。
悲しいかな、我々はまずこの厳しい現実に立って、この問題について考えていかなければならないと思います。
いじめに対する厳罰化を設ける事で解決する部分もあるのでしょうが、それはあくまでも応急処置的な対処法でしかなく、問題の根本解決には到らない部分があるものと確かに感じます。
究極、いじめの発生件数は強制力を以て押さえる事はできても、その原因はただ地下に潜るだけの事でありましょう。
>この問題を考えるとき、私がどうしてもこだわってしまうのは、「自分は自分でありたくて自分であるのではない」という事実です。根源的に、私たちは「自分であること」を他者から負わされ、課せられたのです。物理的に私たちは「生まれた」のではなく、「産み出された」のであり、命名という一方的な行為で、「自分」という刻印を押された存在なのです。
これは実際に師の教えを乞うた学人や、師の著書を拝読した経験がある方々は理解し易い言葉かと思われます。
我々が「自分」という存在であるためには、畢竟、他者の力を借りないと存在し得ない現実…。仏教が「諸行無常」、「諸法無我」を標榜する意味がそこにあるとも感じました。仏教的に非常に理に適った説き方だとも感じました。
特に、
>根源的に、私たちは「自分であること」を他者から負わされ、課せられたのです。
という部分に、師の仏教観が顕れているものと感じます。
仏教はある意味、縁起現成の世界を説く教えですので、「他者から負わされ、課せられた」事で成り立つ自己の現成があるものと感じます。
>私たちが「自分であること」を決意とともに引く受けたのではなく、「自分にさせられた」結果「自分である」存在なら、ここにはすでに原理的な存在の困難、生き難さがあるはずでしょう。
この「生き難さ」という部分は、いわゆる「本当の自分」という言葉に象徴される、「現状の自分」と「そうでない自分」とのギャップにも似た感覚があるのでしょうか。
以前人権主事さんが、上梓された御本の中で「自分探しの旅」というテーマで同じ様な事を論じておられたのを想い出しました。
この「生き難さ」から目を背ける事ができない人間に、仏教という教えは非常に有効、且つ機能的に展開し得るのだと思います。師は常々そう仰っていた様に記憶もしております。
>この存在に耐え、これを引き受けるには、そうするに値する何らかの理由、根拠が必要とされるでしょう。それが「自分であること」を支える力なのです。
ここで言う「何らかの理由、根拠」が「自分であることを支える力」であるならば、いわゆるここで言う「自分」とは、あくまでも「何らかの理由、根拠」により仮設されたものでしかないという事なのでしょう。
それが、仏教で説くところの「無常」・「無我」にも通じてくる部分かと感じております。
それゆえ、「他者との関わり」抜きにして「自己存在」は成り立ち得ないと考えられるのではないでしょうか。
>「自分であること」は最初からこの力をめぐる闘争に投げ込まれているのです。このとき、いつかどこかで、「自分であること」それ自体、ただそれだけのことを、無条件で他者から肯定される経験をしていないと、闘争に踏み込む基礎体力が備給されないと、私は思うのです。
自分という存在は他者との関係性によってのみ生成される―。
その理解が正しいかどうかは解りませんが、その現実から目を逸らさず、真っ正面から向き合って生きていく姿勢、またその生き方を貫く覚悟を決める事が、仏教的生き方の起点でもあると個人的に感じております。
それはまさしく、師の言葉を借りれば「闘争」そのものであり、この混沌とした現実社会に身を曝して生きていく為には、その「闘争に踏み込む基礎体力の備給」が必要になってくるのだと感じました。
>「自分」を開始したのが自分ではない以上、その肯定も他者からされるしかありません。もしその肯定が不十分だと、何らかのもので代償するしかないでしょう。
私なりに師の言葉を解釈すると、ここで言う「代償」が歪んだ形で表れた場合、いじめという排除の論理が具現化してくるのだと理解しています。
それはある意味、世の現実であり、必定の理とも言えましょう。
師が冒頭に述べた
>私は、おそらくいじめや、あるいは差別という行為は、大変残念なことながら、完全に根絶することは困難だと思っています。もちろん、個々のいじめや差別は解消したり解決することは可能だと思いますし、しなければなりません。しかし、人間の行為としてのいじめや差別自体を完全に消滅させることは、まず無理だと考えています。
という言葉の意味は、いじめ撲滅に向けての努力を放棄するものではなく、その社会構造を冷静に分析しているだけのものと感じます。
>私は、いまの「いじめ」問題の経緯をみていると、思春期という、ようやく「自分であること」の闘争に踏み込んできた世代の苦難を思わざるをえません。「自分」という苦役を、他者の排除で代償するしかない孤独を感じざるを得ません。
非常に共感できる部分であります。
やはり問題なのは、思春期の子ども達は「闘争」の真っ直中に身を置くゆえ、時に「他者への排除」を以てでしか自分という存在を自覚できない場合があるのだと思います(また、それを以てでしか表現し得ないとでも言うのでしょうか...)。
それと、情報収集をする際のインフラ(インターネット等)が急激に整備され、目に入ってくる情報があまりにも多くなってきた事も要因の一つかと思われます。
「闘争」真っ最中の彼らにとって、その「闘争」と同時進行で情報を取捨選択していく事が、非常に困難なのだと感じています。
いじめ問題解決に向けての一つのアプローチとして、改めて教育・躾という問題を真剣に考えるのであれば、多少の窮屈さはあっても、秩序の明確化を謳った保守的な教育方針への回帰というのも、一つの選択肢として挙げられるかと思います。
>「いじめ」も「差別」も、それをする側は、必ず自分の行為を正当化する理屈、理屈にならない理屈を準備し、相手に「いじめられる理由」「差別される理由」があると主張します。なぜか。なぜ理屈を主張するのか。それはこれが、根本において自己正当化、すなわち根拠をめぐる闘争だからではないでしょうか。
師の教えを乞うた修行時代がとても懐かしく想い出されます。
道心無きままに安居生活に突入した修行僧は、それこそ気楽な学生生活と一変した叢林という生活環境の中で、新たな「闘争」の機会と向き合う事となります。
そこに、似た様な問題が発生する場合が少なくないと思います。
有無も言わせず身を投じた叢林という新しい環境において、頑ななまでに「根拠をめぐる闘争」と向き合う事となり、それが道心の発露に繋がる場合もあれば、現代社会同様、「いじめられる理由」・「差別される理由」を無作為に相手に押し付ける弊害をも生み出し兼ねません。
それをどう乗り越えていくかが、今後の課題になるものと思われます。
>「いじめ」や「差別」を処罰し禁止するということも、無論必要な対策でしょう。しかし、より深刻なのは、「自分である」という、苦役ともいうべき困難に立ち向かう力をどう養うかを考えることだと思うのです。そのとき必要なのは、他者の「愛情」ではなく、この困難に対する共感であり、この苦役へのいたわりであり、そしてそれに立ち向かうものに対する敬意ではないでしょうか。
今の教育の現場に最も必要とされる価値観なのではないでしょうか。
>ならば、それを供給できる余裕があるのは、ある程度この闘争を経験してきた世代、つまり「大人」でしょう。すなわち、私は、当面、「いじめ」の問題に対処する手段として、学校をなるべく大きく開いて、なるべく多様な大人が学校には入り込み、関与できるようにすることが有効だと思います。
現在の教育現場に対する具体的な一つの提言であろうかと思われます。
それこそ、昔は地域社会ぐるみで犯罪やいじめの防止に努めようとする空気があったものです。
学校教育や家庭の躾一つとってみても、地域社会という共同体で担い合う部分が今よりも多かった様な気もします。
それが許されなくなってしまった原因は一体何なのか―?
課題は多いものと思われますが、その意味も含めて「秩序の明確化を謳った保守的な教育方針への回帰」が必要かと感じています。
>そしてその大人に試行錯誤の自由を認めるべきでしょう。「正しい生き方」「正しい人生」を知っている大人など誰もいません。教育するということは、常に冒険なのです。間違えることを前提に、間違ったときの対策を考えながら、大人は「自分であること」の困難を若い世代と共にし、実例を示したらどうだろうと、私は思うのです。
このアイデアが実際の教育現場で導入される様になったら、荒廃した教育現場の現状も少しは改善されるのではないでしょうか。
拙ログでも度々取り上げてきた、教育現場における官僚的ヒエラルキー体質の弊害(極端とも言えるいじめ問題の隠蔽体質、不祥事数が直接教員の出世に響く能力評価基準...etc.)なども、教育現場に蔓延してきた閉鎖主義的体質の代償かとも思われます。
ここまで来ると、もう国の威厳や行政の面子などと言ってられない現状かとも思われます。それだけこの問題は切迫した状況下にあるのではないでしょうか。
ここは師の仰る様に「学校をなるべく大きく開いて、なるべく多様な大人が学校に入り込み、関与できるようにする」大胆な意識・制度改革が必要なのだと感じます。
教育問題のみならず、国家レベルで抱える全ての諸問題に対しても、師の仰る「試行錯誤の自由」を認める器量が求められているものと感じます。
久々の人権主事さんの熱い語りに、ネット上を介して感銘を受ける事ができました。合掌
 當山人権主事さん(非常勤)の提唱録はこちらから
當山人権主事さん(非常勤)の提唱録はこちらから




P.S.
良かったらクリックして応援して下さい♪