新年明けましておめでとうございます。
すっかり更新が途絶えてしまって本当にごめんなさい。
今日はただちょっと新年のあいさつを書きたくって。
今年もどうぞよろしくお願いします。
早いもので、ここでの生活も後半年。
ちょっと、今年の抱負を書いてみようと思います。
①セントルシアで未達成の目標を達成する。
いろいろありすぎて書ききれないけど、世界遺産の頂上で1泊キャンプ。
②日本に帰って逆カルチャショックを楽しむ。
人ごみとかみんなが日本語しゃべってるのとか電車とか
そんな非日常の生活を楽しみたいです。
③日本のおいしいものをたらふく食べる。
食べたいもの第1位あじの開き、第2位とんこつラーメン、第3位いかの塩辛
気がつくと意外と質素なものばかり。
ところで年末年始はと言えば、日本から友達が来て、
ちょっと海外へ行ってきました。
と、言ってもセントルシアも日本から見たら海外なんですが。
写真をちょこっと載せます。
プエルトリコ(アメリカ領)オールドサンファンの街並み
世界遺産の要塞.。大砲の玉。

プエルトリコを走る車のプレートも世界遺産の絵です。かわいいね。
ドミニカ共和国世界遺産の古い街並み これは泊まったホテル。
コロンブス!! カリブ地域で一番古いとされる教会

年越しの花火。広場のレストランから。
ドミニカ共和国のビール(おいしかった!)
1月2日に帰って来たのですが、セントルシアに到着したとき、
やたらホッとしたんです。
なんだかセントルシアが母国かのように思えてくる今日このごろです
回っている小学校の1つで、リコーダーのワークショップを開催しました
この学校にはピースコー(アメリカの協力隊)のベン君がいて、
バイオリンを弾ける彼は、この学校で毎週1回リコーダーを教えています
私も週1回、この学校に来て図工や音楽を教えているので、
仲のいい友達なのですが・・
私たち2人の悩みは
先生がリコーダーを吹けない
↓
先生が楽譜が読めない
↓
音楽の授業を教えられない
ということ。
そこで、放課後先生たちに教えてあげようということになったのです
打ち合わせ中

ワークショップの様子

ところで、どれくらい先生がリコーダーを吹けないというと
「全く 」
」
といったところです。
あんなにリズム感もいいし、ダンスもできるのに・・。
楽譜の読み方から、音符の長さ、リコーダーの持ち方などなど
基本からじっくり教えました
「うーん、難しいよぉ。指3本とも一緒に動いちゃうよ 」
」
「あ、できた 」(おばあちゃん先生も↓) ↓校長先生も超真剣
」(おばあちゃん先生も↓) ↓校長先生も超真剣


練習時間。みんな真剣

初めてリコーダーが弾けた喜びに
子どもみたいに目をきらきらさせていました
ところで、このワークショップで一つ新しいことを学びました
日本は「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」でしょ?
こちらは「C・D・E・F・G・A・B・C」なのです。
ちょっと気になって、『階名(音符の読み方)』について調べてみました。
日本ではもともと「ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・イ・ロ・ハ」だったんです (知ってた?)
(知ってた?)
今使ってる「ド・レ・ミ・ファ・ソ・・」音階はイタリア式のものを日本風にしたもの。
世界では一般的に「C・D・E・F・・・」のアメリカ式やドイツ式のものが使われているらしいです。
そう言えば、ギターのコードってアルファベットだもんね
ちょっと話がズレちゃいました
音階の読み方は違っても、同じ楽譜から同じ曲が流れてくるんだもんね。
音楽って国境を超えます



セントルシアに来てからの変化

・髪が伸びた
 (一度も切ってない。)
(一度も切ってない。)・焼けた
 (真っ黒)
(真っ黒)・太った
 (+○kg)
(+○kg)・精神的にも性格的にも、強くなった
 (良くも悪くも
(良くも悪くも )
)・ルシアンと喧嘩できるようになった

・現地語が話せるようになった

・友達や家族の温かさが身にしみるようになった

・仲のよかった友達がほとんど結婚、もしくは婚約した
 (10人以上!)
(10人以上!)・行く前に結婚した友達に、子どもができた
 (おめでとう
(おめでとう )
)きっと日本に帰ったら、友達の家族が増えてて、
覚えるの大変なんだろうなぁ(嬉しい悲鳴)
見た目の変化もあるけど、精神面でも、日本でも変化はたくさんありました

なんでもがむしゃらに活動していたこの1年。
危険や間違いを覚悟で、いろいろなことに挑戦したからこそ
学べたこともありました。
どちらかというと失敗の方が多かったかな

これからの1年はこの学んできたことをベースに
もっと成長していかなくっちゃって思います。
もう、ここでもお客さんの期間は終わり。
どしどし、ルシアン化して活動していきたいです。
「ルシアンと本気でぶつかり合うこと」が目標だったりします

本気でぶつかり合えたら、認められた証拠ですから

セントルシアでの1年間は1日1日がとてもゆっくりで、
幸せなことも辛いことも敏感に感じられます

そして、人の温かさを身にしみます。
人の温かさに国境はない。なんてね

支えてくれた多くの人たちへ
感謝しています。
ありがとう

今日は世界遺産のピトンにかかる虹をお届けします。
過去の算数部会の実績発表と、算数プロジェクトの提案

誰に頼まれたわけでなく、自分たちでお偉いさんの予約をとって自ら乗り込んでいきました

なぜこんなことをしたか

それは私でこの国の小学校隊員が、最後になるからです

過去たくさんの小学校隊員が積み重ねてきたものを、
誰にも引き継がずに、終わってしまうのは嫌だからです

そこで、ルシアに良いものを引き継いでもらおうと省庁のお偉いさんにプレゼンをしました

↓プレゼンの一部

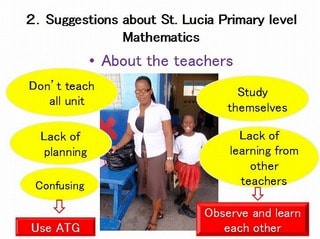
反応は・・・

二重丸

納得してくれ、プロジェクトを是非引き継ぎたいという強い意志を見せてくれました。
プレゼンして、よかったぁ

日本では、文部科学省にこんな若者がプロジェクトの提案をしに行くなんて
絶対にあり得ないことです。
しかし、ここは小さな国

自分で動かそうと思えば、国だって動かせちゃう。
できないことはない、と思わせてくれる国です

提案することは、意外に簡単なこと。
しかしその反面、簡単には動かないのがこの国

仕事に対しては、遅い、期限や約束が守られない、めんどくさい、お金がない。
とても、省庁としての責任感を感じることがありません

余談ですが、日本ほど、政治の賄賂や に対して厳しいん国はないんじゃないかと思います。
ここでは政治の汚職が容易に見られるからです

こういう点で、困難はまだまだ待ち受けています

さて、これからがハンドオーバーの本番

協力隊の腕の見せどころ。
ルシアにルシアなりのいいものを残していけたら嬉しいです。
この↓、ジャングル車
 に乗ってセントルシアの北にある無人のビーチへ。
に乗ってセントルシアの北にある無人のビーチへ。

もちろん、電気も水道もないところ

そこで今日はキャンプをしながら、ウミガメが海から上がってくるのを待ちます。
ところで、ウミガメの産卵について、ちょっと説明

ウミガメは産卵の時期になると、(ここでは3月~7月)
真夜中、産卵のため砂浜に上がってきます。
そして、砂浜に穴を掘り、目から涙を流しながら卵を産み落とします。
産卵を終えた後は、砂をかぶせて海に帰って行くのです。
今日は満月。見られるといいなぁ

 ←電気がないところは月明かりがこんなに明るい
←電気がないところは月明かりがこんなに明るい
そんな願いが届いたか、真夜中、大きなウミガメが砂浜に現る
 !
!で、でかい!1.5mくらいあるでしょうか。
そんな海ガメが一生懸命、後ろ足をスコップにして上手に穴を掘る掘る。
掘り終わると、卵をぽとぽとと穴に落としていきます。
触っていないけど、卵の殻は少し柔らかいみたい



100個程の卵を生んでいる最中、
顔をみてみました

そう、産卵の時ウミガメは涙を流すという話は本当かどうか確かめたくて。
そしたら、どうでしょう。
ほんとだ、泣いてる


なんで涙を流すのか、不思議で調べてみました

夢を壊すようですが、これは泣いているわけではなく、
体内の余分な塩分を濃い塩水として排出して体内の塩分調整を行うために、
常に分泌されているのだそうです

しかし、お産をしているこの海ガメの涙には、
嬉しさや苦しさや、いろんな感情が入っているような気がしました

だって、1時間も頑張ってたんだもん。
さて、こんなに産んだ卵ですが、無事に大きくなる亀はたったの5%ほどだけだそうです

後は、食べられてしまします。
今回産んだ卵も穴の中に水が入っていたため、
生存するのはほぼ無理だろうという話でした。
自然って本当に厳しい世界です

神秘的な世界をのぞかせてもらった日でした

最後に一緒に行ったピースコーの友達と




セントルシアに来て、一番悔しい思いをしたのが
大好きな友達の結婚式に出られなかったこと

今日は、私の小学校から高校まで一緒に過ごしてきた
幼馴染で大親友の「とんちゃん」の結婚式が地元でありました

友達だけじゃなくて先生までにもかわいいと評判だったとんちゃん。
花嫁姿は、さぞかしきれいだったんだろうな

旦那さんは私も知ってる高校時代のクラスメイト

3人でよくふざけ合ってよく遊んでたっけ。
その時はまさか2人がくっつくとは想像もしてなかったけど
10年後、再会した2人がくっついたと聞いて、
なんだか妙に納得しちゃいました。
大好きなトンちゃんの結婚式には絶対出るんだって決めてたのに、
まさか出られないなんて

私には遠くから想像することしかできませんでした。
自分で海外に住むっていう道を選んだわけだから
出席できなくて当たり前。
自分でも納得してるはずなのに、嬉しさ半分
 、さみしさ半分
、さみしさ半分
持っていた4年1組の子どもたちの卒業式もそう

友達の結婚式も今回1回きり。
自分はその場に出席することができません

自分のおばあちゃんや家族が病気になっても
すぐには会えないんだと思うと、
やはり距離を実感してしまいます。
自分の身に何かあったときも同じことです

そこまでしてでも来たかった協力隊なのか
そこまで覚悟してきたのか、
と聞かれれば、答えにつまりますが、
きっと答えは「イエス」です

そして決心をしてきたからこそ、今の充実した生活があるんだと思えます

とにかく、今日は何と言っても、おめでたい日

今日は駒ヶ根時代の友達ブチが作ってくれた
世界各国の子供の笑顔を載せた写真を送ります

とんちゃん、結婚本当におめでとう!
幸せになってね

ついにやってきました
というか、何とかこぎつけました

私たち小学校の隊員で構成される算数部会の1大行事。
JOCV Achievement Test
簡単に言うと、全国統一模試。
対象:セントルシア全土の6年生。
目的:6月に行われるカリブ海全域のコモンエントランス(中学受験)にむけて
自分のレベルを知り、弱点を克服するもの。
さて、試験の様子を学校に覗きに行ってみましょう
さすがみんな真剣です。
なぜか、紙を真横にして書く子が多い。不思議

問題はマークシート式50問50点、文章問題50点。
これはコモンエントランスに沿って作られています。
さて、この協力隊が作る全国模試は、現在大きな問題を抱えています
それはセントルシアにこれ以上小学校の隊員が派遣されず、
全国模試を作る人がいなくなりこの模試がなくなってしまうからです。
カリブ海の支援対象から「教育」の分野が外されたことに起因します。
ということは、私がセントルシアで小学校の隊員の最後の一人
生かすも殺すも私次第。
大きな責任がのしかかっています。
方法はいくつかあります
・小学校の協力隊員を頼んで派遣してもらう。
・短期派遣隊員でつないでいく。
・セントルシア人に良さを知ってもらって、協力してもらい、いずれは引き継ぐ。
・諦める
みなさんはどの方法が良いと思いますか ?
?
答えるまでもないですね。
これからも、めんどくさがり屋のルシアンを相手に納得してもらえるように奮闘します
今日は日曜日
よし!山登りに行こう!
ラスタマンのクリバーに誘われて、
スフレにある山を2つ登ってきました
私の街スフレは山と海に囲まれています。
山の一つに世界遺産 があるのですが
があるのですが
今日はその反対側の山に行ってきました。
頂上になるにつれて、道なんてあってもんじゃありません。
牛も横から応援してます


おおきなナイフ(写真右に持ってるの見えるかな?)で道をかきわけると
なんとも素晴らしい景色が待っていました


上から見る私の街スフレ。まるで地図みたい。
友達だけが知ってるとっておきのビューポイント
さて、これは、何でしょう?
正解は、ナツメグの実。
自然の恵みは、そこらじゅうにいっぱい
のどが乾いたら、道端に流れ落ちてくる自然の水をいただく。
地元の人も水を汲みに来るほど、きれいで冷たくて、まぁまぁおいしい。
ところで、この友達はなんでこんなに山のことを知っているのか
そうです、電気 も水道
も水道 もない
もない
本当の山奥に一人で何か月も住んでいました。
山で野菜を育て、川でお風呂、日の出とともに起き、日の入りとともに寝る
いわば自給自足の生活です。
そしてそんな生活はラスタの宗教に基づいているんです


大自然に囲まれ、大地に根付いたシンプルな生活
人間って本当はこうやって生きてきたんです。
今の日本じゃ、お金や周りの物から切り離された生活は
もう、考えられません
しかしながら、発展と共に、得てきたものはたくさんあると思います。
生活が住みよくなったり、便利になったり
いいことだけど、その代償に大自然の素晴らしさや、
小さなものや命を大事にする心や
そんなものが忘れ去られている気もします
ここにいると、人間って、なんてシンプルに生きられるんだろうって実感します
『生きる』ということは、大変なことだけど
『食べる 』、『寝る
』、『寝る 』、『働く
』、『働く 』
』
実は結構、シンプルなことなんだろうなぁ。
話がだいぶずれました。
そうそうこの山登りで、地元の人もなかなか出会えない、
野生の国鳥、『パロット』に何匹も出会いました。
カラフル な羽をはばたかせ、きれいな鳴き声
な羽をはばたかせ、きれいな鳴き声 で飛んでいく姿は、
で飛んでいく姿は、
まさにこの国の国鳥にふさわしい優雅さでした
今日は久しぶりに暇な休日。
よし!何かに初挑戦しよう
というわけで、朝市へ行ってまるごと1匹マグロを購入

そうです、刺身が食べたくなったんです。
セントルシアの魚は決して安全ではありません・・
でも、きっとできないことはない。きっと大丈夫。お腹も丈夫だし
先輩やネットからさばき方を研究し、いざ!
でかい・・『まな板の上の鯉』ならぬ『まな板の上のマグロ』。
大きな目が、こちらを見てる気がする 。う~~
。う~~
↓スタート! 頭と内臓をとって(血が!)↓三枚におろし・・ ↓なんとか完成! 



包丁も悪いし、初めて自分でさばくので途中からぐちゃぐちゃ
身も、皮や骨に残りまくり。
でも、ちゃんとスプーンですくってネギトロへ
頭ももったいないので煮込みへ (カマ焼き風?!)
(カマ焼き風?!)
でも途中から、魚の目からなんか
鼻水のようなものがドロって出てきて・・ひぃ~
取り出そうと頭を持ち上げたらすべって、鍋へバシャン
服に汁が飛び散るわ、つついてる内に目の玉がとれちゃうわ・・・
最終的にグロテスクな姿に
でも、味はしっかりしみ込んだ、よし!
そんなこんなで、1匹からこんなに料理ができました★
↓ネギトロ丼とおつまみ ↓カマ煮込み(グロテスク・・) ↓マグロの漬け丼 


他にも、マグロの竜田揚げ、マグロのチャーハンなどなど。
ん~おいしい

きっと以前の私だったら、気持ち悪くてできなかったでしょう
さばきながら、小学校の時にやった
「フナの解剖」を思い出していましたもん。
でも、不思議。
「気持ち悪い」という感情より「食べたい」という感情の方が勝っていたんですね。
なんなくできました
ここに来て、生き物からもらう食べ物に対して
とても受容的になりました。
というか、何が起きても気持ち悪いと思わなくなってきました
豚にしても鳥にしても魚にしても野菜にしても、
本来の姿から口元に入るまでの過程を、セントルシア人は自分たちで行います。
日本のスーパーにならぶ食品は、新鮮、安全、便利
素晴らしいと思います。
しかしその反面、本来の姿を見られない、もしくは知らないということは
ある意味こわいと思いました。
自分の食べてるものが、どのようにしてできてくるのか。
命をもらっていることに、感謝の気持ちを本当に持てるのか。
人間は生き物からいつも命をもらわなければ生きていけません。
だからこそ、食べ物が食べられることに、感謝の心を持ち続けたいですね
さて、この初体験。とってもおいしかったです
数時間たった今、お腹の動きがなんかおかしい。
あ、ヤバい。明日健康診断の、検便を提出するんだった・・
悪い結果が出ませんように

この日もまた・・・
同僚は仕事が手につきません

ピースコーの友達はもちろん出勤せず。
すぐ隣にある学校の先生は、事務所(教育委員会)に子どもたちを連れてきて、
みんなでテレビに釘づけ


そこにここの教育長が来て、「こら、お前ら、学校さぼって何してるんだ。」
と、言うのかと思ったら、
「今日は歴史的な日だ。」と、一緒になってテレビに釘づけ

近所の家家から聞こえてくるのは、どでかいテレビの演説の音

見事にみんな、同じ番組を見ている。
よく見ると、いいおじさんがテレビを見ながら泣いてるじゃあありませんか

お酒を片手に・・・

こんなにルシアンを夢中
 にさせた、オバマ大統領
にさせた、オバマ大統領
アメリカの盛り上がりをテレビで見てると、
この日がどのくらい歴史的な日だったかということが分かります

さて、これを機会にルシアンの意外な意見を聞きました

オバマ大統領は世界中にいるピースコー(協力隊)の数を、2倍に増やす計画。
多くのルシアンはそれに喜んでいるんですが、彼はそうではありませんでした

なぜか
 ?
?セントルシアは長い間、イギリスやフランスの植民地でした

彼らは自分たちの文化を持つことを許されず、奴隷として生きてきました。
それが急に独立。
独立というのは、自分たちの国を自分たちの力で運営していくこと。
しかし教養も文化もほとんどなかったここの人たちは、他国の援助が必要でした

今では、食べ物、電化製品、車、何から何まで他の国に頼らないと生きられません。
国の観光地の土地なんかほとんど、白人ホテルオーナーに
知らない間に多くが売られていきました。
だから観光業がさかんな割に、セントルシアの人々にはお金が落ちません

セントルシアは、自分の足で立ち上がれなくなってきているのです

そこで、またさらなる援助。
彼がそれを素直に喜べないのも、納得でした。
彼は、本来の『セントルシアのあるべき姿』を見ているような気がします

セントルシアの中でもこんな意見を持っている人は、少数派だと思います

彼はルシアのことだけじゃなくて、世界や日本のこともよく知っていました。
オバマ氏の就任について、周りがこんだけ盛り上がってるのに、
彼は、少し離れたところから物事をとらえているような気がしました。
今見ている現実の世界は、全てじゃない

みんなの生活を思い返してみてください

私は、日本では日本のテレビばかり見ていました。
そしてその情報や意見に沿うように、自分の考えもできあがっていたんだと思います。
メディアに踊らされていたんだと、今さら気付かされます

もっと広い目で、世界を見なくては本質が見えてこない

たくさんのところから情報を得て、考えて、自分の意見を持つ。
簡単なことではありません

自分を信じないとできないことです

でも、すごくすごく大事なことだと思いました。
話が長くなっちゃって、すみません

オバマ大統領がこれから何をするのか、誰にもまだわかりません。
ただ、たくさんの人に希望の光を与えてくれていることは確かです
















