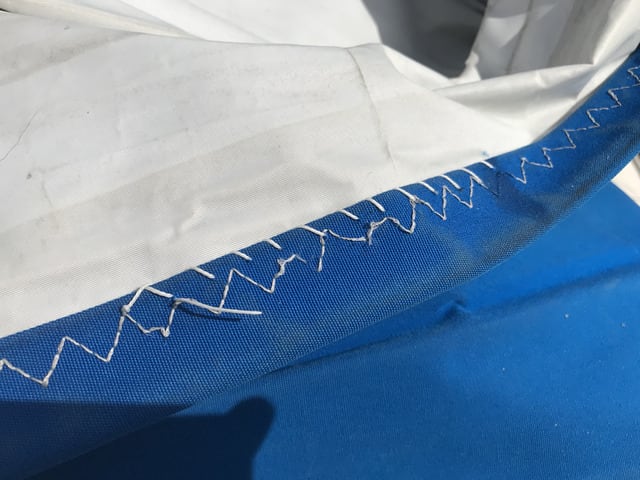近年、魚が獲れなくなったという話はしばしば聞く話です。
この原因は、海水温上昇とか乱獲などが原因だと推測されてますが、瀬戸内海や東京湾、伊勢湾などの閉鎖性水域においては海水の「貧栄養化」にあるのではないかという説があるのだそうです。
海の「富栄養化」という言葉は聞いたことがありますが、「貧栄養化」という言葉は私にとっては初耳です。
「富栄養化」とは、水中に溶けている栄養塩(窒素、リン等)が多すぎる状態のことだそうで、日本では高度成長期に、栄養塩を多く含んだ工場排水や生活排水が大量に流れ込み、赤潮の発生などの海洋汚染がすすみましたね。
下水施設の高度処理化等の対策がすすんだ結果起きてきたのが「富栄養化」の反対の「貧栄養化」なのだそうです。
「貧栄養化」は水中に溶けている栄養塩(窒素、リン等)が少なすぎるため、生物の生産性が低くなることだそうです。漁獲量の低下とか海苔の品質低下(色落ち)などの現象は「貧栄養化」の影響なのではないかというのです。
そのため、工場や下水処理場の水質基準を緩和する動きさえあるそうです。

そういえば、牡蠣の養殖場は、河口部のミネラル分を多く含む水質が重要とのことで、要するにキレイ過ぎる海は牡蠣の養殖に不向きということです。

じゃあ、海は適度に汚れていたほうが良いのか?・・・・・んな訳ないよね。

以上の貧栄養化の話は、アメリカのように汚水をリザーブタンクに貯めておいてマリーナのバキューム施設で処理する方式ではなく、排水パイプの先がダイレクトに海である日本のマリントイレユーザーとしては、少しだけ罪悪感が薄らぐ話でした。

参考にしたサイト→ココ
水質基準緩和に関する記事→ココ
以前書いたマリントイレの話→ココ