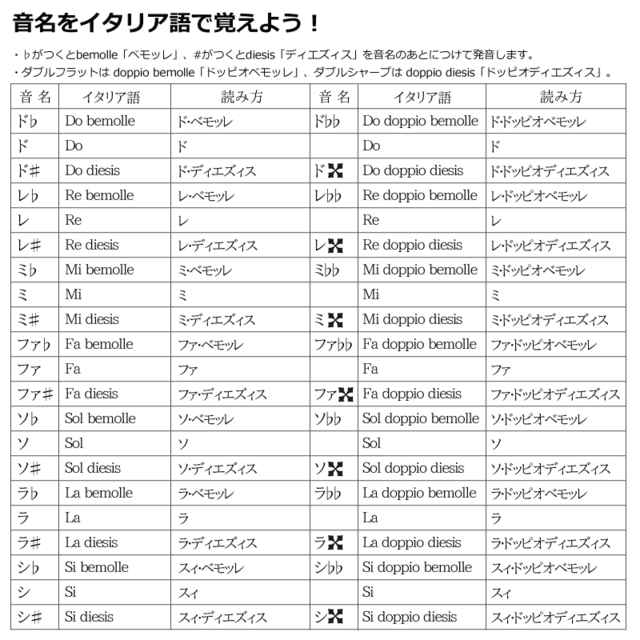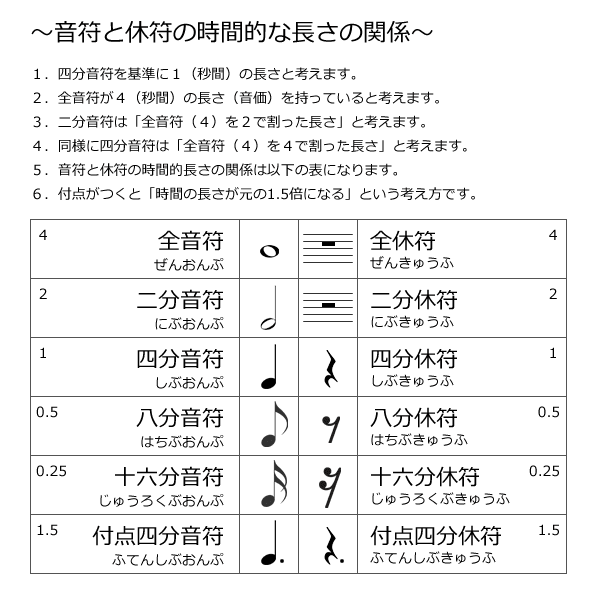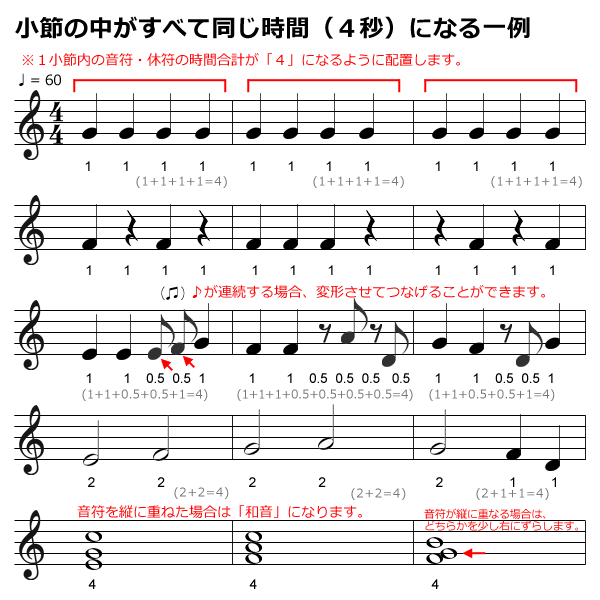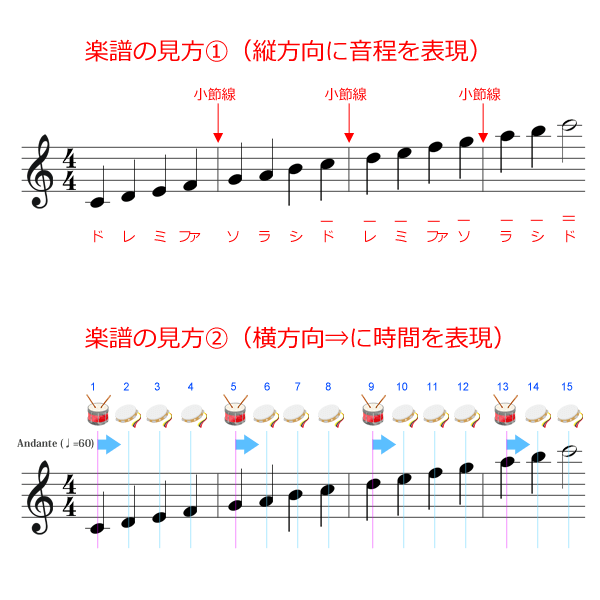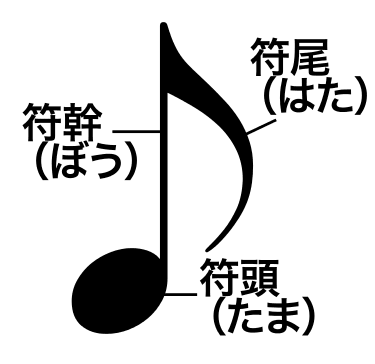例えば見たこともない楽譜、聴いたこともない曲の楽譜をぱっと見たとき(つまり初見時ですね!)、プロ音楽家にはその楽譜がどう見えているのか、みたいなお話を少しさせていただこうと思います。

画像の転載元はこちら⇒優雅にヴァイオリンを弾く女性の写真を無料ダウンロード(フリー素材) - ぱくたそ (pakutaso.com)
クラシック音楽の場合は、過去に作曲され、多くの音楽家達がすでに演奏していることもあって、たとえ自分が初めて見る楽譜だとしても「聴いたことない曲」であることは稀です。たとえ聴いたことがなかったとしても、その曲の音源を探せば出てくる可能性はとても高いのですが、実際のプロ音楽家の演奏現場では、聴いたことのない曲の楽譜(新譜)を渡される局面というのは結構あります。
例えば、スタジオ入りして「はい、これ弾いてね(または歌ってね)」と渡される楽譜は大概未発表曲であり、これから世に出る予定のものであり、まだ誰も演奏したことがない曲の場合がほとんどです。そんな楽譜を見て、30分後にはサラサラと弾き(または歌い)、高クオリティ演奏を実現させてクライアントを満足させなければなりません。
まぁプロなんだから、そのくらいできて当然でしょう?と思うかもしれませんが、実はそんなことないのです。プロだって初めて見る楽譜には多少の恐怖を覚えるものです。
プロが最初に楽譜を見る時、まず「その曲は自分のスキル範囲で対応可能かどうか?」という視点で見ています。曲頭から最後までをざっと眺めて難しい部分がないか、運指に無理がありそうなフレーズは出てこないか、表現の難しい箇所はないか、などを確認しています。プロ演奏家でも、その曲を「弾けそうかどうか」は結構気にするものなのです。
少し弾いてみて対応可能と判断できたら、今度は「どう弾いたらいいかな?」という感覚に移行します。クライアント側の意向もありますが、最終的に演奏責任は自分に返ってくるので、演奏ポイントは早めに掴んでおきたいところです。かっちり弾いたほうがいいのか、ゆったり滑らかなフレーズで弾くのか、曲のサビはどういう感じか、他の楽器が後から混ざってくることを考えて少し控えめに弾いたほうがいいか、ソロっぽく主張が激しい感じでいくのか、など。
試行錯誤の末、OKテイクが出るまで様々な弾き方を試します。演奏スキルと自分がもっている「表現の幅」が試されるところです。弾くのがやっと、という状況でなかなかOKがでず、時間ばかりかかった割に「ん〜・・・まぁ今日はこれでいいでしょう」みたいなギリギリOKをもらって帰るのは悲しいものです。
楽譜がすぐ読めること、演奏技術が確かであること、初見演奏が可能な技術をすべて両立している人が音楽(この場合は演奏現場)で食べていくことができる、という何とも大変厳しい世界です。厳しいとはいっても、人によって立場は異なるので、辛いことばかりではないと思いますが、みなさんはプロ意識についてどう思われますか?
Youtubeでピアノ演奏始めました!こちらから是非どうぞ↓
ATARI MUSIC STUDIO Channel - YouTube