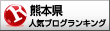2017/1/19のポタリングは、菊池川支流合志川のその支流、塩浸川(しおひたしがわ)流域だったが、内陸に会って「塩浸」とはどういうこと?と思ったので塩浸川について少し調べてみた。
Webで「塩浸」の地名を検索してみる。
坂本竜馬が湯治した霧島の「塩浸(しおびたり)温泉」。熊本県芦北町塩浸(大字)。
長崎県佐世保市塩浸町。福島県浪江町赤宇木塩浸(字)がヒットした。
いずれも山間の川沿いという共通項は地図上で確認できるが、それ以上の情報は得られない。
そこで角度を変えて調べる。
ここ合志市は、北九州島と南九州島を分けている地溝帯に、阿蘇火山麓の大津町から熊本市西部までカマボコ状に隆起してしいる台地上にある。
この台地の北に広がる低地は、陥没によって出来た菊鹿盆地で、南に広がる低地が益城町等を含む熊本平野である。
塩浸川は、北側を流れる合志川と田島地区で合流する。
その西側で合流する上生(わぶ)川は、塩浸川の南を並流する。
県道37号線を北進すると上生川を渡るが、その橋の手前に「塩浸」のバス停と温泉施設が1軒あり、上生川に架かる橋を「塩浸橋」という。
合志川沿いには、熊本市北区植木町、七城町、泗水町に約20軒の温泉がある。泉質は、ナトリウムー炭酸水素塩等の塩化物温泉である。
阿蘇外輪山の開口部に位置する栃の木温泉も塩化物温泉である。
霧島市の塩浸温泉も、ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-炭酸水素塩泉の塩化物温泉である。
この台地の南の端の益城町杉堂に「潮井水源」がある。水道水源にもなっている淡水水源だが「潮」の字が使われている。
「塩浸」は、この地溝帯の地底に閉じ込められていた塩水が湧出し、水田等に甚大な被害をあたえた記憶の名残ではないかと考える。
昨年の熊本地震は、この台地の南際の断層が動いた。
別府-島原地溝帯は、最近約100年間の測量のデータから、島原地溝が14mm/yearの速度で南北に引き延ばされながら、2mm/yearの速度で沈降しているという。(名古屋工業大学都市社会工学科H.P参照 http://www.cm.nitech.ac.jp/cho/earth_science/Lesson-13.pdf)
明治22(1889)年の熊本地震から今回の熊本地震までに1.8m弱南北に離れたことになる。
この台地には、菊池市花房台の断層涯をはじめてとして菊池川、泗水川、塩浸川が断層帯と重なっている。(「古代湖『茂賀の浦』から狗奴国へ」中原英氏のH.P参照 http://chimei.sakura.ne.jp/f-10kikuchi.htm)
不安を煽るつもりはないが、熊本地震の余震はまだまだ続いている。この余震が台地の北際の断層帯のズレを誘発しないことを祈るばかりである。
また、この塩浸川の別名を苧扱川(おこぎがわ)という。
「苧」=「カラムシ」とは、茎の皮から繊維を採るイラクサ科の多年草。縄文時代前期から繊維として利用されている。
史以前帰化植物の可能性が指摘されている(Wikipedia,十日町市博物館参照)。
南関町大津山公園内に町指定建造物「麻扱場(おこんば)橋」(写真1参照)がある。
橋は内田川に架かっていたものを移築したもの。この場合の「麻」も同じ植物を指している。

苧扱川の名称の川は、
長崎県口之津町
福岡県久留米市
香川県観音寺市にある。
(久留米地名研究会古川清久氏のH.P参照 http://chimei.sakura.ne.jp/f-27okongo.htm)
久留米市は、久留米絣が有名である。
これは木綿の生産が盛んだったことによるものであるが、その前史として「苧」の栽培があったと推測する。
特筆すべきは、新潟県十日町市の「からむし」栽培、「からむし」製品・開発の会社のH.Pの記事である。
「天平勝宝5年(753)3月29日に東大寺でおこなわれた仁王会(にんのうえ)に使った屏風を入れる袋の裏地で、生地はカラムシ(苧麻)で織った麻布である。今から1255年以上前の製品であって、幸いなことに、越後国 久疋(くびき)郡夷守(ひなもり)郷の戸主・肥人砦麻呂という者が、労働負担の代納物である庸(よう)として貢納した旨の墨書銘が残っている。
・・・・・
貢納者の肥人砦麻呂は“ヒノヒトノアザマロ”か“コマヒトノアザマロ”と読むことができる。
もし“コマヒト”と読むならば“肥人”は“高麗(こま)人”で朝鮮半島からの帰化人か、その子孫であることも考えられる。」
この記事を見て、この“肥人”とは、肥前、肥後の「肥の国の人」ではないかと考えた。
苧扱川がある口之津町は、有明海の入り口に当たり海上交通の要所。
同じく合志市は、古代湖茂賀の浦の畔海神色が濃い所。
長崎、熊本と福井、新潟の骨格形質は、近い(熊大横瀬久芳氏;参照 http://yrg.sci.kumamoto-u.ac.jp/lecture/presen/s6.pdf)
このことは、古から「肥国」が日本海ルートで越と交流があったと思える。
「夷守(ひなもり)郷の戸主」とあり、派遣された「肥国」の夷守が土着しとも考えられる。
塩浸川と並流する上生(わぶ)川が沿いの上生地区は、白村江の戦いに敗れて唐に抑留された筑紫君薩夜麻(サチヤマ)と同じく、33年後(696年・持統10年)に帰還した壬生諸石(みぶのもろいし)の本貫地とされている。
薩夜麻の身代わりとして長期拘留されているので、将監クラスの30歳前後で捕虜となったとして33年後は、60歳前後。
人生50年の時代にあって一生を捕虜として過ごしたことになる。
が、捕虜とはいえ文化先進地の大陸で過ごしたその経歴は、合志、肥後の発展に寄与したものと信じたい。
壬生諸石は皮石(合志)郡の人と日本書紀にあり、神話時代以後肥後の人ではじめて史書に記録された人名である。彼の帰国に際し朝廷は苦労を労い褒章を与えている。(久留米地名研究会古川清久氏のH.P参照 http://chimei.sakura.ne.jp/f-15tokuou.htm)
僅かの知識であれこれ思いを巡らし、見分してきたことを帰宅してから検証する。
際限なく疑問は広がるが、この作業の過程で思いがけない発見や確信を得ることもある。
だから、自転車ポタリングは楽しい!