先日(1月22日)、岡山大学教育学部ESD協働推進室の主催で第2回ESDリレーセミナーが開かれた。
今回の講師は東京学芸大学の成田喜一郎先生。ホリスティック教育がご専門で、(財)ユネスコアジア文化センター(ACCU)が出した「ESD教材ガイド:持続可能な未来への希望」(ACCUのHPからダウンロードもできる。)の主筆者でもある。(あとで知ったが、寺澤満春というシンガーソングライターでもあらせられるらしい!)
多くの学びがあったのですが、ここではふたつ紹介します。
まず、「ESDとは『如何に生きる(如何に死ぬ)か』という<本質的で根源的な問い>に対するレスポンスであると考えたい」とおっしゃったのが印象的でした。(あ、一緒だと思ってうれしかった)
ESDのカリキュラム、授業づくりについても、
<本質的で根源的な問い>をもとにカリキュラム、授業をつくっていく。
(そうすることで、領域、教科、専門性を超え、つながることができる)
<本質的で根源的な問い>というものはすぐに答えは見つからない。
学習が終わったあともずっと残るもの。
そういう問いをどうしたら引き出せるか。
というところが私には一番心に残りました。
と言うものの、<本質的で根源的な問い>とは何か。これがわかるようでわからない。
帰ってから言及されたHPを調べてみた。
「intel」という会社が「教育支援、教員研修」としてweb上に公開している授業案があるので見てください。
http://www.intel.com/jp/education/teach/index.htm
例えば、最初に事例として出されているのはこんなのです。
小学校1年生の生活科の授業案「あさがおのたねをプレゼントしよう」
あさがおを栽培して、採れた種を誰かにプレゼントするという活動。
そのとき、あさがおを育てる中で学んだこと気づいたことなどを「栽培カード」に書いて、それも一緒にプレゼントする。渡し方も練習する。
この学習における「評価の観点」は、「あさがおの成長のようすを観察し、変化や特性に気づき、それを相手に伝えることができる。」
「単元質問」は、「朝顔を育てる喜びを誰かにも伝えるにはどうしたらいい ?」だそうです。(ふむふむ)
そして、この学習における「本質的な問い」は何かというと、
「人が喜ぶと、なぜ自分も嬉しいのかな?」です。
すごくないですか?
私は教員ではないので、このような考え方を知って参ってしまいました。
勉強したいと思いました。
もうひとつの収穫をご紹介します。
ESDの評価って難しいですよね。
その評価の方法(の可能性)として、学習の振り返りに「創作叙事詩」とその「解題」を書くというものです。そしてそれをフィードバックする。
創作叙事詩=「事実」+「想像力」
「解題」は、「なぜわたくしはそれを書いたか」
(文科省も提示している「ESDでつけたい力」に、多面的かつ総合的な思考力や批判的思考力、多様性を尊重する価値観、分析力、コミュニケーション力等々あるのですが、その「等」とは何かというとき、成田先生は「想像力」だと挙げられました。)
実際、お話のあと、「ESDと私」で全員書いてみました。(約20分)
「叙事詩」というと聞き慣れない言葉なので構えますが、書き出したら意外にすらすら書けるもの。
参加者で一番若いという理由で学生たち3人が指名されて、書いた詩と解題を紹介してくれたのですが、これが素晴らしかった。
90分の講義とそれに触発された思い(これまでの経験を振り返り、この春から教壇に立つ思いも含めて)を素直に瑞々しく表現していて思わずみんな拍手。
「評価」が自己否定につながるようなものであってはいけない。自分を見つめ、元気が出るようなものでなくてはならないというところにも共感しました。
(今日は資料を職場に置いてきてしまい、空で書いているので詳細は違うかもしれないのですがお許しを・・・)
それで、週末にこのお話を聞いてすっかりやる気になった私は早速、今日の岡大ESD学外実習で叙事詩の方をやってみました。
(「本質的な問い」の方はもう少し勉強してから・・)
ちょうど、次回が発表という時期にあたっていたので、
「このESDの授業では、体験から学ぶ、互いから学ぶということを大事にしてきました。
次回のプレゼンとレポートでは、みんながどんな調査をして、どのようにそれを論理的に考察し、人にわかりやすく伝えられるかというところを見せてもらいます。でもこの授業ではそれに加えてもうひとつ大事なこと、何を心で感じたかということを振り返ってもらいたいので、今日は創作叙事詩とその解題を書いてもらいます。これまでの4ヶ月間の講座を通して学んだことや感じたことに自分の想像力を足して書いてみてください。題は「ごみってなあに?」か「ごみと私」です。」と投げてみました。
環境理工学部の学生たち、みんなポカンとした顔をしましたが、30分の時間をあげるとしんとなって書き始めました。
中から一番短いのをひとつだけ紹介します。
ごみと私
ごみと私は身近なもの
ごみは捨てられ
私は死ぬ
ごみはどこにでも捨てられ
私はきちんと埋葬される
このちがいはなんなのか
それは今だにわからない
【解題】
様々な不法投棄の現場を見て感じたごみと私の間柄
この学生は不法投棄ゴミ回収の場では一言もしゃべらず、女子ばかりの中で憮然としていた男子学生です。
13人の叙事詩を読んで、人は外から見て、言うことを聞いているだけではわからないとつくづく感じました。
(この学生の問いって<根源的で本質的な問い>ではないでしょうか・・?)
今回の講師は東京学芸大学の成田喜一郎先生。ホリスティック教育がご専門で、(財)ユネスコアジア文化センター(ACCU)が出した「ESD教材ガイド:持続可能な未来への希望」(ACCUのHPからダウンロードもできる。)の主筆者でもある。(あとで知ったが、寺澤満春というシンガーソングライターでもあらせられるらしい!)
多くの学びがあったのですが、ここではふたつ紹介します。
まず、「ESDとは『如何に生きる(如何に死ぬ)か』という<本質的で根源的な問い>に対するレスポンスであると考えたい」とおっしゃったのが印象的でした。(あ、一緒だと思ってうれしかった)
ESDのカリキュラム、授業づくりについても、
<本質的で根源的な問い>をもとにカリキュラム、授業をつくっていく。
(そうすることで、領域、教科、専門性を超え、つながることができる)
<本質的で根源的な問い>というものはすぐに答えは見つからない。
学習が終わったあともずっと残るもの。
そういう問いをどうしたら引き出せるか。
というところが私には一番心に残りました。
と言うものの、<本質的で根源的な問い>とは何か。これがわかるようでわからない。
帰ってから言及されたHPを調べてみた。
「intel」という会社が「教育支援、教員研修」としてweb上に公開している授業案があるので見てください。
http://www.intel.com/jp/education/teach/index.htm
例えば、最初に事例として出されているのはこんなのです。
小学校1年生の生活科の授業案「あさがおのたねをプレゼントしよう」
あさがおを栽培して、採れた種を誰かにプレゼントするという活動。
そのとき、あさがおを育てる中で学んだこと気づいたことなどを「栽培カード」に書いて、それも一緒にプレゼントする。渡し方も練習する。
この学習における「評価の観点」は、「あさがおの成長のようすを観察し、変化や特性に気づき、それを相手に伝えることができる。」
「単元質問」は、「朝顔を育てる喜びを誰かにも伝えるにはどうしたらいい ?」だそうです。(ふむふむ)
そして、この学習における「本質的な問い」は何かというと、
「人が喜ぶと、なぜ自分も嬉しいのかな?」です。
すごくないですか?
私は教員ではないので、このような考え方を知って参ってしまいました。
勉強したいと思いました。
もうひとつの収穫をご紹介します。
ESDの評価って難しいですよね。
その評価の方法(の可能性)として、学習の振り返りに「創作叙事詩」とその「解題」を書くというものです。そしてそれをフィードバックする。
創作叙事詩=「事実」+「想像力」
「解題」は、「なぜわたくしはそれを書いたか」
(文科省も提示している「ESDでつけたい力」に、多面的かつ総合的な思考力や批判的思考力、多様性を尊重する価値観、分析力、コミュニケーション力等々あるのですが、その「等」とは何かというとき、成田先生は「想像力」だと挙げられました。)
実際、お話のあと、「ESDと私」で全員書いてみました。(約20分)
「叙事詩」というと聞き慣れない言葉なので構えますが、書き出したら意外にすらすら書けるもの。
参加者で一番若いという理由で学生たち3人が指名されて、書いた詩と解題を紹介してくれたのですが、これが素晴らしかった。
90分の講義とそれに触発された思い(これまでの経験を振り返り、この春から教壇に立つ思いも含めて)を素直に瑞々しく表現していて思わずみんな拍手。
「評価」が自己否定につながるようなものであってはいけない。自分を見つめ、元気が出るようなものでなくてはならないというところにも共感しました。
(今日は資料を職場に置いてきてしまい、空で書いているので詳細は違うかもしれないのですがお許しを・・・)
それで、週末にこのお話を聞いてすっかりやる気になった私は早速、今日の岡大ESD学外実習で叙事詩の方をやってみました。
(「本質的な問い」の方はもう少し勉強してから・・)
ちょうど、次回が発表という時期にあたっていたので、
「このESDの授業では、体験から学ぶ、互いから学ぶということを大事にしてきました。
次回のプレゼンとレポートでは、みんながどんな調査をして、どのようにそれを論理的に考察し、人にわかりやすく伝えられるかというところを見せてもらいます。でもこの授業ではそれに加えてもうひとつ大事なこと、何を心で感じたかということを振り返ってもらいたいので、今日は創作叙事詩とその解題を書いてもらいます。これまでの4ヶ月間の講座を通して学んだことや感じたことに自分の想像力を足して書いてみてください。題は「ごみってなあに?」か「ごみと私」です。」と投げてみました。
環境理工学部の学生たち、みんなポカンとした顔をしましたが、30分の時間をあげるとしんとなって書き始めました。
中から一番短いのをひとつだけ紹介します。
ごみと私
ごみと私は身近なもの
ごみは捨てられ
私は死ぬ
ごみはどこにでも捨てられ
私はきちんと埋葬される
このちがいはなんなのか
それは今だにわからない
【解題】
様々な不法投棄の現場を見て感じたごみと私の間柄
この学生は不法投棄ゴミ回収の場では一言もしゃべらず、女子ばかりの中で憮然としていた男子学生です。
13人の叙事詩を読んで、人は外から見て、言うことを聞いているだけではわからないとつくづく感じました。
(この学生の問いって<根源的で本質的な問い>ではないでしょうか・・?)












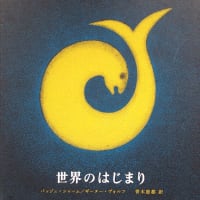







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます