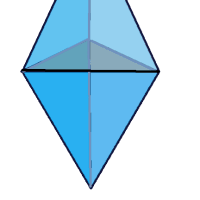延宝2年(1674年)の越後騒動は、松平光長の嫡子・綱賢が跡を継ぐことなく急逝したことが発端でした。光長に他の男子がおらず、跡継ぎ選びが急務となり、候補者として以下が挙げられました。
- 永見万徳丸(のちに綱国)
- 永見長良
- 小栗大六
- 松平義行
藩内評議の結果、40歳を超えた長良の年齢が問題視され、15歳の万徳丸が跡継ぎとして選ばれ、将軍家綱から偏諱を賜り「綱国」と名乗りました。
しかし、家中では家老の小栗正矩が自分の子・大六を跡継ぎにしようとしているとの疑念が広がり、藩財政の悪化や新税による不満から、小栗への反感が強まりました。これにより、家中は「お為方」(永見大蔵派)と「逆意方」(小栗派)に分裂し、890名もの藩士が抗争を繰り広げる事態となりました。光長の財政運営や江戸での豪華な暮らしも、この内紛をさらに激化させた要因の一つです。
こうした緊張は、藩主や家臣だけでなく幕府の介入を招き、騒動がより広範囲な影響を及ぼすまでに至りました。この一連の事件は、江戸時代のお家騒動の中でも特に混乱の象徴とされています。
光長の財政運営や江戸での豪華な暮らしーーーこれは、忠清の力添えが考えられます。
酒井忠清は大老として、幕府全体の安定や藩政の支援にも深く関わっていました。光長が江戸での奢侈な生活を維持しつつ、藩政を続けられた背景には、忠清のような幕閣の有力者からの間接的な支援があったのかもしれません。
光長の財政悪化や越後騒動が拡大する中、幕府の政策や財政融資がどの程度影響を与えたのかを探ると、忠清の力添えが具体的にどのように行われたのかが見えてくるかもしれません。こうした背景の分析は、当時の幕府と藩主間の力学を読み解く手がかりになりそうです。