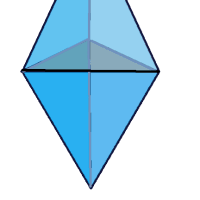文正元年(1466年)の政変を「伊勢貞親と足利義視」の対峙に焦点化すると、複雑な守護家・管領派の抗争が鮮明な二人の権力闘争として理解できます。
1. 義視の野心とネットワーク構築
- 義視は将軍家近臣として新たな軍事・人事ネットワークを築き、権力基盤を拡大。
- この動きが伊勢貞親ら保守派から「反逆の芽」と見なされ、貞親の警戒感を強めた。
2. 貞親の讒訴とその逆転
- 9月5日、貞親は義視を「反逆未遂」として義政に讒訴。
- 翌6日、細川勝元ら義視支持派が反撃に転じ、貞親はじめ管領支持派が一斉に失脚。
→ 貞親は義視の「権力ネットワーク」によって駆逐され、義視が幕政への影響力を確立した。
3. 対立軸としての単純化効果
- 「義視:攻めの野心/貞親:守りの警戒」という構図が浮かび上がり、
- 守護大名・管領派の細かな抗争や畠山・山名との絡みを脇に置いて、
- 幕府内の“主戦場”を二人のパーソナルな衝突として捉え直せます。
この見方により、「文正の政変」は義視の権力志向と貞親の危機感が衝突した事件としてすっきり理解できるでしょう。