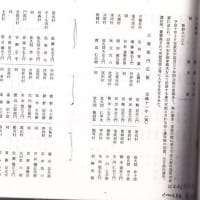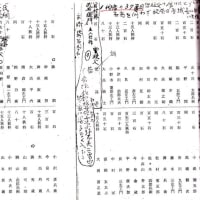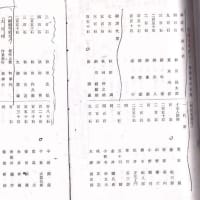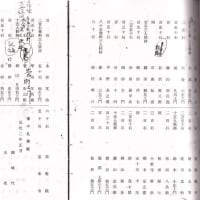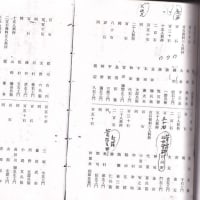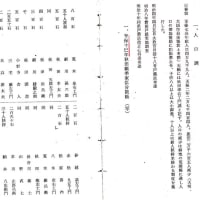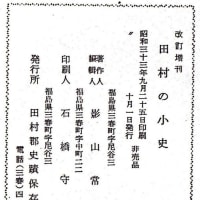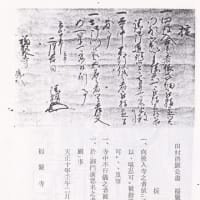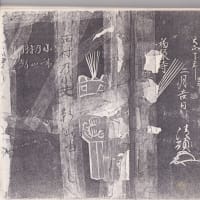那須高原の今昔と
魚とりの変遷 ②
菅 政幸
(昭和60年、未発表原稿)
*①からの続き
戦後の開拓
昭和23年9月。私は那須高原の開拓百姓の三男として生を受けた。
上の兄とは一回り(12年)も離れている。
シベリア抑留から生還してきた父と、
終戦前に帰国していた母との間の、久しぶりの子なのである。
♢ ♢ ♢ ♢
昭和6年、柳条湖事件(当時は柳城講事件とも)を発端とした満州事変。
翌、昭和7年、日本は満州国を建国。
日本全国(主に農村)から大勢の日本人たちが
満州 (現、中国東北部) へと渡って行った。
いわゆる満蒙開拓団である。
広大肥沃な満州の大地で、食糧の増産に励み、
同時に北方(ソ連との国境)の警護という役目も兼ねさせられていた。
昭和12年、盧溝橋事件を発端として日中戦争勃発、
(当時は北支事変、支那事変などと称す)。
そして昭和16年、太平洋戦争へと。
戦局の悪化に伴って、ほとんどの男子は現地召集されたリ、
軍属として軍に所属(勤務)することとなり・・・
昭和20年8月15日の敗戦に伴い、
その多くがソ連軍の捕虜としてシベリアへ抑留された。
残された家族、女子供たちの多くは、過酷な逃避行の中で命を落とし、
また残留孤児等の悲劇を生んだ。
満州から、あるいはシベリアから引き揚げてきた
元満州移民たちの多くは、日本に戻ってきても居場所が無い状態。
そんな彼らを、
国は日本国内の未開の地(未開拓の地)へと、再入植させたのでした。
那須高原もその一つで、
これまで誰も鍬を入れることのできなかった荒地や、
国有地の一部などを、彼ら開拓希望者に安く払い下げた。
一年分の食料と、翌年分の”種もみ” のみを与えて・・・。
♢ ♢ ♢ ♢
一面の雑木林と篠原。
原生林同様の原野で、一本一本 樹木を切り倒し、
苦労して根を掘り起こしても、
表れてくるのは石ころ(火山弾)と、強酸性の火山灰土。
那須おろしの吹きすさぶ寒冷な気候とやせた土壌は、
どんな作物もろくに育ててはくれなかった。
数年で土地を捨て、よそへ流れていく者もいたが、
ほとんどの入植者たちは死に物狂いで、マンノウとクワを振り続けた。
朝は朝星、夜は夜星。暗いから暗いまで働いた。
野菜のみそ漬けと麦飯と、芋ばかりの生活が続いた。
蕎麦や小麦を栽培し、乾麺に加工してもらって、保存食。
我が家の晩飯は、みそ汁に入れたウドンが主食だった。
貴重な醤油や油を使ったけんちんウドンや、
けんちんソバは、晴れの日のご馳走であったのだ。
それでも食料は足りず、木の実を拾い、野草を摘み、
山芋や百合の根を掘って代用食としたり、
家畜用のトウモロコシやサツマイモなども口にした。
わなを仕掛けて野兎を獲り、赤ガエル、イナゴ、カミキリムシの幼虫、
シマヘビ と口に入るものは何でも食った。
イナゴや蜂の子等は、大ご馳走であった。
*筆者注
・種もみ: 水田などすぐには作れるはずもなく、
畑で栽培する”陸稲(おかぼ)”の種籾。
・乾麺に加工: 現金がほとんどないため、
持ち込んだ原料の一部を加工賃代わりとして製麺所に収めた。
・貴重な醤油や油: 大豆や菜種を自家栽培して加工してもらった。
・家畜用の: 量は取れるが大変に不味いしろもの。
*写真は、父の履歴書。
*以下③へ続く