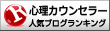こんにちは、のほせんです。
一足飛びに冬がやってきたような具合ですが、
みなさんは、いかがお過ごしでしょうか?
寒くなると交感神経が緊張度を高めるために、さまざまな身体症状があらわれてきますのでご用心ください。
すこし気がかりなときには、ぎんなん先生の井穴刺絡療法でセルフコントロールしてみてください。
また、だんだんとおしつまってきますと、焦燥感、不安感が増したり、
いまの関係をこわして逃げ出したくなったりと、精神的な動揺があらわれやすくなります。
もちろん、そのようなときにはためらわず、わたしどもにお問い合わせください。
- さて、今回は前回のお話につづいて、この国の「人でなし」政権の壁に阻まれ苦闘するがゆえに、
天皇への「直訴」におよんだ山本太郎氏の思考・行動の歴史的意味を読みとるために、
やはり絶望の果ての直訴に向かうほかなかった人たちがたどった昭和の歴史的事件をひもといていきたいとおもいます。
それにしても案の定、御用マスメディアはよってたかって山本太郎氏を袋叩きにし、さすがに
彼も疲れ果てた様子で反省のコメントを吐かせられ、おかげで脱毛症もひどくなっているようです。
ようするにこの平成の時代にもかかわらず、「不敬罪」をマス・ヒステリーによってリンチ(私刑)で実現させたということである。・・・
- さて、昭和の初めの物語は、信仰を抑圧してくる者たち・強権とのたたかいと、内なる信仰の「ころび」の苦悩、
そして敗北と逃亡の果ての即身仏のような死を、徹底して描いた人間の「個の精神」の極限の物語といえるでしょう。
それこそは、高橋和巳の渾身の著作「邪宗門」にほかなりません。
民が神懸かりとなり、また周囲の民がその神懸かりに魅かれて信仰に向かわすものとは、何か?
まずその辺りから紐解いていくとしましょう。
著作、- その二 前史 に、仮の名で新興教団の開祖の女性の生い立ちが記されている。
“ 安政二年、開祖は貧農の三女として生まれたが、その年大飢饉があり、そのうえ “ころり ” が全国的に流行した。
数しれぬ人々が厄災に苦しみ、屍を野ざらしにして死んでいった。
この教団には “六終局 ” という、世なおしの前に、この世が経験せねばならぬ六種のカタストロフの予言があって、
それの開祖誕生の年の惨禍が結びつけられているが、もちろんそれは偶然にすぎない。
開祖生誕の時、生まれてくる児をまびくか否かで、母と姑がいがみ合い、産婆のとりあげた児を、母が血まみれで抱いて、納屋へ逃げ込んだといわれている。
母は産褥熱をわずらって死に、開祖は誰の児かわからぬ児をうんで近くの祠に住んでいた白痴の娘の乳によって育てられた。
しかしこの事実も、むしろありふれたことだったことに意味がある。
生まれたときから歓迎されぬ児として生き、読み書きも教えられずに、子守娘に出され、つぎは地主の家に女中奉公に出された。
そして心に秘め思うこととは関係なく、仕える家の主人の命ずるままに出入りの大工職人にとついだ。
その平凡さが、初期の女性信徒たちの、ドラマなき悲哀と忍従の生活史にそのまま重なった。
開祖が神がかりの状態で口にする言葉は、表現するすべを知らぬながら、体験において共通する女たちの胸をついたのである。”(一部略) - - -
作者は「信仰」に向かう当時の民の心情とその高揚の機微によく理解をしめしている。
- 大工職人にとついだものの、やくざ趣味が昂じて腕を折られて以来その夫は荒んで酒びたりになり、
そして彼女が行商にでたすきに、長女を遊里に売り飛ばし、長男を質屋の丁稚にしていた。
怒った彼女は残った二児をつれて姉の嫁ぎ先に身を寄せたが、その間に夫は死んだ。
酒に酔いつぶれ野壺に落ち、糞尿にまみれて死んだのである。
“ 死と糞尿と蛆虫のイメージ ” が開祖のお筆先が描きだす世界の終末図にひんぴんと現われるのは、おそらくそのせいだろう。 -
- 義兄につまはじきにされ二人の子を外に出し、無理強いに六十をこえる高利貸しと再婚させられたあげく二児の子どもが生まれたが、
度を越した吝嗇の夫に不貞を口実に離縁されたのが三十七歳、五年間辛抱して二人の不幸な子どもを得ただけだった。
さまざまな仕事に励んだが、あるとき行商に出た留守の間に下の娘が餓死していた。
彼女は元の村の白痴娘のいた祠に、生き残った児と住んだが、コレラの流行で
だれ言うとなくコレラのもとはあの乞食女だと言いふらされ、その祠も焼かれた。
一ヶ月余り、夢遊状態で、彼女は六つになる児をつれて山中をさまよい、虫を食い蛇をとらえて食い、
そして次に山から降りてきたとき、子どもの姿はなく、目をらんらんと輝かせて、何かわけのわからぬことを叫びながら町を歩いた。
「六人の子を生んで、四人に先立たれ、残った子にも背かれた母親の命になんの意味があるのだろうか、と。
なぜ長男は戦死したのか。なぜ長女は娼婦になり病毒におかされて死んだのか。なぜ次女は地主の納屋で首をくくったのか。なぜ三女は末子を餓死させたのか。
その三女は山でどうなったかを彼女は言わなかったが、それよりそんな奇妙な問いにまともに答えてやる者はだれもいなかった。
とつとつと、しかしある迫力をもった声で同じことを問いかけるのだった。・・・」(概略) - -
- ただ一人、浄土宗の僧侶がまじめに彼女に応対した。
前世の因縁や浄土の救いを説いてもあんたの耳にはとどかんだろう、どうしてもその五つの問を解かずには死ねんというなら、
自分でものを考えすすめるよすがに、文字を教えてあげようと僧侶が言い、数ヶ月間、乞食女と酒飲み坊主との奇妙な問答がつづいた。・・・
開祖のお筆先に濃厚にみられる末法意識も、その僧侶の影響とおもわれる。
やがてふたたび開祖は山に入って姿を消し、今度あらわれたときには、怪しく人をひきこむ抑揚で、人の悩みを射当て、人の病を癒す祈祷師となっていた。
今度はコレラ患者に彼女が触れると奇跡的に癒されるというまったく逆の噂がたち、医師の手当てをうけられない貧しい人々が彼女を崇拝しはじめた。・・・ -
だれしもがおどろかされるだろう、この彼女の「神懸かり」譚には特段の嘘も誇張もないであろうと、吉本隆明氏はこの著作によせての小論「新興宗教について」でのべている。
- まず田中佐和という超心理学的な能力を商品として売っている若い女性について、つぎのように記している。
“ この種の超心理学的な能力が、他者の心的な状態に、容易に共鳴しうるいわば原始的心性を、
常人よりもおおく保存しているにすぎないことは申すまでもない。・・
彼女の能力の由来の物語は、かくべつ本人が嘘をついているわけではないといっていい。
彼女の夢の話は巫女譚として変わったところはないし、神秘性もない。 後半の記述は、この女性の入眠幻覚あるいは白日夢である。
一頭の猪があらわれ、山道を登るのを背後から牙で押しあげてたすけてくれた。
この猪は愛宕神社の祭神の使いであり、一緒にいた母親には視えないと書いている。
このとき、この女性は入眠状態あるいは白日夢の状態にあった。・・・
この女性はこの入眠体験を契機として一種の精神病理学上の幻視や幻聴をひんぱんに獲得しうるようになったというにすぎない。
じぶんでは「その日を境に、私には霊能が開け、透視・霊視・霊聴が」はじまったとかいっているが、
もちろんそんなことは何の意味もない。ただ手易く病理学上の幻視や幻聴を体験するようになったというにすぎない。
この入眠幻覚の状態は、分裂症患者の体験する症候とすこしもかわりないが、
病者としてかんがえ難いのは、この女性が入眠幻覚の状態で、他者の心的状態に容易に移入しうるため、
この他者体験が入眠幻覚にある客観性(普遍性)を与えることになりえているからである。
また最初の入眠幻覚が、土俗的な宗教体験としてやってきたため、自身にとってはこの心的な状態が
一種の優越感(常人以上の能力をもっているという自負)によって統御されていて、人格的な崩壊をきたさないための支えになっていることによっている。” -
ここでは、分裂病とほぼおなじ症候として「神懸かり」がとらえられていることに留意しておかなければならない。
吉本氏流のややむずかしい言い回しになっいますが、ある意味、眼からうろこの解説になっています。
昔のアフリカ大陸では、もっと積極的で、そのの分裂症気質の青年がえらばれて、次の祈祷師の修行を授けられるということであった。
このことは分裂病的な気質なるゆえに、共同体の存続にかかわる予兆や変異を察知できうる存在として認知されてきたことをものがたっている。・・
さらに吉本氏は説く。
若い霊能者である女性が教祖になる条件を具えているのになれないのはなぜか?
“ この女性は若いためとるに足るほどの生活思想もなく、現実的な労苦にたえて獲得した人生観も世界観もない。
それとは異なりさんざん生活苦をなめて生きてきた貧農の主婦は、更年期になって突然入眠幻覚に没入しうる能力を獲得し、 それが
「惨苦から逃れる」という願望、動機とある必然的なむすびつきをしめしている。・・・
新興宗教のなかでも、かなりすぐれた宗教でありうるとすれば、
その理由はあらゆる思想の優劣を問う場合とちがっていない。
彼女の生活体験から獲得した思想が、体験に裏うちされて血肉化した迫真性をもっているとすれば、
農家の無知な主婦であっても、その生活思想は、宗教体験としての入眠幻覚とむすびつけられて、
かなりの普遍的な真理をもちうるはずである。” (概略)--
さて、ここまできて、宗教というものの成り立ち方がつまびらかになった。
古来より人は、それくらいのある種の能力をもちあわせてきたということであろう。・・・
またそれは血肉化され、普遍性を獲得するまでにいたった宗教となれば、
国家が弾圧しなければならないほど、迫真的な信仰、宗教たりえたともいえよう。
(次回につづきます)
..............................
あなたの推薦クリックを毎回よろしく願います! ![]() へ!
へ!