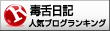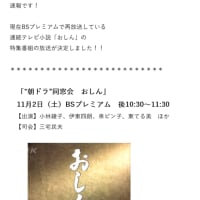夏目漱石「道草」 年末からお正月にかけて読んだので感想を。

今年は漱石を中心に読もうと思っている。恥ずかしながら、文芸作品は大人になってから、読んでいない。だが、私も人生半ばを過ぎたし(たぶんwww)夏目漱石という作家の作品群を本当の意味で味わえるかもしれない、そういう期待をもって読んだ。
夏目漱石という人は、作家というより哲学者で宗教的な、そんな境地にあった人のような気がする。何となく私はそういう感じがしていたけれど、では「道草」を読んでどうだったか。
「道草」は自伝的小説とある。小説の内容は、大学講師である健三の日常。…彼の義父・義母・兄・姉・細君の父親までがお金を借りに、彼の元に頻繁にやって来るようになる、健三の本音は、「お金を貸したくない」けれど、無下に断ることが出来ない、ウダウダ心の中で悩みながら、細君に嫌味を言われながら、自分もさしてお金が余っているわけでもないのに、結局お金を貸してしまう。そういう話なのだ。
こう書くと、物語としては派手さもない。事件らしい事件は「誰かが金を借りに来る」これだけ(笑)だが…
人の生活は意識の連続で成り立っている、色んな思いが頭をよぎる、けれどその思いや感情、意識というもの、心の動きを、動きとして捉えるより前に、次の考えや思いがすぐ頭をよぎる。
「道草」は、この健三の心・意識の連続の瞬間を両手でそっとすくって、竹細工のように編み込んでいったよう。簡潔で美しいけれど、この竹細工の中を覗くと、健三の現在・過去・未来時間を超えた彼の意識の連続が、無限に広がっている。その中の空気というのかなぁ、とても生々しい。湿ったような生あたたかい風、真冬を思わせる凍てつくような北風、やわらかい春のひだまりを感じる空気、その人間の生きている空気感、リアリズムをとても感じる。
あぁこれが夏目漱石なのかぁとひどく感心した。やっぱりお札になった人だけのことあるなと(笑)
夫婦・親子・男・女・色々な立場・関係から生じる個人の姿のネガティブな意識部分をここまで俯瞰(ふかん)した漱石は凄いですね。
とても面白い。「道草」の現代版というのかな、そういうものも、できそう。私は4コマ漫画のような、ああいったものを描かればいいのになと思った。この現代に通じるリアルさというのを、また別な表現で再現できるんじゃないかなと。
物語は地味に終わる。健三が養父と関係を断つということで、とりあえず一件落着する。
ラストの細君と健三は、とても印象に残る。「道草」新潮文庫から抜粋
「安心するかね」
「ええ、安心よ。すっかり片付いちゃったんですもの」
「まだ中々片付きゃしないよ」
「どうして」
「片付いたのは上部だけじゃないか。だから御前は形式張った女だというんだ」
細君の顔には不審と反抗の色が見えた。
「じゃあどうすれば本当に片付くんです」
「世の中に片付くなんてものは殆どありゃしない。一遍起こったことは何時までも続くのさ。ただ色々な形に変わるから他人にも自分にも解らなくなるだけさの事さ」
健三の口調は吐き出すように苦々しかった。細君は黙って赤ん坊を抱き上げた。
「おお好い子だ好い子だ。御父様の仰る事は何だかちっとも分りゃしないわね」
細君はこう云い云い、幾度か赤い頬に接吻した。 (完)
私が現代国語の教師なら、こういう問題を出すでしょう。
何故作家は、『細君は黙って赤ん坊を抱きあげた』で、終わらせずに『おお好い子だ好い子だ』という細君の言葉と接吻する動作で終わらせたのか、それは小説世界にどういう効果をもたらしたのか、400字以内で述べなさい。
と。 そのくらい計算された文章で、素晴らしいなと思う。また別の作品を読んでみたい。