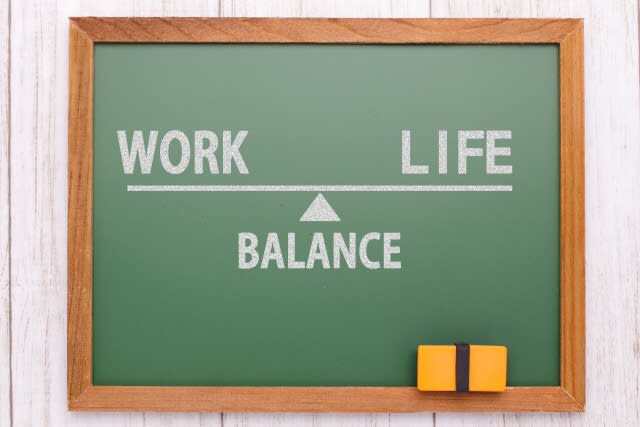【始皇帝】
韓非子は、もともと韓の王族の公子で、秦の始皇帝に採用されました。ただし、最終的には、投獄されて自殺してしまいます。秦は、韓非子の政策によって「富国強兵」と「法制」が強化されました。富国強兵とは、国の「経済力」と「軍事力」を強化することです。それによって、独裁的な君主による中央集権的な国家が形成されました。秦が、中華全土を支配的に統一することが出来るようになったのは、富国強兵と法制によるものだとされています。
【性悪説と徳治主義】
韓非子の思想は、性悪説の立場に立っています。性悪説は、もともと儒家の「荀子」の思想です。荀子は、韓非子の師匠格にあたる人物でした。性悪説とは、人間の本性は悪だとする倫理思想です。荀子は、人間というものは、欲望や快楽に流され、悪に走りやすいものだとしました。自分だけの利益を求め、損になることを避けるからです。
性悪説では、人間は、生まれながらにして悪だとされています。そのため「礼儀」や「道徳」によって縛る必要がありました。道徳や社会規範を重んずるのは、儒家的な思想です。儒家は、君主が徳によって国を治めるべきだとしました。それを「徳治主義」と言います。 徳治主義は、きわめて理想主義的な思想でした。
【法治主義】
儒家の徳治主義は、戦国時代には通用しませんでした。それに代わる方法として、考え出されたのが韓非子の「法治主義」です。法治主義は、現実主義的な考え方でした。法とは、国家が定める「基準」であり、人々の行為の「規範」です。それは、社会的秩序を保つためには欠かせないものでした。法の運用は、相手によって使い分けられません。君主の下では、家臣はみな平等だったからです。法治主義では、法と道徳は切り離されました。ただし、近代的な法律とは異なります。それは、君主側が、一方的に庶民を拘束するものだったからです。法治主義の下では、厳格な法律「成分法」の執行と、専制的な権力によって国家が統治されました。
【法家】
法至上主義の人たちを「法家」と呼びます。その法家を大成させたのが韓非子です。法家は、諸子百家の殿「しんがり」だとされています。韓非子は、特に儒家の道徳に対して批判的でした。儒家が、従来の貴族に対して、特権を認めていたからです。法とその運用の仕方を「法術」と言います。法術は、法家の思想の核心となるものでした。それが、国を治めるのに欠かせないものだったからです。
【法術】
国家を運営する上で、君主が臣下を操縦するための手段を「術」と言います。法術とは、法を使って、臣下をコントロールすることです。その権限は、君主にあります。君主とは、国家機構の頂点にあって、法の運営に努める者のことです。統治をするためには、法を実行するための「強制力」がなくてはいけません。そのために必要だったのが、それを実際に行使できる「権限」です。ちなみに、強制力の基盤となる地位や権力を「勢」と言います。
「信賞必罰」という言葉は、韓非子のものです。韓非子は、信賞必罰によって、君主が臣下を操縦するべきだとしました。信賞必罰の賞は「利益」で、罰は「不利益」という意味です。それぞれ、法の基準に照らして、与えられました。