桑谷村の見学を終えて車に戻り、次に「霊水」に行こうとしていたところ、
参加者の方が全員、「川底下村」に行ったことがないということが判明した。
同窓会の遠足では、過去に何度も行っているが、帰国される方などの入れ替わりもあり、
それならぜひいきましょう、と急遽予定を変更して、川底下村に向かった。
川底下村といえば、北京城内が取り壊しと再開発によりもはやほとんど原型をとどめない今となっては、
中国北方の四合院建築の町並みを楽しむことのできる貴重な近郊の村となっている。
やや観光化が進みすぎ、俗になっている部分はあるのだが、
それでもまだまだ素朴でこの程度なら許容範囲内、と私は思っている。

昼食に選んだお宅。
通りに面しているのは、門構えのみ。どんどん奥につながっている。


門Dunはあとから作ったものっぽいが、それはそれとして、やはりこういう様式に文化を感じる。


古民家群というのは、ただ単に古いだけでは価値がない。
がらくたと骨董は紙一重。
やはりある一定の経済的な基盤を元に、少なくとも小金持ち程度でなければ、
後世の人が見て美しいと感動するものは残らない。
古くてもがらくたはがらくたなのだ。

先ほどの古民家。
長い通路を入り、門から振り返ってみた図。

入り口の入った部分の壁画。
今、我々が利用している国道109号などの舗装された幹線道路ができる以前、
川底下村は、東西交通の大動脈上に位置し、宿場町として栄えた。
この村の成り立ちからして、
明代に山西の洪洞の大槐樹から移住させられてきたというから「軍事」、「交通」と関係が深いことを感じ取ることができる。

正面には、影壁。
「山西洪洞の大槐樹」といえば、世界中の華僑が祖先の地として、崇拝するシンボルである。
明代、モンゴルのとの戦いで、長城の内側---最前線である山西において、あまりにも敵側と密通する漢人らが多く、
その忠誠心のなさ、不甲斐なさに手を焼いた朝廷は、
「山西の連中はあかん。数世代にもわたり、うまく立ち回ることを覚えてしまっている」
と、彼らに見切りをつけ、まったく地の利のない海辺の福建人らと総入れ替えをするという暴挙に出た。
そこで山西から福建に送られる人たちも、福建から山西に移住させられてきた人たちもすべて
まずは「洪洞の大槐樹」と呼ばれている巨大な巨木の下に集められ、そこから各地への入植に振り分けられていった。
福建に飛ばされた長城のふもとの人たちは、そこから海外に飛び出して行き、世界中でチャイナタウンを作った。
子供たちに語り継ぐのはいつも「洪洞の大槐樹」であり、幾世代にもわたり、彼らの心の故郷の象徴となっていった。
10年ほど前、そんなことは露知らず、例によって何の予備知識もないまま洪洞を訪れ、後から知って驚いた。
いずれその写真もフィルムからスキャンしてアップしたいと思うが、
確かにその当時、洪洞の寺院の伽藍の場違いなほどの豪華さをいぶかしく思っていた。
2000年すぎといえば、中国の田舎はまだまだしょぼくさく、旧跡名所の整備もあまり進んでいない。
ましてや山西の片田舎の洪洞は、ただのしょぼけた田舎町だったが、
そこに突如として現れたお寺の豪華絢爛さたるや、少し別世界のようだった。
後から考えれば、あれは海外で成功した華僑たちが、自分たちの故郷のために寄付したお金であんなことになっていたのではないだろうか。
逆に、以前にアップした山西省と炭鉱4、黄土高原の葬式だが、実はここは福建からの移住者の集団により占められた村だ。
名前を「林家口村」といい、村人たちは全員「林さん」。
林という姓も如何にも南方の姓らしい。
彼らは口々に「我々の移住は洪武何年(細かい数字は忘れたが)に福建から移住してきた」といい、
未だに村では、福建から来たといえば、ただ飯、ただ泊まりで大歓迎するという。
リンクした記事の最初の写真の左側の男性は、いかにも暴れはっちゃくのお父ちゃん風の風貌。
縄文系の日本人にもいそうな「南方」の風貌である。
そんな顔が長城のふもとの谷間に存在する理由をなんと、明代初頭まで遡ることができるのだ。
高度成長期以来、もはや地域ごとの人種的な特徴など顕著でなくなってしまった、
出身地ごっちゃまぜの日本人から見ると、大変興味深いエピソードだ。
人々が700年前に作られた運命の手配の元になお生きているという事実は。
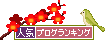

参加者の方が全員、「川底下村」に行ったことがないということが判明した。
同窓会の遠足では、過去に何度も行っているが、帰国される方などの入れ替わりもあり、
それならぜひいきましょう、と急遽予定を変更して、川底下村に向かった。
川底下村といえば、北京城内が取り壊しと再開発によりもはやほとんど原型をとどめない今となっては、
中国北方の四合院建築の町並みを楽しむことのできる貴重な近郊の村となっている。
やや観光化が進みすぎ、俗になっている部分はあるのだが、
それでもまだまだ素朴でこの程度なら許容範囲内、と私は思っている。

昼食に選んだお宅。
通りに面しているのは、門構えのみ。どんどん奥につながっている。


門Dunはあとから作ったものっぽいが、それはそれとして、やはりこういう様式に文化を感じる。


古民家群というのは、ただ単に古いだけでは価値がない。
がらくたと骨董は紙一重。
やはりある一定の経済的な基盤を元に、少なくとも小金持ち程度でなければ、
後世の人が見て美しいと感動するものは残らない。
古くてもがらくたはがらくたなのだ。

先ほどの古民家。
長い通路を入り、門から振り返ってみた図。

入り口の入った部分の壁画。
今、我々が利用している国道109号などの舗装された幹線道路ができる以前、
川底下村は、東西交通の大動脈上に位置し、宿場町として栄えた。
この村の成り立ちからして、
明代に山西の洪洞の大槐樹から移住させられてきたというから「軍事」、「交通」と関係が深いことを感じ取ることができる。

正面には、影壁。
「山西洪洞の大槐樹」といえば、世界中の華僑が祖先の地として、崇拝するシンボルである。
明代、モンゴルのとの戦いで、長城の内側---最前線である山西において、あまりにも敵側と密通する漢人らが多く、
その忠誠心のなさ、不甲斐なさに手を焼いた朝廷は、
「山西の連中はあかん。数世代にもわたり、うまく立ち回ることを覚えてしまっている」
と、彼らに見切りをつけ、まったく地の利のない海辺の福建人らと総入れ替えをするという暴挙に出た。
そこで山西から福建に送られる人たちも、福建から山西に移住させられてきた人たちもすべて
まずは「洪洞の大槐樹」と呼ばれている巨大な巨木の下に集められ、そこから各地への入植に振り分けられていった。
福建に飛ばされた長城のふもとの人たちは、そこから海外に飛び出して行き、世界中でチャイナタウンを作った。
子供たちに語り継ぐのはいつも「洪洞の大槐樹」であり、幾世代にもわたり、彼らの心の故郷の象徴となっていった。
10年ほど前、そんなことは露知らず、例によって何の予備知識もないまま洪洞を訪れ、後から知って驚いた。
いずれその写真もフィルムからスキャンしてアップしたいと思うが、
確かにその当時、洪洞の寺院の伽藍の場違いなほどの豪華さをいぶかしく思っていた。
2000年すぎといえば、中国の田舎はまだまだしょぼくさく、旧跡名所の整備もあまり進んでいない。
ましてや山西の片田舎の洪洞は、ただのしょぼけた田舎町だったが、
そこに突如として現れたお寺の豪華絢爛さたるや、少し別世界のようだった。
後から考えれば、あれは海外で成功した華僑たちが、自分たちの故郷のために寄付したお金であんなことになっていたのではないだろうか。
逆に、以前にアップした山西省と炭鉱4、黄土高原の葬式だが、実はここは福建からの移住者の集団により占められた村だ。
名前を「林家口村」といい、村人たちは全員「林さん」。
林という姓も如何にも南方の姓らしい。
彼らは口々に「我々の移住は洪武何年(細かい数字は忘れたが)に福建から移住してきた」といい、
未だに村では、福建から来たといえば、ただ飯、ただ泊まりで大歓迎するという。
リンクした記事の最初の写真の左側の男性は、いかにも暴れはっちゃくのお父ちゃん風の風貌。
縄文系の日本人にもいそうな「南方」の風貌である。
そんな顔が長城のふもとの谷間に存在する理由をなんと、明代初頭まで遡ることができるのだ。
高度成長期以来、もはや地域ごとの人種的な特徴など顕著でなくなってしまった、
出身地ごっちゃまぜの日本人から見ると、大変興味深いエピソードだ。
人々が700年前に作られた運命の手配の元になお生きているという事実は。



















なかなか一般人だと思いもよりませんです・・・^^;
門構えといいタダモノではない雰囲気を醸し出していますね。
私が最初に訪中したころは指定都市の開放地区しか立ち入ることはできませんでしたので、いーちんたんさんの紀行文は垂涎の的であります。
おお。それは90年代以前ですね。
私も最初来たころは、そんな感じでした。