これに加えて康熙帝は、モンゴル王公らとの親交をさらに深めるため、
康熙20年(1681)には、北京の東北、北京とゴビ砂漠との間の森林地帯に「木蘭囲場」という狩り場を作った。
春先から晩秋に至るまでの実に半年もの間、ここでモンゴル王公らと
日がな狩りやら、キャンプやら、宴会やら、ラマ教の法会やらに明け暮れるのである。
その中には、康熙帝の娘(皇女)を嫁がせた相手の「婿」王公もいたりして、
その皇女が生んだ息子が、将来はこの祭典に参加するような手はずになっていた--。
虎、鹿を中心とした動物が捕れたという。
そんな中、康熙27年(1688)に西北モンゴル、オイラートのジュンガル部のガルダン・ハーンが東に移動して
漠北(ゴビ砂漠の北側。現在の外モンゴル)のハルハ部を襲撃するという事件が起きた。
泡を食ったハルハ部の人々数十万人が、死の恐れも伴うゴビ砂漠の縦断をものともせずに大挙して南下、
康熙帝に保護を求めるという所謂「ハルハ部の大南下」があった。
元々、漠南と漠北のモンゴル諸部は、親戚関係のようなもの。
漠南にたどりついたハルハ部の人々は、康熙帝に助けを求めた。
康熙帝はハルハの人々を受け入れ、避難物資と牧草地を与えた上、
ガルダン・ハーンにモンゴル高原を明け渡し、元いた天山北路に戻るように求めた。

泰陵。
祠の後ろにつながる土饅頭のまわりは、丸くレンガの壁で囲まれており、
その壁の上をぐるりと一周することができる。
ガルダン・ハーンが撤退を承知しないため、両者の関係が次第に悪化。
ついに康熙帝自らが、出陣してガルダン・ハーンとの戦いに臨むという事態に発展した。
康熙29年(1690)、ガルダン率いるジュンガル軍が、モンゴル高原から不毛の地・ゴビ砂漠を縦断し、
木蘭囲場の少し北、北京から直線距離でわずか700里しか離れていないウランブトンに現れた。
そこで清軍と激突するのだが、
ガルダンはなんと、帝政ロシアあたりから買い入れたのか、西洋の最新鋭の大砲を引きずって砂漠を超えて来ており、
そのすさまじいばかりの威力に康熙帝の叔父、生母の弟である「国舅」の[にんべん+冬]国鋼が、
一瞬で大砲に吹っ飛ばされて壮絶な最期を遂げたという。
清側の犠牲は大きく、ガルダンはそのまま一気に北京まで攻め入ると息巻いた。
実際、ウランブトンから北京までは目と鼻の先、
間一髪と言うところまで肉薄したのである。
これを迎え撃つ清側の覚悟も悲壮、
各牛禄(ニル)から鉄砲手を8人駆り出したと言われる。
ニルは八旗の最低単位、一組10人と言うから、その中から8人も出すと言うのは、
「ほとんど傾国」・・・・と記録にも言う。
北京城の城門は固く閉ざされ、城内の米価が三両も上がる騒ぎとなった。
幸いにも、清軍のこのような悲壮な防衛力の厚さに
さすがにガルダンも無理だと観念したのか、和議を申し入れに来て、
そのどさくさにさっさとゴビ砂漠の北へ引き揚げて行った。

泰陵。
土饅頭を取り囲む城壁と土饅頭。
この下に雍正帝が眠る。
清朝の統治層が本気で肝を冷やす事件だったと言っていい。
そんな経緯も受けて、木蘭囲場での活動、その周辺への八旗兵の入植には、さらに一層力が入るようになったのである。
毎年、春の訪れとともに、北京から
王公大臣ら、八旗軍、皇帝一家、後宮の妃ら、皇子皇孫、宦官宮女に至るまで
数万人が木蘭囲場に向けて移動した。
移動中、身分が下の人たちは蒙古包(ゲル、天幕)を立てて野営するが、
皇帝とその家族らのためには、北京から木蘭囲場までの間の450㎞の間に21ヶ所の行宮が建設された。
そうした行宮の周辺には、八旗兵が常駐する村が配置されるようになる。
21ヶ所の行宮の一ヶ所であった承徳では、
康熙42年(1703)、行宮をさらに発展させ、広大な敷地に築山や池、川の中に宮殿が点在する「避暑山荘」の建設が始まった。
その周囲には、皇族、大臣らもこぞって屋敷を建設。
さらに毎年やってくるモンゴル王公らのために、ラマ教の寺院も建てられ、チベットやモンゴルからラマ僧らが呼び寄せられ、常駐するようになる。
承徳はちょっとした街に発展、周囲にはさらに八旗の駐屯軍が配備された。
このように北京から木蘭囲場までの間は、
大げさにいえば、もう足の踏み場もないほどに八旗兵で埋め尽くされたことになる。
北京の北部の各重要関所である居庸関、古北口、喜峰口、独石口もその地帯の中にすっぽりを入っていることは、いうまでもない。
居庸関の場合も、内も外も八旗兵の駐屯地で埋め尽くされ、
しかも居庸関まで、とてもではないが、道中の絨毯爆撃のような幾重にも張り巡らされた防衛線を突破できるものではない。
今でも北京から承徳までの道中を地図で見ると、
「なんとか満族村」、「なんとか旗郷」と言った名前で埋め尽くされている。

北京の東北郊外から承徳にかけての地図。
満族の地名で埋め尽くされている。

泰陵。
土饅頭を取り囲む城壁と土饅頭。
この下に雍正帝が眠る。
ぽちっと、押していただけると、
励みになります!

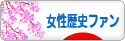
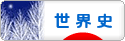
康熙20年(1681)には、北京の東北、北京とゴビ砂漠との間の森林地帯に「木蘭囲場」という狩り場を作った。
春先から晩秋に至るまでの実に半年もの間、ここでモンゴル王公らと
日がな狩りやら、キャンプやら、宴会やら、ラマ教の法会やらに明け暮れるのである。
その中には、康熙帝の娘(皇女)を嫁がせた相手の「婿」王公もいたりして、
その皇女が生んだ息子が、将来はこの祭典に参加するような手はずになっていた--。
虎、鹿を中心とした動物が捕れたという。
そんな中、康熙27年(1688)に西北モンゴル、オイラートのジュンガル部のガルダン・ハーンが東に移動して
漠北(ゴビ砂漠の北側。現在の外モンゴル)のハルハ部を襲撃するという事件が起きた。
泡を食ったハルハ部の人々数十万人が、死の恐れも伴うゴビ砂漠の縦断をものともせずに大挙して南下、
康熙帝に保護を求めるという所謂「ハルハ部の大南下」があった。
元々、漠南と漠北のモンゴル諸部は、親戚関係のようなもの。
漠南にたどりついたハルハ部の人々は、康熙帝に助けを求めた。
康熙帝はハルハの人々を受け入れ、避難物資と牧草地を与えた上、
ガルダン・ハーンにモンゴル高原を明け渡し、元いた天山北路に戻るように求めた。

泰陵。
祠の後ろにつながる土饅頭のまわりは、丸くレンガの壁で囲まれており、
その壁の上をぐるりと一周することができる。
ガルダン・ハーンが撤退を承知しないため、両者の関係が次第に悪化。
ついに康熙帝自らが、出陣してガルダン・ハーンとの戦いに臨むという事態に発展した。
康熙29年(1690)、ガルダン率いるジュンガル軍が、モンゴル高原から不毛の地・ゴビ砂漠を縦断し、
木蘭囲場の少し北、北京から直線距離でわずか700里しか離れていないウランブトンに現れた。
そこで清軍と激突するのだが、
ガルダンはなんと、帝政ロシアあたりから買い入れたのか、西洋の最新鋭の大砲を引きずって砂漠を超えて来ており、
そのすさまじいばかりの威力に康熙帝の叔父、生母の弟である「国舅」の[にんべん+冬]国鋼が、
一瞬で大砲に吹っ飛ばされて壮絶な最期を遂げたという。
清側の犠牲は大きく、ガルダンはそのまま一気に北京まで攻め入ると息巻いた。
実際、ウランブトンから北京までは目と鼻の先、
間一髪と言うところまで肉薄したのである。
これを迎え撃つ清側の覚悟も悲壮、
各牛禄(ニル)から鉄砲手を8人駆り出したと言われる。
ニルは八旗の最低単位、一組10人と言うから、その中から8人も出すと言うのは、
「ほとんど傾国」・・・・と記録にも言う。
北京城の城門は固く閉ざされ、城内の米価が三両も上がる騒ぎとなった。
幸いにも、清軍のこのような悲壮な防衛力の厚さに
さすがにガルダンも無理だと観念したのか、和議を申し入れに来て、
そのどさくさにさっさとゴビ砂漠の北へ引き揚げて行った。

泰陵。
土饅頭を取り囲む城壁と土饅頭。
この下に雍正帝が眠る。
清朝の統治層が本気で肝を冷やす事件だったと言っていい。
そんな経緯も受けて、木蘭囲場での活動、その周辺への八旗兵の入植には、さらに一層力が入るようになったのである。
毎年、春の訪れとともに、北京から
王公大臣ら、八旗軍、皇帝一家、後宮の妃ら、皇子皇孫、宦官宮女に至るまで
数万人が木蘭囲場に向けて移動した。
移動中、身分が下の人たちは蒙古包(ゲル、天幕)を立てて野営するが、
皇帝とその家族らのためには、北京から木蘭囲場までの間の450㎞の間に21ヶ所の行宮が建設された。
そうした行宮の周辺には、八旗兵が常駐する村が配置されるようになる。
21ヶ所の行宮の一ヶ所であった承徳では、
康熙42年(1703)、行宮をさらに発展させ、広大な敷地に築山や池、川の中に宮殿が点在する「避暑山荘」の建設が始まった。
その周囲には、皇族、大臣らもこぞって屋敷を建設。
さらに毎年やってくるモンゴル王公らのために、ラマ教の寺院も建てられ、チベットやモンゴルからラマ僧らが呼び寄せられ、常駐するようになる。
承徳はちょっとした街に発展、周囲にはさらに八旗の駐屯軍が配備された。
このように北京から木蘭囲場までの間は、
大げさにいえば、もう足の踏み場もないほどに八旗兵で埋め尽くされたことになる。
北京の北部の各重要関所である居庸関、古北口、喜峰口、独石口もその地帯の中にすっぽりを入っていることは、いうまでもない。
居庸関の場合も、内も外も八旗兵の駐屯地で埋め尽くされ、
しかも居庸関まで、とてもではないが、道中の絨毯爆撃のような幾重にも張り巡らされた防衛線を突破できるものではない。
今でも北京から承徳までの道中を地図で見ると、
「なんとか満族村」、「なんとか旗郷」と言った名前で埋め尽くされている。

北京の東北郊外から承徳にかけての地図。
満族の地名で埋め尽くされている。

泰陵。
土饅頭を取り囲む城壁と土饅頭。
この下に雍正帝が眠る。
ぽちっと、押していただけると、
励みになります!



















ほおほお。そんな講談がありましたか。
ちょっと興味ありますねー。