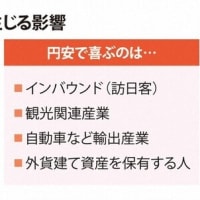ヒグマ(OSO18)はなぜ肉食化したのか
このブログの2023年10月23日の記事「クマの出没が増加―クマはなぜ人前に出
るようになったか」で、その一つの背景として耕作放棄地の増加を指摘しました。
すなわち、以前はクマの生息域だった山奥と集落の間には畑が広がり、クマは人目
につかず集落や町に出ることはできなかった。
しかし、耕作放棄地が増えると、そこは藪となり姿を隠して集落や町に一気に出る
ことができるようになった。
このような状態が続いている間にクマが人を恐れなくなり、集落や町に出没するよ
うになった、という事情が一つの背景としてあります。
さらに、今年はクマの主食であるドングリ類の木の実が不作で、エサを求めて人の
住む場所に出没するようになった、という自然界の異変も関係していました。
前回の記事はおおよそ以上のような説明であったと思います。ここで少し補足して
おくと、以上の記述の事例は東北地方におけるツキノワグマの出没にかんする現象
でしたが、北海道のツキノワグマについては、事情がやや異なります。
今から4年ほど前、「OSO18」と命名されたヒグマが話題となりました。この
ヒグマ「OSO18」は、射殺されるまでに酪農家が飼育していた60頭以上の牛
を次々に襲って食べていました。
しかし「OSO18」は、それと知らずに今年の7月に釧路町内であっけなくハン
ターに射殺されました。
ところでヒグマが、冬眠前の一時期、川を遡上するサケと捕まえる光景はよくテレ
ビで紹介されますが、これはサケが遡上する川筋に生息するクマの場合で、本来は、
木の実などを主食としています。
ところが、食べられた牛の数から推測すると、「OSO18」は動物の肉を主食に
していたとみられます。
「OSO18」のような肉食の個体は特殊だと考えられていますが、そうではなく
環境が生み出した可能性がある、という指摘もあります。
つまり、北海道がOSO18の捕獲を依頼した特別対策班の藤本靖氏は、
ハンターが撃ったシカが山中でかなり放置されている。クマは腐った肉で
も食べる。山をクマのレストランにしているようなものだ。OSOのよう
な危険な個体が増える可能性はある。
と語っています。
藤本氏は、北海道の山中には多くのシカ(エゾシカ)の死骸が放置されており、
その肉を食べたヒグマがその後、肉食化するかもしれない、というのだ。
この意味で、環境だけでなく人為的な要素も加わっているといえます。
その一つは、ハンターの減少です。北海道で鉄砲による猟ができる免許を持っ
ている人は減少傾向にある、という現実です。
90年代には9000人以上いましたが、21年には6600人まで減って
しまいました。
次に、エゾシカを食材として消費するのが難しい、という事情があります。
エゾシカの成獣は大体100~120キロ程度で、1頭から取れる肉は40
キロ前後です。
牛や豚や鶏と比べて歩留まりが悪く処理方法にも一定の技術が要ります。ま
た、加工できる業者も少なく、独自にルートを持っていないと簡単に販売も
できません。
私自身、かつてハンターと猟に出かけ、シカ(この場合はニホンジカ)を捕
って肉を食べたことがありますが脂分が少なくあまりおいしいとは思いませ
んでした。
また、多くのハンターは狩猟だけに興味があり、その動物を解体する技術も
なく、どのように利用するかという点にはあまり興味がありません。
こうして、シカの数はどんどん増えるばかりです。“OSO18”の被害にあっ
た厚岸町では昨年5月、国有林内で100頭分を超すほどのシカの骨や皮が
見つかりました。何者かが不法投棄したとみられています。
町の担当者は年に何回かシカの死骸を回収することがあるそうです。町では
ハンターに適切に処理するよう呼び掛けているが、猟期に捕って放置されて
も抑止する方法はない、とお手上げの状態です。
シカの死骸の放置が問題となるのは、そもそも数自体が増えているからです。
北海道では、昨年度の道内のシカの推定生息数は72万頭で、前年度から3
万頭増えたと推計されいます。
2014~21年度は60万頭台で推移していたが、近年増加傾向にあります。
この理由として、エサ場となる農地の開墾が進んだこと、温暖化で積雪が減
って生息域が拡大したことが挙げられています。
シカの数は1990年代に入って爆発的に増えたが、一方でハンターの減少と高
齢化が進む中で、レジャー目的の一般狩猟者や団体に依存している現状では
シカの絶対数を抑制することはできません。
酪農学園大の佐藤喜和教授(野生動物生態学)は
ヒグマがシカの死骸を食べることに慣れれば、探すようになるだろ
う。そもそも生きているシカを襲う個体もいなくはない。OSOの
ような個体が頻繁に出てくることはないだろうが、シカの残滓(死
骸―筆者注)が増えれば肉食をする個体が出てくる可能性はゼロで
はない。
と危惧しています(以上、『東京新聞』2023年12月3日)。
ヒグマと肉食について、私には忘れられない過去の出来事があります。私が
所属していた大学の探検部は毎年夏に北海道のどこかで一ヶ月の長期合宿を
します。
私は2年連続で知床を選びました。その過程で何回かヒグマに出会いました。
縦走の最後は知床半島先端部の台地にある「知床沼」(私たちが勝手にそう
呼んでいた)の近くをベースキャンプの場にして、周辺を探索しました。
ここは知床半島唯一の水場なので、多くの大学生や登山者がやはりベース
キャンプを張っていました。
私が卒業して数年後に、ある大学のパーティーのテントがヒグマに襲われ、
中にいた大学生の一人が林の中に連れ込まれて、食べられてしまいました。
私はその場にいたわけではありませんが、後にその場にいた他の大学生が
書いた報告書を読むと、ただ襲われただけではなく、食われたとしか思え
ない状況が細かく記されていました。
こうした経験から私は、ヒグマはドングリ類(ブナ、ミズナラなど)を主食
とするという表現はまちがいではないが、私は状況によっては肉食もあり得
る、と考えてきました。
さて、問題はこの先です。きっかけは何であれ、“OSO18”のように牛を
主食にするようなヒグマの行為はほかのヒグマも学習していた可能性は十分
あります。
今後も、シカや牛などを食べる行為が他のヒグマにも学習され何世代が続い
てゆくと、やがてその行為はDNAに組み込まれ、ヒグマは草食動物であり
肉食動物でもある“雑食動物”となってゆく可能性があります。
私は、自然環境の変化でヒグマの主なエサであるドングリ類の減少、シカの
増加、ハンターの減少、シカ肉の利用の困難さなどが、やがて動物の生態を
変えていってしまうのではないか、という危惧を抱いています。
この意味で、“OSO18”は私たちに重要な問題と警告を突き付けていると
思います。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
このブログの2023年10月23日の記事「クマの出没が増加―クマはなぜ人前に出
るようになったか」で、その一つの背景として耕作放棄地の増加を指摘しました。
すなわち、以前はクマの生息域だった山奥と集落の間には畑が広がり、クマは人目
につかず集落や町に出ることはできなかった。
しかし、耕作放棄地が増えると、そこは藪となり姿を隠して集落や町に一気に出る
ことができるようになった。
このような状態が続いている間にクマが人を恐れなくなり、集落や町に出没するよ
うになった、という事情が一つの背景としてあります。
さらに、今年はクマの主食であるドングリ類の木の実が不作で、エサを求めて人の
住む場所に出没するようになった、という自然界の異変も関係していました。
前回の記事はおおよそ以上のような説明であったと思います。ここで少し補足して
おくと、以上の記述の事例は東北地方におけるツキノワグマの出没にかんする現象
でしたが、北海道のツキノワグマについては、事情がやや異なります。
今から4年ほど前、「OSO18」と命名されたヒグマが話題となりました。この
ヒグマ「OSO18」は、射殺されるまでに酪農家が飼育していた60頭以上の牛
を次々に襲って食べていました。
しかし「OSO18」は、それと知らずに今年の7月に釧路町内であっけなくハン
ターに射殺されました。
ところでヒグマが、冬眠前の一時期、川を遡上するサケと捕まえる光景はよくテレ
ビで紹介されますが、これはサケが遡上する川筋に生息するクマの場合で、本来は、
木の実などを主食としています。
ところが、食べられた牛の数から推測すると、「OSO18」は動物の肉を主食に
していたとみられます。
「OSO18」のような肉食の個体は特殊だと考えられていますが、そうではなく
環境が生み出した可能性がある、という指摘もあります。
つまり、北海道がOSO18の捕獲を依頼した特別対策班の藤本靖氏は、
ハンターが撃ったシカが山中でかなり放置されている。クマは腐った肉で
も食べる。山をクマのレストランにしているようなものだ。OSOのよう
な危険な個体が増える可能性はある。
と語っています。
藤本氏は、北海道の山中には多くのシカ(エゾシカ)の死骸が放置されており、
その肉を食べたヒグマがその後、肉食化するかもしれない、というのだ。
この意味で、環境だけでなく人為的な要素も加わっているといえます。
その一つは、ハンターの減少です。北海道で鉄砲による猟ができる免許を持っ
ている人は減少傾向にある、という現実です。
90年代には9000人以上いましたが、21年には6600人まで減って
しまいました。
次に、エゾシカを食材として消費するのが難しい、という事情があります。
エゾシカの成獣は大体100~120キロ程度で、1頭から取れる肉は40
キロ前後です。
牛や豚や鶏と比べて歩留まりが悪く処理方法にも一定の技術が要ります。ま
た、加工できる業者も少なく、独自にルートを持っていないと簡単に販売も
できません。
私自身、かつてハンターと猟に出かけ、シカ(この場合はニホンジカ)を捕
って肉を食べたことがありますが脂分が少なくあまりおいしいとは思いませ
んでした。
また、多くのハンターは狩猟だけに興味があり、その動物を解体する技術も
なく、どのように利用するかという点にはあまり興味がありません。
こうして、シカの数はどんどん増えるばかりです。“OSO18”の被害にあっ
た厚岸町では昨年5月、国有林内で100頭分を超すほどのシカの骨や皮が
見つかりました。何者かが不法投棄したとみられています。
町の担当者は年に何回かシカの死骸を回収することがあるそうです。町では
ハンターに適切に処理するよう呼び掛けているが、猟期に捕って放置されて
も抑止する方法はない、とお手上げの状態です。
シカの死骸の放置が問題となるのは、そもそも数自体が増えているからです。
北海道では、昨年度の道内のシカの推定生息数は72万頭で、前年度から3
万頭増えたと推計されいます。
2014~21年度は60万頭台で推移していたが、近年増加傾向にあります。
この理由として、エサ場となる農地の開墾が進んだこと、温暖化で積雪が減
って生息域が拡大したことが挙げられています。
シカの数は1990年代に入って爆発的に増えたが、一方でハンターの減少と高
齢化が進む中で、レジャー目的の一般狩猟者や団体に依存している現状では
シカの絶対数を抑制することはできません。
酪農学園大の佐藤喜和教授(野生動物生態学)は
ヒグマがシカの死骸を食べることに慣れれば、探すようになるだろ
う。そもそも生きているシカを襲う個体もいなくはない。OSOの
ような個体が頻繁に出てくることはないだろうが、シカの残滓(死
骸―筆者注)が増えれば肉食をする個体が出てくる可能性はゼロで
はない。
と危惧しています(以上、『東京新聞』2023年12月3日)。
ヒグマと肉食について、私には忘れられない過去の出来事があります。私が
所属していた大学の探検部は毎年夏に北海道のどこかで一ヶ月の長期合宿を
します。
私は2年連続で知床を選びました。その過程で何回かヒグマに出会いました。
縦走の最後は知床半島先端部の台地にある「知床沼」(私たちが勝手にそう
呼んでいた)の近くをベースキャンプの場にして、周辺を探索しました。
ここは知床半島唯一の水場なので、多くの大学生や登山者がやはりベース
キャンプを張っていました。
私が卒業して数年後に、ある大学のパーティーのテントがヒグマに襲われ、
中にいた大学生の一人が林の中に連れ込まれて、食べられてしまいました。
私はその場にいたわけではありませんが、後にその場にいた他の大学生が
書いた報告書を読むと、ただ襲われただけではなく、食われたとしか思え
ない状況が細かく記されていました。
こうした経験から私は、ヒグマはドングリ類(ブナ、ミズナラなど)を主食
とするという表現はまちがいではないが、私は状況によっては肉食もあり得
る、と考えてきました。
さて、問題はこの先です。きっかけは何であれ、“OSO18”のように牛を
主食にするようなヒグマの行為はほかのヒグマも学習していた可能性は十分
あります。
今後も、シカや牛などを食べる行為が他のヒグマにも学習され何世代が続い
てゆくと、やがてその行為はDNAに組み込まれ、ヒグマは草食動物であり
肉食動物でもある“雑食動物”となってゆく可能性があります。
私は、自然環境の変化でヒグマの主なエサであるドングリ類の減少、シカの
増加、ハンターの減少、シカ肉の利用の困難さなどが、やがて動物の生態を
変えていってしまうのではないか、という危惧を抱いています。
この意味で、“OSO18”は私たちに重要な問題と警告を突き付けていると
思います。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------