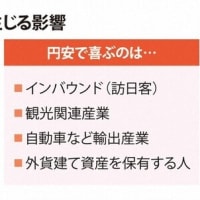川から日本を見る(3)-「塩の道」と文化の形成-
前回の記事では、日本における川の舟運についてその概略を書きました。そこでは、明治期以前(場所によっては大正
初期,さらには昭和初期まで)の日本では川が人や物の運輸交通に大きな役割を果たしていたことを説明しました。
とりわけ、川の舟運は、米や木材のように重いものを大量に運ぶ場合には、不可欠の運搬手段だったといえます。
海から内陸に物資を輸送する場合、人々は、川の舟運が利用できる遡行限界まで舟を利用し、そこからは馬や牛の背
に乗せて最終目的地まで運んだのです。
逆に内陸から海に向かう場合、舟が利用できる場所まで家畜や人間の背で運び、そこで舟に積み替えて下流に向かって
荷物を運びました。
この際、川沿いには幾つもの川の港、つまり「河岸」が発達し、これらは舟運と共に発展してやがて町や都市になって
ゆきました。
今日の内陸都市は、かつては直接間接に、川の舟運と関係し、河岸であった例が少なくありません。
たとえば、阿武隈川中流の福島、北上川上流の盛岡・現北上市・水沢市、利根川沿いの多数の町や都市がそうです。
下の写真は、荒川(または利根川)で使われていた「高瀬舟」(実物大に再建された舟。千葉県立関宿城博物館所蔵)で、
2013年8月に埼玉
県立川の博物館特別展示で公開された)。(注1)
写真 高瀬舟(大型の高瀬舟では1000俵の米俵を積んだ、という記録もある)

ところで、舟運が大きな役割を果たしたのは、米や木材の運搬や人の移動だけではありませんでした。人々の生活に
とっては、塩こそが絶対に欠かせない生活物資でした。
塩は生物としての人間にとって必要不可欠の物質であることは太古の昔から現代まで変わりません。アフリカでは
あの広大なサハラ砂漠を横断し、内陸のヒマラヤ山地のネパールやチベットには、はるばるインド洋から舟と家畜の
背で塩が運ばれました。
事情は日本でも同じです。岩塩が採れない日本では、内陸に住む人たちは海で作られた塩を手に入れる必要があります。
冷蔵庫の無かった時代に、野菜や魚などの海産物を保存するには、乾燥させるか塩漬けにするしか方法がなかったからです。
とりわけ、冬に野菜が採れない寒冷地では、春から秋にかけて収穫した野菜を塩漬け(漬物)にして冬を乗り切らなければ
なりません。
戦国時代に、今川氏と北条氏の経済封鎖で太平洋側からの塩を絶たれて困っていた武田信玄に、それまで敵対していた
上杉謙信が日本海の塩を送って助けた、「敵に塩を送る」という故事にもあるように、塩が絶たれると、人々の生活は成り
立たなかったのです。
そこで、人々は万難を排して、生活必需品である塩を手に入れようとしたのです。他方、沿岸で塩の生産をしていた地域
では確実に売れる商品として、塩の販売ルートを開拓してきました。
下の図1は富岡儀八『塩の道を探る』(岩波書店、岩波新書 1983年)より、図2は平島,裕正『塩の道』(講談社 1975)
引用した全国の「塩の道」の概略図です。
これらの図からも明らかなように、「塩の道」は全国に張り巡らされ、とりわけ内陸奥深くまで塩が川の舟運が利用されてい
たことが分かります。
図1 全国塩の道図(北海道を除く)

言うまでもなく、「塩の道」は、塩だけを運んでいたわけではありません。川を上る舟は塩以外にも前回紹介した、京都の
ひな人形や雑貨が最上川を上って運ばれたように、衣類や様々な加工品なども運ばれました。
ここで、興味深いのは、関東以西の「塩の道」と、いわゆる主要街道との関係です。たとえば、関東から西に向かってみて
みると、川はおおむね南北に流れています。これが、ほとんど「塩の道」となっていました。
ところが、東海道と山陽道は「塩の道」を直角に貫いています。川をそのもの、あるいは川と連結した「塩の道」は生活に
必要な物資や商品を運ぶ「民衆の道」だったのです。
これにたいして、江戸時代に整備された街道とは、主要な都市と都市を最短距離で結ぶ道で、主に政治の中心であった江戸
の幕府権力が地方を支配するために作った、「権力の道」「政治の道」でした。
ただし、関東から東の阿武隈川、北上川、最上川などは南北に走る脊梁山に沿って南北方向に流れており、これらの河川
では、「民衆の道」「生活の道」としての「塩の道」と「権力の道」とは機能的に重なっていました。
もっとも、全ての「塩の道」が川の舟運を経由していたわけではありません。舟が使えない浅くて小さな川しかないところ
では、人や物の運輸交通は陸路を使わざるを得ませんが、その場合でさえ、できる限り川筋に沿って道が作られていました。
なぜなら、川筋というのは山間部のもっとも低い場所を流れ、登り降りがもっと少ない、という地理的に有利な条件がある
からです。
こうした陸路も含めて、ここでは「川の道」という考え方も採用します。
「塩の道」は、物だけでなく、文化や宗教も伝えました。というのも、物が動くときには人も一緒に動いていたので、言語、
風俗、習慣、宗教、広い意味での文化なども伝わったからです。
たとえば、利根川と荒川の流域に現在までも継承されている大杉神社信仰をみてみましょう。
茨城県稲敷市阿波に大杉神社があります。ご神体が大着なすぎの木であることからこの名が付きました。
伝承によれば、「神護景雲元年(767年)、大和三輪で修行を終えて故郷の二荒山に向かう途中の勝道商人の勝道上人が,
疫病に苦しむ当地の惨状を救おうと巨杉に祈念しとところ,病魔を退散させた」。
これより以後,大杉大明神として祀られることになった。この大杉は霞ヶ浦や北浦を航行する船からもよく見えたため,船乗り
のランドマークにもなり,大杉神社は船乗りたちの航海安全の神として広く信仰を集めるようになりました。
各地からの人や物が往来する水路は物流の根幹であると同時に,疫病の伝染経路でもありました。大杉神社はやがて航海安全と
疫病退散の神として,舟運関係者によって利根川水系を中心に荒川・新河岸川,鬼怒川,渡良瀬川,久慈川,那珂川の流域全体
にひろまっていったのです。
現在でも,大杉神社信仰の勧請地は関東北部の河川流域に存在しています。興味深いのは,大杉神社信仰の伝播にあわせて
「大杉囃子」という芸能も広まったことです。
この囃子は元和年間(1615~1623年)に,十二座神楽とともに「悪魔払いの囃子」として紀州から伝えられたとの伝承があり、
現在でも大杉神社信仰がある幾つかの場所では,村を廻る厄払いのお囃子が祭りとして行われています(注2)。
これは,舟運を媒介として信仰と芸能がセットになり,流域文化を形成していった好例です。次に、方言や信仰の分布と河川
交通との関係を見てみましょう。
越中(現在の富山県)の方言は、隣接する越前(福井県)や越後(新潟県)よりも岐阜県の飛騨地方と同様の方言が多いのです。
また、信仰面でも、越後に信州戸隠山への信仰が伝播し,戸隠講が広く分布するが,越中では地元の石動山,立山への信仰が篤く,
戸隠信仰の分布はありません。
越中・加賀と飛騨・美濃方面との間には神通川その他多くの南北流する河川があり、越後と信州との間には信濃川をはじめとして
幾つかの河川が両地域とを結んでいて、民俗文化分布の諸相に行政区画とは別の地域の系統の境界線を形成させた重要な要因とな
ってきたことがわかります。(注3)
また、天竜川中・下流域では、南信州・愛知県東部、静岡県西部が一つの文化圏をなしており、そこでは方言も共通し、「花祭り」
という古来からの神事も共通しています。
このような例はたくさんあります。こうした事例から、近代以前の日本では川舟や川に沿って作られた道がヒト・モノ・文化の
移動と伝達の手段となって、長い年月をかけて地域文化が形成されてきたことが分かります。
(注1)「高瀬舟」の大きさは、全長が25メートルから30メートルほどです。なお舟の名称は場所によって異なります。「高瀬舟」の他に、
同規模の舟としては「ひらた舟」などもある。
(注2)埼玉県立川の博物館『和船大図鑑~荒川をぐなぐ舟・ひと・モノ』2013年:26-27ページ。
(注3)北見,俊夫 1981 『川の文化』(日本書籍 1981)(205-6)
前回の記事では、日本における川の舟運についてその概略を書きました。そこでは、明治期以前(場所によっては大正
初期,さらには昭和初期まで)の日本では川が人や物の運輸交通に大きな役割を果たしていたことを説明しました。
とりわけ、川の舟運は、米や木材のように重いものを大量に運ぶ場合には、不可欠の運搬手段だったといえます。
海から内陸に物資を輸送する場合、人々は、川の舟運が利用できる遡行限界まで舟を利用し、そこからは馬や牛の背
に乗せて最終目的地まで運んだのです。
逆に内陸から海に向かう場合、舟が利用できる場所まで家畜や人間の背で運び、そこで舟に積み替えて下流に向かって
荷物を運びました。
この際、川沿いには幾つもの川の港、つまり「河岸」が発達し、これらは舟運と共に発展してやがて町や都市になって
ゆきました。
今日の内陸都市は、かつては直接間接に、川の舟運と関係し、河岸であった例が少なくありません。
たとえば、阿武隈川中流の福島、北上川上流の盛岡・現北上市・水沢市、利根川沿いの多数の町や都市がそうです。
下の写真は、荒川(または利根川)で使われていた「高瀬舟」(実物大に再建された舟。千葉県立関宿城博物館所蔵)で、
2013年8月に埼玉
県立川の博物館特別展示で公開された)。(注1)
写真 高瀬舟(大型の高瀬舟では1000俵の米俵を積んだ、という記録もある)

ところで、舟運が大きな役割を果たしたのは、米や木材の運搬や人の移動だけではありませんでした。人々の生活に
とっては、塩こそが絶対に欠かせない生活物資でした。
塩は生物としての人間にとって必要不可欠の物質であることは太古の昔から現代まで変わりません。アフリカでは
あの広大なサハラ砂漠を横断し、内陸のヒマラヤ山地のネパールやチベットには、はるばるインド洋から舟と家畜の
背で塩が運ばれました。
事情は日本でも同じです。岩塩が採れない日本では、内陸に住む人たちは海で作られた塩を手に入れる必要があります。
冷蔵庫の無かった時代に、野菜や魚などの海産物を保存するには、乾燥させるか塩漬けにするしか方法がなかったからです。
とりわけ、冬に野菜が採れない寒冷地では、春から秋にかけて収穫した野菜を塩漬け(漬物)にして冬を乗り切らなければ
なりません。
戦国時代に、今川氏と北条氏の経済封鎖で太平洋側からの塩を絶たれて困っていた武田信玄に、それまで敵対していた
上杉謙信が日本海の塩を送って助けた、「敵に塩を送る」という故事にもあるように、塩が絶たれると、人々の生活は成り
立たなかったのです。
そこで、人々は万難を排して、生活必需品である塩を手に入れようとしたのです。他方、沿岸で塩の生産をしていた地域
では確実に売れる商品として、塩の販売ルートを開拓してきました。
下の図1は富岡儀八『塩の道を探る』(岩波書店、岩波新書 1983年)より、図2は平島,裕正『塩の道』(講談社 1975)
引用した全国の「塩の道」の概略図です。
これらの図からも明らかなように、「塩の道」は全国に張り巡らされ、とりわけ内陸奥深くまで塩が川の舟運が利用されてい
たことが分かります。
図1 全国塩の道図(北海道を除く)

言うまでもなく、「塩の道」は、塩だけを運んでいたわけではありません。川を上る舟は塩以外にも前回紹介した、京都の
ひな人形や雑貨が最上川を上って運ばれたように、衣類や様々な加工品なども運ばれました。
ここで、興味深いのは、関東以西の「塩の道」と、いわゆる主要街道との関係です。たとえば、関東から西に向かってみて
みると、川はおおむね南北に流れています。これが、ほとんど「塩の道」となっていました。
ところが、東海道と山陽道は「塩の道」を直角に貫いています。川をそのもの、あるいは川と連結した「塩の道」は生活に
必要な物資や商品を運ぶ「民衆の道」だったのです。
これにたいして、江戸時代に整備された街道とは、主要な都市と都市を最短距離で結ぶ道で、主に政治の中心であった江戸
の幕府権力が地方を支配するために作った、「権力の道」「政治の道」でした。
ただし、関東から東の阿武隈川、北上川、最上川などは南北に走る脊梁山に沿って南北方向に流れており、これらの河川
では、「民衆の道」「生活の道」としての「塩の道」と「権力の道」とは機能的に重なっていました。
もっとも、全ての「塩の道」が川の舟運を経由していたわけではありません。舟が使えない浅くて小さな川しかないところ
では、人や物の運輸交通は陸路を使わざるを得ませんが、その場合でさえ、できる限り川筋に沿って道が作られていました。
なぜなら、川筋というのは山間部のもっとも低い場所を流れ、登り降りがもっと少ない、という地理的に有利な条件がある
からです。
こうした陸路も含めて、ここでは「川の道」という考え方も採用します。
「塩の道」は、物だけでなく、文化や宗教も伝えました。というのも、物が動くときには人も一緒に動いていたので、言語、
風俗、習慣、宗教、広い意味での文化なども伝わったからです。
たとえば、利根川と荒川の流域に現在までも継承されている大杉神社信仰をみてみましょう。
茨城県稲敷市阿波に大杉神社があります。ご神体が大着なすぎの木であることからこの名が付きました。
伝承によれば、「神護景雲元年(767年)、大和三輪で修行を終えて故郷の二荒山に向かう途中の勝道商人の勝道上人が,
疫病に苦しむ当地の惨状を救おうと巨杉に祈念しとところ,病魔を退散させた」。
これより以後,大杉大明神として祀られることになった。この大杉は霞ヶ浦や北浦を航行する船からもよく見えたため,船乗り
のランドマークにもなり,大杉神社は船乗りたちの航海安全の神として広く信仰を集めるようになりました。
各地からの人や物が往来する水路は物流の根幹であると同時に,疫病の伝染経路でもありました。大杉神社はやがて航海安全と
疫病退散の神として,舟運関係者によって利根川水系を中心に荒川・新河岸川,鬼怒川,渡良瀬川,久慈川,那珂川の流域全体
にひろまっていったのです。
現在でも,大杉神社信仰の勧請地は関東北部の河川流域に存在しています。興味深いのは,大杉神社信仰の伝播にあわせて
「大杉囃子」という芸能も広まったことです。
この囃子は元和年間(1615~1623年)に,十二座神楽とともに「悪魔払いの囃子」として紀州から伝えられたとの伝承があり、
現在でも大杉神社信仰がある幾つかの場所では,村を廻る厄払いのお囃子が祭りとして行われています(注2)。
これは,舟運を媒介として信仰と芸能がセットになり,流域文化を形成していった好例です。次に、方言や信仰の分布と河川
交通との関係を見てみましょう。
越中(現在の富山県)の方言は、隣接する越前(福井県)や越後(新潟県)よりも岐阜県の飛騨地方と同様の方言が多いのです。
また、信仰面でも、越後に信州戸隠山への信仰が伝播し,戸隠講が広く分布するが,越中では地元の石動山,立山への信仰が篤く,
戸隠信仰の分布はありません。
越中・加賀と飛騨・美濃方面との間には神通川その他多くの南北流する河川があり、越後と信州との間には信濃川をはじめとして
幾つかの河川が両地域とを結んでいて、民俗文化分布の諸相に行政区画とは別の地域の系統の境界線を形成させた重要な要因とな
ってきたことがわかります。(注3)
また、天竜川中・下流域では、南信州・愛知県東部、静岡県西部が一つの文化圏をなしており、そこでは方言も共通し、「花祭り」
という古来からの神事も共通しています。
このような例はたくさんあります。こうした事例から、近代以前の日本では川舟や川に沿って作られた道がヒト・モノ・文化の
移動と伝達の手段となって、長い年月をかけて地域文化が形成されてきたことが分かります。
(注1)「高瀬舟」の大きさは、全長が25メートルから30メートルほどです。なお舟の名称は場所によって異なります。「高瀬舟」の他に、
同規模の舟としては「ひらた舟」などもある。
(注2)埼玉県立川の博物館『和船大図鑑~荒川をぐなぐ舟・ひと・モノ』2013年:26-27ページ。
(注3)北見,俊夫 1981 『川の文化』(日本書籍 1981)(205-6)