2014年9月26日の朝刊に、経済学者宇沢弘文先生が亡くなられていたことが報じられた。27日の毎日新聞の「余録」では、「現実は経済学者にとって『ある特殊なケース』にすぎない」とした宇沢さんが、「市場外の環境や制度あっての市場経済である」とし、人間的な暮らしと社会を保つために打ち出した『社会的共通資本』という考え方を紹介し、「その知的営為を問題解決に用いなければならぬのは私たちである」としている。
あの人に会いたい 宇沢弘文(1928年 - 2014年)
28日は日曜日なので、先生の死を悼む特集記事が各紙面を埋めることであろう。NHKは特別番組を放映するのであろうか、マスメディアの心を知りたいと思う。私は「経済学と人間の心(2003年、東洋経済新報社発行)」を先生の遺言として、改めて読ませていただいている。
参考:子どもを粗末にしない国にしよう~社会的共通資本の視点~
一般に経済学に人間の心が入ることは許されないこととされ、経済現象、モノと貨幣との関係を客観的(数学的)に説明する学問であることが経済の関係学会では常識とされてきた。農業においても、農業を生活から切り離した生産と考えることが専門とされ、生産費という概念を導入して規模拡大によるコストダウンを目標とすることが常識とされてきた。しかし、その理論が農業を破壊し、地方を疲弊させている。
経済という言葉は、古くより中国では「経世済民」の意味で使用されていた。日本では江戸時代に太宰春台が『経済録』(18世紀前半)で、「凡(およそ)天下國家を治むるを經濟と云、世を經め民を濟ふ義なり」としているそうだ。民を救うための経済が、貨幣経済の進展により民を切り捨てる経済となってしまったことに、異議申し立てる民は少ない。
また、9月26日の毎日新聞の「余録」では、「世間ずれ」の言葉の使い方が、「世間の表裏に精通し、悪賢くなること」の意味から、「世の中の考えから外れている」の意味と考える若い人が圧倒的に多い(10代後半で85%、20代で80%)ことが指摘されている。 「智に働けば角が立つ。情に掉させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。」と夏目漱石が言う住みにくい「人の世」を世間と思っていたが、今の若い人は世間を世の中の規範と考えているのであろうか。
「地方創生」と言われるが、地方はビジネスだけでは創生できない。行政とビジネスと地域共同体をどう絆いで、「すべての人々の人間的尊厳と魂の自立が守られ、市民の基本的権利が最大限に確保できる経済(社会),宇沢弘文」を構築できるかが問われる時代となっている。その社会の規範については憲法に示してある。「余録」の心配に追加すれば、すべての人々を幸福にする社会の構築を目指すことが我々に与えられた責任と思う。このブログでその思いをこれからもつぶやかさせて頂くが、ここでは宇沢弘文先生著「経済学と人間の心」を読んでいただきたいので、その一部を簡単に紹介させていただく。
「昭和天皇と人間の心」
文化勲章受賞者と文化功労者を昭和天皇が招かれた講話の場で、
文化勲章受賞者(建築家) 超高層ビル設計の講話
昭和天皇「君、地震のときは、上の階にいる人はたいへんだそうだよ」
文化勲章受賞者「建物は大丈夫です」
昭和天皇「建物は大丈夫でも、人間はたいへんだそうだよ」
文化勲章受賞者「建物は大丈夫です」
このようなやりとりが3回ほど繰り返されて、昭和天皇はとうとう諦めて、黙ってしまわれた。
文化功労者(宇沢弘文 1983年:文化勲章は1997年)
社会的共通資本等の経済学を講話
昭和天皇「君!君は、経済、経済というけど、人間の心が大事だと言いたいのだね」
昭和天皇のお言葉は、経済学に人間の心を持ち込むのはタブーとしていた私(宇沢弘文)にとって、コペルニクス的転回ともいうべき一つの大きな転機を意味していた。
講話の後、昭和天皇を囲む食事の場で、宇沢弘文先生の旧知の入江侍従長が隣席で、「今日は宇沢くんのペースで飲みすぎてしまったよ」と言われたのに対して、「天皇陛下はなかなか魅力的な方ですね」と申し上げたところ、入江さんがすかさず言われた。「君、あれを育てるのに千年かかったよ!」私たちのこの会話を、昭和天皇は終始にこにこしながら聞いていらしたのである。
「ローマ法王と人間の心」
ローマ法王ヨハネ・パウロ二世から、21世紀を迎えるにあたり新しい「レールム・ノヴァルム」の作成への協力を求められた。(宇沢 弘文 東京大学名誉教授 著「始まっている未来 新しい経済学は可能か」より)
20世紀を迎えるときの基本的な考え方は、「資本主義の弊害と社会主義の幻想」であったのに対して、21世紀への展望を考えるとき資本主義とか社会主義という経済学のこれまでの考え方では決して解決できない。そこで、「社会主義の弊害と資本主義の幻想」こそ新しい「レールム・ノヴァルム」の主題にふさわしいと躊躇なく答えた。
そしてヨハネ・パウロ二世に直接ご進講する機会を与えられ、社会的共通資本の管理はどのような基準にしたがっておこなったらよいかという話題になったとき、「それぞれの職業的専門家の集団が、職業的規律と専門的知見にもとづいておこなうべきである」という持論をお話した後、次のような意味のことをヨハネ・パウロ二世に申し上げた。「いま、人々の魂は荒廃し、心は苦悩に浸されている。この世界の危機的状況のもとで、あなたは倫理を専門とする職業的専門家として、もっと積極的に発言しなければならない」
ヨハネ・パウロ二世はにこにこしながら、言われた。
「この部屋で、私に説教したのは、お前が最初だ」
初稿 2014.9.27 更新 2015.9.17
あの人に会いたい 宇沢弘文(1928年 - 2014年)
28日は日曜日なので、先生の死を悼む特集記事が各紙面を埋めることであろう。NHKは特別番組を放映するのであろうか、マスメディアの心を知りたいと思う。私は「経済学と人間の心(2003年、東洋経済新報社発行)」を先生の遺言として、改めて読ませていただいている。
参考:子どもを粗末にしない国にしよう~社会的共通資本の視点~
一般に経済学に人間の心が入ることは許されないこととされ、経済現象、モノと貨幣との関係を客観的(数学的)に説明する学問であることが経済の関係学会では常識とされてきた。農業においても、農業を生活から切り離した生産と考えることが専門とされ、生産費という概念を導入して規模拡大によるコストダウンを目標とすることが常識とされてきた。しかし、その理論が農業を破壊し、地方を疲弊させている。
経済という言葉は、古くより中国では「経世済民」の意味で使用されていた。日本では江戸時代に太宰春台が『経済録』(18世紀前半)で、「凡(およそ)天下國家を治むるを經濟と云、世を經め民を濟ふ義なり」としているそうだ。民を救うための経済が、貨幣経済の進展により民を切り捨てる経済となってしまったことに、異議申し立てる民は少ない。
また、9月26日の毎日新聞の「余録」では、「世間ずれ」の言葉の使い方が、「世間の表裏に精通し、悪賢くなること」の意味から、「世の中の考えから外れている」の意味と考える若い人が圧倒的に多い(10代後半で85%、20代で80%)ことが指摘されている。 「智に働けば角が立つ。情に掉させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。」と夏目漱石が言う住みにくい「人の世」を世間と思っていたが、今の若い人は世間を世の中の規範と考えているのであろうか。
「地方創生」と言われるが、地方はビジネスだけでは創生できない。行政とビジネスと地域共同体をどう絆いで、「すべての人々の人間的尊厳と魂の自立が守られ、市民の基本的権利が最大限に確保できる経済(社会),宇沢弘文」を構築できるかが問われる時代となっている。その社会の規範については憲法に示してある。「余録」の心配に追加すれば、すべての人々を幸福にする社会の構築を目指すことが我々に与えられた責任と思う。このブログでその思いをこれからもつぶやかさせて頂くが、ここでは宇沢弘文先生著「経済学と人間の心」を読んでいただきたいので、その一部を簡単に紹介させていただく。
「昭和天皇と人間の心」
文化勲章受賞者と文化功労者を昭和天皇が招かれた講話の場で、
文化勲章受賞者(建築家) 超高層ビル設計の講話
昭和天皇「君、地震のときは、上の階にいる人はたいへんだそうだよ」
文化勲章受賞者「建物は大丈夫です」
昭和天皇「建物は大丈夫でも、人間はたいへんだそうだよ」
文化勲章受賞者「建物は大丈夫です」
このようなやりとりが3回ほど繰り返されて、昭和天皇はとうとう諦めて、黙ってしまわれた。
文化功労者(宇沢弘文 1983年:文化勲章は1997年)
社会的共通資本等の経済学を講話
昭和天皇「君!君は、経済、経済というけど、人間の心が大事だと言いたいのだね」
昭和天皇のお言葉は、経済学に人間の心を持ち込むのはタブーとしていた私(宇沢弘文)にとって、コペルニクス的転回ともいうべき一つの大きな転機を意味していた。
講話の後、昭和天皇を囲む食事の場で、宇沢弘文先生の旧知の入江侍従長が隣席で、「今日は宇沢くんのペースで飲みすぎてしまったよ」と言われたのに対して、「天皇陛下はなかなか魅力的な方ですね」と申し上げたところ、入江さんがすかさず言われた。「君、あれを育てるのに千年かかったよ!」私たちのこの会話を、昭和天皇は終始にこにこしながら聞いていらしたのである。
「ローマ法王と人間の心」
ローマ法王ヨハネ・パウロ二世から、21世紀を迎えるにあたり新しい「レールム・ノヴァルム」の作成への協力を求められた。(宇沢 弘文 東京大学名誉教授 著「始まっている未来 新しい経済学は可能か」より)
20世紀を迎えるときの基本的な考え方は、「資本主義の弊害と社会主義の幻想」であったのに対して、21世紀への展望を考えるとき資本主義とか社会主義という経済学のこれまでの考え方では決して解決できない。そこで、「社会主義の弊害と資本主義の幻想」こそ新しい「レールム・ノヴァルム」の主題にふさわしいと躊躇なく答えた。
そしてヨハネ・パウロ二世に直接ご進講する機会を与えられ、社会的共通資本の管理はどのような基準にしたがっておこなったらよいかという話題になったとき、「それぞれの職業的専門家の集団が、職業的規律と専門的知見にもとづいておこなうべきである」という持論をお話した後、次のような意味のことをヨハネ・パウロ二世に申し上げた。「いま、人々の魂は荒廃し、心は苦悩に浸されている。この世界の危機的状況のもとで、あなたは倫理を専門とする職業的専門家として、もっと積極的に発言しなければならない」
ヨハネ・パウロ二世はにこにこしながら、言われた。
「この部屋で、私に説教したのは、お前が最初だ」
初稿 2014.9.27 更新 2015.9.17










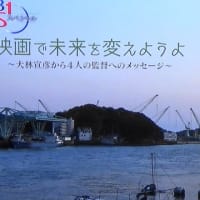



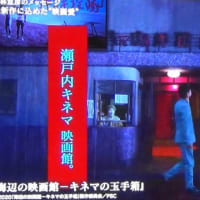
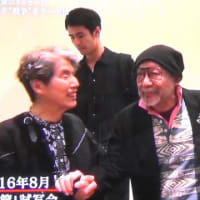

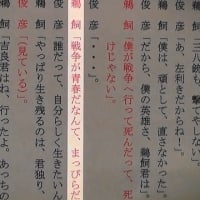



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます