「お金に換算できない大切なもの」を生かすのが里山資本主義なら、「お金で買えないものはない」と考えるのが市場原理主義。
その市場原理主義者が「戦争になれば逃げる。他人は知らない」と発言して瀬戸内寂聴さんを激怒させたそうだ。
もっとも、市場とお金は尊重するが自然と人を尊重しないのが市場原理主義なので、戦争になれば自分は一番に逃げるだけでなく、戦争に至らなくても危険な状態に自然と人を置くことに心を痛めることはないのでしょう。今や政治を動かしているのは政治家ではなく市場原理主義であり、市場原理主義は国のレベルから世界のレベルまで、そしてその一方で国のレベルから個人のレベルまで侵食していて、彼らにとって国民も他者なのですから。
*参考 「市場原理主義」批判と「市場原理」
「お金で買えるもの買えないもの」について考える
ここで唐突ですが、「福島核災害と核時代の破滅的なリスクを語る」を紹介しておきます。ノーム・チョムスキーさんの「自分の罪は問わない。問うのは他人の犯した罪だけだ」という人の心の指摘から、アメリカの世界戦略と日本との関係の歴史についてまでの説明は広く深い。なお、冒頭に出てくるアナンダ・グローバー氏は国連人権理事会の特別報告官で、その報告は国連自由権規約委員会(第7 マイノリティの人権とその保護 4 福島原発事故被害者)で論議されている。
里山はコモンズ(共有地)、宇沢先生の言われる「社会的共有資本」、そして里山における自然との共生"は「世界に誇れる日本の文化」でもある。自然が与えてくれる資源、景観、教育等や3世代家族が同じ地域に生きることの価値はお金では買えない。お金で買おうとすれば心が破壊されてしまう。
例えば、里山を管理するために牛やヤギ、羊に協力してもらおう。農家に最も適しているのは繁殖だ。放牧で里山を管理すれば除草でき、景観と子供の遊びの場が提供できる。地域で協力すれば地域を美しく管理でき絆も深まる。畜産は搾乳や肥育などのシステムが必要だが、システムの一部の放牧繁殖を地域で担えないか。里山の資源、景観、教育を行政、ビジネス、地域共同体でどうつないでシステムを構築するか。それは市場原理主義からは決して生まれない。
里山と農家と市民が、「君あり、故に我あり」という心でつながることでシステムもつながる。「君あり、故に我あり」を呪文として、市場とお金の尊重から自然と人の尊重へと解脱したいものだ。
2014.12.3 一部追加修正
その市場原理主義者が「戦争になれば逃げる。他人は知らない」と発言して瀬戸内寂聴さんを激怒させたそうだ。
もっとも、市場とお金は尊重するが自然と人を尊重しないのが市場原理主義なので、戦争になれば自分は一番に逃げるだけでなく、戦争に至らなくても危険な状態に自然と人を置くことに心を痛めることはないのでしょう。今や政治を動かしているのは政治家ではなく市場原理主義であり、市場原理主義は国のレベルから世界のレベルまで、そしてその一方で国のレベルから個人のレベルまで侵食していて、彼らにとって国民も他者なのですから。
*参考 「市場原理主義」批判と「市場原理」
「お金で買えるもの買えないもの」について考える
ここで唐突ですが、「福島核災害と核時代の破滅的なリスクを語る」を紹介しておきます。ノーム・チョムスキーさんの「自分の罪は問わない。問うのは他人の犯した罪だけだ」という人の心の指摘から、アメリカの世界戦略と日本との関係の歴史についてまでの説明は広く深い。なお、冒頭に出てくるアナンダ・グローバー氏は国連人権理事会の特別報告官で、その報告は国連自由権規約委員会(第7 マイノリティの人権とその保護 4 福島原発事故被害者)で論議されている。
里山はコモンズ(共有地)、宇沢先生の言われる「社会的共有資本」、そして里山における自然との共生"は「世界に誇れる日本の文化」でもある。自然が与えてくれる資源、景観、教育等や3世代家族が同じ地域に生きることの価値はお金では買えない。お金で買おうとすれば心が破壊されてしまう。
例えば、里山を管理するために牛やヤギ、羊に協力してもらおう。農家に最も適しているのは繁殖だ。放牧で里山を管理すれば除草でき、景観と子供の遊びの場が提供できる。地域で協力すれば地域を美しく管理でき絆も深まる。畜産は搾乳や肥育などのシステムが必要だが、システムの一部の放牧繁殖を地域で担えないか。里山の資源、景観、教育を行政、ビジネス、地域共同体でどうつないでシステムを構築するか。それは市場原理主義からは決して生まれない。
里山と農家と市民が、「君あり、故に我あり」という心でつながることでシステムもつながる。「君あり、故に我あり」を呪文として、市場とお金の尊重から自然と人の尊重へと解脱したいものだ。
2014.12.3 一部追加修正










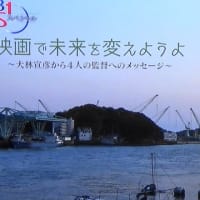



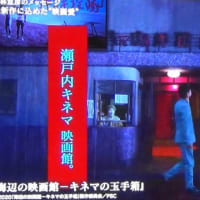
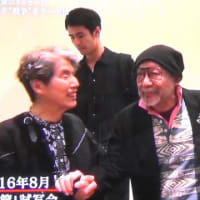

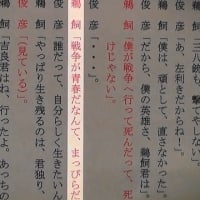



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます