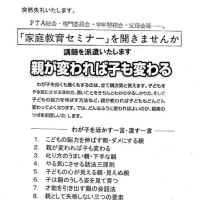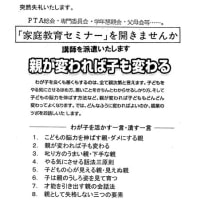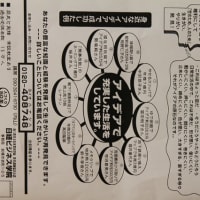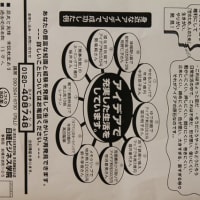前回に引き続いて不登校のことについて記していきたいと思います。5月から6月にかけて不登校の数がとても多くなることについて触れました。
はじめは学校恐怖症と呼ばれることが多かった不登校も、次には、「登校拒否」と呼ばれるようになりました。その後この用語がかなり長い期間に渡って使われることになりました。一般的に学校に登校しない状態を登校拒否の言葉で表現していました。
しかし、その後、登校拒否は「不登校」と呼ばれるようになりました。これは不登校の子どもたちが示す状態を見て、それに合わせて呼び方を変更したものと考えられます。
学校に登校していない子どもたちのうちには、学校への登校を意識的に、意図的に拒否しているわけではなく、何となく特別な意味も意識もなく登校しない状態にある子どもたちも多くみられるようになってきたことが背景にあると思われます。
不安や神経症的な状況から登校を拒否するのではなく、学校生活に意味や意義が見つからない、何となく学校生活は面白くない、学習等への意欲も低くなっていて登校しない子どももみられるようになったことから、「不登校」つまり学校に登校していない状態にある子どもたちということで、状態像を示す言葉として「不登校」と呼ばれるようになったと思われます。
この言葉であれば、登校しない理由は何であれ、登校していない状態を示している子どもたちということですから、どのような場合にも使用できると思われます。現在は不登校の言葉が一般化して使われるようになっています。
さて、次に不登校の出現率等について記してみます。前に、いわゆる戦後において社会的な状況等から児童生徒の欠席率がとても高かったことを記しました。しかし、その後1975年から76年(昭和52年ころ)までは欠席率は次第に下がってきました。子どもの数が少なくなって欠席が少なくなったのではなく、実際に欠席者が少なくなりました。ただこの時期以降は子どもの登校拒否・不登校は次第に多くなりました。最近では子どもの数は著しく少なくなっていますが、不登校の子どもの数はさらに増加しています。
文部省(その後の文部科学省)は昭和40年代から登校していない小・中学生の数を統計的に取り始めました。
身体的な状況や経済的な状況など、理解の出来る理由ではなく、あまり合理的に理解できないと思われる欠席児童生徒を、「学校嫌い」を理由とする欠席として統計を行いました。はじめは年間に50日以上として、1月から12月までの統計でしたが、その後は4月から翌年3月までに年間30日以上欠席した児童・生徒となっています。
最近の統計では、不登校の出現率は、小学校では1.3%程度で、総数は8万人程度です。中学校では、出現率は5%程度で総数は16万人程度です。
なお高校は義務教育ではないので、文部科学省の正式な統計はありません。ただし、高校の中退率は統計としてあります。
いずれにしても、とても多くの子どもたちが学校に登校していない状態にあります。しかも、その状態が長く続くとともに数が増加傾向にあるので大変な問題だと思われます。
いわゆる不登校の子どもたちが現れてから、すでに60年程度が経過していると思われますが、この間、有効な手が打てていない状態が続いています。
また、子どもがなぜ不登校になるのか、その背景要員や理由も明確になっておらず対策が進んでいないのが現状と思われます。
不登校問題に関する経過等についてここまで期してきましたので、次には、さらに不登校の各種の要因や対応策について、現状で行えそうなことを中心に記してみたいと思います。よろしくお願いします。また、感想等もよろしくです。