東奥日報WEBのアンケート『春の山菜、何が好き?』2006年版
合計 347 票
赤字は前回までに食べたもの。
上位のものでもまだ食べてないものがかなりある。これはやはり食べなければ!ということでまさかの第5回。
このアンケートも2011年度版が発表されていました。
東奥日報WEBのアンケート『春の山菜、何が好き?』2011年版
合計 315 票
なんと!山菜の王様『タラの芽』王国が陥落!
『ミズ』が下克上を果たした形だ。2位は不動の宰相『タケノコ』がキープ!
女王『コシアブラ』にいたっては今回も選択肢にないばかりか、『その他』で名前があがることもなかった…。
スーパーでも良く見かけるようになり、かなりメジャーになってきていると思うのだが…。
天ぷらで食べることが多いタラの芽、フキノトウがランクを落としてることから、今回は回答者の年齢層が高かったのかもしれないと考えられた。おばあちゃんは『フキ』の煮物が大好きなイメージあるんだけどなぁ。
さあ、マニアックな『万歳!山菜!!その5!』はじまるよ!

■ワラビ(蕨)・・・コバノイシカグマ科ワラビ属
日本全国はおろか、世界中に分布するメジャーな山菜。

唐草模様に似てる。
 道の駅◇20本で250円
道の駅◇20本で250円
知名度が高いメジャーな山菜の一つだが、食べるためにはあく抜きという少し面倒な工程が必要。
これはワラビ自体に発癌性の毒があるから。この毒、名前をプタキロサイドというらしい。
wikipediaによると、
人間でもアク抜きをせずに食べると中毒を起こす(ワラビ中毒)。また、調理したものであっても大量に食べると体じゅうが大量出血症状になり、骨髄がしだいに破壊され死に至る。【wikipedia】
あらやだ怖い。
しかし、ワラビ中毒がきのこ中毒のように問題にならないことから判るように、副食として食べている程度ならば害はない。またアク抜き処理をすればプタキロサイドはほとんど分解され、ジェノンという物質になる。【wikipedia】
また、ワラビはビタミンB1を破壊するアノイリナーゼという酵素も含んでいるが、こちらは熱で失活する。
これを知って、ほっと一安心。
だが、安心して食べるためにも、美味しく食べるためにもあく抜きは重要な作業工程だ。
ネットでしっかり調べる。
あく抜きに使われるのが木灰(木を燃やした灰)の他、

タンサン(重曹)である。タンサン=重曹の成分は炭酸水素ナトリウム。木灰同様、水に溶けると水溶液は弱アルカリ性を呈する。
ワラビのあく抜きの方法にはお湯に重曹を入れる方法や、ワラビに重曹をふりかけ、その上から熱湯をかける方法などがあるようだが、今回は以下の方法で行った。
1.鍋に2リットルのお湯を沸かす。
2.お湯が沸いたら、ワラビをいれ、その上から10gのタンサンを溶かす。
3.ワラビ全体にお湯がいきわたるよう、ワラビの上下を入れ替える。
4.ワラビ投入から20秒後、火を止め、鍋を下ろす。
5.ワラビが水からはみ出ないよう落とし蓋をし、一晩おく。
6.翌朝、水を捨て、水道水と入れ替える。
7.何度か水替えを繰り返して完成。
(この方法ってあってます?すごい不安なんですけど、プタキロサイドが残んないかどうか。)

ワラビ同様、アク抜きの必要があるゼンマイといっしょにアク抜きした様子。
なに?この赤い水。これでだいじょうぶなの!?
茹でる際に、銅鍋を使ったり、銅線をいっしょに入れると緑色が鮮やかになるそうだ。
ワラビの緑色の成分である葉緑体のクロロフィルは、そのままでは不安定だが、銅イオンと結合し、銅クロロフィルとなることで安定するかららしい。
同様の理由でナスの漬物や黒豆を煮るときににクギやパチンコ玉など、鉄を入れるのも。色素のアントシアニンと鉄イオンが結合sて、紫色がきれいに出るからなんですってよ。奥さん!

(山田靜之ら ワラビ発癌物質-化学研究とDNA修飾- 蛋白質 核酸 酵素 Vol.43 No.6(1998))
プタキロサイドは弱アルカリ性下で究極発癌物質ジエノンへと変化する。このジエノンこそが諸悪の根源『究極発癌物質』で、体内に入るとDNAを切断しまくることとで癌を発生させちゃうらしい。
上記の図を見ると『あく抜き』と言う工程は、煮る事と、重曹水の弱アルカリ性とでワラビの繊維を柔らかくするのに加え、プタキロサイドをジエノンに変化させているのではないかと考えられた。
またその後、水替えを繰り返すことで水を中性に戻し、安全で安定なプテロシンBへと変化させているのではないかと思われる。
と、すれば、現在行われているあく抜きの方法は非常に理にかなっているが、プタキロサイドが発見されたのは1978年。
ワラビ自体は江戸時代以前から食されているが、山菜に木灰をぶっかけて、その後水替えをするという奇抜であるが合理的な方法を誰が思いついたのか?非常に不思議である。
たぶん、茹で大豆をわらで巻いたら納豆ができたり、羊の胃袋でできた水筒に山羊乳を入れたらチーズができた系の偶然の発見なんだろうけど、ほんとに不思議。
・・・・・
大昔、今ほど食べるものが豊富でない時代のこと・・・。
貧しい老夫婦は他に食べるものもないので、アクが強く美味しくないワラビを食べていた。
おじいさんがしばかりのついでに裏山から取ってきたものだ。
「今年も、たくさん生えてきておるな。おや、小さなワラビが・・・。かわいそうだから取らないでおいてやろう。」
「いつも食べ物をありがとう。来年のためにも残しておこうかな。」
ゆうげのとき、おじいさんはいつものように囲炉裏でワラビを煮ていた。
その時、土間の戸が音もなくスーッと開いたかと思うと、家の外から金色に輝くワラビの毛が飛んでくるではないか。
ワラビの毛はあれよあれよという間におじいさんの鼻の中へと入る。
おじいさん、たまらず大くしゃみ!!
『ハックショイ!!!』
おじいさんのくしゃみは囲炉裏の灰を吹き飛ばし、灰が鍋に盛大に入ってしまった!
「あらあら、おじいさん!なんてことするんですか!」とおばあさん。
「食べるものが少ないのに、すまんのう。婆さんや。」とおじいさん。
「灰が入ってしまったけど、仕方ない。いただきましょう。」
「少しくらい灰が入ったほうが薬になるってもんじゃ。」
「まあ、おじいさんたら。ホホホ」
「ハハハ。」
で、食べたら・・・。
「あら、あくが抜けていつもより美味しいわ!」
「ほんとじゃのう!」
二人はこの方法で美味しい茹でワラビを作って売り、村一番の金持ちになったそうな。
おじいさんのやさしさに感激したワラビの精のしわざかも知れません…。
めでたしめでたし。
・・・のような「わらび長者」的なストーリーがあったのかもしれない。

『わらびのたたき』
アク抜きしたわらびを細かく切り、フリージングバッグ等に入れて包丁の背で叩く。
叩けば叩くほど、ぬめりが出てくる。すりこぎですりつぶしてもいいらしい。
醤油やだし汁をかけ、ご飯にかけて食べると、山菜の甘みとほろ苦さ、ぬめりが美味い。
めんつゆや醤油をかけていただく。
ねばりの感じや味わいが山形名物の『だし』に似てる、ご飯が進みそう!

※参考 『山形のだし』
山形県村山地方の郷土料理。夏野菜と香味野菜を細かくきざみ、醤油などであえたもの。ご飯や豆腐にかけて食す。一般的には出汁と区別して、山形のだしと呼ばれる。【wikipedia】

水に長く漬けすぎて身がグズグズになってしまった。味噌をつけて食べる。おつまみにいいですね。
-----

■ぜんまい(薇)・・・ゼンマイ科ゼンマイ属
わらびとともに有名な山菜のひとつ。
あくが強いため、茹でこぼしてアク抜きをする。
天日に干して、手で揉み、針金の様な形で干した『干しゼンマイ』と言う形態で保存が可能。

干しゼンマイ
 道の駅◇300円
道の駅◇300円

くるりと丸まった穂先がかわいいゼンマイ。
時計やおもちゃに入っているねじを巻いて動力にする『発条(ぜんまい)』はこの植物に似ていることから名付けられたそうだ。
ちなみに発条は『ばね』とも読みます。

『ぜんまいのナムル』で食べてみる。
フライパンにごま油を熱し、ぜんまいひとつかみ分を投入。
しょうゆ 大さじ1
酒 大さじ1/2
砂糖 小さじ1
みりん 小さじ1
水 大さじ1
を加え、汁がなくなるまで炒める。
炒りゴマを挽いてかけ、完成。
私がイメージするナムルはもっと茶色っぽい色なのだが、あまり茶色くならなかった。
コリコリとした歯ごたえが楽しく、えぐみ、にがみが甘辛いタレで隠されて美味しくいただけた。
ぜんまいは漢字で書くと薇。
この感じどこかで見たことが・・・?
薇(ぜんまい)
薔薇(ばら)
同じ字!?
華やかな姿が人に愛でられる薔薇。かたや野山にひっそりと生える質実剛健な薇とはなんとも対照的ではないか。
親をなくした双子の姉妹が裕福な貴族、食べるのもやっとな貧民にそれぞれ引き取られる『薔薇と薇』なんてドラマがありそう。
昔、『牡丹と薔薇』って言う昼ドラがあったけどね!
漢字で、『薔薇』と言えば、こんなエピソードがある。
かつて、作家の伊集院静が稀代の美人女優である夏目雅子とバーで飲んでいたときのこと。
「バラという時を漢字で書ける?」と聞いたそうだ。
彼女がすぐに降参すると、彼は手元にあったナプキンにすらすらと“薔薇”と書いて見せたという。
結果、これによって夏目雅子のハートを射止め、二人は結婚したのだった。
みんなで練習しよう。
薔薇
一説によると、薔薇でなく、『憂鬱』だったと言う説もあるらしい。
でも、「ユウウツ」って書けるかい?なんて口説き方はあまりロマンチックじゃないので、薔薇だったと信じたい。
でも一応、練習しよう。
憂鬱

こんにゃくと油揚げとともに、醤油とみりんで炒め煮した。
ぜんまいのコリコリとした食感とほのかな苦味、こんにゃくの歯ごたえと甘いおつゆをぎゅ~っと含んだ油揚げとの相性はバツグン。
ぜんまいの章おわり。
-----

■あざみ(薊)・・・キク科アザミ属
北半球に多く分布する、葉にトゲを持つ植物。
赤~紫の花を咲かせる。
そのトゲで外敵から国を守ったというエピソードで、スコットランドの国花とされている。
東北地方や長野県で食される。葉は味噌汁の具に。根は天ぷらにされる他、ごぼうの代替として使われる。

ぎざぎざに切れこんだ葉っぱの先端にはとげが生えていて、ちくちくと痛い。
洗うのもままならないほど。

広く食べられるように味噌汁の具にしてみた。
ゆでると、とげは鋭くとがってはいるが、柔らかくて痛くないのが意外だった。
苦味はかなり強く、他の野菜がたくさんある中で、わざわざこれを使う理由が良くわかんない。
この苦味こそが、春の味ともいえるのだが・・・。
『春は苦味を盛れ!』
ほろ苦い山菜は春の訪れを感じさせるものだ。
春に苦いものを食べる目的は、冬の間に体にたまった毒を出すと言う意味合いもあるらしい。
苦味の原因は葉物の山菜に多く含まれる「アルカロイド」「タンニン」、根に多く含まれる「ポリフェノール」など。
冬眠から目覚めた熊は、冬の間休んでいた胃腸を活性化させるためにタケノコや木の芽など苦いものを積極的に食べるのだそうだ。
山菜取りにお出かけの際は熊よけを忘れずに…。
-----

■山ウド産直センター◇5本で150円。
以前も食べたが、今回天然モノが売られていたので、買ってみた。

前回の栽培モノ。土をかけて育てるのでクキの大半が白い。

固い皮を削って、にんじんと一緒にきんぴらにした。きんぴらってこんな料理だっけ?
かなりスジっぽかったけど、ウドの放つ清冽な香りがゴボウで作るのとはまったく違った味わいで楽しい。

皮をむいた中身を刻んで酢味噌で食べる。
見た目に反して、えぐみやあくが全然ない!
キュウリやウリのような食感。はちみつにつけたらメロンぽいだろうな。
-----

■ネマガリタケ(姫竹・千島笹)・・・イネ科タケ亜科ササ属
青森県ではおでんの定番。アクが少なく、茹でたり焼いたりして様々な方法で食べられるほか、煮物のメンバーに顔を並べることも多い。
普通のタケノコは竹の子供だが、ネマガリタケは笹の子供。見分け方はタケノコは成長するに従い外皮がはがれていくが、ネマガリタケは皮がついたまま成長するのだそうだ。
 道の駅◇20本300円
道の駅◇20本300円
なんと美しい野菜だろうか!?
白から紫、紫から若緑へとグラデーションを描くその色合いは見ていて飽きない。

皮のまま焼いて、アツアツのところを皮をむいて豪快に貪り食う!!
甘くもほろ苦いその美味と、早く次を食べたいけど熱くて皮を剥けないもどかしさと。
wikipediaによると、
『長野県北信地方と新潟県上越地方の山間部では、根曲竹(長野県側の呼称)またはタケノコ(新潟県側の呼称)と呼ばれるチシマザサの新芽が取れる時期(=5月~6月にかけて)に、鯖の缶詰(水煮)と一緒に味噌汁にして食べる習慣がある。
ですって。
何それ、おいしそう!
と言うわけでやってみた。
【俺のじゃないレシピ】
1.水500mlを鍋に入れる。
2.大羽の煮干の頭を取ってたてに半分に割り、中の内臓を捨てる。これを10匹分、鍋に入れる
3.沸騰させ、1分経ったら、煮干を出す。このだし汁をクッキングペーパーなどで漉す。
4.皮をむいたネマガリタケ、ワカメなどの具を入れ、柔らかくなるまで煮る。
5.味噌25g(おおさじ一杯分くらい)をお玉に取り、火を消す。
6.おたまの中にだし汁を引き込みながら、味噌を溶かしていく。完全に溶けたら、
7.火をつけ、弱火で沸かす。味噌の溶け残りがないように。
8.沸騰の泡が出はじめたら火を消す。
9.サバの水煮の缶詰を汁ごと投入。
10.出来上がり。

おつゆせんべいを入れてせんべい汁風にしてみた。
見た目はちょっと汚らしいのですが、これめちゃめちゃ美味いですね。
サバと味噌がベストマッチ。サバから出る油が味噌と入り混じって出てくるコク、うまみは思い出すだけでもヨダレが出てきます。
良く考えればサバの味噌煮という料理があって、缶詰でも広く出回っているわけですから、サバと味噌との相性がいいのは当たり前。
なのに味噌汁にサバ缶をぶち込むと言う豪快で簡単な料理がここまで美味いとは…。
あまりのうまさに3日続けて食べてしまいました。
初めて食べましたが、今後の春の定番になりそうです。長野の人に感謝!
鯖もネマガリタケも青森の特産品なのにね。
さらに大きな鯖缶ならさぞかし美味かろうと思って、

HONIHO ホニホ 青森の正直 真鯖水煮 370g缶
で試してみました。

竹林から昇るせんべいの太陽をイメージ。名付けて『バンブー・ライジングサン』
さすがにこれは脂が強すぎて、気分が悪くなりました。

ふつうに100円で売ってるノーマルサイズの鯖缶が良いと思います。
以上、今回のトライアルで食べた山菜は
このようになりました!!!(食べたものを赤字で表示。)
あとは

秋田フキ
を食べてみたいですね。
これを見た瞬間、「となりのトトロ」でトトロが傘のかわりにさしてるやつだ!
と思いましたが、
![となりのトトロ [VHS]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/517T41H1PGL._SL300_.jpg)


トトロがさしていたのはフツーの傘でした。
ショック!

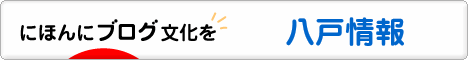

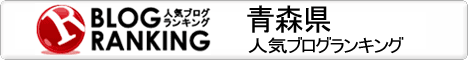

▲管理人のエネルギー源です。面白かったらポチっと押して応援してくださいね!
青森、八戸ブログのリンクとしてもどうぞ!
わさびの根っこって水中で育てると大きく、土で育てると小さくなるでしょ?その理由。
わさびは競争力が弱いから、根っこから菌を殺す毒をばらまくんだって。わさびの殺菌作用は有名だよね。
アリルイソチオシアネートっていって、これがわさびの辛味成分でもあるんだよね。
その毒で根っこに菌を飼ってるライバルの植物が育たないようにするんだけど、わさび自身もその毒にやられて大きくなれないんだって。
わさびドジ過ぎる。
わさびを水中で育てるとその毒が流されていくから、大きくなれるんだって。

| 順位 | 山菜名 | 割合 | 票数 |
| 1位 | タラの芽 | 29.4% | 102票 |
| 2位 | タケノコ | 21.3% | 74票 |
| 3位 | ワラビ・ゼンマイ | 11.2% | 39票 |
| 4位 | ミズ | 9.2% | 32票 |
| 5位 | 山ウド | 6.9% | 24票 |
| 6位 | フキ・フキノトウ | 6.3% | 22票 |
| 7位 | ギョウジャニンニク | 3.2% | 11票 |
| 8位 | シドケ | 2.9% | 10票 |
| 9位 | アザミ | 2.6% | 9票 |
| 10位 | その他(シオデ・ コシアブラ・アケビの芽) | 2.6% | 9票 |
| 11位 | コゴミ | 2.3% | 8票 |
| 12位 | 葉ワサビ | 2.0% | 7票 |
合計 347 票
赤字は前回までに食べたもの。
上位のものでもまだ食べてないものがかなりある。これはやはり食べなければ!ということでまさかの第5回。
このアンケートも2011年度版が発表されていました。
東奥日報WEBのアンケート『春の山菜、何が好き?』2011年版
| 順位 | 山菜名 | 割合 | 票数 |
| 1位 | ミズ | 22.9% | 72票 ↑3rank UP! |
| 2位 | タケノコ | 20.0% | 63票 → |
| 3位 | タラの芽 | 19.0% | 60票 ↓2rank DOWN! |
| 4位 | 山ウド | 14.6% | 46票 ↑1rank UP! |
| 5位 | ワラビ・ゼンマイ | 8.6% | 27票 ↓2rank DOWN! |
| 6位 | ギョウジャニンニク | 4.8% | 15票 ↑1rank UP |
| 7位 | シドケ | 3.2% | 10票 ↑1rank UP |
| 8位 | コゴミ | 2.9% | 9票 ↓3rank UP! |
| 9位 | フキ・フキノトウ | 2.5% | 8票 ↑3rank UP! |
| 10位 | アザミ | 0.6% | 2票 ↓1rank DOWN! |
| 11位 | その他(アイッコ) | 0.6% | 2票 |
| 12位 | 葉ワサビ | 0.3% | 1票 → |
合計 315 票
なんと!山菜の王様『タラの芽』王国が陥落!
『ミズ』が下克上を果たした形だ。2位は不動の宰相『タケノコ』がキープ!
女王『コシアブラ』にいたっては今回も選択肢にないばかりか、『その他』で名前があがることもなかった…。
スーパーでも良く見かけるようになり、かなりメジャーになってきていると思うのだが…。
天ぷらで食べることが多いタラの芽、フキノトウがランクを落としてることから、今回は回答者の年齢層が高かったのかもしれないと考えられた。おばあちゃんは『フキ』の煮物が大好きなイメージあるんだけどなぁ。
さあ、マニアックな『万歳!山菜!!その5!』はじまるよ!

■ワラビ(蕨)・・・コバノイシカグマ科ワラビ属
日本全国はおろか、世界中に分布するメジャーな山菜。

唐草模様に似てる。
 道の駅◇20本で250円
道の駅◇20本で250円知名度が高いメジャーな山菜の一つだが、食べるためにはあく抜きという少し面倒な工程が必要。
これはワラビ自体に発癌性の毒があるから。この毒、名前をプタキロサイドというらしい。
wikipediaによると、
人間でもアク抜きをせずに食べると中毒を起こす(ワラビ中毒)。また、調理したものであっても大量に食べると体じゅうが大量出血症状になり、骨髄がしだいに破壊され死に至る。【wikipedia】
あらやだ怖い。
しかし、ワラビ中毒がきのこ中毒のように問題にならないことから判るように、副食として食べている程度ならば害はない。またアク抜き処理をすればプタキロサイドはほとんど分解され、ジェノンという物質になる。【wikipedia】
また、ワラビはビタミンB1を破壊するアノイリナーゼという酵素も含んでいるが、こちらは熱で失活する。
これを知って、ほっと一安心。
だが、安心して食べるためにも、美味しく食べるためにもあく抜きは重要な作業工程だ。
ネットでしっかり調べる。
あく抜きに使われるのが木灰(木を燃やした灰)の他、

タンサン(重曹)である。タンサン=重曹の成分は炭酸水素ナトリウム。木灰同様、水に溶けると水溶液は弱アルカリ性を呈する。
ワラビのあく抜きの方法にはお湯に重曹を入れる方法や、ワラビに重曹をふりかけ、その上から熱湯をかける方法などがあるようだが、今回は以下の方法で行った。
1.鍋に2リットルのお湯を沸かす。
2.お湯が沸いたら、ワラビをいれ、その上から10gのタンサンを溶かす。
3.ワラビ全体にお湯がいきわたるよう、ワラビの上下を入れ替える。
4.ワラビ投入から20秒後、火を止め、鍋を下ろす。
5.ワラビが水からはみ出ないよう落とし蓋をし、一晩おく。
6.翌朝、水を捨て、水道水と入れ替える。
7.何度か水替えを繰り返して完成。
(この方法ってあってます?すごい不安なんですけど、プタキロサイドが残んないかどうか。)

ワラビ同様、アク抜きの必要があるゼンマイといっしょにアク抜きした様子。
なに?この赤い水。これでだいじょうぶなの!?
茹でる際に、銅鍋を使ったり、銅線をいっしょに入れると緑色が鮮やかになるそうだ。
ワラビの緑色の成分である葉緑体のクロロフィルは、そのままでは不安定だが、銅イオンと結合し、銅クロロフィルとなることで安定するかららしい。
同様の理由でナスの漬物や黒豆を煮るときににクギやパチンコ玉など、鉄を入れるのも。色素のアントシアニンと鉄イオンが結合sて、紫色がきれいに出るからなんですってよ。奥さん!

(山田靜之ら ワラビ発癌物質-化学研究とDNA修飾- 蛋白質 核酸 酵素 Vol.43 No.6(1998))
プタキロサイドは弱アルカリ性下で究極発癌物質ジエノンへと変化する。このジエノンこそが諸悪の根源『究極発癌物質』で、体内に入るとDNAを切断しまくることとで癌を発生させちゃうらしい。
上記の図を見ると『あく抜き』と言う工程は、煮る事と、重曹水の弱アルカリ性とでワラビの繊維を柔らかくするのに加え、プタキロサイドをジエノンに変化させているのではないかと考えられた。
またその後、水替えを繰り返すことで水を中性に戻し、安全で安定なプテロシンBへと変化させているのではないかと思われる。
と、すれば、現在行われているあく抜きの方法は非常に理にかなっているが、プタキロサイドが発見されたのは1978年。
ワラビ自体は江戸時代以前から食されているが、山菜に木灰をぶっかけて、その後水替えをするという奇抜であるが合理的な方法を誰が思いついたのか?非常に不思議である。
たぶん、茹で大豆をわらで巻いたら納豆ができたり、羊の胃袋でできた水筒に山羊乳を入れたらチーズができた系の偶然の発見なんだろうけど、ほんとに不思議。
・・・・・
大昔、今ほど食べるものが豊富でない時代のこと・・・。
貧しい老夫婦は他に食べるものもないので、アクが強く美味しくないワラビを食べていた。
おじいさんがしばかりのついでに裏山から取ってきたものだ。
「今年も、たくさん生えてきておるな。おや、小さなワラビが・・・。かわいそうだから取らないでおいてやろう。」
「いつも食べ物をありがとう。来年のためにも残しておこうかな。」
ゆうげのとき、おじいさんはいつものように囲炉裏でワラビを煮ていた。
その時、土間の戸が音もなくスーッと開いたかと思うと、家の外から金色に輝くワラビの毛が飛んでくるではないか。
ワラビの毛はあれよあれよという間におじいさんの鼻の中へと入る。
おじいさん、たまらず大くしゃみ!!
『ハックショイ!!!』
おじいさんのくしゃみは囲炉裏の灰を吹き飛ばし、灰が鍋に盛大に入ってしまった!
「あらあら、おじいさん!なんてことするんですか!」とおばあさん。
「食べるものが少ないのに、すまんのう。婆さんや。」とおじいさん。
「灰が入ってしまったけど、仕方ない。いただきましょう。」
「少しくらい灰が入ったほうが薬になるってもんじゃ。」
「まあ、おじいさんたら。ホホホ」
「ハハハ。」
で、食べたら・・・。
「あら、あくが抜けていつもより美味しいわ!」
「ほんとじゃのう!」
二人はこの方法で美味しい茹でワラビを作って売り、村一番の金持ちになったそうな。
おじいさんのやさしさに感激したワラビの精のしわざかも知れません…。
めでたしめでたし。
・・・のような「わらび長者」的なストーリーがあったのかもしれない。

『わらびのたたき』
アク抜きしたわらびを細かく切り、フリージングバッグ等に入れて包丁の背で叩く。
叩けば叩くほど、ぬめりが出てくる。すりこぎですりつぶしてもいいらしい。
醤油やだし汁をかけ、ご飯にかけて食べると、山菜の甘みとほろ苦さ、ぬめりが美味い。
めんつゆや醤油をかけていただく。
ねばりの感じや味わいが山形名物の『だし』に似てる、ご飯が進みそう!

※参考 『山形のだし』
山形県村山地方の郷土料理。夏野菜と香味野菜を細かくきざみ、醤油などであえたもの。ご飯や豆腐にかけて食す。一般的には出汁と区別して、山形のだしと呼ばれる。【wikipedia】

水に長く漬けすぎて身がグズグズになってしまった。味噌をつけて食べる。おつまみにいいですね。
-----

■ぜんまい(薇)・・・ゼンマイ科ゼンマイ属
わらびとともに有名な山菜のひとつ。
あくが強いため、茹でこぼしてアク抜きをする。
天日に干して、手で揉み、針金の様な形で干した『干しゼンマイ』と言う形態で保存が可能。

干しゼンマイ
 道の駅◇300円
道の駅◇300円
くるりと丸まった穂先がかわいいゼンマイ。
時計やおもちゃに入っているねじを巻いて動力にする『発条(ぜんまい)』はこの植物に似ていることから名付けられたそうだ。
ちなみに発条は『ばね』とも読みます。

『ぜんまいのナムル』で食べてみる。
フライパンにごま油を熱し、ぜんまいひとつかみ分を投入。
しょうゆ 大さじ1
酒 大さじ1/2
砂糖 小さじ1
みりん 小さじ1
水 大さじ1
を加え、汁がなくなるまで炒める。
炒りゴマを挽いてかけ、完成。
私がイメージするナムルはもっと茶色っぽい色なのだが、あまり茶色くならなかった。
コリコリとした歯ごたえが楽しく、えぐみ、にがみが甘辛いタレで隠されて美味しくいただけた。
ぜんまいは漢字で書くと薇。
この感じどこかで見たことが・・・?
薇(ぜんまい)
薔薇(ばら)
同じ字!?
華やかな姿が人に愛でられる薔薇。かたや野山にひっそりと生える質実剛健な薇とはなんとも対照的ではないか。
親をなくした双子の姉妹が裕福な貴族、食べるのもやっとな貧民にそれぞれ引き取られる『薔薇と薇』なんてドラマがありそう。
昔、『牡丹と薔薇』って言う昼ドラがあったけどね!
漢字で、『薔薇』と言えば、こんなエピソードがある。
かつて、作家の伊集院静が稀代の美人女優である夏目雅子とバーで飲んでいたときのこと。
「バラという時を漢字で書ける?」と聞いたそうだ。
彼女がすぐに降参すると、彼は手元にあったナプキンにすらすらと“薔薇”と書いて見せたという。
結果、これによって夏目雅子のハートを射止め、二人は結婚したのだった。
みんなで練習しよう。
薔薇
一説によると、薔薇でなく、『憂鬱』だったと言う説もあるらしい。
でも、「ユウウツ」って書けるかい?なんて口説き方はあまりロマンチックじゃないので、薔薇だったと信じたい。
でも一応、練習しよう。
憂鬱

こんにゃくと油揚げとともに、醤油とみりんで炒め煮した。
ぜんまいのコリコリとした食感とほのかな苦味、こんにゃくの歯ごたえと甘いおつゆをぎゅ~っと含んだ油揚げとの相性はバツグン。
ぜんまいの章おわり。
-----

■あざみ(薊)・・・キク科アザミ属
北半球に多く分布する、葉にトゲを持つ植物。
赤~紫の花を咲かせる。
そのトゲで外敵から国を守ったというエピソードで、スコットランドの国花とされている。
東北地方や長野県で食される。葉は味噌汁の具に。根は天ぷらにされる他、ごぼうの代替として使われる。

ぎざぎざに切れこんだ葉っぱの先端にはとげが生えていて、ちくちくと痛い。
洗うのもままならないほど。

広く食べられるように味噌汁の具にしてみた。
ゆでると、とげは鋭くとがってはいるが、柔らかくて痛くないのが意外だった。
苦味はかなり強く、他の野菜がたくさんある中で、わざわざこれを使う理由が良くわかんない。
この苦味こそが、春の味ともいえるのだが・・・。
『春は苦味を盛れ!』
ほろ苦い山菜は春の訪れを感じさせるものだ。
春に苦いものを食べる目的は、冬の間に体にたまった毒を出すと言う意味合いもあるらしい。
苦味の原因は葉物の山菜に多く含まれる「アルカロイド」「タンニン」、根に多く含まれる「ポリフェノール」など。
冬眠から目覚めた熊は、冬の間休んでいた胃腸を活性化させるためにタケノコや木の芽など苦いものを積極的に食べるのだそうだ。
山菜取りにお出かけの際は熊よけを忘れずに…。
-----

■山ウド産直センター◇5本で150円。
以前も食べたが、今回天然モノが売られていたので、買ってみた。

前回の栽培モノ。土をかけて育てるのでクキの大半が白い。

固い皮を削って、にんじんと一緒にきんぴらにした。きんぴらってこんな料理だっけ?
かなりスジっぽかったけど、ウドの放つ清冽な香りがゴボウで作るのとはまったく違った味わいで楽しい。

皮をむいた中身を刻んで酢味噌で食べる。
見た目に反して、えぐみやあくが全然ない!
キュウリやウリのような食感。はちみつにつけたらメロンぽいだろうな。
-----

■ネマガリタケ(姫竹・千島笹)・・・イネ科タケ亜科ササ属
青森県ではおでんの定番。アクが少なく、茹でたり焼いたりして様々な方法で食べられるほか、煮物のメンバーに顔を並べることも多い。
普通のタケノコは竹の子供だが、ネマガリタケは笹の子供。見分け方はタケノコは成長するに従い外皮がはがれていくが、ネマガリタケは皮がついたまま成長するのだそうだ。
 道の駅◇20本300円
道の駅◇20本300円なんと美しい野菜だろうか!?
白から紫、紫から若緑へとグラデーションを描くその色合いは見ていて飽きない。

皮のまま焼いて、アツアツのところを皮をむいて豪快に貪り食う!!
甘くもほろ苦いその美味と、早く次を食べたいけど熱くて皮を剥けないもどかしさと。
wikipediaによると、
『長野県北信地方と新潟県上越地方の山間部では、根曲竹(長野県側の呼称)またはタケノコ(新潟県側の呼称)と呼ばれるチシマザサの新芽が取れる時期(=5月~6月にかけて)に、鯖の缶詰(水煮)と一緒に味噌汁にして食べる習慣がある。
ですって。
何それ、おいしそう!
と言うわけでやってみた。
【俺のじゃないレシピ】
1.水500mlを鍋に入れる。
2.大羽の煮干の頭を取ってたてに半分に割り、中の内臓を捨てる。これを10匹分、鍋に入れる
3.沸騰させ、1分経ったら、煮干を出す。このだし汁をクッキングペーパーなどで漉す。
4.皮をむいたネマガリタケ、ワカメなどの具を入れ、柔らかくなるまで煮る。
5.味噌25g(おおさじ一杯分くらい)をお玉に取り、火を消す。
6.おたまの中にだし汁を引き込みながら、味噌を溶かしていく。完全に溶けたら、
7.火をつけ、弱火で沸かす。味噌の溶け残りがないように。
8.沸騰の泡が出はじめたら火を消す。
9.サバの水煮の缶詰を汁ごと投入。
10.出来上がり。

おつゆせんべいを入れてせんべい汁風にしてみた。
見た目はちょっと汚らしいのですが、これめちゃめちゃ美味いですね。
サバと味噌がベストマッチ。サバから出る油が味噌と入り混じって出てくるコク、うまみは思い出すだけでもヨダレが出てきます。
良く考えればサバの味噌煮という料理があって、缶詰でも広く出回っているわけですから、サバと味噌との相性がいいのは当たり前。
なのに味噌汁にサバ缶をぶち込むと言う豪快で簡単な料理がここまで美味いとは…。
あまりのうまさに3日続けて食べてしまいました。
初めて食べましたが、今後の春の定番になりそうです。長野の人に感謝!
鯖もネマガリタケも青森の特産品なのにね。
さらに大きな鯖缶ならさぞかし美味かろうと思って、

HONIHO ホニホ 青森の正直 真鯖水煮 370g缶
で試してみました。

竹林から昇るせんべいの太陽をイメージ。名付けて『バンブー・ライジングサン』
さすがにこれは脂が強すぎて、気分が悪くなりました。

ふつうに100円で売ってるノーマルサイズの鯖缶が良いと思います。
以上、今回のトライアルで食べた山菜は
| 順位 | 山菜名 | 割合 | 票数 |
| 1位 | タラの芽 | 29.4% | 102票 |
| 2位 | タケノコ | 21.3% | 74票 |
| 3位 | ワラビ・ゼンマイ | 11.2% | 39票 |
| 4位 | ミズ | 9.2% | 32票 |
| 5位 | 山ウド | 6.9% | 24票 |
| 6位 | フキ・フキノトウ | 6.3% | 22票 |
| 7位 | ギョウジャニンニク | 3.2% | 11票 |
| 8位 | シドケ | 2.9% | 10票 |
| 9位 | アザミ | 2.6% | 9票 |
| 10位 | その他(シオデ・コシアブラ・アケビの芽) | 2.6% | 9票 |
| 11位 | コゴミ | 2.3% | 8票 |
| 12位 | 葉ワサビ | 2.0% | 7票 |
このようになりました!!!(食べたものを赤字で表示。)
あとは

秋田フキ
を食べてみたいですね。
これを見た瞬間、「となりのトトロ」でトトロが傘のかわりにさしてるやつだ!
と思いましたが、
![となりのトトロ [VHS]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/517T41H1PGL._SL300_.jpg)


トトロがさしていたのはフツーの傘でした。
ショック!

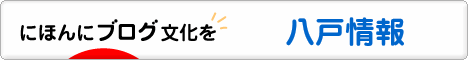

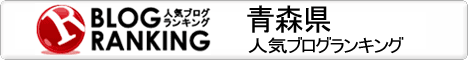

▲管理人のエネルギー源です。面白かったらポチっと押して応援してくださいね!
青森、八戸ブログのリンクとしてもどうぞ!
わさびの根っこって水中で育てると大きく、土で育てると小さくなるでしょ?その理由。
わさびは競争力が弱いから、根っこから菌を殺す毒をばらまくんだって。わさびの殺菌作用は有名だよね。
アリルイソチオシアネートっていって、これがわさびの辛味成分でもあるんだよね。
その毒で根っこに菌を飼ってるライバルの植物が育たないようにするんだけど、わさび自身もその毒にやられて大きくなれないんだって。
わさびドジ過ぎる。
わさびを水中で育てるとその毒が流されていくから、大きくなれるんだって。




















感心してじっくりと読ませていただきました!
読み応えありましたよ♪
アザミですが・・・一度茹でてから食す。
茹で汁からはみ出すと黒くなるのでタップリのお湯で・と聞いてます。
そうすると灰汁も出て癖の無い味に変身です。
アザミはゆで方が足りなかったのですね。来年の楽しみが増えました!
料理の写真をいくつか添付し忘れたので、また更新します。
またアドバイス下さいね!