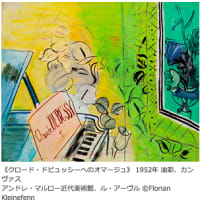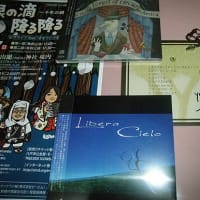中国産食品の輸入が急減・野菜3-5割減、魚も
野菜や魚など中国産食品の輸入が急減している。残留農薬問題で消費者の不安が高まったためだ。今年上期は主要野菜が3―5割減。7月以降も「段ボール入り肉まん」のやらせ報道などでイメージ悪化が続いている。野菜は小売り中心に国産シフトが顕著だが、代替産地を確保しにくい食品も多い。商社は自主検査などで中国産の安全性確認に乗り出した。
輸入減が特に目立つのは生鮮野菜。貿易統計(速報値)によると、1―6月の輸入量は約24万1500トンと前年同期比21%減った。ニンジン・カブは約2万1900トンと51%減、シイタケは31%減、ネギは29%減だった。中国産は輸入の6割を占め、総輸入量も約40万6000トンと約2割落ち込んだ。
>商社は自主検査などで中国産の安全性確認に乗り出した。
・・・って、遅すぎないか?・・・あまりにも。
なんらかの内部操作を疑ってしまいます。
というか、今まで何してた?という印象。
中国を悪者にしているけど、はじめからきちんと管理していれば、こういう自体になってないはずでは?
で、減った3〜5割って今までは安全性確認もせず、スルーだったってことですよね?
責任追及より国際協調を=安全性問題で反論-在米中国大使館 (時事通信) - goo ニュース
【ワシントン16日時事】在米中国大使館スポークスマンは16日、「(製品の)質と安全性の問題はすべての国が取り組むべき問題だ。強化が必要なのは国際協調であって、責任追及ではない」との声明を発表し、相次ぐ中国製品の自主回収を機に米国で中国バッシングが強まっていることに反論した。
まずは自分の襟元を正すべきだろう、と思いつつ、一理あるかな、と。
中国企業が非道だとしても、それを見抜けない&信用する、もしくは加担してるかもしれない海外の企業の社会的責任は追求されるべきだと思います。
正直、日本国内企業もメーカー、流通、かなりやばいですよね。
最近の不祥事(というか、犯罪行為ですが)の連続は、日本でも管理が少しは厳しくなって舞台裏の露出が増えた証明?なんて思ってしまう。
で、裏を返せば「何十年もノーチェックだった」ということでもあり、今騒がれてる日本国内の食害は、まだまだ氷山の一角であり、同時に「今のうちに危ない企業は過去清算しておけ」な、とかげのしっぽ切りな印象すらあります。
食品業界、流通業界が、「ばれなきゃいいじゃん」な“なし崩し体質”であるのは、残念ながら日々強く疑ってしまうところですが、今回の中国騒動が毒だしのチャンスになればと切実に願います。
中国自身の国策として、チェックも厳しくはなりつつあるようですが、「のど元すぎれば」な部分も考えれば、すべてを管理するのは日本以上に困難な気がします。ただ、圧倒的な人海戦術で、徹底したチェックができれば、日本以上の品質管理を実現するのも夢ではないとも思いつつ。
現時点では、不協和音や表面的な取り繕いを感じざるを得ません
中国の残留農薬検査、野菜の7.2%が不合格
【北京=共同】5日の新華社電によると、中国の主要都市で今年1―3月期に行った野菜の残留農薬の検査で、7.2%が不合格となった。国家食品薬品監督管理局幹部は「食品の安全性をめぐる情勢は多少好転しているが、依然厳しい」と指摘した。
検査では、豚肉の残留薬剤などは98%以上が合格基準を満たしたが、水産物の抗菌剤マラカイトグリーンについては10.5%が不合格だった。
中国産の食品に対し国際的な不安が広がる中、中国政府は安全性を懸命にアピール。管理局幹部は問題がある食品が実際に国内で販売される理由について、市場メカニズムや法制度が不十分の上、業者にも信用を重視する意識が欠けていることなどを挙げている。
管理局幹部は今後の対策として、安全性に対する監視体制の強化や問題がある食品の回収制度の整備、劣悪な食品を販売する業者への重点取り締まりなどに取り組む考えを示した。
中国が「食品安全」白書公表、信頼回復への姿勢アピール(読売新聞) - goo ニュース
白書は、食品合格率が昨年の77・9%から、今年上半期に85・1%になったことを紹介した上で、「食品の品質の全体的レベルは安定的に向上し、安全状況は絶えず改善している」と強調。特に、輸出用食品に関しては、一貫して99%以上の合格率を保っていると主張している。
う~ん、食品合格率そのものの内容が問題かも?と穿ってしまいます。
そしてたとえ1%でも、人が死ぬ恐れのある有害物質入りの製品があれば問題外です。(中国の1%は量的に大きい気がする・・・)
中国、批判的スクープ「禁止令」 段ボール肉まん事件で
2007年08月18日19時47分
通達後、紙面をにぎわせていた危険な食品や問題製品についての記事はほとんど見なくなり、当局が発表した安全対策や中国製品の合格率の高さをアピールする報道が目立つ。地元紙記者は、通達直後、上層部から「国家のイメージを損なう報道はいっさいするな」と厳命されたと語る。
・・・こういうところの国としての徹底の迅速さは、日本とはやはり違うのだなぁと。
できれば、中国在住の方や、中国の一般消費者の本音を
聞きたいところです。
自らの健康のためにどういう活動をされてるのか。
現状をどう考えておられるのか・・・
もしも「チャイナ・フリー」の世界になったら・・・【コラム】
世界の製造業を下支えし、「世界の工場」に成長した中国なしの生活は想像しにくい。空前の危機に直面している中国、そして無関係でいられない先進国、それぞれの視点や角度からもう一度「チャイナ・フリー」の意味を見直さなければならない。
米国を震源地にして瞬間的に世界に広がった今回の騒動は、さすがの中国政府も座視できなかったようだ。様々な数字を挙げて欧米各国に反論する一方、食品安全に関する先進諸国とのミーティングを積極的にセッティングし、議論を深めていく協力的な姿勢を打ち出している。
しかし、食の安全問題は今に始まったことではない。食品産業を巡る監視体制の不備や零細企業の乱立など構造的な課題が多く横たわっているだけに、解決は容易ではない。目先のイメージ回復ばかりに専念し、消費者や生産者、そしてそれを支える行政などの問題を含めて全面的に取り組まなければ、かえって取り返しのつかない危機に陥る危険性が非常に高いといわざるを得ない。
若干中国寄りの記事だと感じますが、ある程度の客観性は確保されているかと。
で、米国の中国バッシング背景にも触れつつ、中国政府が本腰をいれざるを得なくなっている現状について言及しています。
大事なのは、安全性の確保と、危険要素の排除(軽減化)ですが、中国サイドだけの問題ではないという部分を、国も企業も、消費者である私たちも心しなくては、と痛感します。
腐敗したシステムを少しでも変えていくために
気がついたことを声=記事にして、企業のアンテナに
ひっかかるようにどんどんアップしていきましょう!
リアルでもどんどん伝えていきましょう!
国、企業との接点をできれば有効に活用できますように。
私たち自身と、私たちの子どもたちと、その子どもたち×∞のために
・・・今、そして未来のために。
参考:
JA中札内村、冷凍枝豆の米国輸出を開始
チャイナフリーをビジネスチャンスに変える動きも。
早い話が:フリーという空気=金子秀敏
中国シンパだそうです。毎日新聞、光市の記事で客観性が高いと思ってたのに。
で、ブログでの批判の声もあがっています。が、こんな中国批判記事も書かれてます。↓
早い話が:食の「中国脅威論」=金子秀敏
う~ん、同じ筆者とは思えない・・・。なんなんだ?
公平な視点ってよほど難しいんだなぁ。
野菜や魚など中国産食品の輸入が急減している。残留農薬問題で消費者の不安が高まったためだ。今年上期は主要野菜が3―5割減。7月以降も「段ボール入り肉まん」のやらせ報道などでイメージ悪化が続いている。野菜は小売り中心に国産シフトが顕著だが、代替産地を確保しにくい食品も多い。商社は自主検査などで中国産の安全性確認に乗り出した。
輸入減が特に目立つのは生鮮野菜。貿易統計(速報値)によると、1―6月の輸入量は約24万1500トンと前年同期比21%減った。ニンジン・カブは約2万1900トンと51%減、シイタケは31%減、ネギは29%減だった。中国産は輸入の6割を占め、総輸入量も約40万6000トンと約2割落ち込んだ。
>商社は自主検査などで中国産の安全性確認に乗り出した。
・・・って、遅すぎないか?・・・あまりにも。
なんらかの内部操作を疑ってしまいます。
というか、今まで何してた?という印象。
中国を悪者にしているけど、はじめからきちんと管理していれば、こういう自体になってないはずでは?
で、減った3〜5割って今までは安全性確認もせず、スルーだったってことですよね?
責任追及より国際協調を=安全性問題で反論-在米中国大使館 (時事通信) - goo ニュース
【ワシントン16日時事】在米中国大使館スポークスマンは16日、「(製品の)質と安全性の問題はすべての国が取り組むべき問題だ。強化が必要なのは国際協調であって、責任追及ではない」との声明を発表し、相次ぐ中国製品の自主回収を機に米国で中国バッシングが強まっていることに反論した。
まずは自分の襟元を正すべきだろう、と思いつつ、一理あるかな、と。
中国企業が非道だとしても、それを見抜けない&信用する、もしくは加担してるかもしれない海外の企業の社会的責任は追求されるべきだと思います。
正直、日本国内企業もメーカー、流通、かなりやばいですよね。
最近の不祥事(というか、犯罪行為ですが)の連続は、日本でも管理が少しは厳しくなって舞台裏の露出が増えた証明?なんて思ってしまう。
で、裏を返せば「何十年もノーチェックだった」ということでもあり、今騒がれてる日本国内の食害は、まだまだ氷山の一角であり、同時に「今のうちに危ない企業は過去清算しておけ」な、とかげのしっぽ切りな印象すらあります。
食品業界、流通業界が、「ばれなきゃいいじゃん」な“なし崩し体質”であるのは、残念ながら日々強く疑ってしまうところですが、今回の中国騒動が毒だしのチャンスになればと切実に願います。
中国自身の国策として、チェックも厳しくはなりつつあるようですが、「のど元すぎれば」な部分も考えれば、すべてを管理するのは日本以上に困難な気がします。ただ、圧倒的な人海戦術で、徹底したチェックができれば、日本以上の品質管理を実現するのも夢ではないとも思いつつ。
現時点では、不協和音や表面的な取り繕いを感じざるを得ません
中国の残留農薬検査、野菜の7.2%が不合格
【北京=共同】5日の新華社電によると、中国の主要都市で今年1―3月期に行った野菜の残留農薬の検査で、7.2%が不合格となった。国家食品薬品監督管理局幹部は「食品の安全性をめぐる情勢は多少好転しているが、依然厳しい」と指摘した。
検査では、豚肉の残留薬剤などは98%以上が合格基準を満たしたが、水産物の抗菌剤マラカイトグリーンについては10.5%が不合格だった。
中国産の食品に対し国際的な不安が広がる中、中国政府は安全性を懸命にアピール。管理局幹部は問題がある食品が実際に国内で販売される理由について、市場メカニズムや法制度が不十分の上、業者にも信用を重視する意識が欠けていることなどを挙げている。
管理局幹部は今後の対策として、安全性に対する監視体制の強化や問題がある食品の回収制度の整備、劣悪な食品を販売する業者への重点取り締まりなどに取り組む考えを示した。
中国が「食品安全」白書公表、信頼回復への姿勢アピール(読売新聞) - goo ニュース
白書は、食品合格率が昨年の77・9%から、今年上半期に85・1%になったことを紹介した上で、「食品の品質の全体的レベルは安定的に向上し、安全状況は絶えず改善している」と強調。特に、輸出用食品に関しては、一貫して99%以上の合格率を保っていると主張している。
う~ん、食品合格率そのものの内容が問題かも?と穿ってしまいます。
そしてたとえ1%でも、人が死ぬ恐れのある有害物質入りの製品があれば問題外です。(中国の1%は量的に大きい気がする・・・)
中国、批判的スクープ「禁止令」 段ボール肉まん事件で
2007年08月18日19時47分
通達後、紙面をにぎわせていた危険な食品や問題製品についての記事はほとんど見なくなり、当局が発表した安全対策や中国製品の合格率の高さをアピールする報道が目立つ。地元紙記者は、通達直後、上層部から「国家のイメージを損なう報道はいっさいするな」と厳命されたと語る。
・・・こういうところの国としての徹底の迅速さは、日本とはやはり違うのだなぁと。
できれば、中国在住の方や、中国の一般消費者の本音を
聞きたいところです。
自らの健康のためにどういう活動をされてるのか。
現状をどう考えておられるのか・・・
もしも「チャイナ・フリー」の世界になったら・・・【コラム】
世界の製造業を下支えし、「世界の工場」に成長した中国なしの生活は想像しにくい。空前の危機に直面している中国、そして無関係でいられない先進国、それぞれの視点や角度からもう一度「チャイナ・フリー」の意味を見直さなければならない。
米国を震源地にして瞬間的に世界に広がった今回の騒動は、さすがの中国政府も座視できなかったようだ。様々な数字を挙げて欧米各国に反論する一方、食品安全に関する先進諸国とのミーティングを積極的にセッティングし、議論を深めていく協力的な姿勢を打ち出している。
しかし、食の安全問題は今に始まったことではない。食品産業を巡る監視体制の不備や零細企業の乱立など構造的な課題が多く横たわっているだけに、解決は容易ではない。目先のイメージ回復ばかりに専念し、消費者や生産者、そしてそれを支える行政などの問題を含めて全面的に取り組まなければ、かえって取り返しのつかない危機に陥る危険性が非常に高いといわざるを得ない。
若干中国寄りの記事だと感じますが、ある程度の客観性は確保されているかと。
で、米国の中国バッシング背景にも触れつつ、中国政府が本腰をいれざるを得なくなっている現状について言及しています。
大事なのは、安全性の確保と、危険要素の排除(軽減化)ですが、中国サイドだけの問題ではないという部分を、国も企業も、消費者である私たちも心しなくては、と痛感します。
腐敗したシステムを少しでも変えていくために
気がついたことを声=記事にして、企業のアンテナに
ひっかかるようにどんどんアップしていきましょう!
リアルでもどんどん伝えていきましょう!
国、企業との接点をできれば有効に活用できますように。
私たち自身と、私たちの子どもたちと、その子どもたち×∞のために
・・・今、そして未来のために。
参考:
JA中札内村、冷凍枝豆の米国輸出を開始
チャイナフリーをビジネスチャンスに変える動きも。
早い話が:フリーという空気=金子秀敏
中国シンパだそうです。毎日新聞、光市の記事で客観性が高いと思ってたのに。
で、ブログでの批判の声もあがっています。が、こんな中国批判記事も書かれてます。↓
早い話が:食の「中国脅威論」=金子秀敏
う~ん、同じ筆者とは思えない・・・。なんなんだ?
公平な視点ってよほど難しいんだなぁ。