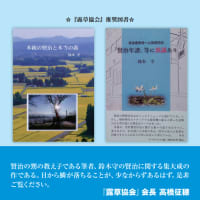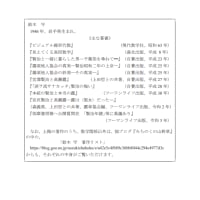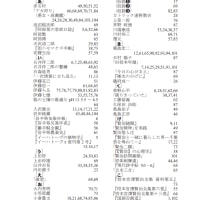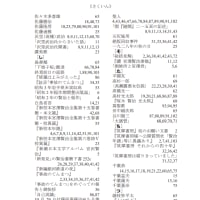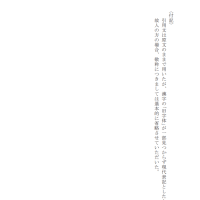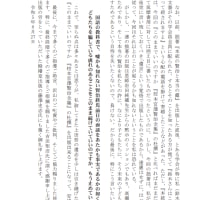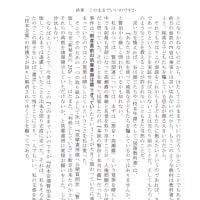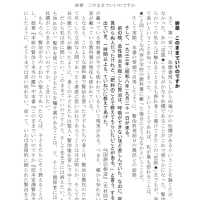羅須地人協会時代―終焉の真実―
ここで少し日本を離れて、第二次世界大戦直後、宮澤賢治はソ連ではどのように見られていたのだろうかということについて少しだけ触れておきたい。そのことを高杉一郎のシベリア俘虜記『極光のかげに』(岩波文庫)が教えてくれるからだ。
まずはこの著者高杉なる人物だが、同書の「あとがき」によれば、彼はそれまで勤めていた改造社が戦争遂行に協力的でないという理由で1944年の7月に解散させられたので職を失い、同年8月8日に名古屋に招集され、満州へ送られたという。そしてその一年後に敗戦にあい、シベリアに送られ軍事俘虜としてそこで4年間抑留され、1949年9月に帰還したという。
さて、前掲書には著者高杉本人が俘虜収容所である将校から受けた尋問の際の次のようなやりとりが綴られている。
そしてこのやりとりから読み取れることの一つに、当時のソ連ではなんと賢治や啄木のことが知られていて、しかもこの二人はアナーキストと目されていたということがある。啄木がそのように見られていたということはむべなるかなと思ったが、まさか賢治もそのように見られていたということはちょっと意外だった。が、少なくとも共産主義国家のソ連では当時賢治はアナーキーストと思われていた節があるということがこれで判った。またこのやりとりからは、将校がアナーキストに敵愾心を持っていることが判るし、ボルシェビズムのソ連がアナーキストを目の仇にするのも理屈としてはわからないわけでもない。
すると思い出されるのが、名須川溢男の伝えるところの、賢治と川村尚三(後に出てくるが実質的な中心人物)との間で行われたという例の次のような交換授業である。
したがって、賢治は『仏教にかえる』と断言して翌夜からうちわ太鼓で町を回ったいうことだから、賢治はその後すっかり労農党とは縁を切ったものと推測されがちである。
ところが、先の尋問のやりとりを知ってしまうと、実は
昭和40年代になってからやっと明らかに
とまれ、賢治は当時のソ連にまでその名が知れ渡っているような人物であり、「アナーキスト?」とも思われていたようだということがこれでわかったから、まして日本の官憲は賢治を徹底してマークしていたであろうというところまでは容易に想像ができる。では、当時日本国内で賢治は思想的・政治的にはどう見られていたのか、そしてそもそも賢治はそのことに関連してどのような活動をしていたのだろうかということをここで改めて考え直してみたい。
その際の示唆を与えてくるのが当時の労農党盛岡支部役員小館長右衛門の次の証言だ。
つまり、賢治の思想的・政治的な側面については「当時のはげしい弾圧下のことでもあり、記録もできないことだし他にそういう運動に尽くしたということがわかれば、都合のわるい事情があったからだろう」ということで「それがいままでだされなかった」だけだと小館は推論していると言える。
そしてそれが、名須川によって昭和40年代に入ってやっとこのように明るみに出され始めたということであり、賢治は当時かなり積極的に活動していてしかも労農党稗和支部の「実質的な中心人物だった」ということまでも小館は断定していることを、私たちは今ならばこうして知ることができるわけである。
そしてこのことに関連しては小館独りのみならず、煤孫利吉によれば
ということだし、あの川村尚三も、
と述べているから、賢治が労農党稗和支部の有力なシンパであったことはもはや疑いようがないし、活動にも熱心であったことがわかる。それは羅須地人協会の会員伊藤與藏(明治43年生まれ、賢治より14歳下)の証言からも裏付けられる。
具体的には、『賢治聞書』(伊藤與藏、聞き手菊池正、昭和47年)によれば、
ということを伊藤は証言して、しかもこの泉国三郎とは当時の労農党稗和支部長であったから、この証言からは賢治が政治的・思想的な面でも他人に積極的かつ熱心に働きかけていたということが導かれるからである。それも、伊藤與藏の場合などは賢治よりも干支で一回りも下回る当時約18歳の若者に対してまでもである。
いつも利用されている賢治
次に歴史的に振り返って見れば、気の毒なことに、賢治は死んでからはいつも誰かに利用され続けてきたという感が私にはある。例えば、『「雨ニモマケズ手帳」新考』の中には、
ということが述べられていて、しかもこの著者小倉豊文は「雨ニモマケズ手帳」研究の第一人者だから、「雨ニモマケズ」延いては賢治が戦意高揚に利用されていたことは否定できなかろう。
となれば、特に戦時中賢治をこのように利用しようとしていた人達にとっては、当時賢治は少なくとも官憲等からは「アカ」と見られていたことはほぼ確実だから、そのような類のことは極めて不都合だったであろう。まして、その賢治が当時の凄まじい「アカ狩り」を恐れて実家に戻って自宅謹慎していたという類の話はなおさらそうであったであろう。では、その時にそれでも賢治を前掲のように利用しようとする人たちはどうしたかといえば、普通に考えればそれらのことにはいち早く蓋をしてしまうということだったであろう。つまり、賢治のそのような類のことはアンタッチャブルなことにしてしまうのが常道であろうことに私は気付く。それはまた、「昭和3年の賢治の病臥」について触れればおのずから「アカ狩り」に対処した「自宅謹慎」であることに繋がっていく危険性が大きいので、その謹慎事情を知っているあの三人は賢治を見舞った(あるいは見舞ったが見えることができなかった)ことを公には書き残していなかったのだという一つの解釈の仕方をも教えてくれる。
というような訳で、賢治のこの類のことに触れることは長らくタブーとなっていたのであろう。そして、その蓋を再びやっとこじ開けたのが名須川溢男であると言えるのではなかろうか。実際、私は今まで羅須地人協会時代の賢治を調べていくつかの著作を公にしてきたが、それらは結果的には通説と違っている場合も多かった。そのせいであろう、拙著を読んでくださった地元の人から『このようなことを公に言ったり活字にしたりすることは花巻ではタブーだったのだよ』と教えられたことがあるから、なおさら私は長らくタブーであったのであろうことを実感する。
どうやら、以上が、このような類のことが賢治歿後しばらく論じてこられなかった有力な理由になり得るのではなかろうか。そして、逆にそれが殆ど論じられてこなかったということが、当時の賢治は政治的・思想的にかなりアナーキーであり、また無産運動の良き理解者、有力なシンパ、ある意味では良きパトロン的存在だった可能性が高いということを意味しているのではなかろうか。そして、先の仮説
 続きへ。
続きへ。
前へ 。
。
 “「「羅須地人協会時代」―終焉の真実―」の目次”へ。
“「「羅須地人協会時代」―終焉の真実―」の目次”へ。

”羅須地人協会時代”のトップに戻る。
【『宮澤賢治と高瀬露』出版のご案内】
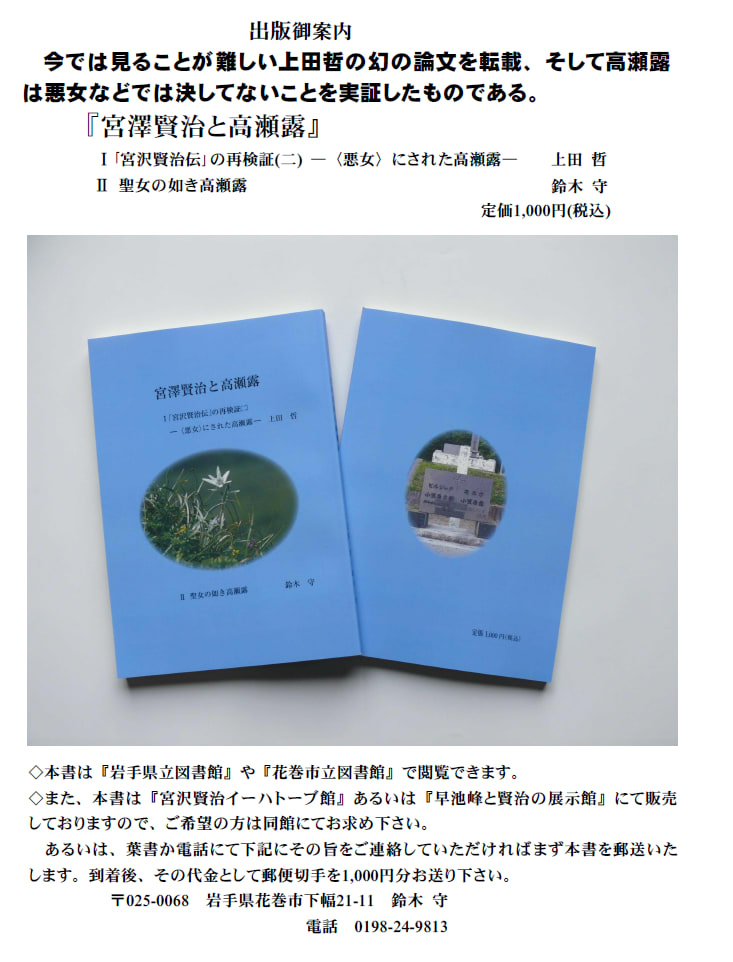
 その概要を知りたい方ははここをクリックして下さい。
その概要を知りたい方ははここをクリックして下さい。
鈴木 守
当時のソ連における賢治評ここで少し日本を離れて、第二次世界大戦直後、宮澤賢治はソ連ではどのように見られていたのだろうかということについて少しだけ触れておきたい。そのことを高杉一郎のシベリア俘虜記『極光のかげに』(岩波文庫)が教えてくれるからだ。
まずはこの著者高杉なる人物だが、同書の「あとがき」によれば、彼はそれまで勤めていた改造社が戦争遂行に協力的でないという理由で1944年の7月に解散させられたので職を失い、同年8月8日に名古屋に招集され、満州へ送られたという。そしてその一年後に敗戦にあい、シベリアに送られ軍事俘虜としてそこで4年間抑留され、1949年9月に帰還したという。
さて、前掲書には著者高杉本人が俘虜収容所である将校から受けた尋問の際の次のようなやりとりが綴られている。
尋問がはじまって、姓名、生年、生地、学歴、職歴、軍歴、父の職業などを質ねられる。…(略)…
「なぜ?」
「軍人が好きでなかったからです」
ふん、というような不信の表情を彼は肩で示した。
「ミヤザーワ・キンジを君は知っているか?」
宮沢金次、宮沢欣二……私は頭の中であれこれと友人を捜し廻ったが、宮沢なる者は私の友人のなかにはいなかった。
「知りません」
「嘘つけ!君のためによくないことになるぞ。イシカーワ・タクボークは?」
石川啄木――あることを想い出して、私は咄嗟にはっとした。金次ではない。宮沢賢治だ。私は忽ちにしてこの質問の意味を悟った。…(略)…
さっきの質問に答えて、私は言った。
「石川啄木は日本の詩人です。宮沢賢治――キンジではありません――は詩人で児童文学の作家です」
「彼らはアナーキストだろう?」
「アナーキスト? 広い意味でのアナーキストと呼ぶことはできるかの知れません。が、彼らは政治的な意味でのアナーキストではありません。文学上のウトピストです。石川啄木は民衆の詩人です。日本のニエクラソフです」
<『極光のかげに シベリア俘虜記』(高杉一郎著、岩波文庫)45p~より>「なぜ?」
「軍人が好きでなかったからです」
ふん、というような不信の表情を彼は肩で示した。
「ミヤザーワ・キンジを君は知っているか?」
宮沢金次、宮沢欣二……私は頭の中であれこれと友人を捜し廻ったが、宮沢なる者は私の友人のなかにはいなかった。
「知りません」
「嘘つけ!君のためによくないことになるぞ。イシカーワ・タクボークは?」
石川啄木――あることを想い出して、私は咄嗟にはっとした。金次ではない。宮沢賢治だ。私は忽ちにしてこの質問の意味を悟った。…(略)…
さっきの質問に答えて、私は言った。
「石川啄木は日本の詩人です。宮沢賢治――キンジではありません――は詩人で児童文学の作家です」
「彼らはアナーキストだろう?」
「アナーキスト? 広い意味でのアナーキストと呼ぶことはできるかの知れません。が、彼らは政治的な意味でのアナーキストではありません。文学上のウトピストです。石川啄木は民衆の詩人です。日本のニエクラソフです」
そしてこのやりとりから読み取れることの一つに、当時のソ連ではなんと賢治や啄木のことが知られていて、しかもこの二人はアナーキストと目されていたということがある。啄木がそのように見られていたということはむべなるかなと思ったが、まさか賢治もそのように見られていたということはちょっと意外だった。が、少なくとも共産主義国家のソ連では当時賢治はアナーキーストと思われていた節があるということがこれで判った。またこのやりとりからは、将校がアナーキストに敵愾心を持っていることが判るし、ボルシェビズムのソ連がアナーキストを目の仇にするのも理屈としてはわからないわけでもない。
すると思い出されるのが、名須川溢男の伝えるところの、賢治と川村尚三(後に出てくるが実質的な中心人物)との間で行われたという例の次のような交換授業である。
夏頃、こいと言うので桜に行ったら玉菜(キャベツ)の手入をしていた、昼食時だったので中に入ったら私にゴマせんべいをだした。賢治は米飯を食べている。『これ、あめたので酢をかけてるんだ』といったのが印象に残っている。口ぐせのように、『俺には実力がないが、お前たちは思った通り進め、何とかタスけてやるから』と言うのだった。その頃、レーニンの『国家と革命』を教えてくれ、と言われ私なりに一時間ぐらい話をすれば『今度は俺がやる』と、交換に土壌学を賢治から教わったものだった。疲れればレコードを聞いたり、セロをかなでた。夏から秋にかけて一くぎりした夜おそく『どうもありがとう、ところで講義してもらったがこれはダメですね、日本に限ってこの思想による革命は起こらない』と断定的に言い、『仏教にかえる』と翌夜からうちわ太鼓で町を回った。
<『岩手史学研究 NO.50』(岩手史学会)220p~より>したがって、賢治は『仏教にかえる』と断言して翌夜からうちわ太鼓で町を回ったいうことだから、賢治はその後すっかり労農党とは縁を切ったものと推測されがちである。
ところが、先の尋問のやりとりを知ってしまうと、実は
川村尚三と「交換授業」をしてレーニンの『国家と革命』を教えてもらった結果、レーニン(ボルシェビキ)の思想ではだめだということを賢治は悟り、やはりアナーキズムでなければならないと認識を新たにしたという解釈も俄然脚光を浴びてくる。賢治は川村に『日本に限ってこの思想(レーニンの思想、ボルシェビズム)による革命は起こらない』と断言はしたが、賢治はアナーキズムによるそれを否定したわけではない、という可能性がある。
ということに改めて気付く そしてもう一つ、 ボルシェビズムのソ連では、賢治は「にっくきアナーキストだ」だということで結構知られていたのかもしれないということを私は心に留めておかないと、もしかすると認識を誤ることがあるかもしれない。
ということにも気付く。なぜならば、件の将校はまず賢治の名を出し、次に啄木の名を出し、そしてこの二人をひっくるめてアナーキストだろう?と訝っているわけだから、賢治は啄木に勝るとも劣らないアナーキーな人物だと少なくとも件の将校は認識していたということが導かれるからである。まずないとは思うが、知らないのは日本人の方だったということも完全には払拭できないのかもしれない。昭和40年代になってからやっと明らかに
とまれ、賢治は当時のソ連にまでその名が知れ渡っているような人物であり、「アナーキスト?」とも思われていたようだということがこれでわかったから、まして日本の官憲は賢治を徹底してマークしていたであろうというところまでは容易に想像ができる。では、当時日本国内で賢治は思想的・政治的にはどう見られていたのか、そしてそもそも賢治はそのことに関連してどのような活動をしていたのだろうかということをここで改めて考え直してみたい。
その際の示唆を与えてくるのが当時の労農党盛岡支部役員小館長右衛門の次の証言だ。
「私は……農民組合全国大会に県代表で出席したことから新聞社をやめさせられた。宮沢賢治さんは、事務所の保証人になったよ、さらに八重樫賢師君を通して毎月その運営費のようにして経済的な支援や激励をしてくれた。演説会などでソット私のポケットに激励のカンパをしてくれたのだった。なぜおもてにそれがいままでだされなかったかということは、当時のはげしい弾圧下のことでもあり、記録もできないことだし他にそういう運動に尽くしたということがわかれば、都合のわるい事情があったからだろう。いずれにしろ労農党稗和支部の事務所を開設させて、その運営費を八重樫賢師君を通して支援してくれるなど実質的な中心人物だった」(S45・6・21採録)
〈名須川溢男「賢治と労農党」より(『鑑賞現代日本文学⑬ 宮沢賢治』(原子朗編、角川書店))所収〉つまり、賢治の思想的・政治的な側面については「当時のはげしい弾圧下のことでもあり、記録もできないことだし他にそういう運動に尽くしたということがわかれば、都合のわるい事情があったからだろう」ということで「それがいままでだされなかった」だけだと小館は推論していると言える。
そしてそれが、名須川によって昭和40年代に入ってやっとこのように明るみに出され始めたということであり、賢治は当時かなり積極的に活動していてしかも労農党稗和支部の「実質的な中心人物だった」ということまでも小館は断定していることを、私たちは今ならばこうして知ることができるわけである。
そしてこのことに関連しては小館独りのみならず、煤孫利吉によれば
「第一回普選は昭和三年(一九二八)二月二十日だったから、二月初め頃だったと思うが、労農党稗和支部の長屋の事務所は混雑していた。バケツにしょうふ(のり)を入れてハケを持って「泉国三郎」と新聞紙に大書したビラを街にはりに歩いたものだった。事務所に帰ってみたら謄写版一式と紙に包んだ二十円があった『宮沢賢治さんが、これタスにしてけろ』と言ってそっと置いていったものだ、と聞いた……。」(花巻市御田屋町、煤孫利吉談 '67(S42)・8・8採録)
<『國文學』昭和50年4月号(學燈社)126p~より>ということだし、あの川村尚三も、
賢治と私とは他の人々との交際とはちがい、社会主義や労農党のことからであった。賢治は仏教だったが私は阿部治三郎牧師から社会科学の本を読ませてもらい、目をその方に開かせてもらった。
盛岡で労農党の横田忠夫らが中心で啄木会があったが、進歩思想の集まりとして警察から目をつけられていた。その会に花巻から賢治と私が入っていた。賢治は啄木を崇拝していた。昭和二年の春頃『労農党の事務所がなくて困っている』と賢治に話したら『おれがかりてくれる』と言って宮沢町の長屋-三間に一間半ぐらい-をかりてくれた。そして桜から(羅須地人協会)机や椅子をもってきてかしてくれた。賢治はシンパだった。経費なども賢治が出したと思う。ドイツ語の本を売った金だとも言っていた。(花巻市宮野目本館、川村尚三談 '67(S42)・8・18採録)
<『岩手史学研究 NO.50』(岩手史学会)220p~より>盛岡で労農党の横田忠夫らが中心で啄木会があったが、進歩思想の集まりとして警察から目をつけられていた。その会に花巻から賢治と私が入っていた。賢治は啄木を崇拝していた。昭和二年の春頃『労農党の事務所がなくて困っている』と賢治に話したら『おれがかりてくれる』と言って宮沢町の長屋-三間に一間半ぐらい-をかりてくれた。そして桜から(羅須地人協会)机や椅子をもってきてかしてくれた。賢治はシンパだった。経費なども賢治が出したと思う。ドイツ語の本を売った金だとも言っていた。(花巻市宮野目本館、川村尚三談 '67(S42)・8・18採録)
と述べているから、賢治が労農党稗和支部の有力なシンパであったことはもはや疑いようがないし、活動にも熱心であったことがわかる。それは羅須地人協会の会員伊藤與藏(明治43年生まれ、賢治より14歳下)の証言からも裏付けられる。
具体的には、『賢治聞書』(伊藤與藏、聞き手菊池正、昭和47年)によれば、
伊藤忠一君がマルクス全集を買いました。それを聞いて先生が、十年かかっても理解はむずかしいよ、と言っていました。今思い出してみると、先生の話の中に、カール・マルクスとか、フリードリッヒ・エンゲルスという名前がなんべんもあったように思います。たぶん社会主義対する先生のお考えもお話になったと思いますが、残念ながら少しも覚えていません。
とか 「与蔵さん、選挙演説を聞きに行きましょう」と誘われたことがあります。演説会場は相生町の繭市場ではなかったかと思います。候補者は泉国三郎でした。
<共に『賢治とモリスの環境芸術』(大内秀明著、時潮社)40p~より>ということを伊藤は証言して、しかもこの泉国三郎とは当時の労農党稗和支部長であったから、この証言からは賢治が政治的・思想的な面でも他人に積極的かつ熱心に働きかけていたということが導かれるからである。それも、伊藤與藏の場合などは賢治よりも干支で一回りも下回る当時約18歳の若者に対してまでもである。
いつも利用されている賢治
次に歴史的に振り返って見れば、気の毒なことに、賢治は死んでからはいつも誰かに利用され続けてきたという感が私にはある。例えば、『「雨ニモマケズ手帳」新考』の中には、
(「雨ニモマケズ」の詩は)一九四二(昭和十七)年には、軍国主義的独裁政治の国策遂行を目的に組織された「大政翼賛会」の文化部編になる「詩歌翼賛」の第二輯「常盤樹」の中に採録され、当時の国民とくに農村労働力の強制収奪に利用されることにもなった。…(投稿者略)…独り農民に関してだけではなくて、一般的に権力に利用される危険性をもっていたといえよう。一九四四(昭和十九)年九月、谷川徹三氏が東京女子大学で「今日の心がまえ」なる題下に行った講演はこの詩を中心とした賢治に関するもので、翌年六月には当時の国策協力の出版「日本叢書」(生活社刊)四として「雨ニモマケズ」の書名で初版二万部も発行された。正に前記「詩歌翼賛」の「常盤樹への採録と相呼応するものと言えよう。
<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)147p~より>ということが述べられていて、しかもこの著者小倉豊文は「雨ニモマケズ手帳」研究の第一人者だから、「雨ニモマケズ」延いては賢治が戦意高揚に利用されていたことは否定できなかろう。
となれば、特に戦時中賢治をこのように利用しようとしていた人達にとっては、当時賢治は少なくとも官憲等からは「アカ」と見られていたことはほぼ確実だから、そのような類のことは極めて不都合だったであろう。まして、その賢治が当時の凄まじい「アカ狩り」を恐れて実家に戻って自宅謹慎していたという類の話はなおさらそうであったであろう。では、その時にそれでも賢治を前掲のように利用しようとする人たちはどうしたかといえば、普通に考えればそれらのことにはいち早く蓋をしてしまうということだったであろう。つまり、賢治のそのような類のことはアンタッチャブルなことにしてしまうのが常道であろうことに私は気付く。それはまた、「昭和3年の賢治の病臥」について触れればおのずから「アカ狩り」に対処した「自宅謹慎」であることに繋がっていく危険性が大きいので、その謹慎事情を知っているあの三人は賢治を見舞った(あるいは見舞ったが見えることができなかった)ことを公には書き残していなかったのだという一つの解釈の仕方をも教えてくれる。
というような訳で、賢治のこの類のことに触れることは長らくタブーとなっていたのであろう。そして、その蓋を再びやっとこじ開けたのが名須川溢男であると言えるのではなかろうか。実際、私は今まで羅須地人協会時代の賢治を調べていくつかの著作を公にしてきたが、それらは結果的には通説と違っている場合も多かった。そのせいであろう、拙著を読んでくださった地元の人から『このようなことを公に言ったり活字にしたりすることは花巻ではタブーだったのだよ』と教えられたことがあるから、なおさら私は長らくタブーであったのであろうことを実感する。
どうやら、以上が、このような類のことが賢治歿後しばらく論じてこられなかった有力な理由になり得るのではなかろうか。そして、逆にそれが殆ど論じられてこなかったということが、当時の賢治は政治的・思想的にかなりアナーキーであり、また無産運動の良き理解者、有力なシンパ、ある意味では良きパトロン的存在だった可能性が高いということを意味しているのではなかろうか。そして、先の仮説
昭和3年8月に賢治が実家に戻った最大の理由は体調が悪かったからということよりは、「陸軍大演習」を前にして行われていたすさまじい「アカ狩り」に対処するためであり、当局から命じられてその演習が終わるまで実家に戻って謹慎していた。……①
を間接的に裏付けてくれているのではなかろうか。しばらくの間論じてこられなかったこと自体が、あれは「自宅謹慎」であったことを傍証してくれている、そんな気もしてくる。 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 “「「羅須地人協会時代」―終焉の真実―」の目次”へ。
“「「羅須地人協会時代」―終焉の真実―」の目次”へ。
”羅須地人協会時代”のトップに戻る。
【『宮澤賢治と高瀬露』出版のご案内】
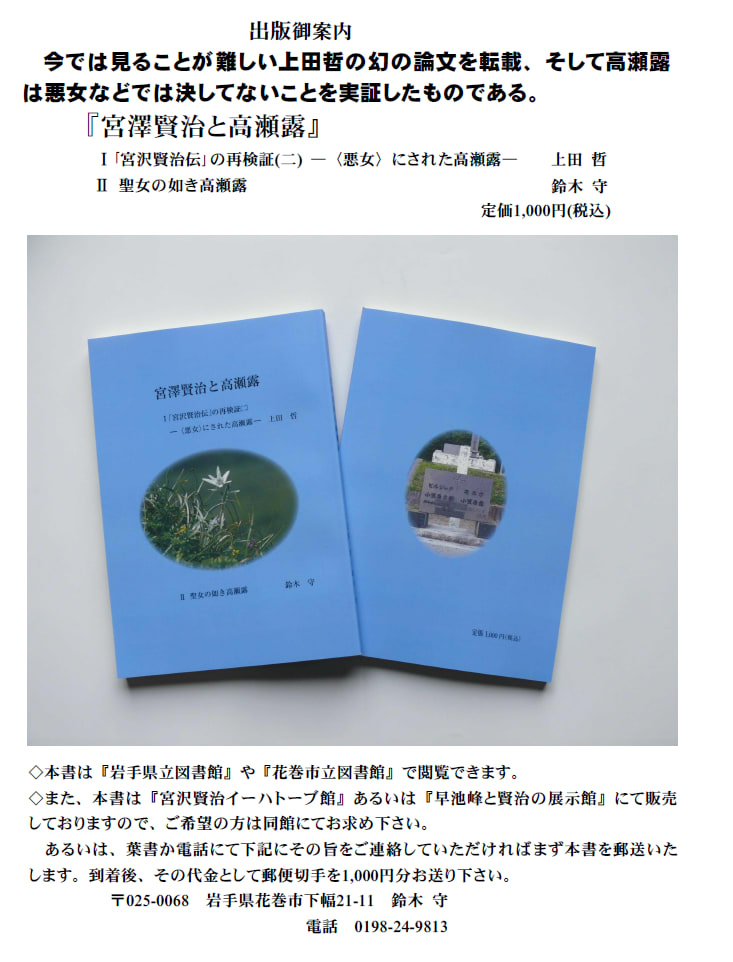
 その概要を知りたい方ははここをクリックして下さい。
その概要を知りたい方ははここをクリックして下さい。