《「羅須地人協会時代」終焉の真相》




 続きへ。
続きへ。
前へ 。
。
 “「羅須地人協会時代―終焉の真実―」の目次”へ。
“「羅須地人協会時代―終焉の真実―」の目次”へ。
*****************************なお、以下は本日投稿分のテキスト形式版である。****************************
るっていうことか…。これじゃまるで、賢治が仮病を使っていたと決めつけてそれをあばこうとしているだけだべ…」と荒木はやや不満げに顔を曇らせた。
「いやそうではなくて、もしかするとその他にもっと大きな理由があったのかもしれないということを探っているだけだ。そもそも病気が理由で実家に帰ったのであれば、手紙には「演習が終るころはまた根子へ戻って云々」ではなくて「病気がちゃんと治ったならばまた根子へ戻って云々」と手紙に書くはずだ。おかしいと思わんか」
と吉田は肩をすくめた。
「逃避行」していた賢治
そこへ私は、荒木に追い打ちをかけそうなのでためらいつつも、
「実は、この時の上京は「東京へ逃避行」だったという見方もあるということをこの度知った。それは佐藤竜一氏が自身の著書『宮沢賢治の東京』の中で主張していたことなのだが、
東京について直ぐ書かれた(六月十日付)「高架線」という詩には、世相が表現されている。
「労農党は解散される」とあり、次のフレーズが続く。
…(中略)…
国家主義が台頭してきていた。その動きは当然、羅須地人協会の活動に影を落とした。この時の東京行は、現実からの逃避行であったに違いない。
という見方をしていた」
と紹介した。
すると、吉田は、
「この昭和3年6月の「伊豆大島行」は伊藤七雄に招かれたもののようだが、この伊藤は当時労農党の幹部であったはずだ。これと似たようなことが川村尚三の場合についても言える。賢治と二人で交換授業をしたこの川村は当時の労農党稗和支部の実質的な代表者であったはずだ。少なくとも、このような労農党の幹部等二人と賢治はかなり親しかったのだから、賢治は労農党の単なるシンパであったというよりはそれ以上の存在だったと考えた方がより自然だと思う。それは当時の労農党盛岡支部役員小館長右衛門の次のような証言、
宮沢賢治さんは、(労農党稗和支部の)事務所の保証人になったよ、さらに八重樫賢師君を通して毎月その運営費のようにして経済的な支援や激励をしてくれた。…(中略)…実質的な中心人物だった。おもてにでないだけであったが。
<名須川溢男「賢治と労農党」>
からも言えると思う」
と自身の見解を述べた。そこへ私がつい口を挟んでしまった。
「実はその「伊豆大島行」に関連してだが、かつてはそのような断定などはしていなかったはずなのに、最近は
伊藤七雄が妹・チヱをともなって花巻の賢治を訪ねてきたのは一九二八(昭和三)年春のことである。
という断定調の通説が一人歩きし始めてる。しかし私は、その訪問時期は昭和2年の秋ではなかろうかと推測している。というのは、伊藤ちゑは藤原嘉藤治に宛てたある書簡の中で、
私共兄妹が秋花巻の御宅にお訪ねした時の御約束を御上京のみぎりお果たし遊ばしたと見るのが妥当で 従って誠におそれ入りますけれどあの御本を今後若し再版なさいますやうな場合は…
としたためているから、伊藤兄妹が花巻を訪ねたという「秋」は昭和3年6月以前の秋でなければならず、自ずから昭和2年の秋のことであると判断せねばならないからだ」
「そんな書簡初耳だ、どこからその資料を入手したんだ?」
と吉田が訊くものだから、私は続けて
「実は、伊藤兄妹の血縁の方から貰った資料の中にあった。もしこれが事実であったとするならば、その時期は高瀬露が羅須地人協会を訪れるのを遠慮し出した時期と丁度入れ替わりになっている。なぜなら、上田哲は
賢治先生をはじめて訪ねたのは、大正十五年の秋頃で昭和二年の夏までいろいろ教えていただきました。その後、先生のお仕事の妨げになってはと遠慮するようにしました。
<『七尾論叢 第11号』(七尾短期大学)>
という、高瀬本人から菊池映一氏が聞いたという証言を得ているからだ。高瀬が賢治の許を訪ねることを遠慮するようになった理由の一つとして、この伊藤ちゑの花巻訪問が密接に関連していたという可能性も否定出来ない。
だから佐藤氏が主張するように、この時の3週間弱の上京は「逃避行」だったと捉えることもたしかに出来る。それはまず第一に、労農党が解散せねばならなくなったこと等の落胆を紛らわすために、第二に、以前から引きずっている高瀬露とのトラブルから逃れるために逃避行していた、と考えられないこともないからだ」
と私見を述べた。すると吉田も、
「逆に、これがもし「逃避行」でなかったとするならば、この時の上京によって賢治は農繁期に3週間弱もの間羅須地人協会を留守にしてしまったのだから、花巻に戻ったら賢治はそのことを悔いて、帰花直後からは周辺の農家の水稲の生育状況を心配しながら大車輪で見廻っていたはずだ。ところが賢治は、花巻に戻ってからも約10日間ほどをぼんやりと無為に過ごしていた。したがって、昭和3年の賢治は農繁期に3週間弱もの間羅須地人協会を留守にしていただけでなく、その農繁期に稲作指導等をまったくしない約一ヶ月間もの空白を作ってしまっていたことになる。この観点からも、佐藤氏の「東京へ逃避行」だったという見方はたしかに否定しきれない」
と同意を示した。
「演習」とは「陸軍大演習」のこと
すると荒木が
「でも変だな。俺は、賢治はその頃になるともうすっかり労農党とは縁を切ったものとばかり思っていた。たしか、川村と交換授業を行った後に、『どうもありがとう、ところで講義してもらったがこれはダメですね、日本に限ってこの思想による革命は起こらない』と言い、『仏教にかえる』と翌夜からうちわ太鼓で町を回った、という話じゃなかったっけ?」
<『岩手史学研究 NO.50』>
と疑問を投げかけたのだが、吉田は、
「たしかに川村はそのような証言をしているが、この交換授業は昭和2年のことだろ。ところが、この上京は昭和3年のことだ。しかも、賢治が伊藤兄妹の水沢の実家を訪れるのならばまだしも、農繁期の6月だというのに上京し、その上わざわざ伊藤兄妹の住む伊豆大島まで訪ねて行っている。賢治と労農党との深い関係は、交換授業が終わった後も続いたと判断せざるを得ないだろう。
それは次のようなこと等からも言えると思う。
第一回普選は昭和三年(一九二八)二月二十日だったから、二月初め頃だったと思うが、労農党稗和支部の長屋の事務所は混雑していた。…(中略)…事務所に帰ってみたら謄写版一式と紙に包んだ二十円があった『宮沢賢治さんが、これタスにしてけろ』と言ってそっと置いていったものだ、と聞いた。
<『國文學』昭和50年4月号(學燈社)>
ということだから、その後も賢治は労農党のシンパ以上の存在だったとならざるを得ないだろう」
と応えた。
これに対して荒木が、結果的に極めて重要なことになるのだが、次のようなことを話しながら、
「そうか、そうすると賢治は当時いわゆる「アカ」と見られていたという可能性がやはりあるということか。ん? なぜ俺が突如こんなことを言い出すのかだって。実は先日たまたまこの本を読んでいたところが、
労農党は昭和三年四月、日本共産党の外郭団体とみなされて解散命令を受けた。…(中略)…
この年十月、岩手では初の陸軍大演習が行われ、天皇の行幸啓を前に、県内にすさまじい「アカ狩り」旋風が吹き荒れた。横田兄弟や川村尚三らは、次々に「狐森」(盛岡刑務所の所在地、現前九年三丁目)に送り込まれたいった。
<『啄木 賢治 光太郎』(読売新聞社盛岡支局)>
と述べられていたからなんだ」
と、ためらい気味にその本を開いて見せてくれた。その途端、
「荒木、やった! これだこれこれ。件の「演習」とはそれこそこの「陸軍大演習」ことだったのだ」
と私は大声を出してしまった。
そして吉田はといえば腕組みをしながら、
「そうだよな、「演習」とは「陸軍大演習」のことだったんだ。なんで僕は今までそれに気付かなかったのだろうか。そうそうそういえば今思い出した。名須川溢雄の論文「賢治と労農党」の中に
八重樫賢師とは、羅須地人協会の童話会などに参加し、賢治から教えを受けた若者であり、下根子に賢治のような農園をひらき、労農党の活動をしていたという。しかもこの八重樫はまさしくその陸軍大演習の直前に、要注意人物ということで北海道に追放されて、その地に死んだ。
というような内容のことがたしか書かれていたはずだ。
これはただごとでは済まなくなったぞ。川村が捕まり、八重樫が北海道に追放されたのだから、彼等との繋がりの強い賢治に官憲の手が伸びない訳はないからな。そして前述の小館長右衛門は当時戦闘的な活動家だったと聞くが、この時の凄まじい「アカ狩り」によって彼が小樽に奔ったのも昭和3年8月だ。定説は覆るかもしれん」
と言って最後は口をつぐんでしまった。
やや間を置いて荒木が
「済まんが今日はこの辺で終わりに出来ないかな。実は明日から愚妻と旅に出るんで…」
と遠慮がちに言うので、私が
「それじゃ、この続きは荒木ご夫妻が旅行から戻ってからということにしよう。それまでに出来るだけ調べておくからさ」
と約束し、解散することにした。
八重樫賢師について
おみやげの信玄餅を三人で味わいながら、荒木夫妻の道中のみやげ話を聞き終えたところで、
「さて、ではこの前の続きを開始しよう」
と吉田が切り出したので、私がまず口火を切った。
「前回最後に八重樫賢師という人物が話題になったよな。実はこの上田仲雄の論文「岩手無産運動史」の中に、
五月以降I盛岡署長による無産運動への圧迫はげしくなり、旧労農党支部事務所の捜査、党員の金銭、物品、商品の貸借関係を欺偽、横領の罪名で取り調べられ、党員の盛岡市外の外出は浮浪罪をよび、七月党事務所は奪取せらる。一方盛岡署の私服は党員を訪問、脱退を勧告し、肯んじない場合は勾留、投獄、又は勤務先の訪問をもって脅かし、旧労農党はこの弾圧に数ヶ月にして殆ど破壊されるに至っている。三・一五事件に続いて無産運動に加えられた弾圧は、この年の十月県下で行われた陸軍大演習によって更に徹底せしめられる。演習二週間前に更迭したT盛岡警察署長により無産運動家の大検束が行われた。この大検束を期として、本県無産運動指導者の間に清算主義的傾向が生じた。 <『岩手史学研究 NO.50』>
ということが論じられていた。そして、この「大検束」を受けた人物の註釈があり、一日内外~一週間の検束処分を受けた者としてほら、
花巻署 川村尚二((ママ)) 八重樫賢志((ママ))
という名前があるだろ。おそらくそれぞれ川村尚三のことであり、八重樫賢師であることは間違いなかろう。
一方、八重樫賢師という青年は「羅須地人協会の童話会などに参加し、賢治から教えを受けた若者」でもあるということだったので私は気になって仕方がなかった。そこで、八重樫賢師のことを知っている人をあちこち探し廻ってみたところ、Aさんという方を紹介してもらった。そのAさんからは、賢師につ
****************************************************************************************************
 続きへ。
続きへ。
前へ 。
。
 “「羅須地人協会時代―終焉の真実―」の目次”へ。
“「羅須地人協会時代―終焉の真実―」の目次”へ。

”羅須地人協会時代”のトップに戻る。
《鈴木 守著作案内》
◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。
本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。
あるいは、次の方法でもご購入いただけます。
☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)
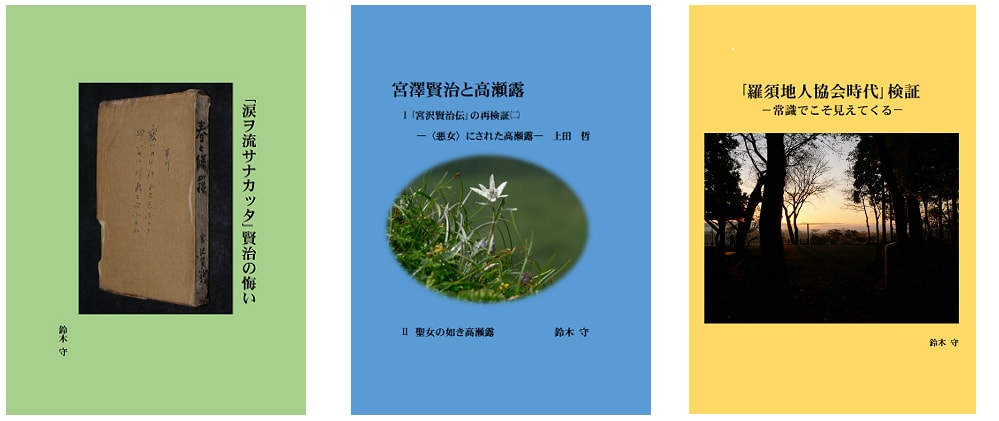
なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。
☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』
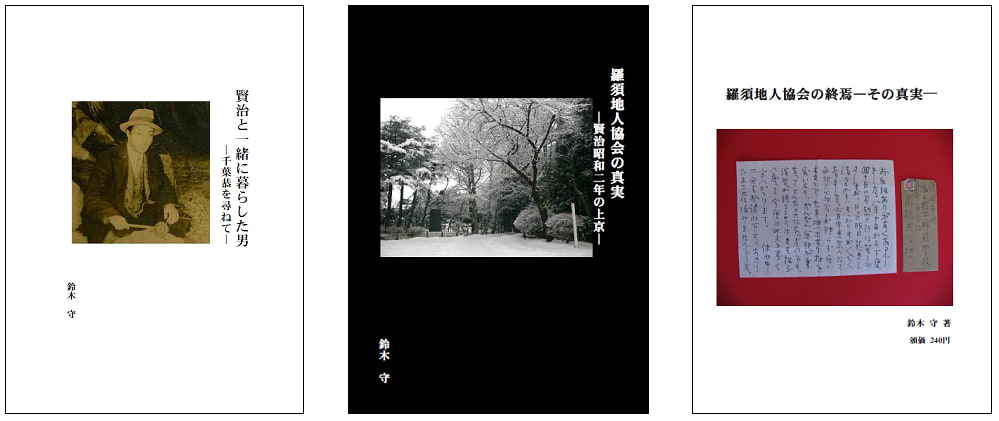




 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 “「羅須地人協会時代―終焉の真実―」の目次”へ。
“「羅須地人協会時代―終焉の真実―」の目次”へ。*****************************なお、以下は本日投稿分のテキスト形式版である。****************************
るっていうことか…。これじゃまるで、賢治が仮病を使っていたと決めつけてそれをあばこうとしているだけだべ…」と荒木はやや不満げに顔を曇らせた。
「いやそうではなくて、もしかするとその他にもっと大きな理由があったのかもしれないということを探っているだけだ。そもそも病気が理由で実家に帰ったのであれば、手紙には「演習が終るころはまた根子へ戻って云々」ではなくて「病気がちゃんと治ったならばまた根子へ戻って云々」と手紙に書くはずだ。おかしいと思わんか」
と吉田は肩をすくめた。
「逃避行」していた賢治
そこへ私は、荒木に追い打ちをかけそうなのでためらいつつも、
「実は、この時の上京は「東京へ逃避行」だったという見方もあるということをこの度知った。それは佐藤竜一氏が自身の著書『宮沢賢治の東京』の中で主張していたことなのだが、
東京について直ぐ書かれた(六月十日付)「高架線」という詩には、世相が表現されている。
「労農党は解散される」とあり、次のフレーズが続く。
…(中略)…
国家主義が台頭してきていた。その動きは当然、羅須地人協会の活動に影を落とした。この時の東京行は、現実からの逃避行であったに違いない。
という見方をしていた」
と紹介した。
すると、吉田は、
「この昭和3年6月の「伊豆大島行」は伊藤七雄に招かれたもののようだが、この伊藤は当時労農党の幹部であったはずだ。これと似たようなことが川村尚三の場合についても言える。賢治と二人で交換授業をしたこの川村は当時の労農党稗和支部の実質的な代表者であったはずだ。少なくとも、このような労農党の幹部等二人と賢治はかなり親しかったのだから、賢治は労農党の単なるシンパであったというよりはそれ以上の存在だったと考えた方がより自然だと思う。それは当時の労農党盛岡支部役員小館長右衛門の次のような証言、
宮沢賢治さんは、(労農党稗和支部の)事務所の保証人になったよ、さらに八重樫賢師君を通して毎月その運営費のようにして経済的な支援や激励をしてくれた。…(中略)…実質的な中心人物だった。おもてにでないだけであったが。
<名須川溢男「賢治と労農党」>
からも言えると思う」
と自身の見解を述べた。そこへ私がつい口を挟んでしまった。
「実はその「伊豆大島行」に関連してだが、かつてはそのような断定などはしていなかったはずなのに、最近は
伊藤七雄が妹・チヱをともなって花巻の賢治を訪ねてきたのは一九二八(昭和三)年春のことである。
という断定調の通説が一人歩きし始めてる。しかし私は、その訪問時期は昭和2年の秋ではなかろうかと推測している。というのは、伊藤ちゑは藤原嘉藤治に宛てたある書簡の中で、
私共兄妹が秋花巻の御宅にお訪ねした時の御約束を御上京のみぎりお果たし遊ばしたと見るのが妥当で 従って誠におそれ入りますけれどあの御本を今後若し再版なさいますやうな場合は…
としたためているから、伊藤兄妹が花巻を訪ねたという「秋」は昭和3年6月以前の秋でなければならず、自ずから昭和2年の秋のことであると判断せねばならないからだ」
「そんな書簡初耳だ、どこからその資料を入手したんだ?」
と吉田が訊くものだから、私は続けて
「実は、伊藤兄妹の血縁の方から貰った資料の中にあった。もしこれが事実であったとするならば、その時期は高瀬露が羅須地人協会を訪れるのを遠慮し出した時期と丁度入れ替わりになっている。なぜなら、上田哲は
賢治先生をはじめて訪ねたのは、大正十五年の秋頃で昭和二年の夏までいろいろ教えていただきました。その後、先生のお仕事の妨げになってはと遠慮するようにしました。
<『七尾論叢 第11号』(七尾短期大学)>
という、高瀬本人から菊池映一氏が聞いたという証言を得ているからだ。高瀬が賢治の許を訪ねることを遠慮するようになった理由の一つとして、この伊藤ちゑの花巻訪問が密接に関連していたという可能性も否定出来ない。
だから佐藤氏が主張するように、この時の3週間弱の上京は「逃避行」だったと捉えることもたしかに出来る。それはまず第一に、労農党が解散せねばならなくなったこと等の落胆を紛らわすために、第二に、以前から引きずっている高瀬露とのトラブルから逃れるために逃避行していた、と考えられないこともないからだ」
と私見を述べた。すると吉田も、
「逆に、これがもし「逃避行」でなかったとするならば、この時の上京によって賢治は農繁期に3週間弱もの間羅須地人協会を留守にしてしまったのだから、花巻に戻ったら賢治はそのことを悔いて、帰花直後からは周辺の農家の水稲の生育状況を心配しながら大車輪で見廻っていたはずだ。ところが賢治は、花巻に戻ってからも約10日間ほどをぼんやりと無為に過ごしていた。したがって、昭和3年の賢治は農繁期に3週間弱もの間羅須地人協会を留守にしていただけでなく、その農繁期に稲作指導等をまったくしない約一ヶ月間もの空白を作ってしまっていたことになる。この観点からも、佐藤氏の「東京へ逃避行」だったという見方はたしかに否定しきれない」
と同意を示した。
「演習」とは「陸軍大演習」のこと
すると荒木が
「でも変だな。俺は、賢治はその頃になるともうすっかり労農党とは縁を切ったものとばかり思っていた。たしか、川村と交換授業を行った後に、『どうもありがとう、ところで講義してもらったがこれはダメですね、日本に限ってこの思想による革命は起こらない』と言い、『仏教にかえる』と翌夜からうちわ太鼓で町を回った、という話じゃなかったっけ?」
<『岩手史学研究 NO.50』>
と疑問を投げかけたのだが、吉田は、
「たしかに川村はそのような証言をしているが、この交換授業は昭和2年のことだろ。ところが、この上京は昭和3年のことだ。しかも、賢治が伊藤兄妹の水沢の実家を訪れるのならばまだしも、農繁期の6月だというのに上京し、その上わざわざ伊藤兄妹の住む伊豆大島まで訪ねて行っている。賢治と労農党との深い関係は、交換授業が終わった後も続いたと判断せざるを得ないだろう。
それは次のようなこと等からも言えると思う。
第一回普選は昭和三年(一九二八)二月二十日だったから、二月初め頃だったと思うが、労農党稗和支部の長屋の事務所は混雑していた。…(中略)…事務所に帰ってみたら謄写版一式と紙に包んだ二十円があった『宮沢賢治さんが、これタスにしてけろ』と言ってそっと置いていったものだ、と聞いた。
<『國文學』昭和50年4月号(學燈社)>
ということだから、その後も賢治は労農党のシンパ以上の存在だったとならざるを得ないだろう」
と応えた。
これに対して荒木が、結果的に極めて重要なことになるのだが、次のようなことを話しながら、
「そうか、そうすると賢治は当時いわゆる「アカ」と見られていたという可能性がやはりあるということか。ん? なぜ俺が突如こんなことを言い出すのかだって。実は先日たまたまこの本を読んでいたところが、
労農党は昭和三年四月、日本共産党の外郭団体とみなされて解散命令を受けた。…(中略)…
この年十月、岩手では初の陸軍大演習が行われ、天皇の行幸啓を前に、県内にすさまじい「アカ狩り」旋風が吹き荒れた。横田兄弟や川村尚三らは、次々に「狐森」(盛岡刑務所の所在地、現前九年三丁目)に送り込まれたいった。
<『啄木 賢治 光太郎』(読売新聞社盛岡支局)>
と述べられていたからなんだ」
と、ためらい気味にその本を開いて見せてくれた。その途端、
「荒木、やった! これだこれこれ。件の「演習」とはそれこそこの「陸軍大演習」ことだったのだ」
と私は大声を出してしまった。
そして吉田はといえば腕組みをしながら、
「そうだよな、「演習」とは「陸軍大演習」のことだったんだ。なんで僕は今までそれに気付かなかったのだろうか。そうそうそういえば今思い出した。名須川溢雄の論文「賢治と労農党」の中に
八重樫賢師とは、羅須地人協会の童話会などに参加し、賢治から教えを受けた若者であり、下根子に賢治のような農園をひらき、労農党の活動をしていたという。しかもこの八重樫はまさしくその陸軍大演習の直前に、要注意人物ということで北海道に追放されて、その地に死んだ。
というような内容のことがたしか書かれていたはずだ。
これはただごとでは済まなくなったぞ。川村が捕まり、八重樫が北海道に追放されたのだから、彼等との繋がりの強い賢治に官憲の手が伸びない訳はないからな。そして前述の小館長右衛門は当時戦闘的な活動家だったと聞くが、この時の凄まじい「アカ狩り」によって彼が小樽に奔ったのも昭和3年8月だ。定説は覆るかもしれん」
と言って最後は口をつぐんでしまった。
やや間を置いて荒木が
「済まんが今日はこの辺で終わりに出来ないかな。実は明日から愚妻と旅に出るんで…」
と遠慮がちに言うので、私が
「それじゃ、この続きは荒木ご夫妻が旅行から戻ってからということにしよう。それまでに出来るだけ調べておくからさ」
と約束し、解散することにした。
八重樫賢師について
おみやげの信玄餅を三人で味わいながら、荒木夫妻の道中のみやげ話を聞き終えたところで、
「さて、ではこの前の続きを開始しよう」
と吉田が切り出したので、私がまず口火を切った。
「前回最後に八重樫賢師という人物が話題になったよな。実はこの上田仲雄の論文「岩手無産運動史」の中に、
五月以降I盛岡署長による無産運動への圧迫はげしくなり、旧労農党支部事務所の捜査、党員の金銭、物品、商品の貸借関係を欺偽、横領の罪名で取り調べられ、党員の盛岡市外の外出は浮浪罪をよび、七月党事務所は奪取せらる。一方盛岡署の私服は党員を訪問、脱退を勧告し、肯んじない場合は勾留、投獄、又は勤務先の訪問をもって脅かし、旧労農党はこの弾圧に数ヶ月にして殆ど破壊されるに至っている。三・一五事件に続いて無産運動に加えられた弾圧は、この年の十月県下で行われた陸軍大演習によって更に徹底せしめられる。演習二週間前に更迭したT盛岡警察署長により無産運動家の大検束が行われた。この大検束を期として、本県無産運動指導者の間に清算主義的傾向が生じた。 <『岩手史学研究 NO.50』>
ということが論じられていた。そして、この「大検束」を受けた人物の註釈があり、一日内外~一週間の検束処分を受けた者としてほら、
花巻署 川村尚二((ママ)) 八重樫賢志((ママ))
という名前があるだろ。おそらくそれぞれ川村尚三のことであり、八重樫賢師であることは間違いなかろう。
一方、八重樫賢師という青年は「羅須地人協会の童話会などに参加し、賢治から教えを受けた若者」でもあるということだったので私は気になって仕方がなかった。そこで、八重樫賢師のことを知っている人をあちこち探し廻ってみたところ、Aさんという方を紹介してもらった。そのAさんからは、賢師につ
****************************************************************************************************
 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 “「羅須地人協会時代―終焉の真実―」の目次”へ。
“「羅須地人協会時代―終焉の真実―」の目次”へ。
”羅須地人協会時代”のトップに戻る。
《鈴木 守著作案内》
◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。
本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。
あるいは、次の方法でもご購入いただけます。
まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)
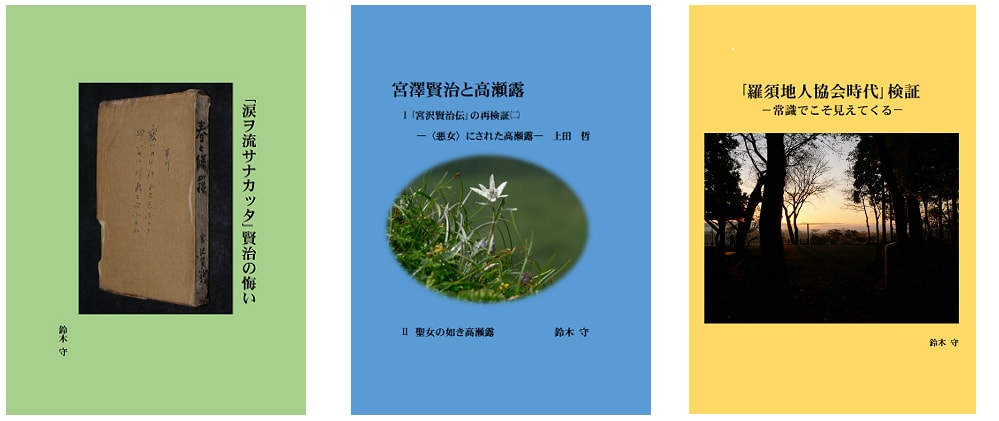
なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。
☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』
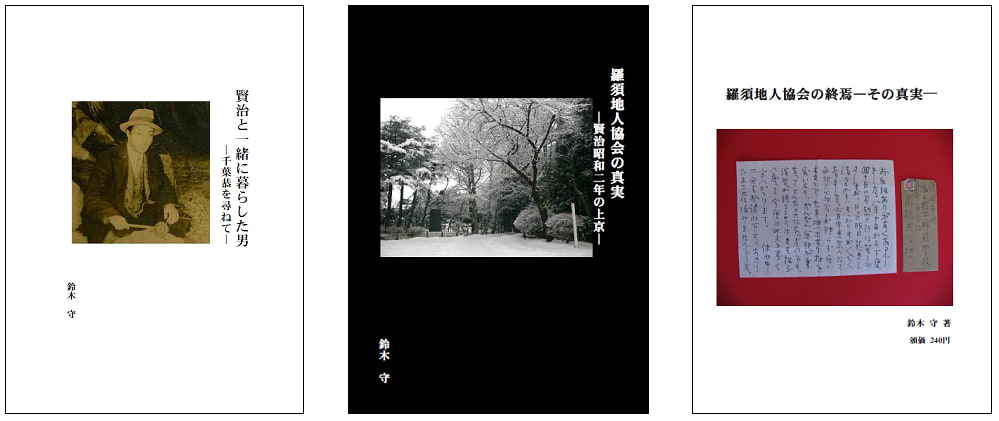











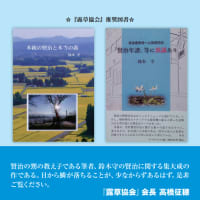
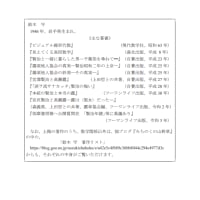
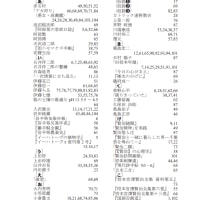
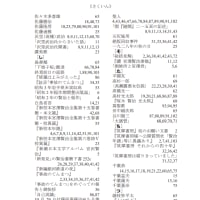

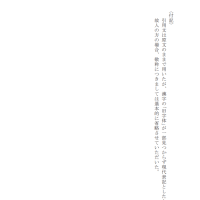
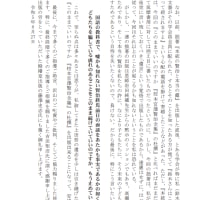
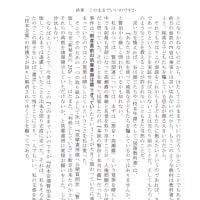
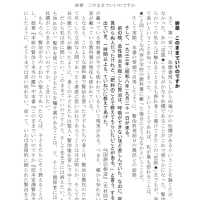
当時の私の記憶では、賢治はエスペラント協会との繋がりもあり、その界隈で石川三四郎のようなキリスト教的アナキストとの接点もあったと記憶しています。チジンという言葉は労農派(ボルシェビキ=共産党)よりも、当時のアナキストの中でよく使われていた言葉ではなかったかと私などは思っています。現地で見た幾つかの賢治の言葉の一つにも仏教的なものを含んでいたりしますが、アナキズムの香りを感じました。労農派との繋がりがあったのは確かでしょう、時代背景から考えれば、有島さんがアナキスト大杉を支えていたように、シンパ以上であってもおかしくないと思います。
今晩は。
この度はご訪問いただきありがとうございました。
やはりそうなんですね。私も、賢治からはアナキズムの強い香りを感じております。
一方、石川三四郎との接点につきましては私は全くわかっておりませんので、今後少し調べてみたいと思います。
なお、この関連で最近びっくりしたことは、
高杉一郎のシベリア俘虜記『極光のかげに』(岩波文庫)によれば、第二次世界大戦直後、シベリアの俘虜収容所で高杉がある将校から尋問を受けた際に、「宮澤賢治を知っているか」「石川啄木を知っているか」「彼らはアナーキストだろう?」と訊かれた。
ということでした。私にはこんなことは全く想定外のことでしたが、当時のソ連では、賢治は啄木に勝るとも劣らない「アナーキスト?」として知られていたということも十分にあり得るということを、今後心に留めておかねばと思ったのでした。
これからもいろいろとご教示賜りたく存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。
鈴木 守
シベリア・フリョ記にそんな一節があるのですね。当方の親戚には農業学校を出て徴兵され”在満”中にソ連軍によってシベリア方面へ連れていかれた村親戚のオジサンがいましたが、このオジサンから祖母の通夜の晩に幼い当方が聞かされていた事は、後から聞くシベリア抑留者の悲惨な話とは別の”ソ連で、よくしてもらい”、”帰国するのが嫌だった”ために舞鶴で待ってくれていた祖母をヤキモキさせ心配かける事になった…という話でした。そのオジサンは足が悪く、舞鶴に降り立ってその後の話は殆どしませんでした。その経験が引きずって自民党員として立ち居振る舞い自治会長もされていましたが、きっと帰ってきた後には様々な圧力がかけられたことだと今になれば想像出来ます。亡父からその後聞かされた話では、オジサンは舞鶴港に”降りない”と船に残った人たちの一人だったという所まではわかって居ましたが、その後当方が知った話や新聞のスクラップの中で、入港前に上陸拒否をしてインターナショナルを歌い赤旗を打ち振った抑留からの帰還兵がストライキを行ったという記事があり、そういうことだったのかと心にしまった記憶があります。昨年にそのオジサンは特養にて亡くなりましたが、全く寂しい老後でした。できれば、シベリア抑留の思想教化された部分の話をもっとシッカリ聞きたかったです。
…ともかく、私にとって賢治が生きた花巻の地はヤマト中央史観のいう所の”不来方”ではなく、イーハトーヴォを思わせる地でしたが、もう、随分変わってしまったのでしょうね。
マンシュウリア(満州)から戻ってきた個々人を戦後の国策で北上山地などの山麓の両側に農耕民として住まわせた開拓村に続く道にムグンファ(ムクゲ)の花が夏に咲いていたこと、高村山荘の近くぼ林檎畑群にリンゴの実が鬼剣舞のころに沢山実っていたことを思い出します。
鉄分の多い地下水が温んでいく境目の時期でした。
何だか、旅の途中の思い出話のような事になってしまい申し訳ありません。また、立ち寄らせていただきます。
昨今の様々な状況を見ていて、注文の多い料理店のような統治者側の注文を”客”が都合良く解釈して実行していく様を思い起こして自嘲気味に文字列を並べながら。(★)