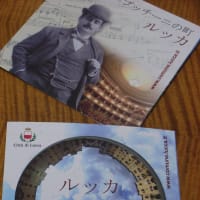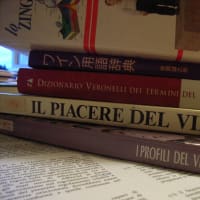って誰かご存知でしょうか?イギリス・ロマン主義の大詩人P.B.シェリーの奥さんで、その名をメアリー・シェリーという女流作家なのですが、英文科出身の身としてその程度は知っていましたが、なんとこの方、「フランケンシュタイン」出版後夫ともどもイタリアに来て、ルッカとピサ周辺を中心に3年余りも滞在していたとは知らなんだ。それも印税でもうかったから物見遊山に来てイタメシを食べ歩きブランド品を買いまくっていたわけではなく、その間に取材した史実をもとに、ルッカを舞台に「Valperga」という長編小説を書いていたのでした。
廃業のため在庫を安くたたき売っている書店でこの小説のイタリア語版を発見し、以上の事実を知ってさっそく買い(このようなことをしているから1001冊もたまる)、三島を片付けたので少しずつ読んでおるのですが、主人公がヴェネツィアを訪れ総督に気に入られる場面など「総督は彼のことを気に入った」と0.5行で片付けられているのに、秋の収穫に忙しい畑のあいだを縫って馬を進める描写などには半ページも費やしてメンメンと綴られていたりするのはさすがロマン主義という感じがします。自分も体験したから詳しく書いているだけという感じもするが。
ただ時代考証はいいかげんで、13世紀末~14世紀初頭が舞台なのに「とうもろこしの収穫が行われていた」り、「毛布代わりにとうもろこしの葉をつなぎあわせてかけていた」りするので、「アメリカ大陸原産のとうもろこしがダンテの時代にあるかいっ!」と思わずツッコミたくなるのは困り物です。ヴェネツィアの描写にも「ゴンドラを進めていくと、大運河の両側に連なる豪壮なパラッツォの数々」が眼に入るというのですが、13世紀末のカナル・グランデにはどれだけ邸館があったっけ?そのうち陣内先生の本をひもとかねば……(こういうことをしているから1001冊がなかなか減らない)。
写真はその(どの?)トウモロコシの粉で作ったポレンタに、豚肉とキノコといんげん豆のソースを乗せた前菜です。ルッカ北方の一大農業地帯・ガルファニャーナ地方特産で、スローフード協会が保護品目に指定している八列とうきび「フォルメントン種」使用。八列に実がなるトウモロコシはここと、日本の北海道にしかないんだそうです。
廃業のため在庫を安くたたき売っている書店でこの小説のイタリア語版を発見し、以上の事実を知ってさっそく買い(このようなことをしているから1001冊もたまる)、三島を片付けたので少しずつ読んでおるのですが、主人公がヴェネツィアを訪れ総督に気に入られる場面など「総督は彼のことを気に入った」と0.5行で片付けられているのに、秋の収穫に忙しい畑のあいだを縫って馬を進める描写などには半ページも費やしてメンメンと綴られていたりするのはさすがロマン主義という感じがします。自分も体験したから詳しく書いているだけという感じもするが。
ただ時代考証はいいかげんで、13世紀末~14世紀初頭が舞台なのに「とうもろこしの収穫が行われていた」り、「毛布代わりにとうもろこしの葉をつなぎあわせてかけていた」りするので、「アメリカ大陸原産のとうもろこしがダンテの時代にあるかいっ!」と思わずツッコミたくなるのは困り物です。ヴェネツィアの描写にも「ゴンドラを進めていくと、大運河の両側に連なる豪壮なパラッツォの数々」が眼に入るというのですが、13世紀末のカナル・グランデにはどれだけ邸館があったっけ?そのうち陣内先生の本をひもとかねば……(こういうことをしているから1001冊がなかなか減らない)。
写真はその(どの?)トウモロコシの粉で作ったポレンタに、豚肉とキノコといんげん豆のソースを乗せた前菜です。ルッカ北方の一大農業地帯・ガルファニャーナ地方特産で、スローフード協会が保護品目に指定している八列とうきび「フォルメントン種」使用。八列に実がなるトウモロコシはここと、日本の北海道にしかないんだそうです。