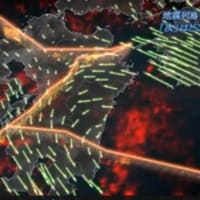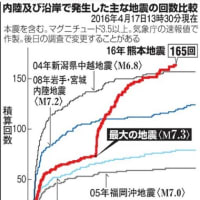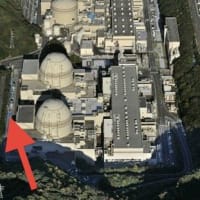今日は、ほとんどの人にとって関係のない話です。こう書くと、すぐみんな逃げて行っちゃうだろうな。
いま『リーダーの人間分析学』で「義経の行動予測」の再放送をしております。以前このブログでとりあげたものです。軍事的天才としては義経の名前をまずあげなければならないでしょう。
義経の騎馬戦というのは、日本の戦史において革新的なものだったとされ、その革新性は信長にもひけをとらないといわれています。
信長の場合は軍事的天才の面もありますが、政治的・経済的才能の面もあります。純粋に軍事面だけなら、あるいは義経に軍配があがるかもしれません。
天才というのは、どうして生まれるのでしょうか。ひとつの答えは「アンオーソドックス」ということのようです。
義経の革新性について、司馬遼太郎は次のように語っています。
「古来、多くの独創家はたいてい正規のコースを出ていない人が多い。エジソンだってそうでしょ。エジソンだって、ちゃんとコロンビア大学を出ていればどうだったかわかりませんよ、後年のエジソンが生まれたかどうか。そういうことが義経にも言えるんで、義経は武士学校というものは出ていないわけです。鎌倉のエリートである梶原景時なんかと意見が合わなかったのも当然でしょうね」
(司馬遼太郎『角川文庫・日本史探訪』(角川書店、1999年)
正規のコースを出ないんですから、天才は教育できませんね。正規のコースを出るということは、社会の規範を刷り込まれる可能性が大です。となれば、革新を期待するのは難しくなるのは道理です。
楽天の野村監督も言っています。4番とエースは育てられない。獲得するしかないと。だから、若くして才能のある人をくじでひくか、よその4番やエースをとってくるしかないということらしいです。
たしかに、凡才でも秀才は育てられる。しかし、凡才が天才を育てるのはなかなか無理があります。
ビジネスでも、天才的なマーケット・クリエーターは突然生まれるようなんですね。千人に三人ぐらいしかいないと言っている人もいるそうです。
この数が当たっているかどうかわかりませんが、そういう希少価値であるのは間違いないでしょう。そして、教育ではそういうクリエイティブな人は育てられないそうです。
天才にしてみたら、この世の中は面倒でうるさくてたまらんでしょうね。だって、自分のほうが圧倒的に優れていることが、内心はよくわかっている。しかし、大多数の凡人は、その真価がわからないというだけで、天才の言うことをさげすんだり無視する。
考えてみたら失礼な話ですね。凡人が自分より優れた人のことを評価するんですから。しかし、それが世の中の実情です。
天才というのは0から1を産む人です。みなさんも感覚的にはおわかりいただけると思いますが、0から1の距離は、1から100までの距離より圧倒的に遠い。
そして、0から1を産める人は極めてまれで、育てられない。教育はあくまで1から100にする凡人的秀才のためのものである。
英国の劇作家バーナード・ショーが言っております。中才は肩書きによって現れ、大才は肩書きを邪魔にし、小才は肩書きを汚す。
せめて、肩書きを汚すことだけはお互いしないようにしたいものです。そういえば、また大臣がお辞めになるそうですな。
最後は三波春夫さんの『元禄名槍譜 俵星玄蕃』の冒頭でしめさせていただきます。
槍は錆びても 此の名は錆びぬ
男玄蕃の 心意気
いま『リーダーの人間分析学』で「義経の行動予測」の再放送をしております。以前このブログでとりあげたものです。軍事的天才としては義経の名前をまずあげなければならないでしょう。
義経の騎馬戦というのは、日本の戦史において革新的なものだったとされ、その革新性は信長にもひけをとらないといわれています。
信長の場合は軍事的天才の面もありますが、政治的・経済的才能の面もあります。純粋に軍事面だけなら、あるいは義経に軍配があがるかもしれません。
天才というのは、どうして生まれるのでしょうか。ひとつの答えは「アンオーソドックス」ということのようです。
義経の革新性について、司馬遼太郎は次のように語っています。
「古来、多くの独創家はたいてい正規のコースを出ていない人が多い。エジソンだってそうでしょ。エジソンだって、ちゃんとコロンビア大学を出ていればどうだったかわかりませんよ、後年のエジソンが生まれたかどうか。そういうことが義経にも言えるんで、義経は武士学校というものは出ていないわけです。鎌倉のエリートである梶原景時なんかと意見が合わなかったのも当然でしょうね」
(司馬遼太郎『角川文庫・日本史探訪』(角川書店、1999年)
正規のコースを出ないんですから、天才は教育できませんね。正規のコースを出るということは、社会の規範を刷り込まれる可能性が大です。となれば、革新を期待するのは難しくなるのは道理です。
楽天の野村監督も言っています。4番とエースは育てられない。獲得するしかないと。だから、若くして才能のある人をくじでひくか、よその4番やエースをとってくるしかないということらしいです。
たしかに、凡才でも秀才は育てられる。しかし、凡才が天才を育てるのはなかなか無理があります。
ビジネスでも、天才的なマーケット・クリエーターは突然生まれるようなんですね。千人に三人ぐらいしかいないと言っている人もいるそうです。
この数が当たっているかどうかわかりませんが、そういう希少価値であるのは間違いないでしょう。そして、教育ではそういうクリエイティブな人は育てられないそうです。
天才にしてみたら、この世の中は面倒でうるさくてたまらんでしょうね。だって、自分のほうが圧倒的に優れていることが、内心はよくわかっている。しかし、大多数の凡人は、その真価がわからないというだけで、天才の言うことをさげすんだり無視する。
考えてみたら失礼な話ですね。凡人が自分より優れた人のことを評価するんですから。しかし、それが世の中の実情です。
天才というのは0から1を産む人です。みなさんも感覚的にはおわかりいただけると思いますが、0から1の距離は、1から100までの距離より圧倒的に遠い。
そして、0から1を産める人は極めてまれで、育てられない。教育はあくまで1から100にする凡人的秀才のためのものである。
英国の劇作家バーナード・ショーが言っております。中才は肩書きによって現れ、大才は肩書きを邪魔にし、小才は肩書きを汚す。
せめて、肩書きを汚すことだけはお互いしないようにしたいものです。そういえば、また大臣がお辞めになるそうですな。
最後は三波春夫さんの『元禄名槍譜 俵星玄蕃』の冒頭でしめさせていただきます。
槍は錆びても 此の名は錆びぬ
男玄蕃の 心意気