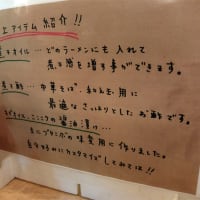三島大社での三島夏祭りの最終日(3日目)、天下泰平と五穀豊穣を祈ってする流鏑馬を観てきました。
馬、かっこいい!
「なにが武田流なんだろう?」と思っていたのですが、この三島大社での流鏑馬は文治元年(1185年)、源頼朝が最初に6月20日に奉納して以来、欠かさず年3回680年間とりおこなわれていたそうなのですが、明治元年に廃止されてしまったのだそうです。それを昭和59年に復活した時に、武田流司家式のやりかたを取り入れたんだそうです。武田流・・・・・ 弓の撃ち方なのかな、的の配置のしかたなのかな、馬の走らせ方なのかな、衣装の具合なのかな。
と思っていたら、詳細に解説している公式サイトがありました。ネットって便利です。
きっと、馬の乗り方から式次第を含めての全部が「武田流」なんでしょうね。「武田流弓馬道は、源 頼朝以来の馬上武道を伝える唯一の流派」と、とてもいさましいことが書いてあります。

しかし、馬の走るのがはあまりにも早すぎて、写真が全然うまく撮れませんでした。
次々と走ってくる馬がかっこよかったのにー。
途中で凄い雨が降り始めたのに、馬たちは走り続けました。そして、雨が一段落してまばらになり始めた頃、「雨が激しいので後半の神事を省略する」というアナウンスが入りました(笑)。走る馬は5頭いて、社史には「一回3本ずつ計9回撃つ」と書いてあるのですが、明らかにそれ以上の回数を走って撃っていました。なかなか小さい的に当てるのは大変みたいです。でも、たまに当たると大きいどよめき。
つづいて。

農兵節を観ました。
ここのサイトによると、農兵節は江川太郎左衛門の部下の柏木総蔵が作り出したもので、韮山発祥なのですが、太郎左衛門が三島の町なかに「農兵練兵場」をつくったおかげで、現在三島の伝統芸能として盛り上げようとしているのだそうです。
5つぐらいの団体があってそれぞれ農兵節を踊っているのですが、それぞれ別の歌い手が同じ歌詞を歌っています。これが、聴いていると意味が分からなくて、なかなか頭に残る特徴的な歌調です。
歌詞だけ書き写しても、あの踊りの異様さは良く分からないのですが、一応写しておきます。
富士の白雪ノーエ 富士の白雪ノーエ
富士のサイサイ 白雪朝日で溶ける
溶けて流れてノーエ 溶けて流れてノーエ
溶けてサイサイ 流れて三島にそそぐ
三島女郎衆はノーエ 三島女郎衆はノーエ
三島サイサイ 女郎衆はお化粧が長い
お化粧長けりゃノーエ お化粧長けりゃノーエ
お化粧サイサイ 長けりゃお客が怒る
お客怒ればノーエ お客怒ればノーエ
お客サイサイ 怒れば石の地蔵さん
石の地蔵さんはノーエ 石の地蔵さんはノーエ
石のサイサイ 地蔵さんは頭が丸い
頭丸けりゃノーエ 頭丸けりゃノーエ
頭サイサイ 丸けりゃカラスが止まる
カラス止まればノーエ カラス止まればノーエ
カラスサイサイ 止まれば娘島田
娘島田はノーエ 娘島田はノーエ
娘サイサイ 島田は情けでとける
ネットで検索してようやく歌詞が分かったのですが、聴いているときは「地蔵は頭が丸い」の部分が「頭が悪い」と聞こえて、「お客さんが怒ると地蔵の頭が悪くなって、そこにカラスが止まる」とはなんなんだろう??と不思議に思いながら聞いていました。

江川太郎左衛門の人もいらっしゃいましたよ。