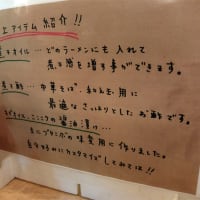前から気になっていた場所に行ってきました。
私、「平将門の首塚」とか「入鹿の首塚」とか「新田義貞の首塚」とか、そういう語感が好きなのです。(趣味が悪いですね)
沼津にあるという首塚は、「明治33年の暴風雨のあと、風と雨と波に洗われた地面から大量の頭骨がゴロゴロと出てきて、びっくりした村人たちが手厚く供養した」というもので、昔この付近で行われた武田水軍と北条水軍の大海戦のときの戦死者の骨だろうと考えられている、とのことでした。

写真の後ろに写っている立派な建物は「本光寺」という日蓮宗のお寺で、なかなか格式と由緒がありそうです。(でも実地で見るとあからさまにこの首塚はお寺の敷地の一角にありそうに見えるのに、実際は全然関係がないということも聞きました)
また、目の前に高校がありまして、首塚は学校の運動場から微妙に見えそうな位置にあります。教育的に、歴史に対する畏敬を与える良い教材になりそうだなぁ。「お首さん」だなんてメルヘンチックな呼び方をされていることも頷けます。
さて、
この首塚は「千本浜」にあるという事で、沼津の地理に疎い私は、その千本浜を、「沼津西方の原・片浜」という地域にあると思い込んでいました。
私は富士や浜松に遊びに行くとき、いつも海岸沿いの県道183号線を通っていくのですが、富士市の境に至るまでの十数km、延々と松林が続いているんですよね。そこは「千本松原」と言いまして、この寂しい地域が昔戦場となったんだろうと。駿河湾からの風が常にビュウビュウと吹き付ける、雰囲気満点の場所です。‘古戦場’というイメージにぴったりの場所です。
ところが、今回行こうと思って事前に確認してみると、首塚の場所はそっちじゃなかった。狩野川の河口付近にある「千本浜公園」というところにあると言うのです。こっちは全然寂しい場所ではなく、むしろ沼津の市街地の一角で、私の思い描いている「千本浜」とはちょとイメージが違います。
それと同時に、私の頭の中の千本浜の戦いのイメージも、描き直さねばならない感じになってきました。

こうやって地図に描いてみると「千本浜公園」も「千本松原」もそんなに離れていないじゃないかと思いますが、でも現地のイメージは全く違う。(私はドライブでいつも片浜付近の千本の松を見慣れていますので、そっちのイメージが、、、、) 戦史的にもこの場所が武田軍の本拠・三枚橋城に近いか、それとも清水江尻港からの援勢が受けやすい位置があったか、それだけで、この「出土した大量の頭骨」の状況は変わってくると思うのです。
・・・・そもそも、この大量の頭、北条方の死体なんですか? それとも武田方の死体なんですか?
前に書いた『北条五代記』と『甲陽軍鑑』の記述を読み比べてみますと、「いったいどの過程でこんなに大量の頭蓋骨が発生したんだろう?」という疑問がむくむくと頭をもたげてきます。いろいろなシチュエーションが考えられますよね。この場所は武田方の三枚橋城にすごく近く、この海戦の後も(2年間は)武田氏は三枚橋城を堅持しつづけてるわけですから、「北条方が首実検のあとに大量の首をここに葬った」(=つまり、首の主は武田方)と考えるのは無理がありそうです。しかし、看板によると、「首は若者のものが多い」そうなのです。若い兵士ばかり、、、、、 1575年の長篠の戦い以降、武田方は主立った宿将と手練れの将兵を失い、連戦の苦しい戦いを強いられるようになっていましたので、若年兵が多いという様子には納得できるものがあります。もしかしてこの骨は武田方の骨なのか?(もちろんその多くは駿河や沼津周辺で徴収されたんでしょうけど)。逆に、北条方が若い兵士が多かったと理由づける材料は無いです。
はたして、この骨は武田の骨なのか? 北条の骨なのか?
・・・・・これが、もうちょっと三枚橋城から離れていてくれると(そう、千本松原の原町付近に)、いろいろと説明ができるんですけどねえ~。
一応、郷土史家の戸羽山瀚氏の本には、「…北条方は、当時最新式の設備と大きさを誇る“あたて”という軍船十艘から成る無敵艦隊を編成して、重須港から出撃した。かくして千本松原から吉原海岸にかけて布陣していた武田勢に、猛攻撃を加えたので、武田方はひとたまりもなく退散、再び海岸に出て砂を掘って塹壕を築き、そのかげより数百挺の鉄砲で応戦したが、かねて用意してあった木板にさえぎられ、武田方の砲撃も、なんらのなすところがなかったのである。武田方も清水港に軍船を配備していたが、二十丁立の小舟では歯が立たず、ついに出撃する事がなかった。しかし3月15日の未明、三隻の小舟で重須港に夜襲をかけたが、追われ、狩野川から出撃した二隻と合して、小舟の足の早さにまかせて逃げてしまった。武田方の大敗のうちに千本浜の海戦は終わった。勝ちに乗じた北条勢は、千本松原に追い打ちを掛けたが、この陸戦がまことに熾烈をきわめたものであったことは、首塚に葬られている頭蓋骨を始め、人骨の切り割られた刀のあとからはっきりと窺われる」、と書いています。
つまり、頭蓋骨の主は武田の少年たちだとハッキリ言ってるんですね。(大人の=つまり偉い身分の将は重須長浜城まで持って行かれたのでしょう)。ほんとかどうかは私は知らない。
なお、沼津市のサイトには、この頭蓋骨の簡潔かつ極めて詳細な分析報告が掲げられています。この分析結果はとても興味深い物です。
まず気になる事。
なぜか頭蓋骨を分類するときに、「右側の頭蓋骨」と「左側の頭蓋骨」に選別している。もちろん400年も経っているわけですから、普通の状態であってもバラバラになってしまうだろうことは分かるし、分析する段階でそれを部位ごとに選別するのも分かる。しかし、この報告書で「右側」と「左側」に分けて報告しているのはどうしてなの?
右;98個で左;105個で、少しの差異はあっても、ほぼ同数が残っていると言ってもいい数字だと思う。
ところが、男女比で調べてみると、驚くべき事が分かります。右側の方は女性が29%だったのに対し、左側は女性が10%も多いのです。つまり、、、、、 右側の足りない分の失われた7個分の骨はすべて女性のもので(そう考えないと計算が合わない)、それから推測して言える事は、「北条方は戦いの後に女性の頭骨の右半分を持ち帰る」習癖があった、ということだと思います。(コラコラ) でも報告書には「脳摘出をしていた疑いも認められる」と書いてあるし、北条軍ってもしかして戦争に際して、変な趣向を発揮する習性があったんじゃないかと思う。女性の右半分の頭骨、、、 食べちゃったのかな(グロい)。
そもそも、なんでこんなに女性の骨が多いんでしょうね?
案内看板には「十代後半の若者の骨の多い事が注目される」と書いてありますが、それよりももっと注目すべきは、女性の骨の多さですよ。3人に1人が女性ですもの。
従軍する遊女や慰安婦や飯炊き女かなとも思いましたが、それにしても多すぎです。どさくさにまぎれて近隣住民の非戦闘員が巻き込まれて殺されたのかな、とも思いましたが、「老年及び幼少年は全く認められない」とあるのでそれも否定されます。
もしかして「武田軍(もしくは北条軍)には娘子軍が存在した」「武田の兵の3分の1は華麗に戦う女剣士だった」とか、そういうむちゃくちゃな視点で妄想を膨らませようかとも思いましたが、十代の少年兵(それでも当時は成年とみなされるのでしょうか)が多い事から見て、案外「我が子の身が心配で心配で、戦場にまでついてきてしまった若いママさんたち」というのが真相に近いかもしれませんね。(ぉぃぉぃ)
あと気になる事、、、「狙われて頭の皮を剥がれた特殊な立場の男性」って記述、、、 何のことなんでしょう?
千本松原は、この戦いのときにすべて(!)切り払われたそうですが、それだと風が強くて困るので、直後に増誉上人という人がやってきて、ふたたび千本の松を植えたんだそうです。

ここからは、富士山がとても綺麗に見えます。
戦国時代のこの戦いの時にも、こんなに綺麗な富士山が見えたんでしょうか?
それよりも、この海岸はとにかく風が強くて、海戦をするのは大変そうなところです。


千本浜公園から見る伊豆半島の大瀬崎(思いっ切り逆光)。
ここは駿河湾の奥にある沼津湾の一番奥なので、ここから見る駿河湾は、山に囲まれた小さな丸い池のように見える錯覚を感じさせる、不思議な場所でした。
(でもその光景はカメラに収まりきれませんでした)
あと、ここの海岸は砂地ではなくて、丸石の海岸なんですね。