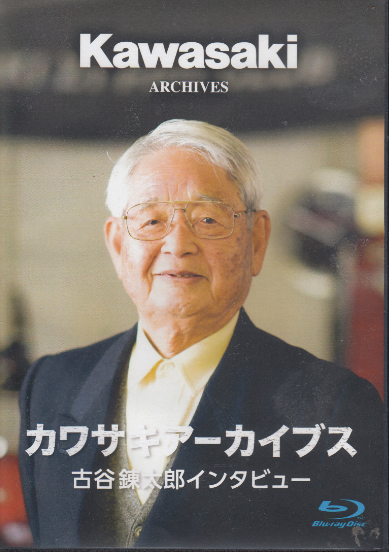★昭和57年に企画部門の中枢を引き受けて、58年夏には大庭本部長体制になり、60年(1985)末までに事業再建は実質的に成功したように見えたのだが、
この年260円であった為替相場は年末には200円となり、昭和61年(1986)に入ってからは更に円高は進んで、150円のレベルにまでなったのである。
輸出主体の二輪事業は、大きな打撃を受けるのだが、4年前と違って悪化の原因が為替問題だけであったので、社長以下本社の信頼も揺るがなかったし、7月の役員人事では、大庭さんは川重副社長に昇格され、単車事業本部長は高橋鉄郎さんに引き継がれたのである。
今になって振り返ってみると、この大庭本部長時代の3年間が、私自身にとってもサラリーマン時代、最も大きな権限も発言力もあった時代だったのかなと思ったりする。
カワサキの二輪事業を再建するために、そのことだけに集中して、自分の思う通りのことを率直に進言したと思う。大庭さんからも全幅の信頼を頂いて、殆どの企案をその通りに進めることが出来た3年間であたっと思う。
『二輪事業のトータルを動かした』と言う実感をいまでも持っているし、『リーダーシップ』とは、上に対して発揮できて初めてホンモノだとも認識した時期でもあった。
この年、大幅な円高で、これに対応する構造対策案をドラスチックに検討していたのである。
★その一つが、ジェットスキーの国内並びに欧州、オーストラリアなど、新市場への導入で、
当時の鶴谷課長が専任で担当してくれたのだが、ヨーロッパでは伊藤忠などとの調整なども含め、オランダに拠点進出を行ったし、
日本国内の販売網の新設、JJSBAなどのレース組織の充実などにスタートしている。
国内では、従来西武自動車のボートのネットワ―クでその一商品として取り扱っていたのだが、ボートとは基本的に違う、所謂『パーソナルウオータークラフト』であるから、その遊びに見合った専門の販売網が要ると思ったのである。
始めて売るのにどうして、専門店が出来るのか?などと言う声もあったが、精力的にその検討して、東灘にジェットスキー専門店1号店を翌年早々にスタートさせているのである。
この年6月では山中湖で行われたジェットスキーレースに出かけているが、このころはまだ上流社会と言うか、金持ちのスポーツで、レースの前夜祭はタキシードやイブニングドレスに着飾った女性が集うなど、二輪とはまた違ったレースの世界に驚いたりした。
ヤマハさんが、この業界に入ってこられたのもこの年である。数はまだまだ少なかったが、カワサキには珍しいトップメーカーだったのである。ヤマハさんが参入の挨拶に来られたりした年である。
★あまりの円高のひどさに、逆にこの機会を利用して、カワサキの二輪事業の構造的な対策を企画を中心に検討開始せざるを得なかったのである。
結果的に私の任期は実質この年までだったので、この年の年末までに構想そのものは認められていたのだが、結果は実現されていない。
もしこの構造になっていたら・・・・・と今でも残念には思っている。 やり残した仕事と言えば、この三つだろう。
●二輪事業としての本社機能の充実
ホンダ、ヤマハ、スズキはそれぞれ本社を持って事業展開をしている。川崎にも勿論本社はあるがそれは全事業のためのもので、世界に事業展開する二輪事業のためのものではない。二輪事業独自の本社機能が是非必要だと今でも思っている。関連事業部は残ってはいるが、当時のような権限はないと思うし、法務班なども消えてしまった。本社機能なしでの事業経営はいろいろと問題があるはずで、それが表面化しているのだが、気付いていないだけである。この本社機能の充実がまず第一だと思っていた。
●円高対策のための『円建て』への移行
この年の円高は凄まじかった。 この年の短期的な対策ではなくて構造的に『円建て』可能な仕組みの再構築を行うことが、事業の安定化に絶対に必要だと思った。カワサキの場合は売り上げの大部分が100%出資の直販会社である。 まず直販会社が円建てに耐えうるような経営体質の強化=剰余金の増加さえ行えば可能である。二輪事業の特に海外は半年分ほどの在庫を持っている。一般に円高は値上げで対策するので、その在庫は円高で有利に働くのである。この方策は販社の剰余金を積み増す分=事業部の利益は減少する。従って事業部の損益ばかりを考えるような経営をやったのでは、実現しない。当時の本社財務担当の松本新さんも100%賛成して頂いた方策なのだが、結果的には逆の方向に実績は動いている。当時の管理の小川優君などと一緒に進めていたプロジェクトである。円建てにしてあれば、今の円高なども何の影響もないはずである。
●もう一つは、労務問題も含めた、生産サイド工場の別会社化構想である。アメリカにあるKMMは別会社である。販売会社も全て別会社である。
世界展開を進めるうえで、世界各国に工場展開する方向になるはずである。明石だけが別会社でないために、事業部の事業全体を見なければならない企画がどうしても工場主体の考えになってしまうという理由で、本社機能の充実とともに、生産別会社構想も本社の経営会議の承認までは取れていたのである。大庭さんは最初は賛成ではなかったが、発動機との合併の際の検討の時に、了承頂いたのである。現在も明石を除いて海外生産はみんな別会社になっている。
★時代は変わったが、今の時代国内の『メーカー』機能は弱小化する方向である。『メーカーからの脱皮=二輪事業展開の再構築』が必要なのである。
今の現役諸君のためにも、提言しておきたいと思っている。
ただ、これは構造問題だから、簡単には出来ない。『確固たる意志』が要る対策である。

★この月毎の実績表の内容を見ても、
4年ほどの激動期を経て、事業の形態も平時に戻りつつある、そんな時期であった。4年前はまだまだ若手部長であった私や田崎さんも、それなりの年次を経て、KMCも後身にゆずらねばならず、更に単車、発動機の合併と言うことで、事業規模では圧倒的に単車なのだが、だからと言って同じ会社の人たちだから、なかなかその人事配分なども、現実には難しいのである。
単車内の人事や組織構造は、殆ど任されて私がやってきたのだが、事業部同志の合併となれば、高橋鉄郎さんにお願いせざるを得ないのである。
そう言う意味では、なかなか複雑な時期だったと思う。特に発動機の企画室長をされていた柏木さんが私の1年先輩だったし、個人的には非常に近かったので、余計にやり難かったのかも知れない。当時柏木さんには非常に気を遣って頂いたが、それが逆に重荷になったりした。
この4年間社長や本社の役員さんと直接に接する機会も多く、それがどんなものかと言うこともよく解った。前年企画室長になった一瞬は、そんな職位のこともアタマをよぎったが、それ以降はむしろ役員は面倒だなと思うようになった。高橋鉄郎さんに生産や技術的な分野にも関心を持てとしょっちゅう言われたのだが、逃げてしまうのでよく怒られたものである。
長く、小さいけれども二輪販売店などのオーナー社長のやり方に接してきたが、このようなトップは本当に長期の政策がやれるのだが。大企業は意外に方針が一貫しないのも、トップの座が4年間などと短いからだと思う。
前任者の方針を引き継いでやるというのは、簡単なようだが、どうしても独自性を出したがるので、継続性はあまりない。
結局は時代が良くて運よく利益が上がり易い問題のない時期を担当した人は幸せなのである。そう言う意味では、電力会社の社長さんがたも、今の時代は大変だろう。
★会社の中で、職制変更と人事は、大きな関心事である。
それを動かせるのが権限、権力なのだろう。そんな権限みたいなものを実質的に持てた3年間だったと思う。若手の部長だったのにそれが可能だったのは、事業が継続できるかどうかの激動期の危機対策がメインであったから、『純粋に』その方策に基づいた組織改革であったり、それに対応した人事であったから、『出来た』のだと思っている。
殆ど周囲に気を遣わずに、実行できた。『本社からの若手人材導入』で事業部にも小川、中村君など新しい血が混じったし、『海外販社人事』など予想外と言う人を充てたりした。一番びっくりされたのが、勤労の三原君のUK社長で労働組合からもホントに大丈夫か?と心配されたりした。販社の社長など資質さえあればそんなに経験など不要だと思っている。三原さん、今年の6月で川重副社長を引かれたが、UK社長時代はみんなが心配したが大丈夫成功されたのである。その後、事業部の人事が特に海外販社関係で自由な発想で行われる端緒になったのは、『労働の三原でも出来た』と言うことがよかったのだと思っている。
それが4年目には、事業も改善されて、安定してきたのである。従来の大会社の人事異動になるのは当然なのである。特に単車と発動機の統合と言うようなことになると、これはやはりトップの専権事項で、私自身はあまり興味関心の薄い分野だったこともあって、自ら引いてしまったような気がする。
そんなこともあって、私の『単車事業再建』と言う大テーマに対応した時期は、大庭さんが引かれたのと一緒に終わってしまった。
この年の7月からは、高橋本部長の時代がスタートするのだが、今から思うと高橋鉄郎さんも、いろいろ悩まれたに違いない。
★この年、家庭では長男が大学を卒業し就職をしたので、実質家を出た。
娘は、大学に入ってこれは1年生から、芦屋の45000円もするいいところから、通うようになった。
長男が就職して幾らか、家計にも余力が出たのかも知れない。
家は急に静かになって、家内とおばあちゃんの3人家族になったのである。
まだ53歳なのである。
背負い切れるかなと思ったようなものが、運よく何となく終わって、私自身もちょっと拍子抜けしたような、この年の終わりころだったように思う。
4年前のように鮮明に覚えていないのは、ホッとしていたのかも知れない。
男はまだ会社で仕事があるのだが、専業主婦は急にすることが少なくなって、拍子抜けするのかも知れない。
家内もそのころどうだったのか?
芦屋に下宿した娘と一緒に、ちょくちょくあちこち出かけていたようである。
★NPO The Good Times のホ―ムページです。(会員さんの のブログもツイッターもFacebookも見られます)