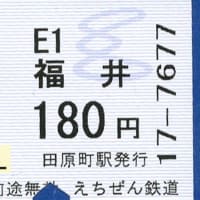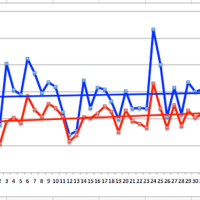円筒分水
桜橋の北詰に、「円筒分水」というものがある。橋の手前で県道322号の中央分離帯が幅広くなっていて、上下線に別れた橋につながるようになっているところ。フェンスで入れないようになっている。

1 「円筒分水」のフェンス 2018.1.13

2 桜橋の円筒分水 2018.1.13 小倉南区桜橋北
覗いてみると円筒形の壁の中に、3つの同心円のコンクリート構造物が作ってあって、一番中の円筒は水没していて中央は深いようだ。二番目の円筒は高くて、内側の水面は外側より少し高い。三番目の円筒は縁まで水が来ていて、外側の最も低い水面に向かって水が流れ落ちている。最も外の低い水面は、円周が幾つかの弧に仕切られていて、そこに落ちた水は、周囲の円筒形の壁に3か所開けられた四角の放流口から出て行っている。放流口には鉄製の落とし板があって、外から操作して水流を遮断できるようになっている。水は澄んでいて気持ち良く流れている。
ここから130メートルほど行った紫川の堰の右岸(こちら側)には取水路が作ってあって、すぐに暗渠になっている。

3 桜橋から見た堰。左端に取水路が作ってある。 2018.2.15

4 取水路。左に本流で上流側から撮影。 2018.2.15

5 右岸(取水側)から見た堰 2018.2.15
この取水が円筒分水に来ているようだ。「円筒分水」というのは取水した水を一定の比率に分けるための仕組みである。その原理はたぶん次のようなものだろう。二番目の水面の円筒の縁から落ちる水の量は、円周の長さに比例する。それを利用しているのだが、正確に比例させるためには湧き出し口から水流が対称に流れてくる必要がある。二番目の円筒はそのためだろう。さらに中央の水没した円筒は地下から湧き出させた水流を整流にし、また侵食を避けるための構造だろう。各放流口の水量の比率は、仕切りの位置によって調整可能である。ここの場合、円弧は二つに分けられていて、両者はほぼ同じ長さの弧を描く。北側の弧はそのまま放流口に繋がるが、南側の弧は低い仕切りでもう一度二分されていて、残り二つの放流口に向かって水を流している。ただし、低い仕切りを水が越えているから、両者の比率は同じではない。ここで取水した水は、徳力付近のいくつかの用水路に分けられ、その水量の比率は話し合いで厳密に決められていたのだろう。
なお、上の写真は幅5センチほどのフェンスの間からデジカメを中に入れて撮った。小さなコンデジでないと撮れない写真。こういうことに備えてストラップが付けてあるから落とす可能性は少ない。また、円筒分水のデータベースというのがネットにある。
この場所をGoogle Map(以下Map)でみると、「小倉南区の円筒分水」と記してある。そのすぐ北側にちょっと気になる記載がある。「徳力軌道 桜橋駅跡地」とある。徳力軌道は、1923年から2年半ほどあった馬車鉄道であるが、その鉄道遺構はないと思う。探してみたが記念碑などの何のサインもなさそう。徳力桜橋駅はその終点であり、北(上り方向)に向かって、徳力図里・守恒・北方の合計4つの駅があったはず。Mapでは、徳力図里駅跡地の記入があったが、最近消されたようだ。よく行くKMD珈琲店から橋を渡ったところ。守恒駅跡地はスーパーのSLの前で、Mapに記入がある。北方駅跡地は記入がないが北九大の正門前だろう。これらのどこにも記念碑などは見当たらない。もしあったらご教示いただければ幸いである。
桜橋の北詰に、「円筒分水」というものがある。橋の手前で県道322号の中央分離帯が幅広くなっていて、上下線に別れた橋につながるようになっているところ。フェンスで入れないようになっている。

1 「円筒分水」のフェンス 2018.1.13

2 桜橋の円筒分水 2018.1.13 小倉南区桜橋北
覗いてみると円筒形の壁の中に、3つの同心円のコンクリート構造物が作ってあって、一番中の円筒は水没していて中央は深いようだ。二番目の円筒は高くて、内側の水面は外側より少し高い。三番目の円筒は縁まで水が来ていて、外側の最も低い水面に向かって水が流れ落ちている。最も外の低い水面は、円周が幾つかの弧に仕切られていて、そこに落ちた水は、周囲の円筒形の壁に3か所開けられた四角の放流口から出て行っている。放流口には鉄製の落とし板があって、外から操作して水流を遮断できるようになっている。水は澄んでいて気持ち良く流れている。
ここから130メートルほど行った紫川の堰の右岸(こちら側)には取水路が作ってあって、すぐに暗渠になっている。

3 桜橋から見た堰。左端に取水路が作ってある。 2018.2.15

4 取水路。左に本流で上流側から撮影。 2018.2.15

5 右岸(取水側)から見た堰 2018.2.15
この取水が円筒分水に来ているようだ。「円筒分水」というのは取水した水を一定の比率に分けるための仕組みである。その原理はたぶん次のようなものだろう。二番目の水面の円筒の縁から落ちる水の量は、円周の長さに比例する。それを利用しているのだが、正確に比例させるためには湧き出し口から水流が対称に流れてくる必要がある。二番目の円筒はそのためだろう。さらに中央の水没した円筒は地下から湧き出させた水流を整流にし、また侵食を避けるための構造だろう。各放流口の水量の比率は、仕切りの位置によって調整可能である。ここの場合、円弧は二つに分けられていて、両者はほぼ同じ長さの弧を描く。北側の弧はそのまま放流口に繋がるが、南側の弧は低い仕切りでもう一度二分されていて、残り二つの放流口に向かって水を流している。ただし、低い仕切りを水が越えているから、両者の比率は同じではない。ここで取水した水は、徳力付近のいくつかの用水路に分けられ、その水量の比率は話し合いで厳密に決められていたのだろう。
なお、上の写真は幅5センチほどのフェンスの間からデジカメを中に入れて撮った。小さなコンデジでないと撮れない写真。こういうことに備えてストラップが付けてあるから落とす可能性は少ない。また、円筒分水のデータベースというのがネットにある。
この場所をGoogle Map(以下Map)でみると、「小倉南区の円筒分水」と記してある。そのすぐ北側にちょっと気になる記載がある。「徳力軌道 桜橋駅跡地」とある。徳力軌道は、1923年から2年半ほどあった馬車鉄道であるが、その鉄道遺構はないと思う。探してみたが記念碑などの何のサインもなさそう。徳力桜橋駅はその終点であり、北(上り方向)に向かって、徳力図里・守恒・北方の合計4つの駅があったはず。Mapでは、徳力図里駅跡地の記入があったが、最近消されたようだ。よく行くKMD珈琲店から橋を渡ったところ。守恒駅跡地はスーパーのSLの前で、Mapに記入がある。北方駅跡地は記入がないが北九大の正門前だろう。これらのどこにも記念碑などは見当たらない。もしあったらご教示いただければ幸いである。