 秋も深まった先月の末、私は泉州への小さな旅をした。大阪府南部から和歌山県あたりに隠れている美のありかを探り当てるかたわら、日没後は、浪花の味覚を愉しむという時間だった。この旅に私を駆り立てたものについても、書いておきたいと思う。
秋も深まった先月の末、私は泉州への小さな旅をした。大阪府南部から和歌山県あたりに隠れている美のありかを探り当てるかたわら、日没後は、浪花の味覚を愉しむという時間だった。この旅に私を駆り立てたものについても、書いておきたいと思う。池大雅(いけのたいが 1723-76)という画家・書家がいる。日本美術の偉人のひとりで、南画(文人画)の大成者とされる人であり、たとえば木村蒹葭堂などは彼の弟子である。そしてこの池大雅の晩年の代表作に『洞庭赤壁図巻』(1771 重文)というすばらしい大作があって、2007年から続けられてきたその修復作業の完成を記念し、10月から11月にかけて、ニューオータニ美術館(東京・紀尾井町)で作品展がおこなわれた。たったの13点のみの展示ながら、これは今年のベスト1に推したいほどすばらしいイベントだった。
鎖国下の近世日本で、洞庭湖や瀟湘、赤壁といった中国の名勝の山水を、明るいタッチで描き継いでいくスタイルは爽やかそのものである。もちろん彼自身、一度も中国など行ったことがないわけで、渡来の画譜類、そしてヨーロッパ絵画の手法も参考にしつつ、彼独自の「胸中山水」を拡大していったが、私は彼の本質はロード・ムービーだと思う。旅を愛し、登山を愛しつつ、彼の筆は横へ、横へと広がっていき、長大なる横長のスクリーンが現出していったのだ。いくら日本国内を歩き回ってスケッチをくり返したところで、本場中国の山水画に近づくことは幻想に過ぎないことは、百も承知だっただろう。それでも彼は、胸中をネガ紙として山水を現像し続け、その筆致は歩行のリズムを正確に刻んだ。
その池大雅が画家としてデビューしてまもない26才の時(1750)に紀州・和歌山を訪ね、リスペクトの意を捧げにいったのが、すでに75才となり、翌年には亡くなる文人画の先駆者・祇園南海(ぎおんなんかい)である。池大雅は出来たての新作『楽志論図巻』(1750)を、私淑する南海に見せ、巨匠は若き才能が遠路はるばる訪ねてきたことに謝意を示し、この新作に跋を寄せた。祇園南海については、こちらの拙文を請参照。
ニューオータニの壁ポスターを見て、南海のまとまった数の作品を見られる稀なる機会が、和歌山市立博物館にあることを知り、居ても立ってもいられなくなり、気づいたら新幹線に乗り、泉州・紀州の旅に出たのである。

















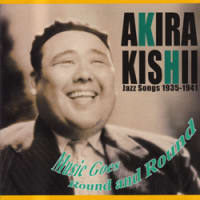


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます