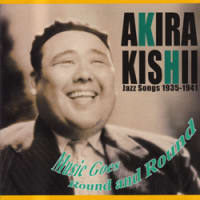先日、脚の悪い老母をわざわざ京都に連れ回した。荻野家の菩提寺である宗派の総本山である知恩院に初参拝させることが主目的である。2日目はあいにく雨に祟られたため、おもに美術館、博物館と屋内観光におとなしく収まった。
知恩院参拝のあと、祇園の「鍵善良房」で葛きりを食べ、その並びの「何必館」でアンリ・カルティエ=ブレッソンの写真展を見た。老母はブレッソンの写真よりも地階の魯山人の器展示のほうが興味を抱いていたようだ。まあそれはそれとして、同館のポスターやバナーに採用された『ムフタール街』(1952)という写真は、私の最も愛するブレッソンの作品である。10歳に満たぬ少年が赤ワインのボトルを2本抱えている。おそらく親のお遣いなのだろう。酒瓶を持って歩くことが大人じみて鼻高々だったのか、得意げな微笑を浮かべている。
ブレッソンの展示を見て刺激を受けたため、東京の自宅に戻っても、ロバート・フランクの『THE AMERICANS』(1958)から十文字美信『感性のバケモノになりたい』(2007)、マルティナ・ホーグランド・イヴァノフ『FAR TOO CLOSE』(2011)などなど、いろいろと手持ちの写真集を片っ端からパラパラとめくっていた。ロバート・フランクについては最近、ドキュメンタリー映画『Don't Blink』も公開されたが、これはじつにいい作品だった。もし機会があったらご覧いただきたいと思う。
にわかの写真熱を充当してくれたのが、試写と試写の移動途中に時間が少しあって寄ることのできたBunkamuraザ・ミュージアムのソール・ライター展〈ニューヨークが生んだ伝説〉である。この人の写真展を初めて見たが、感動的な発見となった。とくに素晴らしいのが、1950年代から60年代にかけてニューヨークの市井を撮影したまま現像もされずにソール・ライターの自宅スタジオに放置されていたカラー写真の作品群である。この時代の写真作品はモノクロームであることが普通だろう。表現と呼べる写真はつねにモノクロームだった。ところが、ソール・ライターはカラーフィルムの色彩を好んだようである。
この時代のニューヨークをカラーで見ることができるのは、ハリウッドのテクニカラー作品以外にはほとんどないと思う。後代に生きる私たちにとってソール・ライターのカラー写真作品は、テクニカラーのハリウッド映画に連なるものである。赤い傘が、オレンジの帽子が、緑の青信号が、ねずみ色の残雪が、まっ黒な遮蔽物が、真っ白なワイシャツが、いずれも眩しい。目を喜ばせる。
ソール・ライターは写真家であり、画家だった。日本美術に精通した彼の抽象画は、禅僧の描く山水と墨蹟であったり、ニコラ・ド・スタールの色彩の横溢であったり、ロラン・バルトが戯れに筆を走らせたざっかけない水彩のようであったりする。やはり、目を喜ばせる。
Bunkamura ザ・ミュージアムにて6/25(日)まで(以後、2018年春に伊丹市立美術館に巡回)
http://www.bunkamura.co.jp/
知恩院参拝のあと、祇園の「鍵善良房」で葛きりを食べ、その並びの「何必館」でアンリ・カルティエ=ブレッソンの写真展を見た。老母はブレッソンの写真よりも地階の魯山人の器展示のほうが興味を抱いていたようだ。まあそれはそれとして、同館のポスターやバナーに採用された『ムフタール街』(1952)という写真は、私の最も愛するブレッソンの作品である。10歳に満たぬ少年が赤ワインのボトルを2本抱えている。おそらく親のお遣いなのだろう。酒瓶を持って歩くことが大人じみて鼻高々だったのか、得意げな微笑を浮かべている。
ブレッソンの展示を見て刺激を受けたため、東京の自宅に戻っても、ロバート・フランクの『THE AMERICANS』(1958)から十文字美信『感性のバケモノになりたい』(2007)、マルティナ・ホーグランド・イヴァノフ『FAR TOO CLOSE』(2011)などなど、いろいろと手持ちの写真集を片っ端からパラパラとめくっていた。ロバート・フランクについては最近、ドキュメンタリー映画『Don't Blink』も公開されたが、これはじつにいい作品だった。もし機会があったらご覧いただきたいと思う。
にわかの写真熱を充当してくれたのが、試写と試写の移動途中に時間が少しあって寄ることのできたBunkamuraザ・ミュージアムのソール・ライター展〈ニューヨークが生んだ伝説〉である。この人の写真展を初めて見たが、感動的な発見となった。とくに素晴らしいのが、1950年代から60年代にかけてニューヨークの市井を撮影したまま現像もされずにソール・ライターの自宅スタジオに放置されていたカラー写真の作品群である。この時代の写真作品はモノクロームであることが普通だろう。表現と呼べる写真はつねにモノクロームだった。ところが、ソール・ライターはカラーフィルムの色彩を好んだようである。
この時代のニューヨークをカラーで見ることができるのは、ハリウッドのテクニカラー作品以外にはほとんどないと思う。後代に生きる私たちにとってソール・ライターのカラー写真作品は、テクニカラーのハリウッド映画に連なるものである。赤い傘が、オレンジの帽子が、緑の青信号が、ねずみ色の残雪が、まっ黒な遮蔽物が、真っ白なワイシャツが、いずれも眩しい。目を喜ばせる。
ソール・ライターは写真家であり、画家だった。日本美術に精通した彼の抽象画は、禅僧の描く山水と墨蹟であったり、ニコラ・ド・スタールの色彩の横溢であったり、ロラン・バルトが戯れに筆を走らせたざっかけない水彩のようであったりする。やはり、目を喜ばせる。
Bunkamura ザ・ミュージアムにて6/25(日)まで(以後、2018年春に伊丹市立美術館に巡回)
http://www.bunkamura.co.jp/