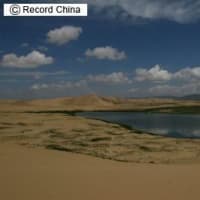■11月3日、テレビ朝日の『報道ステーション』が、チベット特集を放送しました。元朝日新聞の北京駐在員をしていた加藤千洋(ちひろ)さんが、夏休みを取ってしばらく姿を見せなかったのだそうで、知人から「あの白髪の人はチベットに行ってたそうです。特集を放送すると言ってましたよ」と聞いていたので、新聞欄を注意して見ていたのでした。ところが、内閣改造の空騒ぎなどが続いて、さっぱり「チベット」が出て来ません。どうせ、このタイミングで朝日新聞関係の人物がラサに行ったのなら「高山鉄道の宣伝」「ラサの近代化」「西部大開発」ぐらいの話でしょう。と特集予告を知らせてくれた人にも言っていたのですが、実際に放送されて見ると、余りにも予想がばっちり的中したばかりか、予想を遥かに超えるトボケた内容でした!
■冒頭から変です。奇妙です。不自然です!
「まー、考えて見ますと、中国がチベットを併合して半世紀以上が経つんですが、例えばラサの町に有る『垂直のベルサイユ』と言われるポタラ宮、ここを始めとしてチベットに急激なHOO変化がおとずれているという事を加藤さん、6年ぶりに行かれて、感じたとおっしゃっているぅ例えばですね…」
■古傷をつつくような事になりますが、有名なアントニオ猪木さんを盛んに応援していた故梶原一騎さんの大嘘漫画話を受けてテレビ朝日が放送して人気を集めていたプロレス番組で、大声と早口で囃し立てていたのが若い頃の古舘さんでした。この人は、アドリブで奇抜な「比喩(ウソ)」をポンポンと口から出任せで喋り続けるという特技が有るのです。ですから、この人が「報道」番組の中心になると聞いて、観る必要は無いし、万一、速報を知る必要が有っても眉にツバをいっぱい付けて注意して話を聞かねばならないと思っております。
■旅限無も愛用している『全チベット文化圏完全ガイド』(旅行人刊)にラサやポタラ宮に関する非常に詳しい説明が掲載されていますが、「垂直のベルサイユ」なんていう比喩は載っていません!
※これは不正確でした。新しい改訂版には、ポタラ宮の写真に付けたキャプションに「垂直のベルサイユ」が使われていました。ウソを書いてしまいました。すみません。以下は、番組を観終わったばかりの怒りに任せて書いてしまった一節ですが、敢えて削除しないで置きます。
これまでに、内外のチベット関連の本も普通の人よりは多く読んでいる心算ですが、こんな変な比喩は聞いた事が有りません。「…と言われる」という表現は、誰がそんな事を言っているのか?と問い返さねばならない無責任なものです。こんなイイ加減な軽口を「報道」という名前の番組で流して良いのか?!垂直とはなんだ?ベルサイユ宮殿よりも「高層」というだけの意味なのか?両者は、建築目的も歴史的な意義も、まったく似ていないし、どうしてポタラ宮殿とベルサイユが重なるのか、不思議な感性を持っている人がいるのですなあ。もしも、古舘さん個人のプロレス流のホラ話ならば、その旨をちゃんと断わって欲しいものです。
※チベット研究の専門家に聞いた所では、どうやら『垂直のベルサイユ』の出どころは、欧州の冒険家か旅行家ではないか?という結論になりました。これは古館さんのオリジナル思いつきではなく、欧州で発表された出典不明の決まり文句として何度か登場しているようです。
■こうして滑り出した「チベット特集」は、NHK特集どころではないトンデもない番組になりそうな、とても嫌な予感がして来ましたぞ!中国の報道バリアが強くて、チベットは報道されないまま、半世紀が経過したのは悲劇でした。それだけに、貴重な報道機会を得られた人は、しっかりと準備と調査をして「間違った事」を知らせないように、慎重な姿勢で取り組んで欲しいのです。「垂直のベルサイユ」などと、フランスなどに話題を持って行かずに、日本人に分かり易く紹介した方が良いでしょうなあ。
■ラサは、「神の土地」を意味するチベット語の地名です。ソンツェン・ガンポという王様がチャイナの地を見下ろす全ての高原地帯を統一して「吐蕃王国」を建てたのが7世紀です。その後、国内の分裂や動乱が続いて、特にインドから入った仏教が過激な密教色を強めてしまって、オウム真理教が宣伝に利用した「呪殺」が流行するような困った時代を過ごします。しかし、15世紀にツォンカパという天才が現われて、密教の暴走を修正して仏教が再興されるのです。この偉人が活躍した時代は、日本の足利義満とぴたりと重なります。このツォンカパの弟子の一人が、ダライラマ一世とされていますが、実際にモンゴルのアルタン汗から「ダライ・ラマ」(大海のような智恵)という称号を授与されたのは第三世でして、それから転生者によって称号と権威が継承されました。
■元々、ラサ中央にあった岩の丘には宗教的な施設が有ったようですが、ダライマラ五世(偉大なる五世)の治世に巨大な居城の建築が始まります。歴代ダライラマは、ツォンカパが創始した「ゲルク派」の僧侶ですから、この居城もゲルク派の教義と歴史を内包して設計されています。因みに、ポタラは観自在菩薩(観音様)が暮らす天界の宮殿の名前です。漢訳仏典では「補陀落」などの当て字が使われますが、日本では「ほだら」と呼ばれまして、東シナ海から紀伊半島、東北地方まで「ほだら」信仰は孤島や山に根付いて広まりました。
■江戸に最も近い所に有った「ほだら」信仰の聖地は、現在の日光です。「日光」は「二荒」の音読みをヒントにして目出度い漢字の組み合わせで書き換えたものです。どちらも「ニッコウ」ですなあ。元の「二荒」は「ふたら」と読んでいました。つまり、「補陀落」の音読みがナマってから字が当てられたというわけですなあ。この日光には徳川家康さんの霊が祭られまして、北側から徳川幕府を攻撃する精力を霊的に防御する場所として、将軍を筆頭に江戸時代から人々の信仰を集めたというわけです。日光は、「猿軍団」よりもチベットのポタラ宮殿と縁の有る場所だとお分かりになったでしょうか?「ベルサイユ」などとトボケた比喩など百害有って一利無し!まったく、無責任な番組ですなあ。
■加藤千洋さんが「6年ぶり」にラサを訪問したというのは重要な意味を持ちます。1999年にラサに行っているという事ですからなあ。その時に、一体この人は何の目的で出掛けて行ったのでしょう?北京支局の仕事を止める前に観光旅行に行ったのでしょうか?多分、この時にチャイナの広い範囲を見て歩いた記録なのでしょう。この人が共著の形で新書を出しています。購入済みですが、他のチャイナ関連の蔵書の中に埋もれておりまして、内容を論評するのは控えます。しかし、購入時に内容を確認した時の印象では、網羅的な価値は有るけれど、貴重な情報は乏しい、そんな記憶が有ります。偶に観るこの「報道ステーション 」でも、毒にも薬にもならない事を、にこにこしながら喋っているようですが、その雰囲気のまま、ふわふわとした書き方だと思って頂ければ間違いは無いでしょう。嗚呼、先は長いですなあ。また、長くなりそうです。
<ahref="http://blog.goo.ne.jp/nammkha0716/e/0d20cfc61a8c3054ddba8027c6c5818f">其の弐に続く
■冒頭から変です。奇妙です。不自然です!
「まー、考えて見ますと、中国がチベットを併合して半世紀以上が経つんですが、例えばラサの町に有る『垂直のベルサイユ』と言われるポタラ宮、ここを始めとしてチベットに急激なHOO変化がおとずれているという事を加藤さん、6年ぶりに行かれて、感じたとおっしゃっているぅ例えばですね…」
■古傷をつつくような事になりますが、有名なアントニオ猪木さんを盛んに応援していた故梶原一騎さんの大嘘漫画話を受けてテレビ朝日が放送して人気を集めていたプロレス番組で、大声と早口で囃し立てていたのが若い頃の古舘さんでした。この人は、アドリブで奇抜な「比喩(ウソ)」をポンポンと口から出任せで喋り続けるという特技が有るのです。ですから、この人が「報道」番組の中心になると聞いて、観る必要は無いし、万一、速報を知る必要が有っても眉にツバをいっぱい付けて注意して話を聞かねばならないと思っております。
■旅限無も愛用している『全チベット文化圏完全ガイド』(旅行人刊)にラサやポタラ宮に関する非常に詳しい説明が掲載されていますが、「垂直のベルサイユ」なんていう比喩は載っていません!
※これは不正確でした。新しい改訂版には、ポタラ宮の写真に付けたキャプションに「垂直のベルサイユ」が使われていました。ウソを書いてしまいました。すみません。以下は、番組を観終わったばかりの怒りに任せて書いてしまった一節ですが、敢えて削除しないで置きます。
これまでに、内外のチベット関連の本も普通の人よりは多く読んでいる心算ですが、こんな変な比喩は聞いた事が有りません。「…と言われる」という表現は、誰がそんな事を言っているのか?と問い返さねばならない無責任なものです。こんなイイ加減な軽口を「報道」という名前の番組で流して良いのか?!垂直とはなんだ?ベルサイユ宮殿よりも「高層」というだけの意味なのか?両者は、建築目的も歴史的な意義も、まったく似ていないし、どうしてポタラ宮殿とベルサイユが重なるのか、不思議な感性を持っている人がいるのですなあ。もしも、古舘さん個人のプロレス流のホラ話ならば、その旨をちゃんと断わって欲しいものです。
※チベット研究の専門家に聞いた所では、どうやら『垂直のベルサイユ』の出どころは、欧州の冒険家か旅行家ではないか?という結論になりました。これは古館さんのオリジナル思いつきではなく、欧州で発表された出典不明の決まり文句として何度か登場しているようです。
■こうして滑り出した「チベット特集」は、NHK特集どころではないトンデもない番組になりそうな、とても嫌な予感がして来ましたぞ!中国の報道バリアが強くて、チベットは報道されないまま、半世紀が経過したのは悲劇でした。それだけに、貴重な報道機会を得られた人は、しっかりと準備と調査をして「間違った事」を知らせないように、慎重な姿勢で取り組んで欲しいのです。「垂直のベルサイユ」などと、フランスなどに話題を持って行かずに、日本人に分かり易く紹介した方が良いでしょうなあ。
■ラサは、「神の土地」を意味するチベット語の地名です。ソンツェン・ガンポという王様がチャイナの地を見下ろす全ての高原地帯を統一して「吐蕃王国」を建てたのが7世紀です。その後、国内の分裂や動乱が続いて、特にインドから入った仏教が過激な密教色を強めてしまって、オウム真理教が宣伝に利用した「呪殺」が流行するような困った時代を過ごします。しかし、15世紀にツォンカパという天才が現われて、密教の暴走を修正して仏教が再興されるのです。この偉人が活躍した時代は、日本の足利義満とぴたりと重なります。このツォンカパの弟子の一人が、ダライラマ一世とされていますが、実際にモンゴルのアルタン汗から「ダライ・ラマ」(大海のような智恵)という称号を授与されたのは第三世でして、それから転生者によって称号と権威が継承されました。
■元々、ラサ中央にあった岩の丘には宗教的な施設が有ったようですが、ダライマラ五世(偉大なる五世)の治世に巨大な居城の建築が始まります。歴代ダライラマは、ツォンカパが創始した「ゲルク派」の僧侶ですから、この居城もゲルク派の教義と歴史を内包して設計されています。因みに、ポタラは観自在菩薩(観音様)が暮らす天界の宮殿の名前です。漢訳仏典では「補陀落」などの当て字が使われますが、日本では「ほだら」と呼ばれまして、東シナ海から紀伊半島、東北地方まで「ほだら」信仰は孤島や山に根付いて広まりました。
■江戸に最も近い所に有った「ほだら」信仰の聖地は、現在の日光です。「日光」は「二荒」の音読みをヒントにして目出度い漢字の組み合わせで書き換えたものです。どちらも「ニッコウ」ですなあ。元の「二荒」は「ふたら」と読んでいました。つまり、「補陀落」の音読みがナマってから字が当てられたというわけですなあ。この日光には徳川家康さんの霊が祭られまして、北側から徳川幕府を攻撃する精力を霊的に防御する場所として、将軍を筆頭に江戸時代から人々の信仰を集めたというわけです。日光は、「猿軍団」よりもチベットのポタラ宮殿と縁の有る場所だとお分かりになったでしょうか?「ベルサイユ」などとトボケた比喩など百害有って一利無し!まったく、無責任な番組ですなあ。
■加藤千洋さんが「6年ぶり」にラサを訪問したというのは重要な意味を持ちます。1999年にラサに行っているという事ですからなあ。その時に、一体この人は何の目的で出掛けて行ったのでしょう?北京支局の仕事を止める前に観光旅行に行ったのでしょうか?多分、この時にチャイナの広い範囲を見て歩いた記録なのでしょう。この人が共著の形で新書を出しています。購入済みですが、他のチャイナ関連の蔵書の中に埋もれておりまして、内容を論評するのは控えます。しかし、購入時に内容を確認した時の印象では、網羅的な価値は有るけれど、貴重な情報は乏しい、そんな記憶が有ります。偶に観るこの「報道ステーション 」でも、毒にも薬にもならない事を、にこにこしながら喋っているようですが、その雰囲気のまま、ふわふわとした書き方だと思って頂ければ間違いは無いでしょう。嗚呼、先は長いですなあ。また、長くなりそうです。
<ahref="http://blog.goo.ne.jp/nammkha0716/e/0d20cfc61a8c3054ddba8027c6c5818f">其の弐に続く