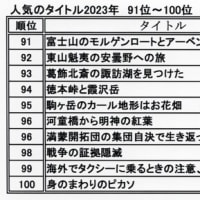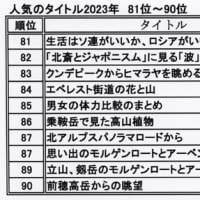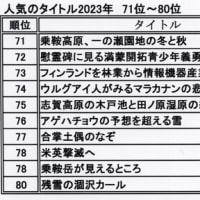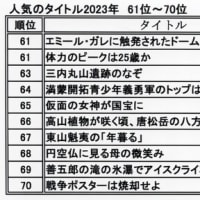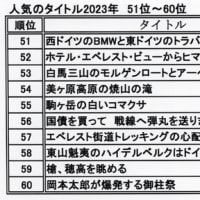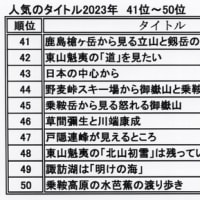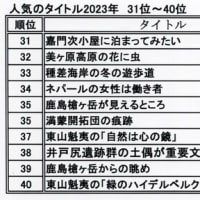諏訪湖に「御神渡り」(おみわたり)ができた。2012年2月5日。

「御神渡り」は、男の神が、女の神に逢いに行く道である。
「御神渡り」は、対岸の下諏訪に向かっている。
多くの人が「御神渡り」を見に来る。
大人も子どもも、遠方からも。
そして、「御神渡り」の「神事」、「拝観式」が行われた。2012年2月6日。

信濃毎日新聞から。
「八剣神社」(やつるぎじんじゃ)の宮司によって、
「御神渡り」の方位が決定され、
「年占い」が行われた。
「世相は厳しい中だが、明るい兆しが見える」
「農作物の作柄は中の上」
「御神渡り」ができるまでは、ヤキモキした。
「御神渡り」は、諏訪の関心事である。
この冬は、寒い。
せっかく寒いのだから?
「御神渡り」ができてほしい。
マイナス10℃は、我慢するから。
「御神渡り」ができれば、4年ぶりになる。
諏訪の気温は、1月29日と1月30日は、マイナス11.3℃。
1月31日は、マイナス9.3℃だった。
これは期待ができる。
諏訪湖は全面結氷していた。2012年1月31日。

下諏訪から、対岸の上諏訪と富士山を眺める。
全面結氷したのだから、
「御神渡り」への期待は、いっそう高まった。
氷はまだ薄い。あとは、雪よ、降るな! もっと、寒くなれ!
雪が降れば、氷が隠れてしまう。
日中の気温が上がれば、氷が融ける。
強風が吹けば、氷が割れて、岸に寄せられてしまう。
2月1日はマイナス8.8℃、2月2日はマイナス8.0℃。
真冬日よ、続いてくれ! 2月3日はマイナス13.9℃。よ~し!

「御神渡り」の卵が、左から右へ走る。もうひといき。
上諏訪から、対岸の下諏訪を眺める。2012年2月3日。
2月4日はマイナス9.1℃。
アジアからのお客さんも、氷上でうれしそうだ。

左から右に走る小さい「御神渡り」をバックに写真。上諏訪沖で、対岸は岡谷。
そして、「御神渡り」ができた。

「御神渡り」は、対岸の下諏訪にある女神、
諏訪大社の下社の方向に走っている。
①は諏訪大社、下社の秋宮。
②は諏訪大社、下社の春宮。
下にかかげた「御神渡り」の図、③から撮影。
「御神渡り」の図。信濃毎日新聞から。

諏訪湖をはさんで、南に諏訪大社、上社の本宮と前宮、
北に諏訪大社、下社の秋宮と春宮がある。
「八剣神社」(やつるぎじんじゃ)は諏訪湖の南、1.5キロにある。
「御神渡り」の神事を行う「八剣神社」によって、
一之御渡り(いちのみわたり)、
二之御渡り(にのみわたり)、
佐久之御渡り(さくのみわたり)、
が認定された。
「御神渡り」の最古の公式記録は、
約610年前の室町時代(1397年)で、
諏訪大社が幕府へ報告している。
「八剣神社」。

「八剣神社」には、「八剣神社御由緒」がある。
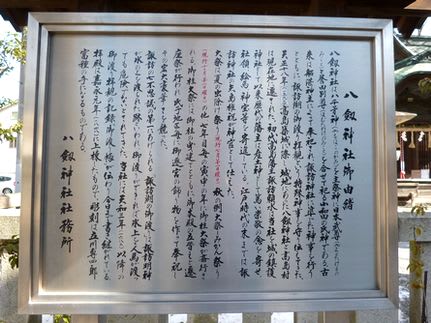
「諏訪湖の御渡(みわた)り拝観という特殊神事を守りつたえてきた」
「御神渡り」(おみわたり)と、広くいわれているが、
「八剣神社」では「御渡り」(みわたり)といっている。
「諏訪の七不思議の第一にあげられる『諏訪湖の御渡り」は、
諏訪明神が氷の上を渡られた跡といわれ、御渡りができれば、
氷上を人馬が渡っても危険でないとされてきた。
当社には天和三年(1683)以降の御渡り拝観の記録、
『御渡り帳』が伝わり、今日まで書き継がれている」
「御渡り帳」の現物は、諏訪市博物館にある。

諏訪市博物館は、「御神渡り」の図でA、
諏訪大社、上社の本宮の前になる。
「御渡帳」は左上。

「御渡り帳」は、1683年から約330年の、
「御神渡り」の神事と、
豊作か凶作かの「年占い」が書かれている。
右の3冊は、「当社神幸記」(とうしゃしんこうき)。
「当社神幸記」は1443年から1681年まで、
240年間の「御渡神事」(みわたりしんじ)が記載されている。
240年間の気候変動がわかる、貴重なものである。
右下に、「当社神幸記」が開いてある。
右のページは、1448年12月9日の「御神渡り」の神事、
左のページは、1449年11月24日の「御神渡り」の神事で、
大祝家(おおほりけ)が、奉行所に報告している。
このときの「御渡神事」は、
諏訪大社、上社の大祝家(おおほりけ)の恒例行事であった。
それに、560年前の、昔は寒かった。
1448年は、12月9日に「御神渡り」ができた。
1449年は、11月24日に「御神渡り」ができた。
年末には、真冬日が続いていたことがわかる。
年末に、それも11月下旬や、12月初旬に、
「御神渡り」ができることは、今では考えられない。
右ページの最後には、その年の「できごと」を、書き加えてある。
「明くる年の4月29日、乱世になり下宮(下社?)が焼失した」
「8月24日、塩尻で合戦があり、数えきれない死者がでた・・・」
なお、「当社神幸記」の開いたページを読まれる方は、
拡大した写真を最後に載せておきました。
「御神渡り」の神事、「年占い」は、
「御渡り帳」の330年の記録を見て占う。
「御神渡り」の神事は、
諏訪大社の上社と気象庁に報告される。
「御神渡り」は氷の膨張によるせり上がり。
諏訪湖沿いに住む人は、「御神渡り」ができるときに、
大音響を聞いたそうだ。昔の「御神渡り」は大きかった。
「御神渡り」の音は、諏訪市博物館へ行けばいい。
アーチをくぐると、

最初に氷にヒビが入る音、
次に、氷がわれはじめる音、
最後は、氷が裂けるときの大きな音がする。
ビシッ、ビシッ、メキッ、ゴゥッー、
怖いような、なんとも、神秘的な音だった。
そして、裂け目に氷が盛り上げってきて、
氷の山脈、「御神渡り」ができる。
「御神渡り」は、諏訪大社、上社の男神が、
諏訪大社、下社の女神に逢いに行く道である。
男神は、建御名方命(タテミナカタノミコト)、
女神は、八坂刀売神(ヤサカトメノカミ)。
「御神渡り」と八ヶ岳。「御神渡り」の図、③から撮影。

対岸は上諏訪。男神、諏訪大社の上社は右奥方向になる。
2012年の「年占い」、
「世相は厳しい中だが、明るい兆しが見える」
「農作物の作柄は中の上」
が、あたってほしい。
「当社神幸記」。

この原文は読めなかった。
左にあった活字体の説明は、どうやら読めた。

「御神渡り」は、男の神が、女の神に逢いに行く道である。
「御神渡り」は、対岸の下諏訪に向かっている。
多くの人が「御神渡り」を見に来る。
大人も子どもも、遠方からも。
そして、「御神渡り」の「神事」、「拝観式」が行われた。2012年2月6日。

信濃毎日新聞から。
「八剣神社」(やつるぎじんじゃ)の宮司によって、
「御神渡り」の方位が決定され、
「年占い」が行われた。
「世相は厳しい中だが、明るい兆しが見える」
「農作物の作柄は中の上」
「御神渡り」ができるまでは、ヤキモキした。
「御神渡り」は、諏訪の関心事である。
この冬は、寒い。
せっかく寒いのだから?
「御神渡り」ができてほしい。
マイナス10℃は、我慢するから。
「御神渡り」ができれば、4年ぶりになる。
諏訪の気温は、1月29日と1月30日は、マイナス11.3℃。
1月31日は、マイナス9.3℃だった。
これは期待ができる。
諏訪湖は全面結氷していた。2012年1月31日。

下諏訪から、対岸の上諏訪と富士山を眺める。
全面結氷したのだから、
「御神渡り」への期待は、いっそう高まった。
氷はまだ薄い。あとは、雪よ、降るな! もっと、寒くなれ!
雪が降れば、氷が隠れてしまう。
日中の気温が上がれば、氷が融ける。
強風が吹けば、氷が割れて、岸に寄せられてしまう。
2月1日はマイナス8.8℃、2月2日はマイナス8.0℃。
真冬日よ、続いてくれ! 2月3日はマイナス13.9℃。よ~し!

「御神渡り」の卵が、左から右へ走る。もうひといき。
上諏訪から、対岸の下諏訪を眺める。2012年2月3日。
2月4日はマイナス9.1℃。
アジアからのお客さんも、氷上でうれしそうだ。

左から右に走る小さい「御神渡り」をバックに写真。上諏訪沖で、対岸は岡谷。
そして、「御神渡り」ができた。

「御神渡り」は、対岸の下諏訪にある女神、
諏訪大社の下社の方向に走っている。
①は諏訪大社、下社の秋宮。
②は諏訪大社、下社の春宮。
下にかかげた「御神渡り」の図、③から撮影。
「御神渡り」の図。信濃毎日新聞から。

諏訪湖をはさんで、南に諏訪大社、上社の本宮と前宮、
北に諏訪大社、下社の秋宮と春宮がある。
「八剣神社」(やつるぎじんじゃ)は諏訪湖の南、1.5キロにある。
「御神渡り」の神事を行う「八剣神社」によって、
一之御渡り(いちのみわたり)、
二之御渡り(にのみわたり)、
佐久之御渡り(さくのみわたり)、
が認定された。
「御神渡り」の最古の公式記録は、
約610年前の室町時代(1397年)で、
諏訪大社が幕府へ報告している。
「八剣神社」。

「八剣神社」には、「八剣神社御由緒」がある。
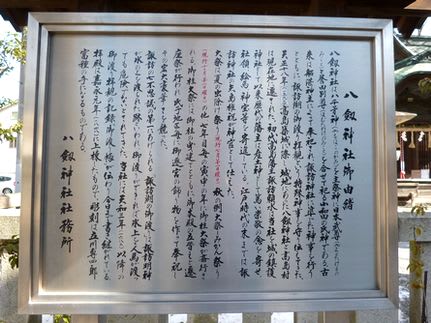
「諏訪湖の御渡(みわた)り拝観という特殊神事を守りつたえてきた」
「御神渡り」(おみわたり)と、広くいわれているが、
「八剣神社」では「御渡り」(みわたり)といっている。
「諏訪の七不思議の第一にあげられる『諏訪湖の御渡り」は、
諏訪明神が氷の上を渡られた跡といわれ、御渡りができれば、
氷上を人馬が渡っても危険でないとされてきた。
当社には天和三年(1683)以降の御渡り拝観の記録、
『御渡り帳』が伝わり、今日まで書き継がれている」
「御渡り帳」の現物は、諏訪市博物館にある。

諏訪市博物館は、「御神渡り」の図でA、
諏訪大社、上社の本宮の前になる。
「御渡帳」は左上。

「御渡り帳」は、1683年から約330年の、
「御神渡り」の神事と、
豊作か凶作かの「年占い」が書かれている。
右の3冊は、「当社神幸記」(とうしゃしんこうき)。
「当社神幸記」は1443年から1681年まで、
240年間の「御渡神事」(みわたりしんじ)が記載されている。
240年間の気候変動がわかる、貴重なものである。
右下に、「当社神幸記」が開いてある。
右のページは、1448年12月9日の「御神渡り」の神事、
左のページは、1449年11月24日の「御神渡り」の神事で、
大祝家(おおほりけ)が、奉行所に報告している。
このときの「御渡神事」は、
諏訪大社、上社の大祝家(おおほりけ)の恒例行事であった。
それに、560年前の、昔は寒かった。
1448年は、12月9日に「御神渡り」ができた。
1449年は、11月24日に「御神渡り」ができた。
年末には、真冬日が続いていたことがわかる。
年末に、それも11月下旬や、12月初旬に、
「御神渡り」ができることは、今では考えられない。
右ページの最後には、その年の「できごと」を、書き加えてある。
「明くる年の4月29日、乱世になり下宮(下社?)が焼失した」
「8月24日、塩尻で合戦があり、数えきれない死者がでた・・・」
なお、「当社神幸記」の開いたページを読まれる方は、
拡大した写真を最後に載せておきました。
「御神渡り」の神事、「年占い」は、
「御渡り帳」の330年の記録を見て占う。
「御神渡り」の神事は、
諏訪大社の上社と気象庁に報告される。
「御神渡り」は氷の膨張によるせり上がり。
諏訪湖沿いに住む人は、「御神渡り」ができるときに、
大音響を聞いたそうだ。昔の「御神渡り」は大きかった。
「御神渡り」の音は、諏訪市博物館へ行けばいい。
アーチをくぐると、

最初に氷にヒビが入る音、
次に、氷がわれはじめる音、
最後は、氷が裂けるときの大きな音がする。
ビシッ、ビシッ、メキッ、ゴゥッー、
怖いような、なんとも、神秘的な音だった。
そして、裂け目に氷が盛り上げってきて、
氷の山脈、「御神渡り」ができる。
「御神渡り」は、諏訪大社、上社の男神が、
諏訪大社、下社の女神に逢いに行く道である。
男神は、建御名方命(タテミナカタノミコト)、
女神は、八坂刀売神(ヤサカトメノカミ)。
「御神渡り」と八ヶ岳。「御神渡り」の図、③から撮影。

対岸は上諏訪。男神、諏訪大社の上社は右奥方向になる。
2012年の「年占い」、
「世相は厳しい中だが、明るい兆しが見える」
「農作物の作柄は中の上」
が、あたってほしい。
「当社神幸記」。

この原文は読めなかった。
左にあった活字体の説明は、どうやら読めた。