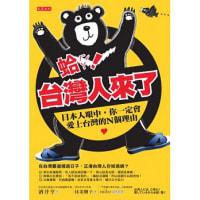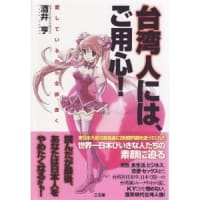最近は、「無米楽」にハマったついでにほかの映画もよく見るようになった。その感想を少し書いておこうと思う。このカテゴリーは、事前の予告で、オペラ座の怪人について書く予定だったが、まあよい。まずは、
キングダム・オブ・ヘブン(Kingdom of Heaven)
中文題名:王者天下
リドリー・スコット監督、オーランド・ブルーム主演で、1087年、十字軍がハッティンでサラディン軍に敗北し、エルサレムが陥落するという史実を踏まえて年代や前後関係は創作を加えて描いた歴史スペクタクル映画。
日本の公式サイトは、http://www.foxjapan.com/movies/kingdomofheaven/。あらすじについては、夢の中のわすれものブログがよい(ただし、年代が100年ずれている。1087年じゃなくて1187年が正しい)。エルサレム王国についてはウィキペディア日本語版はあまり役に立たないので、英語版を参照するとよい。サラーフ・ッディーン(サラディン)については、ウィキペディア日本語もいいが、英語のほうが詳しい。
台湾の友人や2ちゃんねる映画人板での評判は、あまり芳しいものではなかったが、アラブポップスに関するのぶたさんのブログ(http://blog.livedoor.jp/nobuta04/archives/23098026.html#comments)で最新十字軍映画として「やっぱりこれは見にいっておくべきだろう」とされていたので、アラブ関係でもあるから見に行った。5月30日午後7時半から、場所は台北市西門町の絶色。
まあ、映画としては、評判どおり、あまり良い出来だとは思わない。主演のオーランド・ブルームの演技はいちいちだし、シビラ王女は美しいという設定なんだが、エヴァ・グリーンってあんまり美人じゃないし、道具もわりと手抜きが目立った。
ただし、これまで西欧人が作る中東関係、とくに十字軍関係の映画だと、ムスリムやアラブ人側を悪者にするのが多かったのに比べて、この映画では、サラーフッディーンにはハッサン・マスード(シリアの映画スターらしい)を起用、公正で慈悲ある人物として描かれており、アラビア語もふんだんに登場していたし、また、エルサレム王国側でもボードワン4世はムスリムやユダヤ教徒との共存を謳うなど、ムスリムをできるだけ公平、対等に描こうと努力していることはうかがえた。
「ムスリムなどとの共存」のせりふや、主人公の鍛冶屋のバリアンが無意味な流血を避けようと主張するところなどは、ひょっとしたらブッシュ政権によるイラク侵略へのあてつけとも思えるものだった。しかも制作は、イラク侵略を賛美したマードック系の21世紀フォックス。まあ、こういう批判的な作品も流すというのは、商売人というか、英語圏の健全なところというべきであろう。
もっとも、やはり戦闘シーンでは、キリスト教側から見ているため、観客が感情移入するのはどうしてもキリスト教側になりがち。その点ではこの映画を見せられるムスリムはむかつくだろうと思った。まあ基本的に娯楽映画なんだからしょうがないんだが。
私自身、キリスト教を信じていることもあって、キリスト教徒が犯した数々の過ちについては、きちんと検証して反省すべきだと思う。キリスト教会の牧師の中には(米国南部の狂信的福音派だけでなく、理性的な長老派の中でも)、「アラーはヤハウェより劣った神だ」などと平気で言う輩がいて、困る。大体、アラー(アッラーフ)は、ヤハウェと同じ神をあらわすアラビア語形というだけであって、アッラーフとヤハウェは同じなのである。アラビア語のキリスト教聖書では、ヤハウェのことをアッラーフと呼んでいる。そもそも、神に二つあって、上下があるという発想は、それこそ二神教であり、背信者といえる。
しかも十字軍や中南米侵略にいたっては、むしろ当時の文化・文明の完成度という点では、侵略を受けた中東や中南米のほうが完成されていたのであって、そのことを無視して「キリスト教が野蛮な他宗教を救う」式のキリスト教原理主義の発想はおかしい。それこそが博愛を説いたイエスの教えに反している。ましてイスラーム教の側では、キリスト教徒を「啓典の民」、同じ神を信ずるものとしているのだから、キリスト教徒のほうが偏狭だといえるだろう。
それから、個人的な興味をいえば、エルサレム王国が陥落した後、シビラ王女が「わたしはそれでもエデッサ伯国当主で、アンティオキア公国当主で、トリポリ伯国当主だ」みたいなことをいうシーンがあったが(正確には忘れた)、最近マイブーム(死語)になっているレバノンの地名・トリポリ(タラブルス)が出てきたという点で萌えた。
そういえば、2月のレバノン民主化運動で中心的役割果たしたマロン派って、当初は単性論だったのが、今のようにローマカトリックの支配に服したのはこのときなんだよね。ただ典礼だけはもともとの典礼方式を維持したみたいで、だからマロン派の賛美歌はアラビア音楽で、アラビア語やシリア語で歌われる。これについても後日書いてみたい。
そういう意味で、レバノンって古代以来、さまざまな勢力がそこを通り、支配し、戦った歴史の通り道だったんだと。9月には初めて旅行しようと思っている。
キングダム・オブ・ヘブン(Kingdom of Heaven)
中文題名:王者天下
リドリー・スコット監督、オーランド・ブルーム主演で、1087年、十字軍がハッティンでサラディン軍に敗北し、エルサレムが陥落するという史実を踏まえて年代や前後関係は創作を加えて描いた歴史スペクタクル映画。
日本の公式サイトは、http://www.foxjapan.com/movies/kingdomofheaven/。あらすじについては、夢の中のわすれものブログがよい(ただし、年代が100年ずれている。1087年じゃなくて1187年が正しい)。エルサレム王国についてはウィキペディア日本語版はあまり役に立たないので、英語版を参照するとよい。サラーフ・ッディーン(サラディン)については、ウィキペディア日本語もいいが、英語のほうが詳しい。
台湾の友人や2ちゃんねる映画人板での評判は、あまり芳しいものではなかったが、アラブポップスに関するのぶたさんのブログ(http://blog.livedoor.jp/nobuta04/archives/23098026.html#comments)で最新十字軍映画として「やっぱりこれは見にいっておくべきだろう」とされていたので、アラブ関係でもあるから見に行った。5月30日午後7時半から、場所は台北市西門町の絶色。
まあ、映画としては、評判どおり、あまり良い出来だとは思わない。主演のオーランド・ブルームの演技はいちいちだし、シビラ王女は美しいという設定なんだが、エヴァ・グリーンってあんまり美人じゃないし、道具もわりと手抜きが目立った。
ただし、これまで西欧人が作る中東関係、とくに十字軍関係の映画だと、ムスリムやアラブ人側を悪者にするのが多かったのに比べて、この映画では、サラーフッディーンにはハッサン・マスード(シリアの映画スターらしい)を起用、公正で慈悲ある人物として描かれており、アラビア語もふんだんに登場していたし、また、エルサレム王国側でもボードワン4世はムスリムやユダヤ教徒との共存を謳うなど、ムスリムをできるだけ公平、対等に描こうと努力していることはうかがえた。
「ムスリムなどとの共存」のせりふや、主人公の鍛冶屋のバリアンが無意味な流血を避けようと主張するところなどは、ひょっとしたらブッシュ政権によるイラク侵略へのあてつけとも思えるものだった。しかも制作は、イラク侵略を賛美したマードック系の21世紀フォックス。まあ、こういう批判的な作品も流すというのは、商売人というか、英語圏の健全なところというべきであろう。
もっとも、やはり戦闘シーンでは、キリスト教側から見ているため、観客が感情移入するのはどうしてもキリスト教側になりがち。その点ではこの映画を見せられるムスリムはむかつくだろうと思った。まあ基本的に娯楽映画なんだからしょうがないんだが。
私自身、キリスト教を信じていることもあって、キリスト教徒が犯した数々の過ちについては、きちんと検証して反省すべきだと思う。キリスト教会の牧師の中には(米国南部の狂信的福音派だけでなく、理性的な長老派の中でも)、「アラーはヤハウェより劣った神だ」などと平気で言う輩がいて、困る。大体、アラー(アッラーフ)は、ヤハウェと同じ神をあらわすアラビア語形というだけであって、アッラーフとヤハウェは同じなのである。アラビア語のキリスト教聖書では、ヤハウェのことをアッラーフと呼んでいる。そもそも、神に二つあって、上下があるという発想は、それこそ二神教であり、背信者といえる。
しかも十字軍や中南米侵略にいたっては、むしろ当時の文化・文明の完成度という点では、侵略を受けた中東や中南米のほうが完成されていたのであって、そのことを無視して「キリスト教が野蛮な他宗教を救う」式のキリスト教原理主義の発想はおかしい。それこそが博愛を説いたイエスの教えに反している。ましてイスラーム教の側では、キリスト教徒を「啓典の民」、同じ神を信ずるものとしているのだから、キリスト教徒のほうが偏狭だといえるだろう。
それから、個人的な興味をいえば、エルサレム王国が陥落した後、シビラ王女が「わたしはそれでもエデッサ伯国当主で、アンティオキア公国当主で、トリポリ伯国当主だ」みたいなことをいうシーンがあったが(正確には忘れた)、最近マイブーム(死語)になっているレバノンの地名・トリポリ(タラブルス)が出てきたという点で萌えた。
そういえば、2月のレバノン民主化運動で中心的役割果たしたマロン派って、当初は単性論だったのが、今のようにローマカトリックの支配に服したのはこのときなんだよね。ただ典礼だけはもともとの典礼方式を維持したみたいで、だからマロン派の賛美歌はアラビア音楽で、アラビア語やシリア語で歌われる。これについても後日書いてみたい。
そういう意味で、レバノンって古代以来、さまざまな勢力がそこを通り、支配し、戦った歴史の通り道だったんだと。9月には初めて旅行しようと思っている。