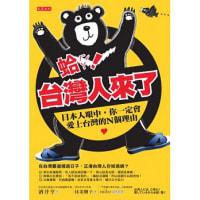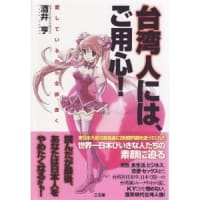台湾語の漫画に関連して、台湾の言語状況とあるべき姿について、ここで改めて私の考えを書いておきたい。
台湾の言語状況に疎く、北京語も満足にできない日本人の中には、台湾語はホーロー人にしかできず、客家語は客家人にしかできないと決め付け、そのため共通語である北京語が必要だという考えている人がいる(たとえば、台中に在住という日本人日本文学研究の教員という川口隆行氏のブログ記事http://ameblo.jp/kawataka/entry-10014146905.html)。
これは、アイヌや琉球やボニンなどの異言語をすりつぶしてきて、外国語も下手な恐怖のモノリンガルである日本人にありがちなトンでもない誤解というべきだろう。
しかし、交通が不便で分類械闘も日常茶飯だった150年前ならいざ知らず族群間の通婚、融合、交流が進んでいる現在の台湾で台湾語がホーロー人しかできないと思い込んでいるとしたら、あまりにも無知というべきだ。
おまけに、この川口氏という人はとんでもないことに、台湾語も客家語も知らないなら憶測で首を突っ込まなければいいものを、
>マイノリティに対する社会(私もそのなかである利益を享受している)の暴力。この暴力の存在を問題化することなしに、「閩南語」を理解できる外労という話をしても、それはつまるところ、「閩南語」を圧倒的な力をもって使用「させる」側(主流のひとたち)を正当化する言説にしかならないし、少数派への暴力の行使を(結果的に)追認してしまうだけである。 国家の論理、そして資本の論理による言語「選択」といったことに対する、「自由」や「抵抗」といったお話も畢竟難しい。
>
などと、台湾語の族群を超えた普及をまるで「暴力」であるかのように書いている始末だ(だったら、北京語はどうなるの?)。無知とはいえ、それこそ暴論である。
その台湾語が北京語唯一主義のせいで、若い世代では下手になっているという事実も無視して、台湾語にどんな暴力があるというのだろう?
暴力というなら、戦前の日本語であり、戦後の北京語である。
しかも「国家の論理」というなら、現在の台湾語も客家語も国家権力によって制度的に保障されたものではない。「資本の論理」というなら、一部中産層に見られる英語への傾きはどうなるのだろうか?
そもそも台湾語が族群を超えて通じるようになったのは、川口氏が憎悪しているような国家や資本の論理ではなくて、それが単純に70%以上の母語だという現実によるものだ。
また台湾の歴史をひもとけばわかることだが、18世紀ごろの時点ではホーロー語(当時はいくつもの変種に分かれていた)と客家語の比率は、2対1だったのが、現在では5対1にまで広がっている。これは別に「資本の論理」などというマルクス主義用語にまみれた大層なものではなくて、単にそれが便利だったからだ。
多数派の母語が全国で通用するのは、スイスのドイツ語もそうだが、自然のことである。それをわざわざ「国家や資本の論理や暴力」などひねくれた見方をするのは、あまりにもイデオロギーにかぶれて現実の生活を観ていない固陋なマルクス主義者の戯言である。
いや、「国家と資本の論理」というならば、圧倒的多数の労働者や農民が日常的に最も使っている言語が台湾語である事実、国家や資本やメディアなど暴力装置が北京語を多用している現実を直視すべきだろう。川口氏が台湾で関係していると見られる大学やメディアは、まさに国家と資本の論理で動いている。そこは台湾語ではなく、北京語ではないのか?
とはいえ、現在の私は北京語を排斥して、無理やり台湾語が取って代わるべきだとは思っていない。
かつてはそう考えていたのは事実だが、人間の思想というのは変わるものである。それはこのブログでもたびたび披瀝している。
現在の私は、台湾語や客家語などの母語もちゃんと保存するべきで、外国人もそれをちゃんと学ぶべきだと思うが、だからといって、もはや北京語が優勢な流れは否定できないし、その北京語も台湾独自の特色を持ったピジン語である以上は、むしろ「台湾ピジン華語」に積極的な意義と役割を認めようと考えている。
しかしながら、頭の固い人が世の中に多いようで、昨年、ある統一派論者が私を名指しで罵倒した文章でも私の思想を歪曲したうえで、以前の主張を固持していると決め付けていたほか、一部でいまでに私のことを「ホーロー主義者」などと誤解している人がいる。
李登輝みたいな変わり方は良くないが、ここ2年くらいの私は「台湾独立」「台湾語の地位向上」「北京語および漢字の廃止の是非」などに関して、180度ではないにしても、かなり大きな思想的変化を遂げている。そんなことは、このブログを観ていればわかることだろう。
つまり、現在の私はすでに「台湾語至上主義者」ではない。いや、そもそも私はホーロー語の公用語化を強く主張していた時期から、すでに客家語もできたし、客家語や原住民族諸語もホーロー語と同様に、国語および公用語にすべきだと主張してきた(ところが、私を「ホーロー・ショービニスト」などと非難する外省人や日本人は、客家語がまったくできないし、ホーロー語もできない輩が多い)。
大体、現在の私は台北で若い世代と話すときは台湾華語を主に使うし、特に女性に対してはそうだ。以前は親友が北京語をしゃべろうものなら、嫌がったものだが、最近は平気である。
というのも、北京語およびそれに関連する言語的、および社会言語的ないくつかの事実に気づいたからだ。
それはまず、北京語の使用が決して台湾主体性意識を阻害していない事実が判明したためである。
確かにかつての私は、将来的には北京語と漢字を廃止して、台湾語や客家語などもローマ字で表記して(もともとローマ字表記の原住民族諸語とともに)国語にするという遠大な理想を抱いていた。それは、台湾における外来政権の日本や国民党がまさに台湾人から母語を奪うことで国家統合を企図してきたこと、またバルト三国などほかの外来政権に支配されてきた地域でも同様の企図があったことを考えて、土着言語の民族言語としての復興こそが独立の基盤になると考えたからであった。
実際、それは私の夢想ではなくて、国民党政権が続いていた1990年代までの台湾の民主化抵抗勢力に共通する心情でもあった。
しかし、2000年に民進党政権になってからは、90年代までの言語と政治意識をめぐる状況は変容を見せてきた。
特に2004年に陳水扁が再選されると、台湾社会における台湾主体性意識、つまり台湾は台湾であって、中国ではないという意識が急速に定着した。それ以前から、若い世代を中心にこうした意識は広まっていたが、04年以降はそれが国民党教育の洗脳を受けてきた中年層にも拡大したことが特色である。
だから、現在台湾社会ではめっきり「われわれ中国人」という言葉は聞かれなくなった。国民党系のメディアですら、「われわれ」という枕詞の後に続くのは「台湾」や「台湾人」になり、国民党系のメディアですら中国をかつてのように「大陸」と呼ぶよりも、「中国」と正しく呼ぶことが増えてきた。
今の台湾では「われわれ中国人」という表現は、違和感を感じられるものになっている。この現象は、明らかに04年の陳水扁再選とその夏のアテネ五輪における金メダル獲得を境に急速に定着したというのが、私の分析だ。
第二に、台湾において現実に使われている北京語は、もはや中国の普通話や国府が押し付けてきた標準国語とは異なり、台湾語などの表現が混入して、さらに語彙表現語法ともきわめて単純化したピジン・クレオールになっているという事実である。
これは、聯合報や学術論文のように標準国語の教育をみっちり受けた外省人やインテリ層が書いた文章しか読んでいない日本の学者には気がつかないことだろう。だから、日本の研究者が書いたものでは「台湾の国語は中国の普通話とは、ほとんど変わらないものである」などと書かれていることが多い。
しかし、それは現実に市井で使われている口頭言語、およびインテリ層とはいえない普通の若者や庶民が書いているような文体、文章語の現実を知らないという無知から来る非科学的な断定である。
言語はインテリ層だけが使うものではない。まして、北京語が若い世代でここまで普及している現在、それが独自の「崩れ方」や発展を見せておらず、従って変化もたいしたものではないと考えているとしたら、それこそ愚かである。
現在の台湾人の書く台湾ピジン華語の表現は、概しておおざっぱで、細かな表現、あるいはどぎつい表現が乏しい。語法や語彙にも台湾語の影響が見られる。昨年聯合報あたりが問題にした学生の「火星文」(記号なども多用した文体)はその究極の姿であるが、しかし聯合報的な「標準国語」に固執していれば「火星文」としかいいようがない文章語や口頭言語が、今の台湾社会の主流なのだ。
そして、実際、台湾ピジン華語を多用している若者や庶民自身が、「中国の北京語とは違う」と認識しているのであり、この認識こそが重要なのである。
同じように、台湾ピジン華語は、なるほど北京語の数ある変種の一つかも知れない。しかし、すでに中国普通話の各地のバリエーションとは通じにくくなっている部分があり、それを「中国とは違う、われわれの言葉だ」と認識している台湾人がいる。
ということは、これはまさしく違う言葉なのである。
そもそも言語が同じか違うかは認識によるものが大きい。
オランダ語は低地ドイツ語の一部を切り取ったものに過ぎないのに、オランダ人自身がそれを「低地ドイツ語とは異なる言語」だと認識しているからこそ、それをオランダ語と呼ぶのである。
逆に日本語は、これは文部省による洗脳の結果でもあるのだが、津軽と薩摩で大きく異なり、意思疎通ができなくても、やはり日本語だと思っている。思わなくてもいいはずなのに、そう思っている。
しかも、第一の事実と第二の事実は同時に並行して発展しているのである。つまり、台湾で北京語が普及したが、それが台湾ピジン華語という独自の発展を遂げており、またその言語を使うことで台湾主体性意識もはぐくまれ、さらにそれが台湾ピジン華語のさらなる独自の発展を促しているのである。
台湾ピジン華語のピジンゆえの簡略化された文体や表現は、まさに普通話との違いを証明している。文体というのも重要な要素である。
ということで、現在の私は台湾の特色あふれた北京語を認め、評価する立場にある。
ただし、北京語が普及したからといって、北京語が歴史的に無理やり強制された言葉であるという史的事実を隠蔽したり糊塗したりするべきではない。しかしだからといって、過去に強制された事実があったとしても、それを排除すべき理由にもまたならない。
それはたとえば、カリブ海諸国などに典型的に見出される英語あるいはフランス語クレオールの状況を考えれば納得できるはずである。
ここでは例として、反植民地論の父フランツ・ファノンの母語であったマルチニーク諸島のフランス語クレオールに沿ってみよう。あれほどフランスに対する反植民地闘争を強く意識していたファノンにとってすら、クレオールは母語であった。
しかしだからといって、マルチニークにおけるクレオールが、フランス帝国主義がフランス語を先住民に強制し、土着言語を消滅させてきた傷跡を示していることは明白な事実である。それが普及しているからといって、強制されていなかったというとしたら、それは歴史の歪曲であり、犯罪である。
だが、そうした歴史は歴史として記憶しておけばいいことであって、それにもかかわらずマルチニークはそのクレオールを母語として使わざるを得ない。
これと同じことが、台湾におけるピジン華語についてもいえる。
台湾においてピジン華語が普及した原因としては、国民党政権が外来政権として台湾人に呼ばれもしないのに侵略してきて、住民がもともと話していなかった北京語を押し付けたためである。
だが、台湾における民主化と民進党への政権交代を経て、台湾において主体性意識、独自性の意識が高まった。それはむしろかつては押し付けられた北京語を通じて行われたものであった。
この時点で、台湾における北京語は、その起源と出自においては外来性と強制が刻印されているものの、民主化と本土化への関与によって、改めて独自性を獲得し、また示すものになったのである。
歴史の刻印は認めなくてはならない。今日、国民党や北京語を盲目的に正当化しようとする日本人や一部台湾人に欠けているのは、歴史の事実を直視することである。
しかし、歴史的な過ちが、現在における過ちだとは限らない。それは歴史的に正しかった植民地主義や慰安婦が、現在において過っていることとパラレルである。
台湾において北京語が強制されてきた歴史的経過は、過ちとして記憶されなければならない。しかし、現実に独自性を担っている道具としてはその効用を活用しなければならない。
ただしここで国民党勢力が誤解してはならないのは、私がここで評価している「北京語」とはあくまでもピジン華語、火星文などに見られる、対岸の中国人には理解しがたい、台湾としての独自性をもった北京語の生活言語としての姿であって、聯合報や保守的勢力が固執する、もはや台湾ではほとんど誰も使いこなせない「標準国語」という虚構の規範言語のことではない。
台湾人によって徹底的に崩された北京語を評価するということなのだ。
その一方で、私自身はもちろん台湾語の響きが大好きである。最近は北京語も多用するようになったが、やはり軽快かつ諧謔さを含み、表現も豊富な台湾語には愛着を持っている。だからこそ台湾語とその他の土着言語の保存も願ってやまない。
現在の趨勢からいえば、20年後には台湾ピジン華語がますます優勢になって、台湾語も少数派になるだろう。しかし、やはり台湾語が消えてしまうには惜しい言語だと思う。だからこそ、自由時報その他の本土派メディアは、台湾語の保存に力を注いでほしいものだ。
台湾の言語状況に疎く、北京語も満足にできない日本人の中には、台湾語はホーロー人にしかできず、客家語は客家人にしかできないと決め付け、そのため共通語である北京語が必要だという考えている人がいる(たとえば、台中に在住という日本人日本文学研究の教員という川口隆行氏のブログ記事http://ameblo.jp/kawataka/entry-10014146905.html)。
これは、アイヌや琉球やボニンなどの異言語をすりつぶしてきて、外国語も下手な恐怖のモノリンガルである日本人にありがちなトンでもない誤解というべきだろう。
しかし、交通が不便で分類械闘も日常茶飯だった150年前ならいざ知らず族群間の通婚、融合、交流が進んでいる現在の台湾で台湾語がホーロー人しかできないと思い込んでいるとしたら、あまりにも無知というべきだ。
おまけに、この川口氏という人はとんでもないことに、台湾語も客家語も知らないなら憶測で首を突っ込まなければいいものを、
>マイノリティに対する社会(私もそのなかである利益を享受している)の暴力。この暴力の存在を問題化することなしに、「閩南語」を理解できる外労という話をしても、それはつまるところ、「閩南語」を圧倒的な力をもって使用「させる」側(主流のひとたち)を正当化する言説にしかならないし、少数派への暴力の行使を(結果的に)追認してしまうだけである。 国家の論理、そして資本の論理による言語「選択」といったことに対する、「自由」や「抵抗」といったお話も畢竟難しい。
>
などと、台湾語の族群を超えた普及をまるで「暴力」であるかのように書いている始末だ(だったら、北京語はどうなるの?)。無知とはいえ、それこそ暴論である。
その台湾語が北京語唯一主義のせいで、若い世代では下手になっているという事実も無視して、台湾語にどんな暴力があるというのだろう?
暴力というなら、戦前の日本語であり、戦後の北京語である。
しかも「国家の論理」というなら、現在の台湾語も客家語も国家権力によって制度的に保障されたものではない。「資本の論理」というなら、一部中産層に見られる英語への傾きはどうなるのだろうか?
そもそも台湾語が族群を超えて通じるようになったのは、川口氏が憎悪しているような国家や資本の論理ではなくて、それが単純に70%以上の母語だという現実によるものだ。
また台湾の歴史をひもとけばわかることだが、18世紀ごろの時点ではホーロー語(当時はいくつもの変種に分かれていた)と客家語の比率は、2対1だったのが、現在では5対1にまで広がっている。これは別に「資本の論理」などというマルクス主義用語にまみれた大層なものではなくて、単にそれが便利だったからだ。
多数派の母語が全国で通用するのは、スイスのドイツ語もそうだが、自然のことである。それをわざわざ「国家や資本の論理や暴力」などひねくれた見方をするのは、あまりにもイデオロギーにかぶれて現実の生活を観ていない固陋なマルクス主義者の戯言である。
いや、「国家と資本の論理」というならば、圧倒的多数の労働者や農民が日常的に最も使っている言語が台湾語である事実、国家や資本やメディアなど暴力装置が北京語を多用している現実を直視すべきだろう。川口氏が台湾で関係していると見られる大学やメディアは、まさに国家と資本の論理で動いている。そこは台湾語ではなく、北京語ではないのか?
とはいえ、現在の私は北京語を排斥して、無理やり台湾語が取って代わるべきだとは思っていない。
かつてはそう考えていたのは事実だが、人間の思想というのは変わるものである。それはこのブログでもたびたび披瀝している。
現在の私は、台湾語や客家語などの母語もちゃんと保存するべきで、外国人もそれをちゃんと学ぶべきだと思うが、だからといって、もはや北京語が優勢な流れは否定できないし、その北京語も台湾独自の特色を持ったピジン語である以上は、むしろ「台湾ピジン華語」に積極的な意義と役割を認めようと考えている。
しかしながら、頭の固い人が世の中に多いようで、昨年、ある統一派論者が私を名指しで罵倒した文章でも私の思想を歪曲したうえで、以前の主張を固持していると決め付けていたほか、一部でいまでに私のことを「ホーロー主義者」などと誤解している人がいる。
李登輝みたいな変わり方は良くないが、ここ2年くらいの私は「台湾独立」「台湾語の地位向上」「北京語および漢字の廃止の是非」などに関して、180度ではないにしても、かなり大きな思想的変化を遂げている。そんなことは、このブログを観ていればわかることだろう。
つまり、現在の私はすでに「台湾語至上主義者」ではない。いや、そもそも私はホーロー語の公用語化を強く主張していた時期から、すでに客家語もできたし、客家語や原住民族諸語もホーロー語と同様に、国語および公用語にすべきだと主張してきた(ところが、私を「ホーロー・ショービニスト」などと非難する外省人や日本人は、客家語がまったくできないし、ホーロー語もできない輩が多い)。
大体、現在の私は台北で若い世代と話すときは台湾華語を主に使うし、特に女性に対してはそうだ。以前は親友が北京語をしゃべろうものなら、嫌がったものだが、最近は平気である。
というのも、北京語およびそれに関連する言語的、および社会言語的ないくつかの事実に気づいたからだ。
それはまず、北京語の使用が決して台湾主体性意識を阻害していない事実が判明したためである。
確かにかつての私は、将来的には北京語と漢字を廃止して、台湾語や客家語などもローマ字で表記して(もともとローマ字表記の原住民族諸語とともに)国語にするという遠大な理想を抱いていた。それは、台湾における外来政権の日本や国民党がまさに台湾人から母語を奪うことで国家統合を企図してきたこと、またバルト三国などほかの外来政権に支配されてきた地域でも同様の企図があったことを考えて、土着言語の民族言語としての復興こそが独立の基盤になると考えたからであった。
実際、それは私の夢想ではなくて、国民党政権が続いていた1990年代までの台湾の民主化抵抗勢力に共通する心情でもあった。
しかし、2000年に民進党政権になってからは、90年代までの言語と政治意識をめぐる状況は変容を見せてきた。
特に2004年に陳水扁が再選されると、台湾社会における台湾主体性意識、つまり台湾は台湾であって、中国ではないという意識が急速に定着した。それ以前から、若い世代を中心にこうした意識は広まっていたが、04年以降はそれが国民党教育の洗脳を受けてきた中年層にも拡大したことが特色である。
だから、現在台湾社会ではめっきり「われわれ中国人」という言葉は聞かれなくなった。国民党系のメディアですら、「われわれ」という枕詞の後に続くのは「台湾」や「台湾人」になり、国民党系のメディアですら中国をかつてのように「大陸」と呼ぶよりも、「中国」と正しく呼ぶことが増えてきた。
今の台湾では「われわれ中国人」という表現は、違和感を感じられるものになっている。この現象は、明らかに04年の陳水扁再選とその夏のアテネ五輪における金メダル獲得を境に急速に定着したというのが、私の分析だ。
第二に、台湾において現実に使われている北京語は、もはや中国の普通話や国府が押し付けてきた標準国語とは異なり、台湾語などの表現が混入して、さらに語彙表現語法ともきわめて単純化したピジン・クレオールになっているという事実である。
これは、聯合報や学術論文のように標準国語の教育をみっちり受けた外省人やインテリ層が書いた文章しか読んでいない日本の学者には気がつかないことだろう。だから、日本の研究者が書いたものでは「台湾の国語は中国の普通話とは、ほとんど変わらないものである」などと書かれていることが多い。
しかし、それは現実に市井で使われている口頭言語、およびインテリ層とはいえない普通の若者や庶民が書いているような文体、文章語の現実を知らないという無知から来る非科学的な断定である。
言語はインテリ層だけが使うものではない。まして、北京語が若い世代でここまで普及している現在、それが独自の「崩れ方」や発展を見せておらず、従って変化もたいしたものではないと考えているとしたら、それこそ愚かである。
現在の台湾人の書く台湾ピジン華語の表現は、概しておおざっぱで、細かな表現、あるいはどぎつい表現が乏しい。語法や語彙にも台湾語の影響が見られる。昨年聯合報あたりが問題にした学生の「火星文」(記号なども多用した文体)はその究極の姿であるが、しかし聯合報的な「標準国語」に固執していれば「火星文」としかいいようがない文章語や口頭言語が、今の台湾社会の主流なのだ。
そして、実際、台湾ピジン華語を多用している若者や庶民自身が、「中国の北京語とは違う」と認識しているのであり、この認識こそが重要なのである。
同じように、台湾ピジン華語は、なるほど北京語の数ある変種の一つかも知れない。しかし、すでに中国普通話の各地のバリエーションとは通じにくくなっている部分があり、それを「中国とは違う、われわれの言葉だ」と認識している台湾人がいる。
ということは、これはまさしく違う言葉なのである。
そもそも言語が同じか違うかは認識によるものが大きい。
オランダ語は低地ドイツ語の一部を切り取ったものに過ぎないのに、オランダ人自身がそれを「低地ドイツ語とは異なる言語」だと認識しているからこそ、それをオランダ語と呼ぶのである。
逆に日本語は、これは文部省による洗脳の結果でもあるのだが、津軽と薩摩で大きく異なり、意思疎通ができなくても、やはり日本語だと思っている。思わなくてもいいはずなのに、そう思っている。
しかも、第一の事実と第二の事実は同時に並行して発展しているのである。つまり、台湾で北京語が普及したが、それが台湾ピジン華語という独自の発展を遂げており、またその言語を使うことで台湾主体性意識もはぐくまれ、さらにそれが台湾ピジン華語のさらなる独自の発展を促しているのである。
台湾ピジン華語のピジンゆえの簡略化された文体や表現は、まさに普通話との違いを証明している。文体というのも重要な要素である。
ということで、現在の私は台湾の特色あふれた北京語を認め、評価する立場にある。
ただし、北京語が普及したからといって、北京語が歴史的に無理やり強制された言葉であるという史的事実を隠蔽したり糊塗したりするべきではない。しかしだからといって、過去に強制された事実があったとしても、それを排除すべき理由にもまたならない。
それはたとえば、カリブ海諸国などに典型的に見出される英語あるいはフランス語クレオールの状況を考えれば納得できるはずである。
ここでは例として、反植民地論の父フランツ・ファノンの母語であったマルチニーク諸島のフランス語クレオールに沿ってみよう。あれほどフランスに対する反植民地闘争を強く意識していたファノンにとってすら、クレオールは母語であった。
しかしだからといって、マルチニークにおけるクレオールが、フランス帝国主義がフランス語を先住民に強制し、土着言語を消滅させてきた傷跡を示していることは明白な事実である。それが普及しているからといって、強制されていなかったというとしたら、それは歴史の歪曲であり、犯罪である。
だが、そうした歴史は歴史として記憶しておけばいいことであって、それにもかかわらずマルチニークはそのクレオールを母語として使わざるを得ない。
これと同じことが、台湾におけるピジン華語についてもいえる。
台湾においてピジン華語が普及した原因としては、国民党政権が外来政権として台湾人に呼ばれもしないのに侵略してきて、住民がもともと話していなかった北京語を押し付けたためである。
だが、台湾における民主化と民進党への政権交代を経て、台湾において主体性意識、独自性の意識が高まった。それはむしろかつては押し付けられた北京語を通じて行われたものであった。
この時点で、台湾における北京語は、その起源と出自においては外来性と強制が刻印されているものの、民主化と本土化への関与によって、改めて独自性を獲得し、また示すものになったのである。
歴史の刻印は認めなくてはならない。今日、国民党や北京語を盲目的に正当化しようとする日本人や一部台湾人に欠けているのは、歴史の事実を直視することである。
しかし、歴史的な過ちが、現在における過ちだとは限らない。それは歴史的に正しかった植民地主義や慰安婦が、現在において過っていることとパラレルである。
台湾において北京語が強制されてきた歴史的経過は、過ちとして記憶されなければならない。しかし、現実に独自性を担っている道具としてはその効用を活用しなければならない。
ただしここで国民党勢力が誤解してはならないのは、私がここで評価している「北京語」とはあくまでもピジン華語、火星文などに見られる、対岸の中国人には理解しがたい、台湾としての独自性をもった北京語の生活言語としての姿であって、聯合報や保守的勢力が固執する、もはや台湾ではほとんど誰も使いこなせない「標準国語」という虚構の規範言語のことではない。
台湾人によって徹底的に崩された北京語を評価するということなのだ。
その一方で、私自身はもちろん台湾語の響きが大好きである。最近は北京語も多用するようになったが、やはり軽快かつ諧謔さを含み、表現も豊富な台湾語には愛着を持っている。だからこそ台湾語とその他の土着言語の保存も願ってやまない。
現在の趨勢からいえば、20年後には台湾ピジン華語がますます優勢になって、台湾語も少数派になるだろう。しかし、やはり台湾語が消えてしまうには惜しい言語だと思う。だからこそ、自由時報その他の本土派メディアは、台湾語の保存に力を注いでほしいものだ。