【生物学の歴史】いったん体細胞に分化した細胞が遺伝子に手を加えないで、簡単な外部刺激だけで胚細胞に逆戻りする(初期化される)、という小保方第1論文の主張は、応用物理学の世界に当てはめれば、
「銅から金ができた」(共に周期律表で同じ列にある)、
「常温超伝導を達成した」
という言明に匹敵するほど、細胞生物学の世界において驚天動地の「大発見」といえる。
事実、論文共著者のひとり笹井氏は「コペルニクス革命」に匹敵すると述べている。
http://www.cdb.riken.jp/en/04_news/articles/pdf/14/140130_stap.pdf
これがどれほど驚異的な発見であるかを理解するには、生物学理論の歴史を駆け足でおさらいする必要がある。
17世紀の後半にロバート・フックが「細胞」を初めて発見し、1839年にシュヴァンが「すべての生物は細胞から成り立つ」という「細胞説」を唱えた。だが、この説では「細胞の起原」は不明であった。ウィーンの病理学者コーンハイムのように、「細胞は血清中の成分が凝集して生じる」と唱える学者もいた。細胞の「自然発生」説である。
パスツールの実験やルドルフ・ウィルヒョウの研究により、細胞が細胞以外のものから自然に発生することは否定された。ウィルヒョウはこれを「すべての細胞は細胞から」という有名な命題に要約している。
一度滅菌し、空気を遮断した容器や真空パックに保管することで、素材や食品の腐敗を防ぐ手法は、この原理を応用したものだ。
他方、生物学・医学におけるもう一つの重要な問題は「獲得形質の遺伝」である。ラマルクは化石の研究から進化が起こったことを証明したが、「進化の原動力」として個体が生後に獲得した形質が遺伝することによる、と主張した。
チャールズ・ダーウィンは探検船ビーグル号に乗ってガラパゴス諸島を訪れ、そこで見つけた小鳥が互いにかけ離れた島毎に違った進化をとげているのを見つけ、環境の淘汰圧による「新種の誕生」を考えた。
細胞の自然発生を否定したウィルヒョウの「細胞病理学」とダーウィンの「種の起源」はともに1859年に出版されている。「自然界における生存競争」の理論はマルクスにより「階級闘争」の理論に歪曲され、マルクス主義に「科学」の装いを施すことになった。マルクスが「資本論」(1867)を出版するにあたり、ダーウィンに献辞を捧げようとして断られた話は有名である。
遺伝的な単位(遺伝子)の存在は、オーストリアのメンデルの実験により(1866)に実証され、単一遺伝子に関して「メンデルの法則」が提唱されている。
「体細胞と生殖細胞は別の細胞で、世代が交代しても生殖細胞のもつ遺伝子は次の世代に受け継がれる。こうして生殖細胞は次の世代につながっている」と「胚細胞の道」(1885)を主張したのがワイズマンで、この時に体細胞と胚細胞が峻別されたのである。
この理論によって、獲得形質はなぜ遺伝せず、進化が「自然選択」によって起こるかが説明できるようになった。
現代のオックスフォード大の動物学者リチャード・ドーキンスは、「胚細胞の道」を「遺伝子の川」と言い換え、生命体40億年の歴史とは絶えざる遺伝子の流れだと指摘し、遺伝子の側から見ると個体は「遺伝子の乗り物」であり、「利己的な遺伝子」は乗り物を変えながら、生き残り次の世代に自分のコピーを増やそうとしている、と主張している。
20世紀になって、忘れられていたメンデルの法則が発見され、遺伝子の座が染色体にあることが明らかにされ、モルガン等の実験によりショウジョウバエの染色体における主な遺伝子の座を示す最初の遺伝子地図が作られた。
その後、遺伝的単位が核酸DNAであることがエイブリィにより発見され、やがてその構造がワトソンとクリック(1953)により解明された。さらに遺伝子から細胞の形質素材(タンパク質)への流れは一方的であり、遺伝子DNAのもつ情報はメッセンジャーRNAに転写され、転移RNAによりリボソームに運ばれ、そこでタンパク質情報に翻訳されるという経路が解明された。こうして、タンパク質が遺伝子DNAを書き換えることはできないという「セントラル・ドグマ」が提唱された。
このドグマの唯一の例外は、レトロウイルスの遺伝子RNAが逆転写酵素を利用して、その遺伝子をDNAに翻訳し、宿主細胞遺伝子の中にもぐり込むという例である。
「獲得形質の遺伝」という問題は、「氏か育ちか」という問題でもある。ダーウィンの理論では「氏」が重要であり、ラマルクの理論では「育ち」が重要となる。
免疫理論においては、免疫細胞が特異抗体を産生する現象をめぐり、「指令説」と「選択説」の論争になった。最初に提唱されたイェルネの「選択説」では、抗原がもつ情報が何らかの方法で、遺伝子DNAに指令を与え、それによって特異抗原に適合する特異抗体が、カギとカギ穴のように、形成されると主張した。
だがこの説では、血中に存在する「自然抗体」中には、自然界に存在しない化学物質に対しても反応する抗体が、あらかじめ存在するという事実が説明できない。
代わって提唱されたのが、バーネットによる「自然選択説」である。この理論によると、抗体産生遺伝子は発生初期に遺伝子の組み換えや体細胞突然変異を起こし、遺伝的な多様性に富む自然抗体を作りだす。しかし体細胞と反応する自己抗体産生クローンは「禁止クローン」として間引かれてしまい、出生時には「自己」と反応する抗体はなくなり、「他者」と反応する抗体産生クローンのみが残っている。そこで「自然界にない抗原と反応する抗体がある」という現象はうまく説明されるようになった。
この説を実験的に証明して、ノーベル賞を授与されたのが利根川進氏である。
卵細胞への体細胞核の移植やiPS細胞のように増殖関連遺伝子の導入を除いて、体細胞の環境を操作して胚細胞を作成する実験には誰も成功していない。というよりも、これまで誰もそれに取り組まなかったといえよう。なぜならそれは生命科学の研究史が確立した医学生物学の常識に反しているからである。
「ストレス」という言葉は、もともとのセリエの学説では、外部のストレッサー(ストレスを与えるもの)が与える変化を生体(主体)が受けとめる状態を意味していた。だが,
今では誤用されてストレッサーの意味で用いられている。
が、主体がストレスと受けとめるかどうかは主体(個体)により異なる。普通の人がムチで打たれたら苦痛だが、マゾヒストはそれを快感と受けとめる。従ってこういうあいまいな用語を科学の論文に用いるのは不適当だ。
「つよい外部ストレッサーが作用すると分化した体細胞が初期化する」という命題は、取りも直さず「セントラル・ドグマ」の否定であり、バーネット=利根川の「クローン選択説」の否定であり、獲得形質の遺伝を否定したダーウィン=ワイズマンの業績の否定である。つまり現代生物学は18世紀末まで逆戻りするということだ。
胚細胞がもつ遺伝子セット(ゲノム)の個々の遺伝子には、1.単に発現がオンになるもの、2.遺伝子組み換えが生じて、別の遺伝子に再構成され、その遺伝子がオンになるものの、2種類がある。後者は私の知るかぎり免疫遺伝子の場合がそうである。
小保方第1論文は、体細胞を初期化できた証拠として、STAP細胞には、分化したT細胞のマーカーである、T細胞状態(TCR)遺伝の再構成が認められる写真を示した。(これは切り貼りの疑いがつよい。)他方で出来上がった「STAP幹細胞」には「調べた8株」で、再構成遺伝子が認められないという。(3/3プロトコル発表)
T細胞遺伝子を再構成した細胞は「クローン拡張」といって、増殖能力をもつ。それが他の体細胞と違う点だ。その場合、同じ免疫遺伝子が受け継がれる。つまり複製しても同じ受容体しか発現しない。こういう幹細胞を胚盤胞に移植してキメラマウスを作ったら、重症の免疫不全を起こすに決まっている。マウスのエイズだ。
このところに基本的疑問を感じたので、メルマガで問題提起したのだが、ネットの誰かは知らないが、問題が受けとめられて、事態を解決する方向に動いたのは何よりだと思う。
「銅から金ができた」(共に周期律表で同じ列にある)、
「常温超伝導を達成した」
という言明に匹敵するほど、細胞生物学の世界において驚天動地の「大発見」といえる。
事実、論文共著者のひとり笹井氏は「コペルニクス革命」に匹敵すると述べている。
http://www.cdb.riken.jp/en/04_news/articles/pdf/14/140130_stap.pdf
これがどれほど驚異的な発見であるかを理解するには、生物学理論の歴史を駆け足でおさらいする必要がある。
17世紀の後半にロバート・フックが「細胞」を初めて発見し、1839年にシュヴァンが「すべての生物は細胞から成り立つ」という「細胞説」を唱えた。だが、この説では「細胞の起原」は不明であった。ウィーンの病理学者コーンハイムのように、「細胞は血清中の成分が凝集して生じる」と唱える学者もいた。細胞の「自然発生」説である。
パスツールの実験やルドルフ・ウィルヒョウの研究により、細胞が細胞以外のものから自然に発生することは否定された。ウィルヒョウはこれを「すべての細胞は細胞から」という有名な命題に要約している。
一度滅菌し、空気を遮断した容器や真空パックに保管することで、素材や食品の腐敗を防ぐ手法は、この原理を応用したものだ。
他方、生物学・医学におけるもう一つの重要な問題は「獲得形質の遺伝」である。ラマルクは化石の研究から進化が起こったことを証明したが、「進化の原動力」として個体が生後に獲得した形質が遺伝することによる、と主張した。
チャールズ・ダーウィンは探検船ビーグル号に乗ってガラパゴス諸島を訪れ、そこで見つけた小鳥が互いにかけ離れた島毎に違った進化をとげているのを見つけ、環境の淘汰圧による「新種の誕生」を考えた。
細胞の自然発生を否定したウィルヒョウの「細胞病理学」とダーウィンの「種の起源」はともに1859年に出版されている。「自然界における生存競争」の理論はマルクスにより「階級闘争」の理論に歪曲され、マルクス主義に「科学」の装いを施すことになった。マルクスが「資本論」(1867)を出版するにあたり、ダーウィンに献辞を捧げようとして断られた話は有名である。
遺伝的な単位(遺伝子)の存在は、オーストリアのメンデルの実験により(1866)に実証され、単一遺伝子に関して「メンデルの法則」が提唱されている。
「体細胞と生殖細胞は別の細胞で、世代が交代しても生殖細胞のもつ遺伝子は次の世代に受け継がれる。こうして生殖細胞は次の世代につながっている」と「胚細胞の道」(1885)を主張したのがワイズマンで、この時に体細胞と胚細胞が峻別されたのである。
この理論によって、獲得形質はなぜ遺伝せず、進化が「自然選択」によって起こるかが説明できるようになった。
現代のオックスフォード大の動物学者リチャード・ドーキンスは、「胚細胞の道」を「遺伝子の川」と言い換え、生命体40億年の歴史とは絶えざる遺伝子の流れだと指摘し、遺伝子の側から見ると個体は「遺伝子の乗り物」であり、「利己的な遺伝子」は乗り物を変えながら、生き残り次の世代に自分のコピーを増やそうとしている、と主張している。
20世紀になって、忘れられていたメンデルの法則が発見され、遺伝子の座が染色体にあることが明らかにされ、モルガン等の実験によりショウジョウバエの染色体における主な遺伝子の座を示す最初の遺伝子地図が作られた。
その後、遺伝的単位が核酸DNAであることがエイブリィにより発見され、やがてその構造がワトソンとクリック(1953)により解明された。さらに遺伝子から細胞の形質素材(タンパク質)への流れは一方的であり、遺伝子DNAのもつ情報はメッセンジャーRNAに転写され、転移RNAによりリボソームに運ばれ、そこでタンパク質情報に翻訳されるという経路が解明された。こうして、タンパク質が遺伝子DNAを書き換えることはできないという「セントラル・ドグマ」が提唱された。
このドグマの唯一の例外は、レトロウイルスの遺伝子RNAが逆転写酵素を利用して、その遺伝子をDNAに翻訳し、宿主細胞遺伝子の中にもぐり込むという例である。
「獲得形質の遺伝」という問題は、「氏か育ちか」という問題でもある。ダーウィンの理論では「氏」が重要であり、ラマルクの理論では「育ち」が重要となる。
免疫理論においては、免疫細胞が特異抗体を産生する現象をめぐり、「指令説」と「選択説」の論争になった。最初に提唱されたイェルネの「選択説」では、抗原がもつ情報が何らかの方法で、遺伝子DNAに指令を与え、それによって特異抗原に適合する特異抗体が、カギとカギ穴のように、形成されると主張した。
だがこの説では、血中に存在する「自然抗体」中には、自然界に存在しない化学物質に対しても反応する抗体が、あらかじめ存在するという事実が説明できない。
代わって提唱されたのが、バーネットによる「自然選択説」である。この理論によると、抗体産生遺伝子は発生初期に遺伝子の組み換えや体細胞突然変異を起こし、遺伝的な多様性に富む自然抗体を作りだす。しかし体細胞と反応する自己抗体産生クローンは「禁止クローン」として間引かれてしまい、出生時には「自己」と反応する抗体はなくなり、「他者」と反応する抗体産生クローンのみが残っている。そこで「自然界にない抗原と反応する抗体がある」という現象はうまく説明されるようになった。
この説を実験的に証明して、ノーベル賞を授与されたのが利根川進氏である。
卵細胞への体細胞核の移植やiPS細胞のように増殖関連遺伝子の導入を除いて、体細胞の環境を操作して胚細胞を作成する実験には誰も成功していない。というよりも、これまで誰もそれに取り組まなかったといえよう。なぜならそれは生命科学の研究史が確立した医学生物学の常識に反しているからである。
「ストレス」という言葉は、もともとのセリエの学説では、外部のストレッサー(ストレスを与えるもの)が与える変化を生体(主体)が受けとめる状態を意味していた。だが,
今では誤用されてストレッサーの意味で用いられている。
が、主体がストレスと受けとめるかどうかは主体(個体)により異なる。普通の人がムチで打たれたら苦痛だが、マゾヒストはそれを快感と受けとめる。従ってこういうあいまいな用語を科学の論文に用いるのは不適当だ。
「つよい外部ストレッサーが作用すると分化した体細胞が初期化する」という命題は、取りも直さず「セントラル・ドグマ」の否定であり、バーネット=利根川の「クローン選択説」の否定であり、獲得形質の遺伝を否定したダーウィン=ワイズマンの業績の否定である。つまり現代生物学は18世紀末まで逆戻りするということだ。
胚細胞がもつ遺伝子セット(ゲノム)の個々の遺伝子には、1.単に発現がオンになるもの、2.遺伝子組み換えが生じて、別の遺伝子に再構成され、その遺伝子がオンになるものの、2種類がある。後者は私の知るかぎり免疫遺伝子の場合がそうである。
小保方第1論文は、体細胞を初期化できた証拠として、STAP細胞には、分化したT細胞のマーカーである、T細胞状態(TCR)遺伝の再構成が認められる写真を示した。(これは切り貼りの疑いがつよい。)他方で出来上がった「STAP幹細胞」には「調べた8株」で、再構成遺伝子が認められないという。(3/3プロトコル発表)
T細胞遺伝子を再構成した細胞は「クローン拡張」といって、増殖能力をもつ。それが他の体細胞と違う点だ。その場合、同じ免疫遺伝子が受け継がれる。つまり複製しても同じ受容体しか発現しない。こういう幹細胞を胚盤胞に移植してキメラマウスを作ったら、重症の免疫不全を起こすに決まっている。マウスのエイズだ。
このところに基本的疑問を感じたので、メルマガで問題提起したのだが、ネットの誰かは知らないが、問題が受けとめられて、事態を解決する方向に動いたのは何よりだと思う。












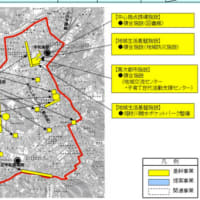
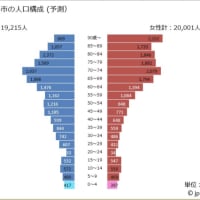



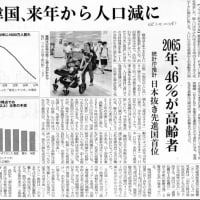










先日の小保方会見は弁護士主導で、科学的問題を法律的問題に摩り替えようとしていましたが、大変不愉快なことでした。茶番劇は止めて欲しいですね!
以前も書きましたが、一部の獲得形質が遺伝することは、現代の生物学ではむしろ常識です。仲野先生の『エピジェネティクス』は索引と参考文献がないので読むのをやめられましたか?
>【書評】小山慶太「科学史人物事典」/難波先生よりのコメント欄
>エピジェネティクスに対する理解が深まった現在では、一部の獲得形質が遺伝する事はほぼ常識となっています。有名な例としては、蝗害を引き起こすトビバッタ(locust)は数世代にわたって生息密度が高い状態が続くと、孤独相から群生相へと相転移して渡りに適した形態に変化しますが、この相変異は世代をまたいで「遺伝」します。