9月22日(日)京都駅7時50分集合 8時06分発に乗車。橿原神宮前に9時16分に到着
最終の人数は10名です。 電動自転車を10名申込みして居たので、丁度10名で良かった。
最初に行ったのは、「剣の池」此処は何時も素通りで、今回は池の前で説明
『日本書紀』には、第15代応神天皇の11年冬10月、軽池、鹿垣(かのかき)池、厩坂(うまやさか)池と共に剣池を造った、とある。
『日本書紀』にはもう一度剣池に関する説話が登場する。皇極天皇3年(644)の6月、すなわち大化改新のちょうど一年前に、剣池で一本の茎から二つの花を咲かせた珍しい蓮が見つかった。当時繁栄の絶頂期にあった蘇我本宗家の蝦夷(えみし)は、「これは、蘇我臣が栄えるという目出度い前兆と勝手に考えて、金泥で蓮の花を描かせ、大法興寺(飛鳥寺)の丈六の仏に献上した。皮肉なものである。それから一年後、蘇我蝦夷・入鹿親子は中大兄皇子や中臣鎌足らが起こしたクーデターによって滅ぼされる運命にあった。net引用
13-3289 み佩かしを 剣の池の 蓮葉に 溜まれる水の 行くへなみ 我がする時に 逢ふべしと 逢ひたる君を な寝ねそと 母聞こせども 我が心 清隅の池の 池の底 我れは忘れじ 直に逢ふまでに。
解説と朗唱
次に行った場所は、輕
柿本朝臣人麻呂妻死之後「泣血哀慟」作歌二首 井短歌
女性の所に、度々も行きかねて、恋焦がれているうちに、訃報を得て、どうにもたまらず、輕の市に来てみると、畝傍山の鳥の声も聞こえず。 女性の姿も全くなく、仕方なしに彼女の名を呼んで袖を振ったという歌。
石川・輕・大輕・見瀬は由緒ある処です。
推古朝では、見瀬・丸山古墳の前方部の整備と。第33代推古天皇の即位宣言をした処とされる伝説も有る。
橿原から~明日香村・野口へ 橘寺と川原寺の間に出て、橘寺は聖徳太子の誕生地と言われる処。
8-1636 大口の 真神の原に 降る雪は 痛くな降りそ 家もあらなくに 舎人娘子
13-3268 「長歌」 三諸の 神奈備山ゆ との曇り 雨は降り来ぬ 天霧らひ 風さへ吹きぬ 大口の 真神の原 ゆ 思ひつつ 帰りにし人 家に至りきや 「思いやり心」
13-3269 「反歌」 帰りにし 人を思ふと ぬばたまの その夜はわれも 眠も寝かねてき 「おもいやり心」
今回は「橘寺」省略して、川原寺に行く
川原寺 『日本書紀』~『続日本紀』 中に10回に及ぶ川原寺の記事がある。 就中、天武紀14条には、川原寺行幸を伝える。川原寺は礎石を残すのみで、古い建造物は残していない。写経を始めたのは川原寺が最初です。 現在は『弘福寺』が跡地に建立され、礎石の保管が有る。
川原寺
次に向かったのは、『伝飛鳥板蓋宮遺跡』は、荒川式井戸を中心に石敷きの遺跡は上層部の『飛鳥浄御原宮跡』そのものとされ、この下の中層・下層に「伝飛鳥板蓋宮跡遺跡」があるとされている。
◆ 飛鳥浄之宮尓御宇天皇代・天渟中原瀛真人・大海人・浄御原天皇・謚:40代天武天皇。
浄之宮讃歌
19-4260 大君は 神にしませば 赤駒の 腹這ふ田居を 都と成しつ 大伴御幸
19-4261 大君は 神にしませば 水鳥の 須抱く水沼を 都と成しつ 作者未詳
尚この西方に池をめぐらせた庭園跡、建物跡も発掘され、プライベートの皇居ともいわれる。
1-51 采女の 袖吹かへす 明日香風 都を遠み いたづらに吹く 志貴皇子
原文の歌碑 その後ろで団体写真。
『伝飛鳥板蓋宮遺跡』 の解説版 木陰で明日香風に吹かれながら説明を聞く
次に「酒船石」に行く
| この石造物は「酒船石さかふねいし」と呼ばれていますが、かなり古いものです。 名前の通り、酒を搾る槽とも、あるいは油や薬を作るための道具ともい われていますが、この石の東約40メートルのやや高いところでここへ 水を引くための土管や石樋が見つかっていることから、庭園の施設だと いう説もあります。(現地の案内板による) 他の説として、 砂金精選、辰砂 ( 銅で着色した鮮紅色の釉うわぐすりのこと) 製造とい った用途説もあります |
net引用
次は『飛鳥寺』
飛鳥寺は588年に百済から仏舎利(遺骨)が献じられたことにより,蘇我馬子が寺院建立を発願し,596年に創建された日本最初の本格的な寺院。
法興寺・元興寺ともよばれた。現在は安居院(あんごいん)と呼ばれている。
創建時の飛鳥寺は,塔を中心に東・西・北の三方に金堂を配し,その外側に回廊をめぐらした伽藍配置だった。 寺域は東西約200m,南北約300mあった。百済から多くの技術者がよばれ,瓦の製作をはじめ,仏堂や塔の建設に関わった。瓦を製作した集団は,この後豊浦寺や斑鳩寺の造営にも関わっていく。さらに,これらの技術を身につけた人たちやその弟子たちが全国に広がり,各地の寺院造営に関わるようになる。
6-992 故郷の 明日香はあれど あをによし 奈良の明日香を 見らくし良しも 大伴坂上郎女
飛鳥寺 金堂
飛鳥大仏
年代のわかる現存の仏像では日本最古のものと言われている。
金銅仏の釈迦如来像(飛鳥大仏)は推古天皇が止利仏師(とりぶっし-鞍作鳥・鞍作止利 くらつくりのとりともよばれるように,もともとは馬具製作に携わっていた百済からの渡来系氏族の一人)に造らせた丈六(約4.85m)仏。605年に造り始め,606年に完成した。
しかし,887年と1196年の落雷のため火災に遭い本堂が焼失したが江戸時代に再建された。飛鳥大仏も補修されたが,顔の一部,左耳,右手の中央の指3本だけが当時のまま残っている。法隆寺金堂の国宝釈迦三尊像とよく似ている。net引用
左側 聖徳太子 右側 阿弥陀如来坐像
三体の水かけ地蔵が有る。 飛鳥大仏を後にして~
「国立飛鳥資料館」に行く。
「国立飛鳥資料館」 二面石
石像物 橋の上から写す
主な展示品
新羅土器・施釉陶器 飛鳥・藤原京出土
山田道 敷葉遺構 石神遺跡出土
壬申乱模型
富本銭 飛鳥池遺跡出土
各地の土器・瓦 飛鳥・藤原京出土
荷札木簡 飛鳥・藤原京出土
金属製人形・木製人形・斎串・土馬 飛鳥・藤原京出土
他
明日香風が心地よく、爽やかな日でした。 皆さまお疲れ様でした。






































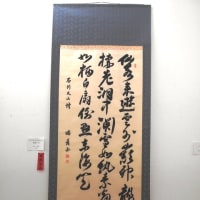
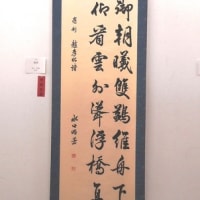
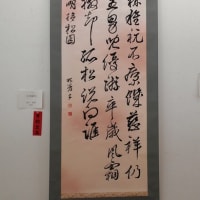





日本書紀も全部は無理でも部分的にピックアップすると面白く読めそうですね。
爽やかな秋空の下、電動自転車でスイスイと快適だったことでしょう。
引率お疲れ様でした~
今回は、長い文章になったから、スルーして下さいと書くつもりが、書けおえたら、疲れて忘れてました。
日中は、日差しがきつかったが、日陰に入ると、爽やか心地よい風が吹いて気持ち良かったわ~
有難う~疲れがなかなか取れないです。歳ですね・・・
飛鳥寺は去年行ったなぁ~。
明日香村とかサイクリングしたわ
大仏を説明するおじさんが面白かったよ。
サイクリングに良い季節になりましたね
明日香村もサイクリングしたんだね。
明日香風が爽やかで良い気持ちだったでしょ~