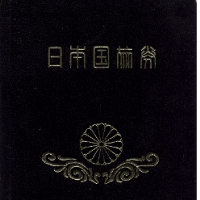「原田神社の秋祭り」の紹介で、 何やら由緒正しい神社と言う事ですが、詳しい事は知りませんねん。
「原田神社の秋祭り」の紹介で、 何やら由緒正しい神社と言う事ですが、詳しい事は知りませんねん。
と書いたら「オイオイ、あれは無いやろ、せめて、もうチョット由来でも書いたらどないや?」と同窓生に言われましてん。
ヘッ?何で知ってるんやろ?一言もサイトについては喋った覚えが無い。
実際、誰が見てるか判りませんなぁ!気付けよ・・。
と言う事で、少々補足を。
とは言っても、神社の由来なんてのは大して面白い事も無し、第一どこまでがホンマやら神話やら判らん。
社務所で由来書を買うたら、逐一書いてある。
そんなもんを、今更ここでグタグタ書きとうもない。
といいつつグダグダ要らん事を書いてますなぁ。
郷土史を趣味にしてはる方も大勢いてはることやし、門外漢が、書いたところで中途半端、それやったら、いっそ思いっ切り簡単に、受け売りの歴史などを。
天武天皇の頃に創建されたと言うてるけれど、これは証拠も何も無し。
主祭神はスサノオノミコト、例によってその他一杯言うてたけど、くだくだしいから略。
延喜式には載ってないいうねんから、その程度のお宮さん。(ゴメン)
東は現在の吹田市江坂から、西は尼崎市富松までの、70以上の村々の産土神で、西牧総社(にしのまきそうじゃ)と呼ばれてたらしいです。
これはすごい広い地域でっせ!
西牧(にしのまき)は元々馬を飼うてた皇室直轄の牧場で、後、奈良の春日大社の紳領やったとも聞いてます。
祗園社、牛頭天王社とも呼ばれてたそうです。
足利三代将軍が崇敬し原田六車荘(大阪空港南東地域)を紳領として寄進されたそうな。
所が、荒木村重の兵火で社殿、文書、宝物全て丸焼け。
どうやら、荒木村重は、この辺を焼け野原にしてしもたらしい。
天正九年(1581年)に再建。
貞享五年(1688年)「原田大明神」の神号を京都の吉田家(何者?)から贈られて原田神社になったそうですわ。 東正面の大鳥居は貞享五年(1688年)建立。
東正面の大鳥居は貞享五年(1688年)建立。
鳥居そのものは、珍しい事もなんとも無いけど、注文時の文書、寸法図面から運賃、村、町の費用の割前など書類一式がほぼ完全に残ってるんやそうです。
それが珍しいんやて。なんじゃいな。
氏子は慶安五年(1652年)22ヶ村、貞享五年(1688年)8ヶ村と減少、幕末には現在の7ヶ村になってたらしいですね。
境内からは銅鐸も出てきて、これは現物も記録も残ってます。
1000年以上の歴史をこない簡単にすましてエエんかいな?
改めて見直すと、地元密着、マイナーな神社ですねぇ。
伊勢神宮を頂点とする神社本庁の傘下ではなく、いうたら独立系。
社殿の前は一寸した運動場ぐらいの広さが、何~にもなしの広場。
さすがに球技はアカンけど、それ以外はどんな遊びもお咎め無し。
毎月一日(ついたち)には、境内に市が立ちます。
雑貨、瀬戸物、衣料、日用品、骨董とも呼べん古道具、中古品等々、ものの見事に安物揃い。
初めて見た人は「まるで戦後の闇市やんか!」とビックリするようです。
私等はごく普通の光景やと思ってますけどねぇ。
お祭りと正月、成人式、七五三、一日市(ついたちいち)以外は人出はほとんど無し。
たまに「お宮参り」を見かけるくらいで、日当たりがエエから、ジイサン、バアサンの日向ぼっこスポットと、子供の格好の自転車練習場。
子供時代は、紙芝居を石灯籠に駆け上って、ただ見してましたねぇ。
普段ののどかなたたずまいといい、通勤、通学、買い物客が境内を行き来する気安さがよろしいなぁ。
初夏から盛夏には20:00頃から、セミの幼虫が大挙して出現、脱皮しようと玉垣に鈴なりによじ登ってます。
東南アジアの某国やったら、一網打尽に捕まえて、カリッと空揚げ。
塩トンガラシで味付けて、屋台で売れるねんけどね。
エビセンみたいな味して美味しいねんけど、日本では誰も買わんわなぁ・・。
「オ~オ~、今年もセミが出て来る季節になったか」と、夏にセミが出てくるのんは当たり前やと思てたら、「商店街の直ぐ横で、あんなんが見られるとは、スゴイ!」と言う人が居てました。
感心してるのかバカにしてるのか?
今時の有名神社に良くある、商売気丸出しの、ガッついたところが無いのが好き。
もっとも商売気出しても、売り物が無いわなぁ。(これがイカンねんなぁ・・。)
駅の真東隣にあるから、神社の森がホームからよう見えますねん。
西には大石塚小石塚の古墳の森がドカーンと見えます。
「岡町は緑が多いねぇ」と誉めてもらえるのが嬉しいですね。
2002/11/05