
●写真①:「正月三が日」の参拝客が約100万人と、九州では太宰府天満宮に次いで多い宮地嶽神社=福津市宮司の同神社本殿前で、2006年1月1日午後4時57分撮影
・琢二と清の郷土史談義
『津屋崎学』
第7回:2006.10.07
「宮地嶽神社」はどんな社(やしろ)なのか
清 「福津市宮司の宮地嶽神社秋季大祭、宮地放生会は、9月23日で3日間の秋祭りが終わったばってん、今年はいつもと感じが違っとったね。例年、祭りの呼び物で女性人気歌手が務める〝祭王〟や神輿が練り歩く御神幸行列は、21日の祭り初日に宮地浜のお旅所まで「お下り」しとったのを、今年は23日にお旅所から神社に戻る「お上り」の御神幸行列=写真②:9月23日午後1時07分撮影=にと趣向が変わった。21日夜は、初の試みという〈ねがいかなえ開運花火大会〉が宮地浜で催されたもんね」
琢二 「多くの人出が期待できる休日に焦点を当てた模様替えのようだが、伝統や慣習は時代によって少しずつ変わっていくとはいえ、あんまり感心せんな」
清 「津屋崎の氏神様の波折神社の祭神は、このあいだ叔父さんから聞いたばってん、だいたい宮地嶽神社ちゃ、どんなお社やろか。商売繁盛の神様で、日本一の大注連縄、大鈴、大太鼓の三つがあるとは、よう知っとうけど……」
琢二 「主祭神の神功(じんぐう)皇后と、勝村大神(かつむらおおかみ)、勝頼大神(かつよりおおかみ)の三柱を祀ってある。神社では、口碑社伝等によると1600年前、皇后が新羅遠征で渡韓の折、宮地嶽の山上に天神地祇を遥拝する祠(ほこら)を建て、勝運と航海の安全を祈願し、帰還後に神社を創建されたという。つまり皇后と、この祠の祀りを命じられた従神・勝村大神、勝頼大神と合わせ〝宮地嶽三柱大神〟と崇め祀っているということたい。勝村大神は藤之高麿、勝頼大神は藤之助麿という名だ。宮地嶽神社は、商売繁盛、家内安全、交通安全の守り神として西日本一円の信仰を集め、年間200万人の参拝者がある。本殿に架けられた大注連縄は長さ13.5㍍、直径2.5㍍、重さ5㌧。これに、直径2.2㍍、重さ450㌔・㌘の大鈴と、直径2.2㍍、重さ1㌧の牛の一枚皮で作られた大太鼓を加えて日本一のトリオと神社の自慢だ」
写真②:宮地浜のお旅所から神社に戻る「お上り」の御神幸行列
清 「神功皇后は、福津市在自の金刀比羅神社にも祀ってあったね」
琢二 「宮地嶽神社本殿裏の神社境内には、直径約34㍍の円墳『宮地嶽古墳』=写真③:05年8月12日午後4時撮影=がある。7世紀前半に造られたと見られ、『大塚古墳』とも呼ばれている。墳丘内部に高さ、幅各約5㍍の巨石を積み重ねて造られた全長23㍍、最大幅2.8㍍、天井までの高さ最大3.1㍍という全国で2番目に長い大規模な横穴式石室を持つ。この横穴式石室古墳は、土中に封じ込めた石造りの家のような墓だな。7世紀の初めに大和朝廷を牛耳った豪族、蘇我馬子の墓とされる、奈良県明日香村の〈石舞台古墳〉の石壁よりはるかに長大で、大岩屋といえる。〈石舞台古墳〉は、横穴式石室古墳の上の盛り土が流失して石室だけがむき出しになったものだ。
それから、宮地嶽古墳の素晴らしさは、石室の大きさだけでなく、出土品も逸品ぞろいということだ。天子のシンボルとされる竜文を透かし彫りした金銅製の王冠をはじめ、唐草文のある鞍金具やあぶみなどの馬具、束頭が塊状で刀身の長さが2.6㍍もあるという国内最大級の祭祀用の金銅装頭椎大刀(こんどうそうかぶつちのたち)、深緑に澄み渡った瑠璃玉、古代様式の骨臓器の銅壺など副葬品約300点が発見され、うち大刀など約20点は国宝に指定されており、副葬品の豪華さから"地下の正倉院〟とも呼ばれている。被葬者は、古代の宗像の豪族で、娘を天武天皇の后とした『胸形君徳善(むなかたのきみとくぜん)』と考えられている。巨石古墳発掘を機に、古墳内部に不動明王を祀る『奥の宮不動神社』を鎮座し、今は石室内部へ立ち入りできず、入り口で礼拝する信者も多い」
写真③:「宮地嶽古墳」の日本最大級の横穴式石室入り口
清 「胸形君というのは、聞いたことがある。金銅装頭椎大刀というのは、えらい大きな刀やね」
琢二 「胸形君は、津屋崎を含む宗像地方に勢力を持ち、当時の海上交通を担うとともに、〝海の正倉院〟と言われる宗像市・沖ノ島の祭事に深く係わった氏族だな。徳善の娘は尼子娘(あまこのいらつめ)といい、天武天皇の第一皇子・高市皇子(たけちのみこ)を産んだ。高市皇子は、672年に起きた壬申の乱での英雄とされ、のちに太政大臣になり、持統10年に亡くなった。『万葉集 巻ニ』には、柿本人麻呂が前線で指揮する皇子の英姿を讃えて詠んだ挽歌が載っているよ。宮地嶽古墳から出土した骨臓器の銅壺は、奈良で火葬した尼子娘の遺骨を実家の墓に納めたものと見られる。宮地嶽古墳は、2005年に国史跡に指定された『津屋崎古墳群』40基のうち、南端付近にある。国宝・金銅装頭椎大刀の復元品=写真④:03年8月22日午前9時30分撮影=は、福津市津屋崎庁舎と宮地嶽神社にある。津屋崎には、こんなすごい大刀を持つ一族が住んでいたのかと感動するぞ。いっぺん見といたがいい」
写真④:国宝「金銅装頭椎大刀」の復元品(福津市津屋崎庁舎1階で=2012年11月14日現在ではJR福間駅2階の市行政・観光情報ステーションに貸出中です)
清 「はい、分かりました。それにしても、宮地嶽古墳は、宮地嶽自然歩道の入り口の小高い所にあるけど、あんな大きな石がよう持ち運べたよね」
琢二 「いいところに気づいたな。あんな大きな原石は宮地嶽神社近くにはない。5㌔も離れた津屋崎・恋の浦海岸にあるのを船で運んだと考えられているが、宮地嶽古墳の高台まで運び上げるのは大変な労力と技術が要っただろう。巨石を構築しての古墳築造に加えて、数多い国宝を含む豪華な副葬品からみて、相当権威のある豪族が津屋崎を支配していたことを示している。こうした偉大な先祖がいて、古代から栄えていたことは津屋崎の誇りだ」










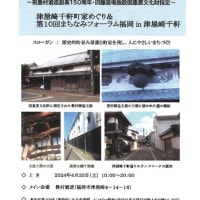






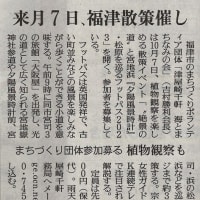








唐津街道・手光道・津屋崎道の3本を、中世河津氏はどのように管理したんだろうと、亀山城のあたりをボーッと歩いていたときのこと。亀山神社裏手麓に、代々の河津氏が奉じた禁裏屋敷跡の貴人の墓、と書かれた墓石群を発見。300メートル北東から移築の由。中世武将の墓でも、50センチくらいの五輪塔がせいぜいなのに、1メートルを越す玄武岩の自然石が6~7基あったと思います。
「きんり」と聞いて徳善しか発想できない場所で、私はモチロン、300メートル北東に胸肩一族の住居があった!と早合点したのでした。
墓石群全体で、河津に関わる古墳の内郭とか氏神かもしれません。が、サイズ・形態が墓石に相応しいこと、あえて禁裏という言葉を遺していることが優先するように思えます。素人は、徳善さんのオウチだ!と早合点すべきでしょう。
杷木町の斉明陵が築かれた時代まで、九州王朝を確信して、イヤ、妄信したい心情なのですが、次の壬申の乱について、大津町瀬田でないと、事跡が符合しないとする熊本人もいらっしゃる。でしょデショ~?!武装して瀬田の唐橋なんか走れないもん。日本人が橋梁構造を知らない時代で、浮橋、つまりデカい飛び石しかなかった時代に、カラハシは無いですよ。などと、贔屓の引き倒しの昨今です。
ところで、福間駅南方ウカミ神社は、海が入り込み浮かんで見えたのでしょうか。普通にウカ・ミタマ神社なのでしょうか。