きのうはエイプリルフール。
円谷プロの特設サイトを楽しみにしていたのに、サーバーが重すぎてほとんど見られなかったのが悲しい。メトロン星人の陰謀に違いない。
それはともかく、「エイプリルフールネタだったらよかったのにね」という残念な記事がこれ。
特集:生かせ!知財ビジネス/逆説理論で“開発” 宙に浮く飛行艇 - FujiSankei Business i./Bloomberg GLOBAL FINANCE
はてなブックマーク - 特集:生かせ!知財ビジネス/逆説理論で“開発” 宙に浮く飛行艇 - FujiSankei Business i./Bloomberg GLOBAL FINANCE
まあそのなんというか。
逆説の航空理論って何なのか、鈴木政彦氏がどういうお方なのか、グローバルエナジーがどんな会社なのか、まったく存じませんけれど(面倒なので調べてない)、「機体が大きくなるほど空気をつかめ、安定して飛べるはず」ということだけは絶対にありえない。
それこそ「水からの伝言」レベルのナンセンスである。締めの名セリフがトンデモだから記事すべてが胡散臭くなり「エイプリルフールネタじゃないのかこれ」と思ってしまう。いや、本当にエイプリルフールのネタ記事ならよかったのに。
なぜ「機体が大きくなるほど空気をつかめ、安定して飛べるはず」ということが絶対にありえないのか。
「逆説の航空理論」が何なのはともかく、空気を利用し地球の重力に逆らって飛び上がるのには違いない。であれば、未来永劫いつまでも絶対確実に「2乗3乗の法則」からは逃れられない。
「2乗3乗の法則」とは何か。名前はいかめしいけれど、小学生でもわかる簡単なことだ。
よく飛ぶ模型飛行機ができたので、設計図を10倍に拡大して自分が乗れる実機を作ろうとする。
そのとき胴体の長さと幅、そして翼の長さと幅も10倍になる。当然、平面図つまり翼の面積は10×10=100倍になる。
ところが、三次元の物体の本当の大きさは「体積」であり、高さ方向の係数がかかる。これも10倍だから10×10×10=1000倍だ。
結果として「翼面積は100倍、体積(=重量)は1000倍」の鈍重なシロモノができあがり、これではまともに飛べない。
飛行機はムクの塊じゃないから体積そのまま重量が増えるわけではないけれど、それにしても「巨大化すれば重量がかさみ、相対的に翼面積が減少して飛ばすのが難しくなる」のは避けられない。これこそが飛行機の発明以来たくさんの技術者を悩ませてきた「2乗3乗の法則」だ。
さらに追い討ちをかけると、エンジン(推力)にも2乗3乗の法則が効いてくる。
プロペラやジェットエンジンの推力を決めるのは前方投影面積だ。要するにたくさんの空気をつかまえて後ろに押し出せば強い力が出る。だからといってそのまま大きさを倍にすると、前方投影面積は4倍なのに体積は8倍となり、推力重量比が低下してしまう。まったく困ったものだ。
要するに、空を飛ぶものは小さければ小さいほど楽であり、大きければたいへん苦労するのだ。
チョウはお気楽にふわふわ空気の中を漂っているけれど、ジェット旅客機は何キロも必死に滑走路を走らないと飛び立てない。これこそが冷厳な物理学(2乗3乗の法則)に支配される航空機の姿だ。
「ベルシオン飛行艇」の理屈は知らないけれど、実験映像を見る限り「驚異の飛行艇」は長さ1メートル程度の小さいものだ。チョウやハエがホバリングしても誰も驚かないように、この大きさの模型飛行機がホバリングするのは簡単だ。極論すれば、ちょっと強力なエンジンがあれば機体の設計など大して影響がない。
鈴木氏の言うように「機体が大きくなるほど空気をつかめ、安定して飛べる」実機が軽やかに飛んでみせたら私も大いに感心するが、革命的に強力なエンジン(ミノフスキー融合炉とかS2機関とかシズマドライブ)ができない限り絶対無理だ。
先日の毎日新聞のフリーエネルギー記事(幻影随想: 毎日新聞がフリーエネルギー詐欺に引っ掛かっている件について)もそうだけれど、大手マスコミの記者でも科学部以外はびっくりするほど科学的常識が抜けている。私のようなド素人でも「えーと、ネタだよねこれ? …違うの?」と呆れてしまうくらいだ。
しっかりしてくださいよまったく。
円谷プロの特設サイトを楽しみにしていたのに、サーバーが重すぎてほとんど見られなかったのが悲しい。メトロン星人の陰謀に違いない。
それはともかく、「エイプリルフールネタだったらよかったのにね」という残念な記事がこれ。
特集:生かせ!知財ビジネス/逆説理論で“開発” 宙に浮く飛行艇 - FujiSankei Business i./Bloomberg GLOBAL FINANCE
世界が栃木県の片田舎で生まれた発明に大きな注目を寄せ始めた。驚異の飛行艇が現れた。
その飛行艇は両翼がない。魚のマグロが3本寝たような形状である。ほとんど滑走することなく垂直に近い角度で上昇し、180度旋回や横転を瞬時にこなす。圧巻は、空中停止。そのままゆっくり下降して着陸できるが、上昇や直進を再開することもできる。まるで水中を泳ぐ魚のように自由自在。見た者誰もがUFOの実在を信用するようになる。
≪全く新しい航空理論≫
飛行艇の名は「ベルシオン飛行艇」だ。栃木県に研究施設を持つベンチャー、グローバルエナジーが開発した。
視察に訪れた航空理論のある専門家は目の前で見ていながら信用せず「どういうトリックを使っているのか」と声を荒げた。
通常の航空理論は機体に備わった両翼の上下間で、機体が直進滑走する際に発生する気圧差により揚力を発生させ、空中へ舞い上がる方式であるからだ。直進速度が落ち揚力が減少すると失速して墜落する。だが眼前の機体は空中停止し、両翼がないのだ。
開発者の鈴木政彦会長は「空気をつかむ、という新しい考え方で飛んでいる。正統な航空理論を学んできた方は自己否定になるため信じないが」と笑う。
“空気をつかむ”とは、両サイドの胴体で空気を逃がさないように空気抵抗を作り“抵抗の反作用で浮く”ことだという。例えば、水泳は水をつかんで後方へ押しやる時の反作用で体を前へ進める。空気中も同じ。空中停止はさながら立ち泳ぎだ。
同社は実は、回転時に発生する負のトルクがなく、微風時から回転し騒音もない「ベルシオン式風車」で知名度を上げつつある。現在、関連のベルシオンパワー(杉崎健COO)が事業化を進めており、大手コンビニが環境対策の一環で広島県呉市内の店舗で導入テストを始めている。ゆくゆくは各店舗の使用電力を風力発電で補う構想だ。
≪外国企業が殺到中≫
鈴木氏は「最初開発したのはベルシオン式風車の方。従来の風車理論とは逆説の位置にあり、学界から批判された。従来の風車は航空理論から生まれたもの。つまりベルシオン式風車の力学を証明するには、飛行艇の開発が必要だった。逆説の正しさを証明したかったのだ」と語る。
飛行艇の情報はやがて口コミで伝わり、各国から視察や交渉申し込みが現在、殺到している。米、独、印、中、東南アジアや中東諸国の企業や研究所、政府関係者だ。「知的財産権交渉が中心となるので、各国で知的財産権を確立しておくことが課題。世界で500件以上を出願する予定で、著名な米国知財弁護士であるヘンリー幸田先生と相談し、戦略的に進めている」とする。
一方、国内組の出足は遅い。鈴木氏は「権威も実績もないベンチャーが日本で認めてもらうには、海外で認めてもらうことから始めなくてはいけないことが分かった。残念なことだが仕方ない」と、ため息をもらす。
「今夏、人が乗れるグラスファイバーかカーボン製の長さ5、6メートルの実機を作成し試験を許可してくれるどこかの湖上で飛ばしたい」と鈴木氏。最初に乗って飛行するのは「もちろん自分だ。機体が大きくなるほど空気をつかめ、安定して飛べるはず」と少しも恐れていない。
歴史上の大発明家と変わらぬ、旺盛な開拓者精神がそこにはある。(知財情報&戦略システム 中岡浩)
はてなブックマーク - 特集:生かせ!知財ビジネス/逆説理論で“開発” 宙に浮く飛行艇 - FujiSankei Business i./Bloomberg GLOBAL FINANCE
まあそのなんというか。
逆説の航空理論って何なのか、鈴木政彦氏がどういうお方なのか、グローバルエナジーがどんな会社なのか、まったく存じませんけれど(面倒なので調べてない)、「機体が大きくなるほど空気をつかめ、安定して飛べるはず」ということだけは絶対にありえない。
それこそ「水からの伝言」レベルのナンセンスである。締めの名セリフがトンデモだから記事すべてが胡散臭くなり「エイプリルフールネタじゃないのかこれ」と思ってしまう。いや、本当にエイプリルフールのネタ記事ならよかったのに。
なぜ「機体が大きくなるほど空気をつかめ、安定して飛べるはず」ということが絶対にありえないのか。
「逆説の航空理論」が何なのはともかく、空気を利用し地球の重力に逆らって飛び上がるのには違いない。であれば、未来永劫いつまでも絶対確実に「2乗3乗の法則」からは逃れられない。
「2乗3乗の法則」とは何か。名前はいかめしいけれど、小学生でもわかる簡単なことだ。
よく飛ぶ模型飛行機ができたので、設計図を10倍に拡大して自分が乗れる実機を作ろうとする。
そのとき胴体の長さと幅、そして翼の長さと幅も10倍になる。当然、平面図つまり翼の面積は10×10=100倍になる。
ところが、三次元の物体の本当の大きさは「体積」であり、高さ方向の係数がかかる。これも10倍だから10×10×10=1000倍だ。
結果として「翼面積は100倍、体積(=重量)は1000倍」の鈍重なシロモノができあがり、これではまともに飛べない。
飛行機はムクの塊じゃないから体積そのまま重量が増えるわけではないけれど、それにしても「巨大化すれば重量がかさみ、相対的に翼面積が減少して飛ばすのが難しくなる」のは避けられない。これこそが飛行機の発明以来たくさんの技術者を悩ませてきた「2乗3乗の法則」だ。
さらに追い討ちをかけると、エンジン(推力)にも2乗3乗の法則が効いてくる。
プロペラやジェットエンジンの推力を決めるのは前方投影面積だ。要するにたくさんの空気をつかまえて後ろに押し出せば強い力が出る。だからといってそのまま大きさを倍にすると、前方投影面積は4倍なのに体積は8倍となり、推力重量比が低下してしまう。まったく困ったものだ。
要するに、空を飛ぶものは小さければ小さいほど楽であり、大きければたいへん苦労するのだ。
チョウはお気楽にふわふわ空気の中を漂っているけれど、ジェット旅客機は何キロも必死に滑走路を走らないと飛び立てない。これこそが冷厳な物理学(2乗3乗の法則)に支配される航空機の姿だ。
「ベルシオン飛行艇」の理屈は知らないけれど、実験映像を見る限り「驚異の飛行艇」は長さ1メートル程度の小さいものだ。チョウやハエがホバリングしても誰も驚かないように、この大きさの模型飛行機がホバリングするのは簡単だ。極論すれば、ちょっと強力なエンジンがあれば機体の設計など大して影響がない。
鈴木氏の言うように「機体が大きくなるほど空気をつかめ、安定して飛べる」実機が軽やかに飛んでみせたら私も大いに感心するが、革命的に強力なエンジン(ミノフスキー融合炉とかS2機関とかシズマドライブ)ができない限り絶対無理だ。
先日の毎日新聞のフリーエネルギー記事(幻影随想: 毎日新聞がフリーエネルギー詐欺に引っ掛かっている件について)もそうだけれど、大手マスコミの記者でも科学部以外はびっくりするほど科学的常識が抜けている。私のようなド素人でも「えーと、ネタだよねこれ? …違うの?」と呆れてしまうくらいだ。
しっかりしてくださいよまったく。











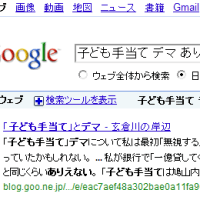

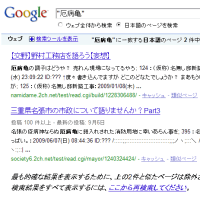
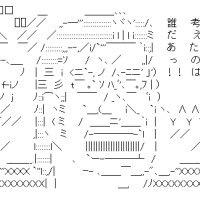



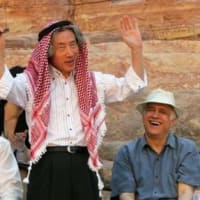

もちろん、「モーターの推力とバッテリーの軽量化」ですが・・・
子供の頃(30年以上前・・)には考えられなかったことですよ(w
ホバリングの場面なんかは、風上に機体を立てれば
あれくらいできますよねぇ・・・・
スホーイのデモフライトでも似たようなシーンがありますね。
アクロバット機なんかもやりますしねぇ。(こっちは人乗ってるし・・)
一応ベルシオン風車も見てみましたが、垂直式って・・・
昔薬局の前でクルクルまわっていた看板の焼きなおしに見えます・・・・
つまり面積もしくは体積と重さの比が重要ですか。
ちなみに、「浮くかどうか」に目を向けると航空力学でもなんでもありません。
もっと根源的なものです。つまるところ密度ですね。それと抵抗。
ヘリウム風船は大きかろうが動力が無かろうが浮きます。これは空気よりも密度が低いからです。
つまり、「密度の低いもの」に動力を付けた「飛行」の否定に2乗3乗など大きさ云々を持ち出すのは・・・。
だってね。その辺飛んでるふつーの飛行船だって翼ほとんど無い割に、すげー巨体じゃんw
それと・・・。ちなみに虫の「クモ」はあんな形なのに、糸を吐いて空を漂えます。これは抵抗の力。
あれがトンデモ話かどうかは置いといて、2乗3乗の法則ってものを持ち出すのは、ちょっとずれているかも知れませんよ。
パワーさえありゃ飛ぶだろって話は、よーっく分かりますねー。
より大きく、より軽いもので問題になるのは「強度」です。