こんばんは。
昨日は、夏季休暇のあいだに、前期をとおして発表してきた「戦後派」と呼ばれる作家の作品群の傾向、背景、主題をよりあきらかとして、後期の展望を深化させるために勉強会を行いました。提出いたしましたレポートを中心に、大江という作家、「戦後派」というくくりをめぐって議論がありました。以下そのレポートです。
『死者の奢り』論 ―〈僕〉の視点から見た〈死者〉たち―
学部3年生
私はこの作品を読んだ時、もっぱら作品内に登場する〈死者〉たちの存在が気になった。というのは普通、人間という者は死んだらすぐに火葬される者であり、「死者の奢り」のように生身の肉体が現存し、しかもそれがアルコール漬けの水槽に沈んでいるという光景は、読んでいて不思議に思った。しかし今私が述べた〈人間は死んだらすぐに火葬される〉という思考はあくまでも現代的なものであり、作品の発表当時(昭和三十二年)の価値観とは必ずしも一致しないということは留意しておかなければならない。
今レポートではそういったことに注意を払いながら、作品内に登場する〈死者〉たちの存在を、生者である〈僕〉の視点を交えながら捉えてゆきたい。
まず〈死者〉たちは冒頭(P8 l,1)から主格として描かれているが、これは作品内での〈死者〉たちの存在感を示している。その〈死者〉たちは〈柔軟な皮膚〉=〈肉体〉を保持しているが、生者である〈語り手〉=〈僕〉とは異なった感覚の〈独立感〉も持っている。
つまり〈死者〉たちは生者としての肉体は保持しつつも、生者とはまるで異なった存在であることがいえる。それは〈死者〉たちからかすかにでる〈浮腫〉からも読み取れることができる。〈浮腫〉は〈死者〉たちの肉体を豊かにする一方で、〈死者〉として成長しないという肉体的イメージを私に連想させる。肉体的にも成長しない〈死者〉たちは、肉体的にも生者とは異なった存在なのである。
しかしながら、これら〈死者〉たちは生者としてのイメージを連想させる〈囁き〉の声をだすことで、〈死者〉ではあるけれど、〈死者〉になりえていないことが表されている。
そういった〈死者〉たちと、主人公・〈僕〉が接し始めるのは、〈死者〉たちを沈めた水槽のある部屋で〈僕〉が一人ぼっちになった時(P17 l,6)である。〈僕〉は〈死者〉たちに性別があることを認識するが、〈死者〉たちを特定の個人までには区別しない。区別しない代わりに〈僕〉は〈死者〉たちを《物》として捉える。それは火葬される通常の死体とは異なる形で、むしろそれとは独立した形でアルコール漬けの〈死者〉たちを捉えるということである。
《物》として独立した〈死者〉たちの安定した存在は、彼等の存在の不動性が示されている。自分は《物》だと認める一人の〈死者〉との対話(P18 l,7)を通じて、〈死者〉たちは生前の意識がなくなった後に《物》としての死を始める。この時、〈僕〉はアルコール漬けにある〈死者〉たちも〈死〉を伴う存在であるということを認識する。
その直後の中年の女性の〈死者〉との対話では、〈僕〉が女性の〈死者〉に対して内面で思っていることを忖度する形で、女性は〈僕〉に返答している。ここでは単に〈死〉を伴う〈死者〉と、〈生〉を伴う〈僕〉との関係性が表されている。
また少し間を置いて、〈僕〉は戦中に射殺された過去を持つ兵隊の肉体(ここでは〈頭部〉)を注視することによって(P23 l,10)、〈僕〉はその生前の姿を思い浮かべている。ここでは《物》としての〈死者〉とは違った側面で〈死者〉を眺めている〈僕〉がいる。肉体を介した兵隊との対話を通じて、自己の過去に対して抱いている兵隊の内面に踏み込もうとする〈僕〉の行為によって、《物》としてではなく生者としての過去をもつ〈死者〉の存在が〈僕〉の中で浮かび上がってくる。
戦争を実践的に経験したことのある兵隊の肉体に残る〈銃創〉(P25 l,6)は、まさしく彼の過去を表すものである。ここでは〈死者〉の存在は戦争を寓意させる存在であるということがいえる。
戦争の終結が唯一の希望であった時代に、〈死〉に直面しながら少年期を送ってきた〈僕〉は、戦後も心の中の死体を払拭することができず、また希望ももっていない。ここで主格が〈僕ら〉になっていることに注意したい。これは希望を持つことができない戦後派世代全般を指しているのだろう。つまり、希望をもって死んだ〈死者〉である兵隊に対して、一向に希望が持てないといったそういった世代のことを指しており、そういった戦後派世代の姿が、〈死者〉の存在を通して示されているのだろうと私は思う。
議論のテーマが「政治」になっても(P26 l,2)、〈政治についてしか話さない〉兵隊に対し、〈押しつけられそう〉と政治的事柄に消極的な〈僕〉が描かれている。〈僕〉は政治的関与を好まないのだ。
兵隊との長い対話を終えた〈僕〉は(P26 l,9)、兵隊であった〈死者〉の肉体を細かく観察して、生前の〈死者〉の性格を推察することによって、〈僕〉は生者としての過去ある〈死者〉の存在を再認識している。
ただそのような再認識も、十二歳ほどの少女の〈死者〉の前では消えている。彼女と出会った時(P32 l,8)、〈僕〉は生者としての痕跡の残る少女のセクスを確認するが、これは少女が《物》へと移る前の〈死者〉、すなわち生者としての過去のある〈死者〉であることを示している。しかし、そのセクスをもつ少女も、水槽に移されることで《物》へと推移してしまう。
結局、〈死者〉は生者としての過去ある〈死者〉と一度見えても、〈僕〉にとっては〈死者〉は《物》へと推移していく存在なのではないか、というのが私の結論である。
大江健三郎「死者の奢り」論
学部2年生
大江健三郎のデビュー当時において良き理解者、援護者であった江藤淳によれば〈処女作の通例にもれず、ここにこの作家のほとんどすべての主題の萌芽がかくされている〉という「死者の奢り」には、たしかに大江の小説の主旋律をなしている性(セクス)、倦怠感、主人公の自我によって分け隔てられる内部/外部―大きな枠としてそれは戦前・戦後の世代間という形態を伴って現れる―が扱われている。特に主人公が自身予測し得ない急な倦怠感は、作品内に頻出する単語である以上に、以後の大江の作品でも重要なモティーフである。
〈僕〉、女学生、管理者と教授、助教授といった人物の、大学構内での一日が舞台となったこの作品は「死者の奢り」という表題を示す通り、奢った物言いの死者へのアプローチが対話によりなされている。死者は男女を問わない。軍人もいれば少女もおり、それらを〈僕〉は「《物》」と規定する。この規定の感覚に同調しているのは、女学生だけである。そのことを〈僕〉は気づいている(p.39)が、同時に主人公は彼女を〈厄介に感じていた〉(p.39)とも思っている。この径庭は女学生が執拗に性差によって区別を行うことによっても確かめ得る、そしてそれは彼女が、眼の前の死体を通して、胎内の生命を思考している点にその根を張っている。だがまた、彼女と〈僕〉とを結びつけるものとして用いられるのが倦怠感だ。〈僕〉の眼から推察される女学生の疲労が、死体を「《物》」として見られ得るものとなって機能する。だがあくまでも〈僕〉の倦怠感は、多分に体力的な面による女学生の疲労よりもさらに他者との接触に伴い深化・尖鋭化していく。その点で、この作品は〈僕〉に参与する者が登場しないと言える。死者との対話は言うなれば「《物》」に仮託して語られる自己だ。〈完全な《物》の緊密さ〉の死者とは、「緊密に描かれる自己像」と言い換えられる。表題は、奢った自己を意味していることが明らかになるのだ。それを踏まえて読めば、管理人や教授や助教授、手押車の男が主人公に対して向ける〈憎悪〉や〈〉の視線も意味を持つ。一見、不条理なまでの彼らの〈僕〉に対する侮蔑的な態度も、表題の奢りに対する外部からの反応であるとしたら、その意味を通した上であれば、作者の意図した点がどこにあるのか分かるのではないか。
ではそれはどこにあるのかというと、倦怠感である。〈僕〉は死者との対話の後、急な〈ものうい疲れ〉の萌芽(p.28)を感じる。そして生の側にいる人間は〈僕を拒む〉(p.28)という発想をする。倦怠感は思考に先んじてあらわれる。これは外部との接触が肉体によって行われるためだが、この倦怠感は、管理人の顔に表れる疲労の表情(p.42)とも、女学生とも異なり、肉体の兆候よりも感覚に優先されるものだ。外部と自我との違和感が、倦怠感となって〈僕〉を襲う。そしてついに〈損をするのは、いつも僕だ〉(p.42)という位置にまで思考は他者との接触を拒んでしまう。堕胎を計画していた女学生が転倒を機に出産を決意したのを〈罠にかかってしまっている〉と〈僕〉が考えるのは、女学生の〈はっきりした皮膚を持ってからでなくちゃ、収拾がつかない〉という言葉を受けてだと思われる。皮膚という内部と外部を隔てるものを与えることが、ひいては生を与えることにもなり、それを〈面倒〉という〈僕〉を通して、外部の持つ個的なものである自我への暴力性が描かれている。そして肉体は階段を降りているが内的には執拗な感情の膨張を感じるという終盤にいたって、報酬の交渉という外部との接触の義務を有した〈僕〉が、同時に接触の拒否を感じるという心身の乖離を来す状態に陥る。ここで作者は、現代の人間の持つ自己の乖離を描きだして物語の幕を下ろす。以上の考察から、この作品には自我への外部の暴力性をあばくという主題が一貫していると言えるのである。
大江健三郎「死者の奢り」
学部4年生
「監禁されている状態、閉ざされた壁のなかに生きる状態を考えることが、一貫した僕の主題でした。(略)」これは『死者の奢り』(昭和33・3)の後記の冒頭部分である。戦後の初期作品の中心的テーマとして定評となっている。また、『厳粛な綱渡り』(昭和40・3)では「私は頽廃した無気力な青年をえがくことで文学的出発をしました。私は、現代日本の青年の最も典型的なパターンとしてそれをえがいてきました。(略)」と自評している。この〈無気力〉であることは、作品中の〈僕は希望を持っていない〉(42頁)という言葉と強く結びついている。今回は、〈無気力〉とも通ずる〈疲れ〉や〈誇り〉という言葉に焦点をあて「死者の奢り」の〈僕〉像を探っていく。
テキストで〈誇り〉という言葉は次の2つの場面に分けてみられる。ひとつは管理人について〈官立大学の医学部につとめていることを誇りにしているのだろう〉(16頁)と、管理人が竹竿を〈熟練した感じ〉で使いこなす場面での〈この仕事に誇りを持っているのだろう〉(19頁)。ふたつめは、教授とのやりとりでの〈こんな仕事をやって、君は恥ずかしくないか?君たちの世代には誇りの感情がないのか?〉(36頁)である。〈誇り〉とは人間が存在する基盤となるものだが、それを突き付けられた時(36頁)、〈僕〉は〈徒労〉や〈疲れ〉を感じている。これは、時代背景として、戦後、アメリカの占領下におかれた日本は、日本人としての誇りを持てずに日常生活を送ることを余儀なくされたことが原因ではないか。戦中、〈僕〉はまだこどもで、〈戦争の終わることが不幸な日常の唯一の希望であるような時期に成長してきた。(中略)戦争が終り、その死体が大人の胃のような心の中で消化され、消化不能な固形物や粘液が排泄されたけれども、僕はその作業には参加しなかった。そして僕らには、とてもうやむやに希望が融けてしまったものだった〉(25頁)と戦争について語る。ここでは戦争終結が〈不幸な日常〉からの〈希望であるような時期〉とし、決して希望とは言われていない。文末は〈僕ら〉と複数形になり、〈僕〉の同世代から発せられる言葉となっている。
〈疲れ〉はテキスト内で8回使われ、向けられている対象は〈僕〉に2回、〈女子学生〉に5回、〈管理人〉に1回であった。テキストの36頁の〈僕〉の〈疲れ〉は、〈生きている人間と話すのは、なぜこんなに困難で、思いがけない方向にしか発展しないで、しかも徒労な感じがつきまとうのだろう〉と、他者(ここでは生者)を通して自分自身が感じざる負えないものである。これは42頁にある〈自分がひどく曖昧でまず自分を説得しなければならない厄介な仕事が置きっぱなしになっている事に気がついて、やりきれない(中略)損をするのは、いつも僕だ〉と自分でも理解しているが、どうにもできない感情が、〈疲れ〉として表出される。
〈誇り〉や希望を〈持つ必要がない〉(42頁)または〈希望を持ったり、絶望している暇がない〉(43頁)と僕は述べているが、生者である以上、希望をもつ必要がないという希望を抱いている。矛盾を抱えている葛藤が、〈疲れ〉や〈徒労〉感を生み出している。
多くの議論、疑問点が噴出した作品でしたが、実存の問題、性の問題が内包されている点において、戦後の文学の中のひとつの共通を示すものでした。この「死者の奢り」に限らず、戦後文という広大な作品の世界全体のなかで、なにかつかめたらという思いを強く致しました。
昨日は、夏季休暇のあいだに、前期をとおして発表してきた「戦後派」と呼ばれる作家の作品群の傾向、背景、主題をよりあきらかとして、後期の展望を深化させるために勉強会を行いました。提出いたしましたレポートを中心に、大江という作家、「戦後派」というくくりをめぐって議論がありました。以下そのレポートです。
『死者の奢り』論 ―〈僕〉の視点から見た〈死者〉たち―
学部3年生
私はこの作品を読んだ時、もっぱら作品内に登場する〈死者〉たちの存在が気になった。というのは普通、人間という者は死んだらすぐに火葬される者であり、「死者の奢り」のように生身の肉体が現存し、しかもそれがアルコール漬けの水槽に沈んでいるという光景は、読んでいて不思議に思った。しかし今私が述べた〈人間は死んだらすぐに火葬される〉という思考はあくまでも現代的なものであり、作品の発表当時(昭和三十二年)の価値観とは必ずしも一致しないということは留意しておかなければならない。
今レポートではそういったことに注意を払いながら、作品内に登場する〈死者〉たちの存在を、生者である〈僕〉の視点を交えながら捉えてゆきたい。
まず〈死者〉たちは冒頭(P8 l,1)から主格として描かれているが、これは作品内での〈死者〉たちの存在感を示している。その〈死者〉たちは〈柔軟な皮膚〉=〈肉体〉を保持しているが、生者である〈語り手〉=〈僕〉とは異なった感覚の〈独立感〉も持っている。
つまり〈死者〉たちは生者としての肉体は保持しつつも、生者とはまるで異なった存在であることがいえる。それは〈死者〉たちからかすかにでる〈浮腫〉からも読み取れることができる。〈浮腫〉は〈死者〉たちの肉体を豊かにする一方で、〈死者〉として成長しないという肉体的イメージを私に連想させる。肉体的にも成長しない〈死者〉たちは、肉体的にも生者とは異なった存在なのである。
しかしながら、これら〈死者〉たちは生者としてのイメージを連想させる〈囁き〉の声をだすことで、〈死者〉ではあるけれど、〈死者〉になりえていないことが表されている。
そういった〈死者〉たちと、主人公・〈僕〉が接し始めるのは、〈死者〉たちを沈めた水槽のある部屋で〈僕〉が一人ぼっちになった時(P17 l,6)である。〈僕〉は〈死者〉たちに性別があることを認識するが、〈死者〉たちを特定の個人までには区別しない。区別しない代わりに〈僕〉は〈死者〉たちを《物》として捉える。それは火葬される通常の死体とは異なる形で、むしろそれとは独立した形でアルコール漬けの〈死者〉たちを捉えるということである。
《物》として独立した〈死者〉たちの安定した存在は、彼等の存在の不動性が示されている。自分は《物》だと認める一人の〈死者〉との対話(P18 l,7)を通じて、〈死者〉たちは生前の意識がなくなった後に《物》としての死を始める。この時、〈僕〉はアルコール漬けにある〈死者〉たちも〈死〉を伴う存在であるということを認識する。
その直後の中年の女性の〈死者〉との対話では、〈僕〉が女性の〈死者〉に対して内面で思っていることを忖度する形で、女性は〈僕〉に返答している。ここでは単に〈死〉を伴う〈死者〉と、〈生〉を伴う〈僕〉との関係性が表されている。
また少し間を置いて、〈僕〉は戦中に射殺された過去を持つ兵隊の肉体(ここでは〈頭部〉)を注視することによって(P23 l,10)、〈僕〉はその生前の姿を思い浮かべている。ここでは《物》としての〈死者〉とは違った側面で〈死者〉を眺めている〈僕〉がいる。肉体を介した兵隊との対話を通じて、自己の過去に対して抱いている兵隊の内面に踏み込もうとする〈僕〉の行為によって、《物》としてではなく生者としての過去をもつ〈死者〉の存在が〈僕〉の中で浮かび上がってくる。
戦争を実践的に経験したことのある兵隊の肉体に残る〈銃創〉(P25 l,6)は、まさしく彼の過去を表すものである。ここでは〈死者〉の存在は戦争を寓意させる存在であるということがいえる。
戦争の終結が唯一の希望であった時代に、〈死〉に直面しながら少年期を送ってきた〈僕〉は、戦後も心の中の死体を払拭することができず、また希望ももっていない。ここで主格が〈僕ら〉になっていることに注意したい。これは希望を持つことができない戦後派世代全般を指しているのだろう。つまり、希望をもって死んだ〈死者〉である兵隊に対して、一向に希望が持てないといったそういった世代のことを指しており、そういった戦後派世代の姿が、〈死者〉の存在を通して示されているのだろうと私は思う。
議論のテーマが「政治」になっても(P26 l,2)、〈政治についてしか話さない〉兵隊に対し、〈押しつけられそう〉と政治的事柄に消極的な〈僕〉が描かれている。〈僕〉は政治的関与を好まないのだ。
兵隊との長い対話を終えた〈僕〉は(P26 l,9)、兵隊であった〈死者〉の肉体を細かく観察して、生前の〈死者〉の性格を推察することによって、〈僕〉は生者としての過去ある〈死者〉の存在を再認識している。
ただそのような再認識も、十二歳ほどの少女の〈死者〉の前では消えている。彼女と出会った時(P32 l,8)、〈僕〉は生者としての痕跡の残る少女のセクスを確認するが、これは少女が《物》へと移る前の〈死者〉、すなわち生者としての過去のある〈死者〉であることを示している。しかし、そのセクスをもつ少女も、水槽に移されることで《物》へと推移してしまう。
結局、〈死者〉は生者としての過去ある〈死者〉と一度見えても、〈僕〉にとっては〈死者〉は《物》へと推移していく存在なのではないか、というのが私の結論である。
大江健三郎「死者の奢り」論
学部2年生
大江健三郎のデビュー当時において良き理解者、援護者であった江藤淳によれば〈処女作の通例にもれず、ここにこの作家のほとんどすべての主題の萌芽がかくされている〉という「死者の奢り」には、たしかに大江の小説の主旋律をなしている性(セクス)、倦怠感、主人公の自我によって分け隔てられる内部/外部―大きな枠としてそれは戦前・戦後の世代間という形態を伴って現れる―が扱われている。特に主人公が自身予測し得ない急な倦怠感は、作品内に頻出する単語である以上に、以後の大江の作品でも重要なモティーフである。
〈僕〉、女学生、管理者と教授、助教授といった人物の、大学構内での一日が舞台となったこの作品は「死者の奢り」という表題を示す通り、奢った物言いの死者へのアプローチが対話によりなされている。死者は男女を問わない。軍人もいれば少女もおり、それらを〈僕〉は「《物》」と規定する。この規定の感覚に同調しているのは、女学生だけである。そのことを〈僕〉は気づいている(p.39)が、同時に主人公は彼女を〈厄介に感じていた〉(p.39)とも思っている。この径庭は女学生が執拗に性差によって区別を行うことによっても確かめ得る、そしてそれは彼女が、眼の前の死体を通して、胎内の生命を思考している点にその根を張っている。だがまた、彼女と〈僕〉とを結びつけるものとして用いられるのが倦怠感だ。〈僕〉の眼から推察される女学生の疲労が、死体を「《物》」として見られ得るものとなって機能する。だがあくまでも〈僕〉の倦怠感は、多分に体力的な面による女学生の疲労よりもさらに他者との接触に伴い深化・尖鋭化していく。その点で、この作品は〈僕〉に参与する者が登場しないと言える。死者との対話は言うなれば「《物》」に仮託して語られる自己だ。〈完全な《物》の緊密さ〉の死者とは、「緊密に描かれる自己像」と言い換えられる。表題は、奢った自己を意味していることが明らかになるのだ。それを踏まえて読めば、管理人や教授や助教授、手押車の男が主人公に対して向ける〈憎悪〉や〈〉の視線も意味を持つ。一見、不条理なまでの彼らの〈僕〉に対する侮蔑的な態度も、表題の奢りに対する外部からの反応であるとしたら、その意味を通した上であれば、作者の意図した点がどこにあるのか分かるのではないか。
ではそれはどこにあるのかというと、倦怠感である。〈僕〉は死者との対話の後、急な〈ものうい疲れ〉の萌芽(p.28)を感じる。そして生の側にいる人間は〈僕を拒む〉(p.28)という発想をする。倦怠感は思考に先んじてあらわれる。これは外部との接触が肉体によって行われるためだが、この倦怠感は、管理人の顔に表れる疲労の表情(p.42)とも、女学生とも異なり、肉体の兆候よりも感覚に優先されるものだ。外部と自我との違和感が、倦怠感となって〈僕〉を襲う。そしてついに〈損をするのは、いつも僕だ〉(p.42)という位置にまで思考は他者との接触を拒んでしまう。堕胎を計画していた女学生が転倒を機に出産を決意したのを〈罠にかかってしまっている〉と〈僕〉が考えるのは、女学生の〈はっきりした皮膚を持ってからでなくちゃ、収拾がつかない〉という言葉を受けてだと思われる。皮膚という内部と外部を隔てるものを与えることが、ひいては生を与えることにもなり、それを〈面倒〉という〈僕〉を通して、外部の持つ個的なものである自我への暴力性が描かれている。そして肉体は階段を降りているが内的には執拗な感情の膨張を感じるという終盤にいたって、報酬の交渉という外部との接触の義務を有した〈僕〉が、同時に接触の拒否を感じるという心身の乖離を来す状態に陥る。ここで作者は、現代の人間の持つ自己の乖離を描きだして物語の幕を下ろす。以上の考察から、この作品には自我への外部の暴力性をあばくという主題が一貫していると言えるのである。
大江健三郎「死者の奢り」
学部4年生
「監禁されている状態、閉ざされた壁のなかに生きる状態を考えることが、一貫した僕の主題でした。(略)」これは『死者の奢り』(昭和33・3)の後記の冒頭部分である。戦後の初期作品の中心的テーマとして定評となっている。また、『厳粛な綱渡り』(昭和40・3)では「私は頽廃した無気力な青年をえがくことで文学的出発をしました。私は、現代日本の青年の最も典型的なパターンとしてそれをえがいてきました。(略)」と自評している。この〈無気力〉であることは、作品中の〈僕は希望を持っていない〉(42頁)という言葉と強く結びついている。今回は、〈無気力〉とも通ずる〈疲れ〉や〈誇り〉という言葉に焦点をあて「死者の奢り」の〈僕〉像を探っていく。
テキストで〈誇り〉という言葉は次の2つの場面に分けてみられる。ひとつは管理人について〈官立大学の医学部につとめていることを誇りにしているのだろう〉(16頁)と、管理人が竹竿を〈熟練した感じ〉で使いこなす場面での〈この仕事に誇りを持っているのだろう〉(19頁)。ふたつめは、教授とのやりとりでの〈こんな仕事をやって、君は恥ずかしくないか?君たちの世代には誇りの感情がないのか?〉(36頁)である。〈誇り〉とは人間が存在する基盤となるものだが、それを突き付けられた時(36頁)、〈僕〉は〈徒労〉や〈疲れ〉を感じている。これは、時代背景として、戦後、アメリカの占領下におかれた日本は、日本人としての誇りを持てずに日常生活を送ることを余儀なくされたことが原因ではないか。戦中、〈僕〉はまだこどもで、〈戦争の終わることが不幸な日常の唯一の希望であるような時期に成長してきた。(中略)戦争が終り、その死体が大人の胃のような心の中で消化され、消化不能な固形物や粘液が排泄されたけれども、僕はその作業には参加しなかった。そして僕らには、とてもうやむやに希望が融けてしまったものだった〉(25頁)と戦争について語る。ここでは戦争終結が〈不幸な日常〉からの〈希望であるような時期〉とし、決して希望とは言われていない。文末は〈僕ら〉と複数形になり、〈僕〉の同世代から発せられる言葉となっている。
〈疲れ〉はテキスト内で8回使われ、向けられている対象は〈僕〉に2回、〈女子学生〉に5回、〈管理人〉に1回であった。テキストの36頁の〈僕〉の〈疲れ〉は、〈生きている人間と話すのは、なぜこんなに困難で、思いがけない方向にしか発展しないで、しかも徒労な感じがつきまとうのだろう〉と、他者(ここでは生者)を通して自分自身が感じざる負えないものである。これは42頁にある〈自分がひどく曖昧でまず自分を説得しなければならない厄介な仕事が置きっぱなしになっている事に気がついて、やりきれない(中略)損をするのは、いつも僕だ〉と自分でも理解しているが、どうにもできない感情が、〈疲れ〉として表出される。
〈誇り〉や希望を〈持つ必要がない〉(42頁)または〈希望を持ったり、絶望している暇がない〉(43頁)と僕は述べているが、生者である以上、希望をもつ必要がないという希望を抱いている。矛盾を抱えている葛藤が、〈疲れ〉や〈徒労〉感を生み出している。
多くの議論、疑問点が噴出した作品でしたが、実存の問題、性の問題が内包されている点において、戦後の文学の中のひとつの共通を示すものでした。この「死者の奢り」に限らず、戦後文という広大な作品の世界全体のなかで、なにかつかめたらという思いを強く致しました。















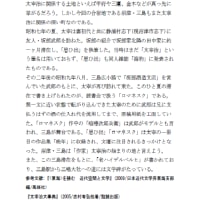

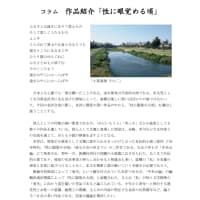
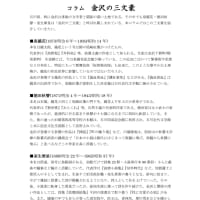
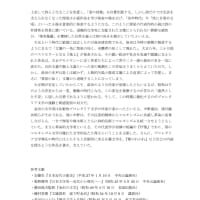
今回の勉強会は前期の集大成ということで……いつもより緊張しました。また、先行論の数も多く、自分が何に焦点をあて論じていくかとても悩みましたが、他の方が何を論じるのか楽しみでした。
今回の議論で改めて感じたことは、自分の意見がどうしても先行論に引っ張られてしまい、自分の読みなのか何なのか混乱し、作品の深部を自分の目でみることができませんでした。
とても初歩的なことで恥ずかしいのですが、後期の発表ではそこから見直していきたいです。
個人的に好きな作品でしたので、ぜひ、今回参加されなかった方のご意見もお聞きしたいと思っております。
そして、後期からの発表や議論も前期に増してよいものになるよう取り組んでいきたいと思っています。
発表おつかれ様でした。今回の議論では様々なことが指摘されましたが、発表者の主な論点としては・・・
①「倦怠感」、「無気力」とった大江の作家論
②〈死者〉を通して見える〈僕〉の存在
でありました。発表者同士の議論では・・・
①作品全体を通して見える〈僕〉の捉え方(学部生三年生への指摘)
②《物》になる前の十二歳の少女がどう規定されているか、「暴力性」という言葉の意味(学部生二年生への指摘)
③テキスト内の個人としての〈誇り〉と日本人としての〈誇り〉の関係性(学部生四年生への指摘)
となりました。これらを踏まえて院生の方から以下のことが指摘されました。
①〈死者〉と〈死体〉の違い
②〈臭い〉の解釈
③妊娠している女子学生の問題
④仕事が無駄になり徒労に終る〈僕〉の実感のなさ
⑤大江の抒情
以上のように、大江健三郎の作家論と「死者の奢り」の〈僕〉から読み取れるテキスト論を合わさった形で発表が行われましたが、レポートで言及されていない点が多々あるということが院生の指摘により分かりました。そこで上記で述べられた不足点を復習として再考察してみたいと思います。といっても①~⑤全てを解釈するには限界があるので、とりあえず①「〈死者〉と〈死体〉の違い」の考察を短めですが、以下に述べていきます。
復習―〈死体〉と〈死者〉の差―
○解釈1
① 会話文は全て〈死体〉(P12,13,14,35,41,46,47,48,52)で用いられている。
② 初使用される場面
「死者」:P8冒頭
「死者たちは、濃褐色の液に浸って、腕を絡みあい、頭を押しつけあって、ぎっしり浮かび,
また半ば沈みかかっている。」
「死体」:P12 l,11
「タイルが淡く変色している水槽の縁に両手を支えて、僕はアルコール溶液に浸かっている死体の群がりをみた。」
○〈死者〉の解釈①
▽対話において用いられず、また冒頭で観念的に語られている〈死者〉
→〈僕〉の観念として表されている〈死者〉
○ 〈死体〉の解釈①
▽〈死体〉を実際に見ている場面で初めて用いられ、また対話でも表記として表されている〈死体〉
→実際に存在している実在として表されている〈死体〉
○解釈2
③全て単数形で用いられる〈死体〉、単数・複数で用いられる〈死者〉
「これらの死者たちは、死後ただちに火葬された死者とはちがっている。(P17 l,16)」
「死んですぐに火葬される死体は、これほど完璧に《物》ではないだろう、と僕は思った。(P17 l,17)」
④〈解剖用死体〉としての〈死体〉
「僕は昨日の午後、アルコール水槽に保存されている、解剖用死体を処理する仕事のアルバイターを募集している掲示を見るとすぐ、医学部の事務室へ出かけて行った。(P13 l,13)」
○〈死者〉の解釈②
▽〈僕〉の観念として表される〈死者〉は、単数・複数で使い分けられている
→数量を単数・複数と使い分けることで、〈僕〉の観念性を裏付けている
○〈死体〉の解釈②
▽実在として単数形で表されている〈死体〉は、〈解剖用死体〉としての役割を持っている
→数量を単数形に統一することで、〈解剖用死体〉としての〈死体〉の実在性を裏付けている
○まとめ
以上、私の見解では〈死者〉は「〈僕〉の観念として表されている語句」であるのに対して、〈死体〉は「作品内の実在性を表すために用いられた語句」として解釈いたしました。
私の見解いかがでしょうか?コメントをお待ちしております。
名前をつけとくのを忘れました。
返信がおくれ申し訳ありません。
〈死者〉が〈僕〉の観念性の呼称で、もう一方が、作品内のそこにある〈物〉としての〈死体〉であるというご見解と解釈いたしました。ひとつの物を、呼称によって区別する手法は、明らかな不作為である以外には文学研究の上で大事であると思いましたので、勉強会でのご指摘の際には、目からうろこであると同時に、「あれ、やはりこの問題があったか」と、不覚だったことが思われます。
イシイさんの解釈は僕もほとんど賛成です、というか、賛成した上の次元にこそ、この〈死者〉・〈死体〉をめぐる呼称の問題はあると考えます。まずこの作品であつかわれている(作品であつかわれたものを社会通念上僕らが呼称するものとして)死体には、三つの呼称があると思います。〈物〉、〈死者〉、〈死体〉がそうです。これよりも、それ自体を規定するために用いられる文飾があり、軍属についていた、少女である、足がすらりと長い、といった社会地位、性別がわかるものはありますが、あくまでも上の三つとは、それよりも下位に位置する規定条件であると思われます。
さらに、〈完全な《物》〉と書いている点にも注目すれば、二重の括弧による表記は、おそらく、強調、ないしは限定づけといった意味合いを含んでいるものだと考えられます。それが、〈完全〉と表記されるのは、僕にカントの言う〈物自体〉の概念を想起させるのです。認識不可能な、存在の純粋な概念規定でありますが、『死者の奢り』で表記される〈物〉も、そうした性質を持ったものであるといえます。認識下の影響から脱した状態における水槽で浮き沈みする「それ」を、〈死者〉や〈死体〉と呼ぶ〈僕〉とは? という点こそが、この呼称をめぐる問題の本質だと思います。
なお、イシイさんのお書きになったコメントの箇所での〈実在性〉という語句が、どの程度におけるものなのか、やや判然といたしませんでした。リアリティー、とは異なるのでしょうか?
なるほど、<死者><死体>の分け方を把握した上で改めてそれらを見つめる<僕>とは何なのかということを考えてみる必要はありますね。
私の使った<実在性>は<観念性>の対極に位置する意味で用いました。僕の<観念性>(主観と言ってもよい)である<死者>に対し、他の登場人物全てにその<実在性>を認識されている<死体>を分けて考えてみました。ですからそこに<実在>しているという点からでは、リアリティーとも言い換えられると思います。