
昭和40年代の日本に邪馬台国ブームをもたらした目の不自由な文学者・宮崎康平と、彼を支え続けた妻・和子のきずなを描く感動ドラマ。監督は『明日の記憶』の堤幸彦。邪馬台国を探し出すことに執念を燃やす一方、とっぴな行動で注目を集めた康平を竹中直人が演じ、どこか憎めない康平に惹(ひ)かれ、二人三脚の人生を歩む和子を吉永小百合が演じる。九州の美しい大自然を舞台に描かれる、太古のロマンを追い求めた夫婦の愛の物語を堪能したい。[もっと詳しく]
堤幸彦監督のジャンルを問わない小器用さが、まったく裏目に出た駄作。
この作品も、製作委員会の中に木下工務店と加賀電子が入っている。
アメリカの画像関係の会社との提携路線の中で、デジタル映像ソリューション路線を標榜する加賀電子はともかくとして、木下工務店のスポンサードの名前を見かけるたびに、フーンという気持ちが去来する。
何度もこの個人的な映画レヴューに書いていることだが、映画を製作するということは、カネの段取りをつけることがほぼ90%の比重を持つと思ったほうがいい。
構想10年などと、もったいをつけている作品は多いが、そのほとんどは予算がつかなかっただけのことである。
日本でいえば、東映・東宝をはじめとするメジャー映画社のプレゼンツであろうが、商社とかが入りながら、資本市場で大混乱を招いているJDC(ジャパン・デジタル・コンテンツ)などのコンテンツ信託を基盤としながら、ファンド形式で(あくまで形式だけで実体はお寒いものなのだが)製作委員会方式でつくりあげられている「話題の作品」であろうが、製作会社が現状に絶望しながら、背伸びをする形で、リスクをもってプロデュースしているようなインディペンダントな映画作品であろうが、結局のところ、製作費をどう確保するかということが、最大のミッションであることはいまさらいうまでもない。

木下工務店の映画出資を判断するのは、キノシタマネージメントの代表、木下直哉である。
木下工務店は、ある時期に資本にM&Aされているので、木下といっても偶然の一致で、創業一族と無関係だ。
40代の木下直哉は、映画好きで、1万本以上の映画に淫しているらしい。
僕と同じだ(笑)
彼のインタヴューは以下を参照。
http://www.bunkatsushin.com/modules/bulletin1/article.php?storyid=106
出資は、かなりの数にのぼるのだが、「兇悪な出資ライン」として楽しく揶揄されているのは、「破壊屋」さん。
http://hakaiya.web.infoseek.co.jp/html/2009/20090618_1.html
最初の出資が、森田健作の製作・企画・原案・脚本・出演の「日本に渇!」の『I am 日本人』(06年)。
その後に、『未来予想図』『築地魚河岸三代目』『櫻の園』と続いて本作『まぼろしの邪馬台国』に続く。
今後のラインアップも上記を参照。まさに、兇悪なラインアップである(笑)。
まあ、サラリーマン担当者が船頭多くして責任の一端もとろうとしない、日本の幼稚な製作委員会システムに比べれば、オーナー企業に近い木下直哉のお遊び(本人に言わせれば正統で効果的な広告投資らしいが)はまだましだとも思えるが、センス悪すぎ!という奴である。

『まぼろしの邪馬台国』の舞台となっている島原は、たまたま相方の関係で、十回近くは訪れている。
島原鉄道も、バスやタクシーやフェリーも、観光・交通機関は、現在はさまざまな出資母体の混成だとしても、元は宮崎一族からつながっているものだろう。
映画のロケ地となっている島原城近くの武家屋敷跡や雲仙岳・霧島温泉郷も見慣れたものであり、この作品でいえば、阿蘇地方や有明を望む宇土半島も、いくつかの古墳群や佐賀で発掘され弥生期最大の環壕集落跡とされる吉野ヶ里遺跡も、訪れたことは何度もある。
そして、「邪馬台国論争」そのものも、一応は大学で歴史学を専攻していたこともあり、外野の野次馬だとしても、現在までの論争の変遷は、おおよそは把握しているつもりだ。

たしかに、三輪山麓の纏向(まきむく)遺跡から貴重な発掘がなされていることも含め、邪馬台国あるいは卑弥呼の墓の場所の同定に関しては、畿内説と九州説でいえば、ほぼ8割~9割がたは、畿内説に学会レベルでは傾いているように思える。
ただ、僕個人は、九州説のほうが、なんとなく浪漫が感じられて魅かれるところがある。
結局のところ、1世紀から3世紀にかけて親魏倭王として中国の「魏志倭人伝」などに繰り返し記述され、鬼道を使いながら王国を統括していた卑弥呼という存在を、天照大神に擬したり、神功皇后と同定したり、有力ではあるが一地方の部族長とみなしたりという推理が戦わされることになる。
ここでは高天原の天孫降臨や記紀にみられる東遷伝説、そしてなによりヤマト王権(天皇制)の起源を巡る論争であり、推定でもあるのだ。
もちろん、日本人はどこからきたのか、その歴史的起源の問題とも重なっている。

『まぼろしの邪馬台国』の主人公、宮崎康平は何度も運命的な事件に巻きこまれている。
1917年島原の土建業宮崎組の息子として生まれているが、早稲田大学に進み、森繁久弥などと演劇活動をしており、脚本家になろうと映画会社に入社したりしている。
長崎原爆を被爆もしているが、戦後すぐ宮崎組は倒産、父の代からの島原鉄道の経営に就くことになる。
49年、昭和天皇の島原地区への行幸に際して、その準備の過労のため、眼底網膜炎を患い、目が不自由となる。
妻にも逃げられ、幼いこどもをふたり抱えながら、労働争議などでもたいへんな時に、出会ったのが当時ラジオ局で勤めていた和子である。
59年、諫早大水害で島原鉄道は大きな被害を受ける。
その際に、土器を見つけ、島原鉄道の役員からも解任を受けた宮崎康平は、以降は「まぼろしの邪馬台国」を求めて、和子と二人三脚で調査・研究を続け、67年口述筆記で書き上げた『まぼろしの邪馬台国』が第1回吉川英治賞を夫婦で受賞、ベストセラーとなり以降の「邪馬台国」ブームを巻き起こすことになるのである。
宮崎康平は学生時代から文学青年でもあり、歴史好きでもあった。
城山三郎は「盲人重役」というタイトルで、彼をモデルに小説をしたためている。
妻に去られ、途方に暮れて、子供をあやしている時に、子守唄としてつくったのが『島原の子守唄』。島倉千代子やペギー葉山がヒットさせた。
また、さだまさしと父親がらみで親交があり、『関白宣言』は宮崎康平をモデルにしているといわれる。
とにもかくにも、個性的で破天荒な人物であったのだろう。

監督に堤幸彦。脚本に朝ドラでも人気の大石静。音楽は現在乗りに乗っている大島ミチル。卑弥呼のテーマをセリーヌ・ディオンに歌わせてもいる。
『母べえ』に続いて、吉永小百合が出演し、テレビなどを通じて、結構宣伝もしている。
しかし、映画として観た場合は、僕にはとんでもない駄作のように思える。
エキセントリックな宮崎康平という人物を、竹中直人が演じているのだが、普段でも暑苦しい演技の竹中直人が、結構のめりこんで役作りをしたのだろうが、そのぶん、余計に暑苦しくなっている。
綾小路きみまろ、大槻義彦、草野仁、大仁田厚などをチョイ役で登場させているが、別にお遊びにもなっていない。
島原鉄道の経営をめぐる確執も、底の浅い権力劇にしかみえない。
歴史的人物を評伝風に扱った教育映画なのか、夫婦による歴史発掘という心温まるヒューマン・ドラマなのか、宮崎康平という破天荒の男をユーモラスに扱った涙と笑いの映画なのか、太古の卑弥呼の時代を想う古代ロマン映画なのか、さっぱりわからない。
堤幸彦監督は、結構苦労人であり、ジャンルが違うような題材をそこそこ器用にまとめあげる監督なので、いまや売れっ子ではある。
けれども、『まぼろしの邪馬台国』では、その小器用さが、まったく裏目に出ているのかもしれない。











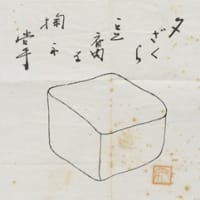


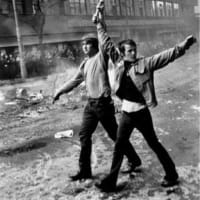



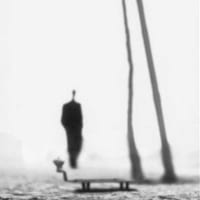

>・・・古代ロマン映画なのか、さっぱりわからない。
最初に妻となる和子の少女時代のエピソードが置かれていることから判断して、彼女の立場から観た夫婦愛の映画なんでしょう。
でも、映画にきちんとした方向性のある作り方がされていないのは確かで、こういう双葉さん的な評価の仕方に感動致しました。(笑)
>竹中直人
単調でちょっと戴けなかったです。
>大槻義彦
実社会では論破する人が論破される役を演ずると言うパロディーでしたね。
吉永小百合の卑弥呼も頑張っているんでしょうが、日本ではなんか「神話」的な時代映像はみすぼらしくなるんですよね。平安時代以降はまあまあ演出手法が蓄積はされていますけど。
「タイタン」じゃないけど、スサノオあたりで見ごたえのある活劇でもやって欲しいんですけどね。