池田先生のブログ経由で読んで思わず笑ってしまった記事がコレだ。
そうか、いつのまにか日本は総力戦を戦っていたのか。
そりゃ閉塞感に包まれるはずだ(笑)
以前、コメントでもちょっと話題になっていたので簡単にまとめておきたい。
財政について、再建はもう現実的ではないので、一度何らかの形で破綻させて
しまった方が良いという意見は、確かに一部にある(もちろん公では言わないけど)。
これは一見突飛に見えるが、よく考えてみれば非常に合理的な考えだ。
これから数年で、大胆な規制緩和を進め、人も金も新規事業に移して成長率を高めつつ
社会保障の高齢者自己負担引き上げや消費増税など、痛みを伴う歳出カットを積極的に
すすめて財政規律を復活させるなどというスーパー上げ潮路線が可能だろうか?
中川秀直さんに開発独裁でもしてもらえばいけそうな気もするが、
党内でも干され気味なのでまず無理だろう。
そもそも、ほんのちょっぴりの社会保障の切り下げと、(民間と競争するためには
国債ばかり買っていたら大赤字になるのは確実なので今のうちに民営化しただけの)
郵政民営化という平凡な改革ですら、いまだに議論したがるバカがいる国だ。
ということは、2030年ごろになって「やっぱりダメでした」とやられてしまうと
それまでに極楽浄土だの天国だのに脱出完了した人は(食い逃げできたわけだから)
大喜びだろうが、残された世代はたまったもんじゃない。
特に、その頃に60代になっている団塊ジュニアは、今の団塊どころじゃない
言われようだろう。
「数だけ多いお荷物世代」
「こうなるのは分かっていたくせに、なんの手も打たなかったA級戦犯」
「医療も年金もこれからは自己責任」
積み上がった借金を大増税と超緊縮財政ではけさせるにしても、インフレでチャラ
にするにしても、経済は破滅的な打撃を受け、まさに戦後の焼け野原状態になる
だろう。
その頃まで先延ばしすれば、それだけ焼け野原の面積が拡大し、さらにはそれまで
現役世代からの不毛な所得移転が続くわけだから、イノベーションや出生率といった
日本全体の地力も損なわれ続けることになる。
だったら、カタストロフィは早い方が良いではないか、というのが早期破綻論の
ロジックだ。
考えてみれば、これは歴史上何度も繰り返されてきた“リセット”だ。
第二次大戦後、インフレで戦時国債という無駄な公共事業費をチャラにすることで
その後の発展につながったことは記憶に新しい。
「本土決戦」なんていって後数年頑張っていたらどうなっていたか。
明治維新もそうだ。
幕府・大名・そして士族という既得権を崩し、最後は“秩禄”という家禄相当分の
債権を踏み倒すことで、近代国家への道をスタートさせた。
この時代が羨ましいのは、多少の混乱はあったものの、基本的には武士たちが
既得権の放棄を受け入れてくれたことだ。
もちろん、「侍の権利を守れ!」という自称労働者政党も、
「侍と平民は連帯しよう!」といって商売するバカもいなかった。
21世紀も引き続き日本を成長させていくために、斜陽国から新興国家へ、強制的に
リセットボタンを押すべきだと、彼らは考えている。
個人的には、実質的な財政破綻の影響がどうなるかなど、分からない部分が多すぎ
るので、なるべく財政再建を意識しつつ、上げ潮も並行して進めるべきだと考えている。
今のところはそっちの方が多数派なので、早期破綻論というのは一部の過激派と
言えるかもしれない。
それにしても、改革否定派(潜在的破綻派と言い替えてもいいが)
の面々を見ていると、実に不思議な気分になる。
若年層で後者を支持する人間には、むしろ破綻でもっともダメージを受ける
グループが多い気がするのだ。
たとえばアウトサイダーはどんな状況になっても生きていけるので問題ない。
むしろ、成り上がるチャンスと期待する向きすらある。
大企業や官庁で働いていれば、貧しくとも死ぬ状況にまではならないだろう。
問題なのは、非正規雇用労働者などの弱者だ。
インフレで金融資産保有層が大ダメージを受ければ、表面上の格差は縮小するだろう。
だが06年前後の好況時を見ても分かるとおり、賃上げという果実は付加価値の高い
業務を担当している正社員に優先して回されるから、このインフレ時にも非正規
および中小下請け企業の賃金上昇率は、物価上昇率にはとうてい追いつかないはず。
資産が無ければ文字通り野垂れ死にするんじゃないかな。
まあ、そういうケースも含めての“ゼロリセット”なんだろうけど。
そう考えると、この状況でさらに
「景気浮揚対策として、国債中心に200兆!」
をマニフェストに掲げる国民新党は、実は早期破綻推進政党なのかもしれない。
そうか、いつのまにか日本は総力戦を戦っていたのか。
そりゃ閉塞感に包まれるはずだ(笑)
以前、コメントでもちょっと話題になっていたので簡単にまとめておきたい。
財政について、再建はもう現実的ではないので、一度何らかの形で破綻させて
しまった方が良いという意見は、確かに一部にある(もちろん公では言わないけど)。
これは一見突飛に見えるが、よく考えてみれば非常に合理的な考えだ。
これから数年で、大胆な規制緩和を進め、人も金も新規事業に移して成長率を高めつつ
社会保障の高齢者自己負担引き上げや消費増税など、痛みを伴う歳出カットを積極的に
すすめて財政規律を復活させるなどというスーパー上げ潮路線が可能だろうか?
中川秀直さんに開発独裁でもしてもらえばいけそうな気もするが、
党内でも干され気味なのでまず無理だろう。
そもそも、ほんのちょっぴりの社会保障の切り下げと、(民間と競争するためには
国債ばかり買っていたら大赤字になるのは確実なので今のうちに民営化しただけの)
郵政民営化という平凡な改革ですら、いまだに議論したがるバカがいる国だ。
ということは、2030年ごろになって「やっぱりダメでした」とやられてしまうと
それまでに極楽浄土だの天国だのに脱出完了した人は(食い逃げできたわけだから)
大喜びだろうが、残された世代はたまったもんじゃない。
特に、その頃に60代になっている団塊ジュニアは、今の団塊どころじゃない
言われようだろう。
「数だけ多いお荷物世代」
「こうなるのは分かっていたくせに、なんの手も打たなかったA級戦犯」
「医療も年金もこれからは自己責任」
積み上がった借金を大増税と超緊縮財政ではけさせるにしても、インフレでチャラ
にするにしても、経済は破滅的な打撃を受け、まさに戦後の焼け野原状態になる
だろう。
その頃まで先延ばしすれば、それだけ焼け野原の面積が拡大し、さらにはそれまで
現役世代からの不毛な所得移転が続くわけだから、イノベーションや出生率といった
日本全体の地力も損なわれ続けることになる。
だったら、カタストロフィは早い方が良いではないか、というのが早期破綻論の
ロジックだ。
考えてみれば、これは歴史上何度も繰り返されてきた“リセット”だ。
第二次大戦後、インフレで戦時国債という無駄な公共事業費をチャラにすることで
その後の発展につながったことは記憶に新しい。
「本土決戦」なんていって後数年頑張っていたらどうなっていたか。
明治維新もそうだ。
幕府・大名・そして士族という既得権を崩し、最後は“秩禄”という家禄相当分の
債権を踏み倒すことで、近代国家への道をスタートさせた。
この時代が羨ましいのは、多少の混乱はあったものの、基本的には武士たちが
既得権の放棄を受け入れてくれたことだ。
もちろん、「侍の権利を守れ!」という自称労働者政党も、
「侍と平民は連帯しよう!」といって商売するバカもいなかった。
21世紀も引き続き日本を成長させていくために、斜陽国から新興国家へ、強制的に
リセットボタンを押すべきだと、彼らは考えている。
個人的には、実質的な財政破綻の影響がどうなるかなど、分からない部分が多すぎ
るので、なるべく財政再建を意識しつつ、上げ潮も並行して進めるべきだと考えている。
今のところはそっちの方が多数派なので、早期破綻論というのは一部の過激派と
言えるかもしれない。
それにしても、改革否定派(潜在的破綻派と言い替えてもいいが)
の面々を見ていると、実に不思議な気分になる。
若年層で後者を支持する人間には、むしろ破綻でもっともダメージを受ける
グループが多い気がするのだ。
たとえばアウトサイダーはどんな状況になっても生きていけるので問題ない。
むしろ、成り上がるチャンスと期待する向きすらある。
大企業や官庁で働いていれば、貧しくとも死ぬ状況にまではならないだろう。
問題なのは、非正規雇用労働者などの弱者だ。
インフレで金融資産保有層が大ダメージを受ければ、表面上の格差は縮小するだろう。
だが06年前後の好況時を見ても分かるとおり、賃上げという果実は付加価値の高い
業務を担当している正社員に優先して回されるから、このインフレ時にも非正規
および中小下請け企業の賃金上昇率は、物価上昇率にはとうてい追いつかないはず。
資産が無ければ文字通り野垂れ死にするんじゃないかな。
まあ、そういうケースも含めての“ゼロリセット”なんだろうけど。
そう考えると、この状況でさらに
「景気浮揚対策として、国債中心に200兆!」
をマニフェストに掲げる国民新党は、実は早期破綻推進政党なのかもしれない。














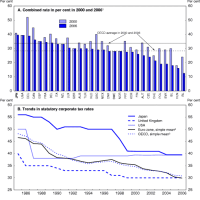





「清濁併せ呑む」という姿勢もどこかで持っておいたほうがいいのかな、という気もします。(こんなこというと甘いと言われそうですが)
>第二次大戦後、インフレで戦時国債という無駄な公共事業費をチャラにすることで
その後の発展につながったことは記憶に新しい。
「本土決戦」なんていって後数年頑張っていたらどうなっていたか。
加えて言うと、インフラがや産業基盤が辛うじて残っていたところへ朝鮮半島の特需が起きて、もろもろの問題を吹っ飛ばしてしまった一面もありますよね。
個人的に良著だと思った一冊です。戦後政治史の簡単な説明もあって、わかりやすかったです。
「今こそ知りたい消費税」(林信吾・葛岡智恭 著)
http://www.nhk-book.co.jp/shop/main.jsp?trxID=0130&webCode=00882952009
それ以外政治家の仕事はない。よくまあこんな仕事をしようとして立候補するなあ。
何か自分の力を、まちがえているのではないか。
其れとも勘違いか。
来年予算を組めるか?
第一の基本は年寄りに大きく被害(?)が出るようにすることである。彼らの資産はどのみち、中身がないから、其れが表に表れるだけである。
年金なんかもうないだろう。仕組みを見るとできるわけがない。おれも良く知らなかった。
とにかく若者が行きやすい世界を作ること。
改革ではない。如何にうまく倒産するかである。
幕末の政治家、小栗上野介を思い出す。
確か<これで、幕府は蔵を持って倒産する>といったとか。
我々日本人の力量と、エリートの能力が示される。
万歳。始まるぞ。
毎年税収の2倍近くの国債発行をするのはどう見ても異常で、
民主党は「無駄を省いてばら撒く」と言っているが
政権交代してやるべきことは「無駄を省いて財政再建」でしょう。
無駄を省く行革にしても「クビを切らない」と言い切り改革意識がまるで感じられない。
官公労を支持母体とする彼らにとって毎年30兆以上の地方公務員の人件費は「無駄」ではないのも明白。
自民も民主も「大衆迎合のパターナリズム」「老人優遇」の守旧派ドグマに侵されている。
76ページから77ページにかけて下のようなことを書いています。
”江戸時代も終わりになると、武士たちは「武士であることの費用」の重圧に耐えられなくなってきていた。猪山家にしてもそうである。武士身分でなければ、借金を抱えなくて済んだのである。今日、明治維新によって、武士が身分的特権(身分収入)を失ったことばかりが強調される。しかし、同時に明治維新は武士を身分的義務(身分費用)から解放する意味をもっていたことを忘れてはならない。幕末段階になると、多くの武士にとっては身分利益よりも身分費用の圧迫の方が深刻であった。
明治維新は武士の特権を剥奪した。これに抵抗したものもいたが、ほとんどはおとなしく従っている。その秘密には、この「身分費用」の問題が関わっているように思えてならない。”
つまり武士にとっても特権を手放した方が損をしないようになっていたのです
もし労働者が労働者の権利なんか形骸化されていると知れば、たとえ権利がなくなっても
問題がないのかもしれない。
しかし何も起きなかった。いい加減な「経済評論家」だなあと呆れた。
しかし当時と比較しても国の財政は悪化している。ある日突然自分の預金を引き出せなくなるかもしれない。今は嵐の前の静けさのような気がする。
たしか、武士の特権的収入は何代も一定だと、特権的支出(先祖供養)が重荷になるとかと解釈してました。教育費も支出としては重荷ではあったが武術では無く、当時は低く見られていた算術だったため
、維新を潜り抜け勝ち組になったと、読後思っていました。
これはいくらなんでも冗談だろうと思って見に行ったらホントですね・・・こういう政党が連立政権入りしてしまうのか。