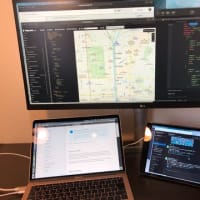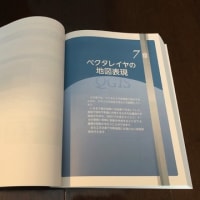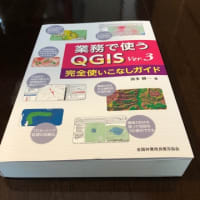日本にGoogleマップが登場してから5年、本日その記念イベントが開催された。私はというと、イベントの案内を目にしたが、どうも参加する気になれずに、昼間都内にいたにもかかわらず、午後はみなとみらいの会社に戻って、しばし港の向こうにかかるベイブリッジを眺めていた。
ずっと地図関係の分野で仕事をしている私には、いくつかの実績もあるし、同様に古傷もある。古傷に触れられるとうずくものだ。Googleマップの開発パートナーであっても・・・
実績といえば、90年代後半の日本の電子地図の黎明期において、特に日本特有の”印刷品質”の電子地図の普及を推進したことが一つ、それから、2000年代前半から日本でのFOSS4Gの利用推進を行ったことについては、私としても自負しているところである。いずれの場合も、私は事業のプロデューサーという立場で関わっており、立場上のミッションは、「事業として成功させること」になる。
前者の電子地図、カーナビ系の味気のないワイヤーフレームのベクトル地図を、グラフィカルな印刷品質の地図でもって凌駕して、熱心なマーケティング活動で、当時PCの必須アイテムとまで言われた「電子地図ソフト」の最右翼の地位を確保し、必勝パターンを手中に収めたかと思った矢先、97年春にマピオンという「地図がタダで見れる」サービスが出現した。マピオン自体は、アメリカで先行していたMapQuestやVicintyの模倣サービスだったのだが、国内業界のことしか知らなかった私には、とにかく驚きだった。こんなサービスが成立してもらったら、電子地図ソフトの市場は伸び悩んでしまうのだから。案の定、MapFanなど、マピオンをまねたサービスが国内に林立し、電子地図ソフトの利用者はハイエンドユーザーだけに限られるようになってしまった。
マピオンやMapFanは大資本による運営なので、数年間赤字でもそんなに困らない。しかし、当時私が勤めていた会社はそういうわけには行かない。しかも地図の整備とメンテに巨費を投じているわけだから、電子地図ソフトで十分に儲けておかなければ困る。しかし、迫り来る現実は、十分儲かる前にその事業構造を転換しなければならないという不幸な状況だった。私は、「タダで地図が見れる」サービスによって、いずれ電子地図ソフトが消滅する日を想定して(実際にその日は来てしまったわけだが)、そのマピオンに自社の地図コンテンツを提供する契約を取り付けたりもしたのだが、当初描いた「電子地図ソフトが大多数のPCにインストールされる」という夢は現実になることはなかった。
さて、お次は2000年代。私はGISの世界に身を転じていた。FOSS4Gがもたらす可能性にいち早く気がつき、空間データベースをバックエンドに配置したWebマッピングサイトの構築では、2004年当時は実に先進的なポジションを確保していた。オープンソースのメリットに加え、当時価格が高かった地図データの調達にも工夫を行って、従来の数分の1の導入コストで地図サイトが実現するようにした。国内のGIS業界に与えた影響は大きく、多くのユーザーから歓迎された。一方、それまで元気が良かった「国産WebGISエンジン」には打撃を与えることとなった。
そして、これから儲けるぞ、という矢先の2005年にGoogleマップ(2月にアメリカで先行)が出現した。それだけならば、単にスクロール地図の登場で済んだが、APIは、地図特有の難しさを考えず、Webアプリケーションの開発知識だけで地図サイトを構築できるというアプローチで、実に新鮮であった。しかし、それ以上に「無償」で使えることの業界に与えたインパクトは大きかった。
当時私の会社では、地図・GISアプリケーションの構築事業が軌道に乗り始めていた。Googleマップで言うと、”APIの下側”の部分をFOSS4Gで作り上げるのが強みだったが、幸い顧客層が通り一遍の背景地図ではない地理データを活用していたので、経営への悪影響は無かったのだが、もっと幅広い顧客層へ事業領域を広げていけるという期待が、どんどん遠ざかっていくのがわかった。FOSS4Gは時代の必然だったのだが、Googleマップというもう一つの、しかも巨大な時代の必然が、大多数の人の注目を集めてしまうのを、端から見ているしかなかった。そして、FOSS4Gだけでは事業の広がりは限定されるため、FOSS4GとGoogleマップのハイブリッドアプリケーションの構築が主力になっていった。
振り返ってみれば、地図の世界は、90年代半ばまでは地図専業者によって様々な革新が行われて来たが、その後メガプレーヤーが制する時代に移行した。そのプレーヤーも90年代は国内大資本だったが、2000年代はアメリカの超巨大資本になった。
ところで、グーグルの日本法人は、「日本のためにマップをこのように改良しました」と説明している。確かに、Googleマップの登場は、明らかに時代のパラダイムを変えた。Googleマップが無いとWeb自体が成立しなくなるほどの浸透を遂げた。ただ、彼らはGoogleマップ自体の構想に関わった”プロデューサー”ではなく、アメリカのディレクションの下で、それを日本人の欲しがるレベルに最適化した”匠”というポジションだと思う。あのアメリカの味のないGoogle Mapsと比べれば、日本人らしい創意工夫が随所に見て取れて拍手なのだが、その多くの要素は、既に90年代の電子地図で採り入れらていたものの焼き写しが多い。なので、私にはそれほどの進歩には感じられないのが正直なところだ。でも、まだ5年だし、USセントリックなガバナンスで、あれだけやれれば正直よくやれていると評価するし、これからなのかもしれないが・・・
で、私の会社の事業はどうなるか。人間万事塞翁が馬(私の座右の銘の一つ)。事業が軌道に乗った矢先にハシゴを外されるようなことは、どうやら繰り返されるみたいなので、それを見越してしたたかにやっていこうか。
ずっと地図関係の分野で仕事をしている私には、いくつかの実績もあるし、同様に古傷もある。古傷に触れられるとうずくものだ。Googleマップの開発パートナーであっても・・・
実績といえば、90年代後半の日本の電子地図の黎明期において、特に日本特有の”印刷品質”の電子地図の普及を推進したことが一つ、それから、2000年代前半から日本でのFOSS4Gの利用推進を行ったことについては、私としても自負しているところである。いずれの場合も、私は事業のプロデューサーという立場で関わっており、立場上のミッションは、「事業として成功させること」になる。
前者の電子地図、カーナビ系の味気のないワイヤーフレームのベクトル地図を、グラフィカルな印刷品質の地図でもって凌駕して、熱心なマーケティング活動で、当時PCの必須アイテムとまで言われた「電子地図ソフト」の最右翼の地位を確保し、必勝パターンを手中に収めたかと思った矢先、97年春にマピオンという「地図がタダで見れる」サービスが出現した。マピオン自体は、アメリカで先行していたMapQuestやVicintyの模倣サービスだったのだが、国内業界のことしか知らなかった私には、とにかく驚きだった。こんなサービスが成立してもらったら、電子地図ソフトの市場は伸び悩んでしまうのだから。案の定、MapFanなど、マピオンをまねたサービスが国内に林立し、電子地図ソフトの利用者はハイエンドユーザーだけに限られるようになってしまった。
マピオンやMapFanは大資本による運営なので、数年間赤字でもそんなに困らない。しかし、当時私が勤めていた会社はそういうわけには行かない。しかも地図の整備とメンテに巨費を投じているわけだから、電子地図ソフトで十分に儲けておかなければ困る。しかし、迫り来る現実は、十分儲かる前にその事業構造を転換しなければならないという不幸な状況だった。私は、「タダで地図が見れる」サービスによって、いずれ電子地図ソフトが消滅する日を想定して(実際にその日は来てしまったわけだが)、そのマピオンに自社の地図コンテンツを提供する契約を取り付けたりもしたのだが、当初描いた「電子地図ソフトが大多数のPCにインストールされる」という夢は現実になることはなかった。
さて、お次は2000年代。私はGISの世界に身を転じていた。FOSS4Gがもたらす可能性にいち早く気がつき、空間データベースをバックエンドに配置したWebマッピングサイトの構築では、2004年当時は実に先進的なポジションを確保していた。オープンソースのメリットに加え、当時価格が高かった地図データの調達にも工夫を行って、従来の数分の1の導入コストで地図サイトが実現するようにした。国内のGIS業界に与えた影響は大きく、多くのユーザーから歓迎された。一方、それまで元気が良かった「国産WebGISエンジン」には打撃を与えることとなった。
そして、これから儲けるぞ、という矢先の2005年にGoogleマップ(2月にアメリカで先行)が出現した。それだけならば、単にスクロール地図の登場で済んだが、APIは、地図特有の難しさを考えず、Webアプリケーションの開発知識だけで地図サイトを構築できるというアプローチで、実に新鮮であった。しかし、それ以上に「無償」で使えることの業界に与えたインパクトは大きかった。
当時私の会社では、地図・GISアプリケーションの構築事業が軌道に乗り始めていた。Googleマップで言うと、”APIの下側”の部分をFOSS4Gで作り上げるのが強みだったが、幸い顧客層が通り一遍の背景地図ではない地理データを活用していたので、経営への悪影響は無かったのだが、もっと幅広い顧客層へ事業領域を広げていけるという期待が、どんどん遠ざかっていくのがわかった。FOSS4Gは時代の必然だったのだが、Googleマップというもう一つの、しかも巨大な時代の必然が、大多数の人の注目を集めてしまうのを、端から見ているしかなかった。そして、FOSS4Gだけでは事業の広がりは限定されるため、FOSS4GとGoogleマップのハイブリッドアプリケーションの構築が主力になっていった。
振り返ってみれば、地図の世界は、90年代半ばまでは地図専業者によって様々な革新が行われて来たが、その後メガプレーヤーが制する時代に移行した。そのプレーヤーも90年代は国内大資本だったが、2000年代はアメリカの超巨大資本になった。
ところで、グーグルの日本法人は、「日本のためにマップをこのように改良しました」と説明している。確かに、Googleマップの登場は、明らかに時代のパラダイムを変えた。Googleマップが無いとWeb自体が成立しなくなるほどの浸透を遂げた。ただ、彼らはGoogleマップ自体の構想に関わった”プロデューサー”ではなく、アメリカのディレクションの下で、それを日本人の欲しがるレベルに最適化した”匠”というポジションだと思う。あのアメリカの味のないGoogle Mapsと比べれば、日本人らしい創意工夫が随所に見て取れて拍手なのだが、その多くの要素は、既に90年代の電子地図で採り入れらていたものの焼き写しが多い。なので、私にはそれほどの進歩には感じられないのが正直なところだ。でも、まだ5年だし、USセントリックなガバナンスで、あれだけやれれば正直よくやれていると評価するし、これからなのかもしれないが・・・
で、私の会社の事業はどうなるか。人間万事塞翁が馬(私の座右の銘の一つ)。事業が軌道に乗った矢先にハシゴを外されるようなことは、どうやら繰り返されるみたいなので、それを見越してしたたかにやっていこうか。