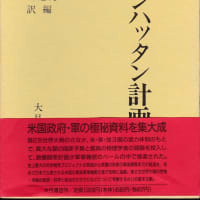▲ 写真館を営む四男文清(ウンセイ)が、自分の逮捕を予感し、最後に撮った家族記念写真 映画の終末に近いシーン
侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督の映画 『悲情城市』(1989年イタリア・ベネチア国際映画祭グランプリ受賞)自主上映に関わった時代があった。今から20年以上も前のことである。1990年(日本公開)の映画で、一度見て傑作だと思った。映画は第2次世界大戦終結前後の台湾の大家族の物語として設定され、多くの登場人物が出てくる。記憶が薄れる前に、短文を地域の映画愛好会の冊子に載せた。手元に今、映画のビデオがないのだが、20数年後の感想はまたの楽しみとして、冷戦終結前後の記憶として、どうしても書きたい気持ちがこみあげてきた勢いで書いたもの。
以下1990年10月17日発行 『映画大好き』 4号 より
悲情城市 ひじょうじょうし 1989年 日本公開 1990年 4月28日
映画からあふれだす「情」のなかで、もはや 悲劇ではないものに達する
天上有星 地上有花 人間有深情 (侯孝賢のことば)
1989年、イタリアのヴェネチア国際映画祭でグランプリを獲得した侯孝賢(ホウ・シャオシェン)の『悲情城市』を『ヴァレエティ』誌は小津安二郎の(風)のゴッド・ファーザーと名付けた。
確かにこの映画は物語の細部と人物の描写に深みがあり、幾重にも波乱のある複雑な物語の進行に比べて、カメラアングルはシンプルで、ごく限られている。(これが小津と比較される一つの理由でもあるだろう)
このカメラアングルは、映画全体を、「ある時代を描くことの困難さと冒険」を痛烈かつ冷静に描き出してみせる不思議さをもっている。
舞台は台北(タイペイ)の東、港町の基隆(キールン)。日本の敗戦によって、50年にわたる台湾支配から解放され、喜びに沸いたのも束の間、中国本土で、毛沢東ひきいる共産党との権力闘争に破れた蒋介石の国民党政府が逃亡をよぎなくされ、台湾の台北を臨時首都とするまでの激動の4年間を港町で商売を営む75歳の林阿祿と彼の4人の息子たち大家族の運命を中心に描かれる。
この映画のナレーションは 寛見(ヒロミ)と阿雪(アスア)という女性の声で、語られている。登場人物の男たち、特に林家の長男の文男の代表するややあらっぽい、商売や戦争にあけくれる現実派の人間たちに対して、ある出来事に対して別様に対処する女性たちの姿がつつましく、あるいは淡々と描き込まれる。
一方、林家の四男の文清(ウンセイ)とその仲間たちは、台湾における知識人グループである。日本敗戦後の混乱期に理想派の彼らが、台湾においてどのような活動をなし、またなし得なかったかを、1947年の2.28事件を中心に、国民党政府・軍・民衆との関係を対比させながら描いている。台湾史上、最も悲劇的と言われる時代を四男の文清によって語り得ないこと(映画の中では文清は耳が聞こえず、話せない人物として設定されている)を語らせている。
このあたりの描写は、台湾が2.28事件をきっかけに、世界でもまれにみる長期にわたる戒厳令(1945年5月20日~1987年7月15日解除)がしかれ、いまなお民主化や、権力批判することがタブー化されている歴史的経過があり、いまひとつ事実関係ははっきりせず、台湾現代史にうとい私には、象徴的描写に流れているような危惧感を抱いた。
しかし考えてみれば1920年以降、大陸での国民党と共産党の内戦以来、徹底したイデオロギーの対立をよぎなくされ、戦後の国共内戦のさらなる激化によって、当時国府軍の支配下にあった台湾においては、他所に例をみない凄惨な、民主主義者・左翼の処刑劇となっていく。その上、第2次大戦後の東西の冷戦は、トルーマンとスターリンという最悪の組み合わせの枠組みの中で、台湾の民主化は現在に至るまで、縁遠いものにさせられていったのである。
さて、問題はイデオロギーそのものにあるのではない。
映画の快楽は、映画そのものによって示されなければならない。侯孝賢(ホウ・シャオシェン)の『悲情城市』はまさしくそのようなものだ。
「小津安二郎のゴッドファーザー」のように楽しめるのである。映画に登場するそれぞれの男たちは、宿命を生きる。その道を生きることによってしか発散できないような香気、艶を漂わせているのである。
映画の登場人物や家族関係は複雑だが、物語の進行にともなって少しずつ明確になっていく人物も多く、それほど苦にならない。
ショットは長く、人物の顔に肉薄する劇的なクローズアップシーンなどはない。何か映画的激情に走りたい人には、小津安二郎の映画のテンポに耐えられないように、この映画のテンポに耐えられないかもしれない。
しかし、深い快楽のためには、人間は、ある場面ではストイックな時空を持たなければならないように、この映画の快楽のためには、しばしラストシーンまで待たなくてはならない。
侯孝賢は自作の『悲情城市』についてインタビューに答え
「この映画は事実を描いたというよりあの時代についての私たちの主観的イメージに基づいて、当時の時代状況や、時代の息吹を模索したというべき。撮影にあたっては、距離を置いた傍観者であることをとりわけ心がけ、一切の批判なしに描き出そうと考えたのです。感覚的に傍観者の側に立つことによって、多層的で、奥深い空間表現をしたいと考えた」
と語っている。
さて、この『悲情城市』の比類のなさは、絶えず、政治や、商売や、遊興で慌ただしげにこの世を去っていく男たちの生き方ーーーー理想的にか、美的にか、享楽的にか、暴力的にかーーーに対して、
この映画のナレーターの形で表現されていく、文清の妻ヒロミ、文雄の娘アスアたち、女の視点によって、歴史(事件)が多声性、多元性を帯びはじめ、悲劇が単なる悲劇としてではなく、悲劇が記録され、保存され、希望へと変形させていく、まがいもない生命力を持つものへの信頼との競演、つばぜりあいみせているからなのだ。
映画の全体を貫くこの映画のタイトルのようなこみあげる深い悲しみは、軍隊に逮捕されることを知りながら写真館(自宅)に戻り、最後の家族写真を自動タイマーで撮影するシーンで絶頂に達する。
四男・文清役を演ずるトニー・レオンの瞳がカメラのレンズを向こう側から見つめ、カメラのシャッターが切れるとき、人は映画の中でのみ出会っているはずの想像上の文清とその家族の運命を眺めているのではなく、観客その人がシャッターを押したのだと知るのである。映画の画面をやすやすとのりこえて、見る者自身に、あふれ出てくる情感の不思議さの中で、台湾の被ってきた悲劇や宿命に対して目撃者として召喚されている自分自身を発見する。
![]()


映画の中の人物が、次第に動きを失ってついに静止するとき、その一枚の記念写真は、一人一人の生存の輝きを産毛一本一本を描こうとした一人の画家のマチエールのように彼の映画の感触の豊かさを感じさせる。

1989年に完成し公開されたこの『悲情城市』は、その年、天安門で起きた事件とともに、これから決して忘れることはないだろう。
『悲情城市』は撮ることによってしか、存在することがなかった「情」にあふれ、その「情」はあふれ出すべき現実の時を知っているのだから。」
▲ブログ主注記 上の記述では、「台湾の民主化が今なお」というという表現があるが、2013年の今のことではない、私が書いた時点1990年の頃のことである。1989年ベネチア映画祭グランプリ受賞により、ようやく戦後タブーとされていた事件や歴史の一端を世界の支援のもとに、語ることができるようになってきた。台湾に敷かれていた戒厳令がようやく解かれた直後の映画撮影であり、侯孝賢の慎重な態度が貫かれているのが、1990年、映画を見てひしと感じたことを付け加えておく。
映画のジャンルに属すべきブログの内容であるが、「書かれたもの」という意味で、あえて、本の分類に入れた。ブログのジャンル分けは細かくすればするほど細分化され、想像上の読んでもらうべき相手に届かない。